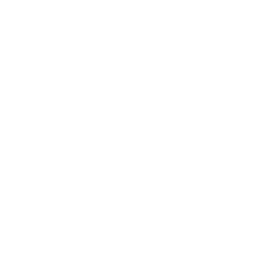«Headline
Author
前田 洋介
[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

SOUNDTRIP 2023 / media HYPERIUM / Immersive Sound@ L.A.

2023年のグラミー賞でBest Immersive Audio Albumを受賞した、Stewart Copeland, Ricky Kej & Herbert Waltl「Divine Tides」。その制作を担当したプロデューサー / Herbert Waltl 氏とエンジニア Eric Schilling 氏にインタビューの機会を得た。イマーシブオーディオに対しての向かい合い方、ミキシングに対する考え方、制作者目線での貴重なコメントをいくつもいただくことができたのでご紹介していきたい。
長年にわたり、音楽業界に多大なる足跡を残しているミュージシャンであり、プロデューサーのHerbert Waltl 氏と、グロリア・エステファンを始め、ラテン、ポップスなど多彩な音楽の制作に携わるエンジニアのEric Schilling 氏のお二人にHerbert Walti氏が1996年に立ち上げたmedia HYPERIUMでお話を伺った。まずは、お二人のこれまでの実績、今年のグラミー賞を受賞した作品について振り返る。
Herbert Waltl 氏は3度のグラミー賞受賞、3度のグラミー賞ノミネート、数々のプラチナディスクの制作に携わったプロデューサーである。テクノロジーに精通し、新しいフォーマットへの積極的な取り組みでも知られる。1996年にmedia HYPERIUMを立ち上げ、サラウンド作品の可能性を求めて様々な研究を行ってきた。その後、イマーシブオーディオにも積極的に取り組み、Ray Charles / Lady Gaga / Pink / Sting / Jason Derulo / Sheryl Crow / Chick Corea / S.F. Symphony / BR Symphony Orchestra / Royal Concertgebouw Orchestraなどの作品に携わっている。グラミー賞でもBest music DVD Awardなどにノミネートされていることからわかるが映像関連の制作の評価も高く、映画のサウンドトラックなどの制作も行っている。まさに、サラウンド〜イマーシブと音楽フォーマットの進化とともに歩み続けている、技術をしっかりと理解したプロデューサーと言えるだろう。
Eric Schilling氏は、アメリカのトップエンジニアの一人。2000年以降に4度のグラミー賞受賞、7度のラテングラミー賞受賞。代表的な作品としては、Gloria Estefanとの16枚のアルバムが挙げられる。それ以外にもNatalie Cole / Jon Secada / Elton John / Natalie Imbruglia / Shakiraなどのアルバムを手掛けている。ラテン音楽のエッセンスを取り入れたポップスに代表作が多い。サンフランシスコ出身だが、伝説的なプロデューサーBill Szymczykとの出会いから、彼のフロリダのスタジオBayshore studioへと移籍、そこで上記したようなマイアミ発の数多くのヒット作品に携わるようになる。現在も自宅と自身のスタジオはマイアミ、オークランドにある。近年はAlicia Keysのアルバムの360 Reality Audioフォーマットへのリミックス作業を、彼女のメインエンジニアであるAnn Mincieliを中心に、George Massenburgらと今回インタビューで伺ったmedia HYPERIUMで行った。他にも数多くのイマーシブ作品に関わっている。
2023 Grammy Winnerとなった「Divine Tides」は、Stewart Copeland / Ricky Kej & Herbert Waltlによる、様々なカテゴリーの音楽を集めた宝箱のような作品。クラシック、ラテン、ゴスペル、そのベースにはRicky Kejの出身であるインド音楽など多種多様なエッセンスが詰まっている。元The PoliceのドラマーStewart Copelandは近年映画のサウンドトラックの制作を精力的におこなっており、さらにはオーケストラ向けの楽曲や、バレエ音楽、オペラなども手掛けている。そんな世界観にインド出身の新進気鋭のミュージシャンRicky Kejのエキゾチックなエッセンスをベースとしたメロディー、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団によるオーケストレーション、Southan Gospel(南アフリカをベースとするゴスペル)でグラミー賞ワールド・ミュージック部門の常連であるSoweto Gospel Choirによるハーモニー、Rasika Shekarなどインド出身のミュージシャンによるコラボーレーションが重ねられ、2021年にリリース。そして2023年の本年にグラミーを受賞した作品だ。
これを、Herbert WaltiとEric Schillingがmedia HYPERIUMでイマーシブにミキシングした。この作品は、ステレオ音源で聴いてみていただいてもわかるように広大な世界観を持つ。Stewart Copelandによる空間が拡張していくようなパーカッションサウンド。もともとイマーシブオーディオのために作られたような世界観を持つこのアルバムが、二人によるイマーシブミックスでその本来の姿を現しグラミーを再び受賞している。ステレオでの新譜とイマーシブミックスが2度にわたりグラミーを受賞したのはかなり珍しいケースなのではないだろうか。
インタービューをおこなったmedia HYPERIUMはロサンゼルスの南、ロングビーチの西にある小高い丘陵地Rolling Hillsにある。高級住宅地であるこの場所の一角にあるオフィスビルにこのスタジオはある。プール付きの豪邸が立ち並ぶ本当に静かな住宅街の商業エリアに突然スタジオがある、といったところだ。このスタジオにはミキシング用の部屋があるのみで、別の場所でレコーディングされたものをここでミキシングしているそうだ。
スピーカーはNeumannが選択されている。イヤーレベルのスピーカーはKH420、解像度が高く、大音量でなくともサウンドの迫力を感じることができる素晴らしいモデルだと絶賛されていた。イマーシブではスピーカー数が多いため、すぐに音圧過多になり疲れてしまうが、少し控えめの音量でもしっかりとサウンドを確認できるNeumann KHシリーズはお気に入りのモデルだということ。配置されたスピーカーのレイアウトは7.2.5 + 4B。イヤーレベルに7本のKH420、トップレイヤーにはKH310、ボトムはKH120とNeumannのKHシリーズで統一されている。ちなみに、特別な音響処理がなされている訳では無いオフィスとして作られたこの部屋の響きを気に入って使っているということだが、なぜこのようにバランスの取れたサウンドがするのかはあまり考えたことはなく、スピーカーを置いて鳴らしてみたら良い音がした、それがすべてだとシンプルかつ明確な答えをいただいた。

📷オフィス施設の一室に作られたスタジオ。写真の通り、水平面に7chのNeumann KH420、上部にはSONY 360 Reality Audioに合わせ仰角30度に設置された5chのKH310と、Dolby Atmosに合わせて仰角45度に設置された4chのKH150。壁面には厚手のカーテンが張り巡らされてはいるが、吸音・遮音などは行われていない。聴音用のパネルが左右に設置されているのみのシンプルなスタジオである。
さてここからは、どのようなお話を聞くことができたかお伝えしていきたい。映画音楽にも関係があった二人はサラウンド、そしてDolby Atmosなどのイマーシブフォーマットに以前より取り組まれていた。ステレオに対しての可能性の広がりをフォーマットの拡張とともに感じ、それぞれのフォーマットで作品をリリースしている。
中でも360 Reality Audioは、完全な360度 4πの空間を持つフルオブジェクト指向のフォーマットということでいち早くその先進性、可能性を感じ取って作品制作に携わってきている。音楽の表現として下方向が加わったということは大きいと言う印象を持たれていた。確かに下から聴こえてくる直接音というものは少ないかもしれないが、音響空間の再現にとっては非常に重要であるということを感じている。低音の表現に関しても、やはり音を配置できる空間が広いことで柔軟性が上がるというよりは必然性を持って音の配置が行えるようになった、という感覚ということだ。楽曲として、作品として、然るべき位置から然るべき音が鳴る。表現の自由とも言い換えることができるのかもしれないが、その一方で、これまでにそれほど音の配置に悩んだことはない、というコメントは印象的であった。普段の暮らしで接している音空間、それこそが4πの空間でありそれを再現する。その中に音楽としての刺激、感覚を盛り込んでいくという作業は非常に楽しい作業だとのこと。Dolby Atmosとの同時制作の場合にも、360 Reality Audioから制作をして順に再現できる空間を狭くするという手法をとっているということだ。
エンジニアのEric氏は、携わったアーティストのライブパフォーマンスのサポートなども行っていることもあり、音楽を生で楽しんでいる環境の音、そんなものまでも再現したという欲求もあるという。それを考えるとイマーシブオーディオは最適なフォーマット、というよりもイマーシブだからこそ会場の熱気のようなものまで伝えることができるようになってくるのではないかと大きな可能性を感じているということだ。アメリカはライブパフォーマンスを楽しむということを非常に重要視するカルチャーがある。ライブを楽しむということは、ミュージシャンのパフォーマンスを楽しむということであり、才能に触れ、それに感動するということでもある。音楽という一瞬にして消えていくパフォーマンスとの出会い、それを非常に大切にしているし、それに対しての対価を惜しまない。そんな文化が根底にあると感じている。
これはヨーロッパでも同様で、ヨーロッパに根付くクラッシク音楽の下地は同じようなところから来ているのではないだろうか。少し脱線してしまうが、アメリカ人の強さは、日本語で言うところの「一期一会」であると筆者は感じている。一度切りの出会い、チャンスをいかにつかめるか?その瞬間にかけるパワーが桁違いに感じられる。いま楽しむと決めたら、その時間は徹底的に恥も外聞もなく楽しむ。瞬間のパワーがすごいから、素晴らしいパフォーマンスに出会ったときの反応もすごい、それが連鎖的に全体の空気となり、さらに素晴らしい音楽、時間、空間を生み出す。遠慮がないといえばそうなのかもしれないが、音楽、エンターテインメントに触れるということにおいて遠慮は必要ないもの。会場の熱気、熱狂をそのまま詰め込んだイマーシブオーディオのアルバムが誕生するのは時間の問題かもしれない。

📷作業デスク前方はこのようになっており、ボトムの3chのKH150の姿が見える。さらに2本KH150が置かれているが、これはボトム・バックサイド用で360RA作業の際に接続して使っているということだ。
音楽の持つ可能性はイマーシブオーディオの誕生により確実に進化する。表現のできるキャンパスが広がったことで、これまでと違う音楽がこれから次々と登場してくるだろう。イマーシブオーディオを楽しむ環境も今はイヤホンやヘッドホンだが、これはアメリカには合っていない。車社会であるがゆえに、カーオーディオへのイマーシブオーディオの普及が重要なポイントになるという。カーオーディオが進化すれば、運転をしながらでも新しい体験、楽しみとしてイマーシブオーディオがさらに普及するだろうということだ。ロサンゼルスのようにどこへ移動するのも車で、そして渋滞も当たり前、1時間程度のドライブは日常茶飯事という環境であれば、カーオーディオというのはひとつのキーワードである。「なんせ、いつも車の中にいるからね、、」と少々うんざりとした表情で話してくれたが、その一方でイマーシブオーディオにおけるリスニング環境の未来については明確なビジョンが見えている様子でもあった。
映画から普及が始まったイマーシブオーディオだが、固定された画面のある映画よりもヴィジュアルの存在しない音楽のほうがより自由であり、可能性が広がっているのではないかという。映画もイマーシブにより映像に描かれた世界の再現性というところに大きく寄与しているのは間違いないし、映像を印象づける強力なインパクトの一端になっている。しかし音にとって、大きな印象の差異を引き起こす映像がないということは、ユーザーそれぞれが音楽を自由に受け取り、それを楽しむことができるということでもある。映画音楽なども手掛けてきたからこそ感じる、音楽としてのイマーシブの可能性。二人のお話からは新たなフロンティアとして音楽表現の手法がより拡がったことを楽しんでいる様子がよく伺えた。
*ProceedMagazine2023号より転載
*記事中に掲載されている情報は2023年09月13日時点のものです。