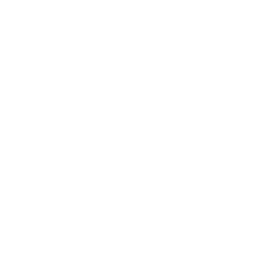«Headline
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

Apogee Symphony Studio Series:Launch Event with Bob Clearmountain at Power Station NYC 参加レポート

2024年10月9日、ニューヨークの老舗レコーディングスタジオである”The Power Station at BarkleeNYC” (旧Avatar Studios)で、Apogee社が主催するあるイベントが行われるという案内を受け取った。同社の新しいプロフェッショナルオーディオインターフェースのラインナップ“Symphony Studio Series”のローンチイベントということだが、案内をよく見ると、ボブ・クリアマウンテン氏の名前がある。同氏の紹介はもはや不要と感じるほど著名なグラミーエンジニアだが、これまでに手がけたAtmos作品を聴きながら、直々にイマーシブリスニングにまつわるトークやQ&Aの時間があるという。映画館は別としても、まだまだ音楽作品をAtmosで、さらに整った環境で聴くことができるチャンスは少ない。しかも名だたる名曲を手がけたエンジニア本人の解説が聞けるなんて、行かない理由が見つからない。というわけで、単身乗り込ませていただくことになった。
当日、19時のスタートを前にマンハッタンの西側中ほどにあるスタジオに着くと、ドリンクや軽食を楽しみながら話し込む多くの人で賑わっている。セッションが行われたのは同スタジオのアイコンとなっているSTUDIO A/LIVE ROOM。今回はProToolsからApogee Symphonyを通して、スピーカーはGenelecの協力で7.1.4のシステムが組まれていた。早めに良い席を取るつもりだったがセンターには予約席などもあり、やや後方、サークル内ギリギリの位置へ着席。 8341/ 8361を組み合わせたシステムの内側に何とか食い込んだ。

その後しばらくして、50から60ほどある客席もどんどん埋まり、いよいよセッションがスタートした。Apogeeのグローバルセールスマネージャー、グレッグ・チャン氏からのイントロダクションを経て、紹介されたクリアマウンテン氏はにこやかに挨拶し会場の大きな拍手に応えた。「知った顔も多くて逆にとても緊張するよ、このセッションの後もみんな友達でいてくれると良いんだけど・・」と笑いを交えながら、早速楽曲の試聴へ移っていった。全てAtmosミックスで、過去作品のリミックスから、新作もあるということだ。
一曲目はJoe Bonamassa “Pilgrimage”。これは実際にクリアマウンテン氏がAtmosでイマーシブコンテンツとしてミキシングした2枚目のレコードということだ。曲の最終盤、特徴的な足音のサウンドをリア側に配置することで、イマーシブならではの浮遊感、余韻が演出されているように感じた。短いイントロ曲ながら、初端からクリエイティビティが炸裂したミックスを体験し、オーディエンスの空気もやや興奮気味になったことが明らかだった。
次はROXY MUSIC ”Avaron”。会場からの大きな歓声と拍手で迎えられたこの曲を聴きつつ、いかにしてイマーシブ、ひいてはAtmosミキシングと向き合っているかという話題になる。同曲のボーカルは実際に今回のセッションが行われた部屋ずばりその場所で録音されたもので、本人も「これが私のキャリアにおいて大きな意味を持っていた」と語り、大事な作品であることが伺える。リリースは1982年だが、実は当時から「もっとスピーカーがあればいいのに」と感じていたとのこと。もっとリバーブやディレイを“配置”できる場所があればと思っていたということで、Atmosに取り組んだ経緯を次のように語った。「5.1chが25年ほど前に登場した際、妻(Apogee創業者のベネット氏)が、これをやるべき、次の大きなムーブメントになるだろう、と言っていました。彼女は常に技術の最先端にいるので、私たちは5.1chについても様々なことを試して、多くを学びました。そうしているうちにAtmosが登場し、これまでのサラウンドでの経験も経て即座にそのポテンシャルを理解しました。『ああ、これは本物だ。やらなくては』と直感したんです。」
実際のミキシングでの考え方については、このように語る。「同様のイマーシブミキシングをしたことがある人は、『なぜ特徴的な楽器をこんな場所に配置するんだろう』とか、『コーラスや曲のクライマックスをリアスピーカーに?』と懐疑的に思うかもしれません。そういった意見は理解できますし、場合によっては少々気を散らしてしまうことも考えられます。ただ、これまで聴いた曲に関しては、私自身は必ずしもそうではないと思っています。いずれも(サイドやリアに特徴的に配置される要素は)メインとなる部分ではなく、楽曲の要素として存在しています。例えばリア側に配置すると、聴く人を思わず振り向かせることができます。『あれは何だろう?あっちで何が起こっているんだ?』という感じで。言うなれば演劇を観ているようなものですね。劇場に座っていると、突然、後ろの方にスポットライトが当たって、サックスプレーヤーや素晴らしい歌手が登場するようなイメージです。」
文字だけを追うと奇を衒ったような考え方に聞こえるかも知れないが、実際に聴くと全くそんなものではないことが分かる。元々の作品を手がけたからこその楽器編成や楽曲のパーツへの解釈、ステレオからサラウンドを通して広くなったキャンバスの捉え方、それらを組み合わせて新たな演出が加えられる。当然、曲自体の本質やメッセージが変わることはないが、やはり「表現の幅」の次元が増えたとでも言うべきか、説得力のある楽曲体験だった。
その後もどんどん試聴が続いていったが、Atmosで大事なことについていくつか言及があった。一つ目はステムとエフェクト、特にリバーブの扱いである。クリアマウンテン氏は、Atmosをミキシングする場合には基本的にステムではなく本来のマルチトラックから始めることを推奨した。「ステムにはエフェクトがすべて組み込まれていることが多いからです。バックグラウンドのステムからでは、後々あまり広がりを持たせることができず、Atmosフォーマットがなし得るものを最大限に活用できないと思う」と説明した。リバーブを新たに追加したり、リバーブのエリアを広げたり、ディレイを異なる場所に配置することで、楽器に常に結びついているわけではなく、より没入感のある効果を生み出すことができるということだ。そのサンプルとしてBryan Adamsの“Run to You”より、間奏部分のギターのみを抜粋して、元の音とAtmosミックスに使用している音を順に聴き比べた。筆者個人としては今回のセッションで最も印象に残ったパートだったが、解説として次のように語られた。
「空気感を持たせるために、いくつかの異なるインスタンスを使います。例えば、サイドに別個のディレイのペアを用意し、それが後ろの別のディレイにフィードされ、再生成されるという感じです。そうすると、波のようなエフェクトが返ってきて、それぞれにより多くのリバーブがかかります」と、独自の手法を披露。「巨大なスタジアム、または渓谷の中にいるように感じたと思います。こうしてエフェクトを拡張していくことで素晴らしい体験にすることができます」と締めくくった。当然感動したのは筆者だけではない。我々オーディエンスの多くはただひたすら、元の音からここまで「体験」として変えることができるのかと感嘆するのみだった。
また同氏の名前を冠したApogee Clearmountain’s Domain(プラグインスイート)について「リバーブの他にディレイなど様々なものが含まれていて、今のところはステレオですが、いずれはもっと大きくなるでしょう」という発言もあり、今後の展開に期待したい。
さて、Atmosを扱う上で大事なことの二つ目に話は移る。センタースピーカーの扱いについてだ。「私にとってはセンタースピーカーは非常に重要で、“焦点”と捉えています。例えばボーカルはミックスの焦点であるべきだと考えていますし、ミキシングルームに入ってコンソールの前に座ったとき、目の前にあるのがセンタースピーカーですから、言うまでもなく重要な要素です。」
ただ、一般的に、ミックスが後に映画やテレビ番組で使われることになった場合を考慮してセンタースピーカーを使わない場合もあるという。ダイアログ用に空けておく必要があるからだ。ただし、そういった場合はおそらくリレコーディングミキサーによって全体的に再度ミックスされ別物になることも考えられるため、オリジナルのミックスとしてはセンタースピーカーを使う方が良いと考えていると語った。「(焦点が定まっていると)再生しながら部屋を歩き回っても、すべてが同じ場所にきちんと留まっているように感じられます。特にボーカルに関しては、移動してほしくない。私は、ボーカルがどこかに飛び出して動き回るのではなく、あくまでセンターに留まってほしいと考えています」と話し、またLFEについても、フルレンジのスピーカーの場合不要と思うこともあるかも知れないが、音楽ならドラムや管弦楽、シンセサイザーの低音、映画なら特に爆発音などを実際に体感できるという観点で効果的だ、とその重要性を解説した。
さらに、AtmosでのLFEの注意点として、バイノーラル設定について「さまざまなオプションがあって、オフ、近距離、中距離、遠距離の設定があり、それぞれの設定を調整できます。しかしLFEはグレーアウトされていて、変更できないんです。上げたり下げたりもできません。なので、LFEが自分の望むところにあるか入念に確かめなければなりません。スピーカーのセットアップによって音が変わる場合もありますからね」と付け加えた。
次に再生された曲はBryan Ferry ”I Thought”(2002年のアルバム’Frantic’より)。この曲をAtmosでミックスした理由として、曲の物語性がある種トリガーだったことを明かした。「ある男が自分の恋人と出会うという幻想についてのストーリーです。彼女は自分に恋をすると思い込んでいますが、曲が進むにつれて、実際にはそれが彼のエゴであることに気づきます。彼女が本当に自分に恋をするわけがないと理解し、彼はどれほどの愚か者だったのかを悟っていきます。曲の冒頭はセンタースピーカーから非常に小さく始まり、徐々に進行します。ブライアン・イーノのような音が多く重なり、頭の中で回り始めるのを感じることができます。彼は徐々に混乱していく感じです。望みもなく、『ああ、どうしよう・・』と思っているような…。とにかく、私はこの曲、この物語をAtmosで作る必要があると思いました。」
そしてこの曲に続き、クリアマウンテン氏が一部ミックスを担当していて、氏の良き友人でもあるというサウンドデザイナーのアラン・マイヤーソン氏が、映画『DUNE』(邦題「DUNE/デューン 砂の惑星」)のサウンドについて解説する動画が再生された。パンデミック中の制作だったこともあり、通常各地でオーケストラの各楽器を収録して後に合体する方法が一般的だったが、同映画の音楽を担当したハンス・ジマー氏は違う方法を選択した。マイヤーソン氏は「(ジマー氏が)ハイパーサウンドデザインモードに入った」と表現したが、例えばアップライトベースはベースとしての音に加えて、スラップで演奏する際に発生する特徴的な倍音や噪音もサンプル化された。そうして収録された各楽器やボーカルなどから、数として合計2000以上にも及ぶサウンドのライブラリを作成したという。さらにそのライブラリから短く音を切り出し、ピッチを変え、他にも様々な処理を施しながら異なるキーグループに分けるという壮絶な作業があったそうだ。
前述のBryan Ferryの楽曲からの一連の話題でクリアマウンテン氏が伝えたかったこととして述べたのは、「Atmosでミキシングする時はその作品に自分が入り込み、作品に対峙するに相応しい熱意と労力を持って、クリエイティブに取り組むべき」ということだ。音楽であれ映画であれ、物語を理解し、自分もその世界にどっぷりと浸かり、全体のデザインを組み上げていく。非常にシンプルでストレートなメッセージだが、まさに真理であり、試聴した作品にはその姿勢がありありと映し出されていた。

話はクリアマウンテン氏が手がけたライブ音源のAtmosミックスに移っていく。2022年に急逝したフー・ファイターズのテイラー・ホーキンスの追悼コンサートで、8万7千人の観客を抱えた超大型ステージでのライブ収録だ。自身が「多くのライブパフォーマンスの収録を手掛けてきましたが、これが私のキャリアの中でのハイポイント」と評するもので、「ライブにおけるイマーシブ体験としては、初めての完璧なアプリケーションとも言えます」と前置きし、同ライブで演奏されたQueenの”We Will Rock You”が再生された。
「ブライアン・メイとロジャー・テイラー、そしてフー・ファイターズのメンバー、さらにルーク・スピラーという素晴らしいシンガーも参加しました。ショーの前に彼らから伝えられたのですが、『イントロのパートでは4人のドラマーが演奏する』ということでした。
なので、当然ステレオではすべてのドラムが一緒に聞こえることになりますが、その話を聞いた瞬間、私は『これはAtmosでミックスするチャンスだ』と思いました。ステレオでの収録とライブストリーミングが主軸で、Atmosの話はそれまで出ていませんでしたが、このチャンスは逃せませんでした。ロジャー・テイラーのドラムが前に聞こえ、ルーファス・テイラーが後ろにいて、さらにはドラムのローディーがステージ袖で調整する音も聞こえて、周囲に囲まれているように感じるでしょう。これは面白い体験になると思いました。実際そうなったと思っています」と、ライブならではのリアルな体験をリクリエイトした意欲作であることを語った。確かにその説明のとおり、再生が始まると一瞬にして熱気が再現されるような感覚を覚えた。心地よい緊張感と高揚感で、誰もが知る同曲のシンプルかつアイコニックなリズムが、複数のドラムでエネルギーの塊のように身体に響く。これはAtmosでミキシングを経験したことがない筆者でも「やり甲斐があるだろうな」と一瞬で腑に落ちる素晴らしいコンテンツだった。
ちなみにこの時オーディエンスから、「かなり音圧の高い収録音源だったと思うが実際には作業中どのくらいの音量でモニターしているか?」という質問があった。それに対し、「実際にはかなり静かに聴いています。85dB以下、たぶん65dBくらい。そうすると、非常に大きな音に感じられるのです。低音量でもワクワクするようなエキサイトできる音にできれば、自然とボリュームを上げたときにも効果的になります。プロデューサーや他の人がいない限り、私は通常85dB以上で聴くことはあまりありません。」ということだ。
セッションも終盤に向かい、この後はオーディエンスとのQ&Aに移っていった。その内容をいくつか抜粋したい。
Q1)ヘッドホンでのバイノーラルでのモニターについて、通常どれくらいの時間を費やしていますか?
A1)ほとんど時間をかけていません。たまにチェックすることはありますが、スピーカーでモニターした方が音像の距離感が掴みやすいと思います。
Q2)すべての楽曲がイマーシブに適していると思いますか?
A2)いいえ、そうは思いません。いくつかの音楽ジャンル、例えばブルースなどは、基本的に高い密度を持たせたいので、音像を分離させたくない。一つのまとまったサウンドであるべきだと思います。もちろん合う楽曲もあるかもしれませんが、すべてのジャンル、すべての楽曲を無理にイマーシブにするべきではないと思います。
Q3)Atmosで制作する際、通常のステレオと比べて収録の際のマイキングに変化はありますか?
A3)それほど違いはないと思います。あるアルバムを制作したとき、プロデューサーがトライしてみようと言って各チャンネルにさまざまなアンビエントのマイクを加えて立てたことがありました。ただ、収録後に聴いてみると、実際のミックスにはあまり役に立たなかった経験があります。やはり、それよりもミキシングの段階で人工的に響きを足す方が、コントロールがうまくいくように思います。私は実際の空間のインパルスレスポンスを使用してリバーブをかけることが多いですが、ドラムなどの楽器には非常によくマッチします。またドラムに関してはオーバーヘッドや近め・遠めのマイクペアなど、いくつかパターンを用意するようにしています。
Q4)ステレオで録音されたクラシックなレコードをAtmosにリミックスしたものが多いですが、アーティストが特にAtmosで聴くために音楽を作ったレコードに関わったことはありますか?
A4)ええ、実は、マイケル・マーコート(Michael Marquart)と新作でAtmosの制作をしたことがあります。A Bad Thinkというバンドで彼は素晴らしい音楽を作っています。私たちはこれまで4枚のアルバムを制作しました。最初のアルバムでは、彼は5.1やAtmosについてあまり知らなかったのですが、5.1chでミックスしたものを聴いてもらうと、「素晴らしい!」と言って気に入ってくれました。それからは、彼の音楽やプロデュースのリファレンスとして、5.1chサラウンドやAtmosを意識して書くようになりました。実際、彼らはAtmosを意識した音楽を作っています。本当に良い作品です。
Q5)コンソール上でミックスバスのコンプレッションはどのように扱っていますか?
A5)カスタムのコンプレッサーで処理しています。それまで通常ミックスではステレオバスコンプレッサーを使っていたのですが、5.1chになった時あまりしっくり来なかったので、「これはなんとかしたい」と思うようになりました。SSLのG seriesのコンソールを使っていますが、パッチできるVCAが8つ空いていたので、コントロールのための電圧を使って他のVCAのスレーブにできないかと考えました。信号のレベルを少しブーストするためのオペアンプは必要でしたが、実際には非常にうまくいって、5.1ch用のバスコンプレッサーを作ることができました。しかし今度はAtmosになるということで再度、より複雑になりますが挑戦する必要が出てきてしまいました。幸運なことに私の優秀なアシスタントのブレンダン・ダンカンがSSLのステレオVCAカードが搭載されたユーロラックというものを見つけ出してくれて、それでさらに8つのVCAを追加することができました。全て繋ぎ合わせると16chのアナログバスコンプレッサーが出来上がった、という訳です。Apogeeのスタッフも協力してくれていくつかノブを取り付けてくれたので、サイド、リア、オーバーヘッドにどれだけのコンプレッションをかけるかを調整できるようになりました。全て別々に調整できるので、特にライブパフォーマンスのイマーシブミックスには非常に便利になりました。

こうしてあっという間に2時間弱に及ぶセッションは幕を閉じたが、最後にクリアマウンテン氏は「今日お話しした手法などは、あくまで私が試して上手くいったり気に入ったりしたことであって、皆さんに『これは絶対にこうしろ』とか、『こうしなくてはならない』などというつもりは毛頭ないことを強調しておきたいと思います。もっと違うアプローチが世の中にはたくさんあるはずです」と述べた。これだけの素晴らしい作品を世に送り出してきたにも関わらず謙虚な姿勢に感銘を受けると同時に、Atmosミックスのテクニックやイマーシブが可能にする表現にはまだまだ余地があると感じていることも理解でき、Atmosフォーマット、ひいてはイマーシブコンテンツへの同氏の期待の高さが感じられた。
セッションの後、短時間だったがタイミングを得て、自己紹介をしつつ直接クリアマウンテン氏本人と話をすることができた。物腰の柔らかい気さくな人柄で、快く写真にも応じてくれた。今回のレポートで、拙い文章表現ではあるが同氏のクリエーションの一端から発見やヒントがあれば幸いである。この機会を与えてくださった前田洋介氏に感謝の意を表して結びとしたい。ありがとうございました。
Nov. 2024 寄稿:佐藤えり沙
*記事中に掲載されている情報は2024年12月05日時点のものです。