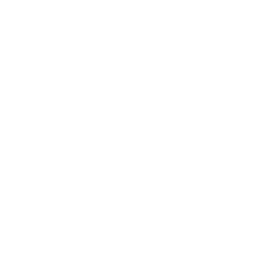«Headline
Author
前田 洋介
[ROCK ON PRO Product Specialist]レコーディングエンジニア、PAエンジニアの現場経験を活かしプロダクトスペシャリストとして様々な商品のデモンストレーションを行っている。映画音楽などの現場経験から、映像と音声を繋ぐワークフロー運用改善、現場で培った音の感性、実体験に基づく商品説明、技術解説、システム構築を行っている。

SOUNDTRIP 2023 / Apogee Studio / 製品開発現場におけるDolby Atmos環境

Apogee Electronics社が持つApogee Studio。本社に隣接するスタジオでのDolby Atmosへの取り組み、製品と連携して育まれるテクノロジー。アメリカでのDolby Atmosへの興味、関心などを含めてレポートしていきたい。Apogeeはデジタルレコーディングを牽引してきたレジェンドとも言えるメーカーであるが、改めてそのレコーディング業界における功績を振り返るところから始めていこう。
1985年に3人の創業者により設立されたApogee。正式な会社名としてはApogee Electronics Corpである。3名の創業者のうちBetty Bennettは、現在も同社の社長を務めており、Bob Clearmountainの妻としての顔も持つ人物である。今はAudio Interfaceメーカーとして認知されているApogeeだが、そのルーツはDigital Filterにある。デジタルレコーディングの黎明期である1980年代に、当時新しいリスニングメディアであったCDのデジタル歪みなど、デジタルメディア特有の問題を解決する技術をリリースしている。Apogeeの924 / 944 Anti-Aliasing Filterは、瞬く間に評価を得てリリース翌年の1986年には業界標準のデジタル・マルチトラック・レコーダーであったSONY PCM-3324、その互換機を製作していたMitsubishiのオプションとして採用されている。このフィルターは「冷たい」「硬い」と言われていたデジタル音声を、アナログライクなサウンドにすることができる魔法のようなフィルターであった。
次にリリースしたのが、AD-500 / AD-1000。このAD/DAコンバーターではUV22と呼ばれる画期的なディザーを登場させる。UV22ディザーは、その名前を見ることは少なくなったもののYAMAHAを始め多くの3rd Partyメーカーが採用した技術だ。Digital Filter、そしてディザーと画期的な技術を発表するApogeeはデジタル・オーディオの持つ持病のようなデメリットを、次々と過去のものへとしていった。
そして1997年にはAD-8000をリリース。Pro Toolsでのレコーディングがスタジオに浸透し始めた時期に登場したこの8ch AD/DAは、サウンドにこだわるスタジオの代名詞ともなっていた。当時、アナログレコーディングにこだわるエンジニアもAD-8000であればデジタルでも大丈夫、とPro Toolsへの移行を加速させた機材のひとつ。その後、Master Clock GeneraterであるBig Ben、ホームレコーディングに向けたEnsemble、Duet、さらにはiOS対応のONE、JAM、Micなどとターゲットを明確にした製品をリリースしていく。

📷往年のApogee製品ラインナップ。リリースした製品数は少ないものの、すべてが歴史を彩る銘機と呼ばれるのもばかり。1990年代のデジタルレコーディングを支えたAD-500/1000/8000は時代を代表するサウンドを作ったもの。その伝統のサウンドは現行の製品にしっかりと受け継がれている。左下のプラグインのようにUV22は様々な他メーカーの製品でも採用されディザーの重要性を業界に知らしめたApogeeの技術を象徴する製品だ。
このようにApogeeの歴史を振り返ると、時代を作った銘機が揃っていることがわかる。確固たる技術、サウンドへのこだわり、イノベーションを持った製品をリリースするメーカーであり、今日のデジタルレコーディングのベースとなる技術はApogee由来のものが数多く存在する。そのベースには、本社に隣接するApogee studioの存在が大きく関わってくる。実際のレコーディングの現場が機材を開発しているオフィスの隣にある。しかもそのスタジオをメインで使用しているのはBob Clearmountain氏であり、そこからのフィードバックを得て製品開発、チューニングを行っているということを考えるとApogeeの製品クオリティーの高さにも納得がいく。また、一部のエントリーモデルを除き、プロシューマ向けの製品はすべて本社で生産しているというのもApogeeのこだわり。一部のブティック・ブランド、ガレージメーカー以外でMade in USAというのは今や貴重な存在だ。
それでは、Apogee Studioの紹介に移りたい。本社の隣にあるApogee Studioは、Old Neveをメインコンソールに据えたレコーディングスタジオ。近年はライブパフォーマンスの配信なども行っているそうだ。このスタジオも7.1.4chのイマーシブ対応に改装がすでに行われていた。Old Neveのアナログコンソールに、7.1.4chのスピーカーセット。アンバランスに感じなくもないが、それだけイマーシブミックスの需要が高いということだろう。

📷Old NEVEのコンソールが据えられたApogee Studioのコントロールルーム。モニタースピーカーはNeumann KH310での7.1.4chとなる。もちろん、Audio InterfaceにはApogee Symophony mk2。Appleとの関係も深いApogeeらしく、Logic ProでのDolby Atmosミキシングのデモも見せていただいた。
スピーカーはすべてNeumann KH310で統一されている。1980年代〜1990年代にラージモニターとアナログコンソールでの作業を行ってきたエンジニアがNeumann KHシリーズを愛用しているケースが多いように感じるのは筆者だけだろうか?ラージモニターのような豊かなローエンドを持つこのシリーズ、特に3-wayのKH310がお気に入りだということだ。実際にそのサウンドも聴かせてもらったのだが、様々な機材が置かれたコントロールルームでのイマーシブ再生ということを考えると反射が多く理想的とは言えない環境ではあったが、Apogee Symphonyの持つストレートでトランジェントの良いサウンドとNeumann KH310の豊かなボリューム感により、直接音の成分が多く部屋の響きが持つ雑味をあまり感じることもなくイマーシブ再生を聴くことができた。部屋としてのアコースティックを大きく変えることは難しいが、このように機材のセレクトによりその影響を軽減できるということはひとつの大きな経験となった。
もちろん、イマーシブミキシングの際にNeveアナログコンソールの出番はない。このコンソールはステレオ仕様となるためモニターセクションとしての利用もできない。それでもレコーディングを行うということにおいて、誰もが憧れる素晴らしいサウンドを提供することに疑いの余地はないだろう。ミキシングルームを別に用意することが多いイマーシブのミキシングルーム。別記事でも紹介しているVllage Studioもイマーシブ・ミキシングのためのスタジオは、収録用の部屋とは別のAvid S6が設置された部屋である。
それでもイマーシブ対応を果たしている理由は、Apogee Studioが音楽制作のためのスタジオであるとともに、Apogeeの製品開発のための施設でもあるということにほかならない。単純に制作スタジオということであれば、合理的な判断の上で別にイマーシブ・ミキシングルームを作ることになるだろうが、Apogeeがイマーシブ制作の環境を持つということの意味として、Apogeeのプロダクトの使用感、機能のチェックなどにも利用するということになるからだ。
ここで使われているのはもちろん、Apogee Symphony mk2。そしてバージョンアップにより機能が追加されたイマーシブ対応のモニターセクション。そのテストヘッドとしてこの環境が活用されている。さらに、音質面であったり深い部分でのユーザー・エクスペリエンスを確認するために、このほかにも2部屋、合計3部屋のイマーシブミックス環境を整えている。部屋の大きさ、部屋の設備、接続される機材、音の環境、そういったことを様々なケースでテスト、検証のできる環境がここには揃っている。ユーザの目線での製品開発、使い勝手の検証、そういったことを即座にフィードバックできる環境を持っているということもApogeeならではと言えるのだろう。
もうひとつ用意されたイマーシブ環境のスペースを見ていく。こちらはGenelec the ONEで7.1.4chを構築した部屋。アメリカのスタジオらしく、遮音、吸音といった日本のスタジオのような音響設計は入っていない。正面の角に設置されたベーストラップと調音パネルが数枚設置されているのみである。この部屋はミキシングルームとしての操作デスクをミニマムにしている。PC、Audio Interface、Displayがデザインされたひとつのデスクに収められ、これだけでミキシングのシステムが完成している。
この部屋でもそのサウンドを聴かせてもらった。部屋自体の響きはあるはずなのだが、締まった低域とダイレクトに耳へ届く中高域。吸音は最低限なのに濁りを感じることのないサウンドには驚いた。低域に関しては、やはり床の影響が大きいのではないかと想像している。日本のスタジオは、遮音のために浮床構造を用いて外部からの音の侵入を防いでいる。そのために、部屋自体がその名の通り宙に浮いているような状態となっている。音というのは振動であり、その振動を遮断するということが遮音ということになる。アメリカのスタジオはどこも床はコンクリート。平屋の建物が多いロサンゼルスということもあり、地面からそのままコンクリートを流し込んだ床になっているのだろう。日本であれば、湿気を抜くためにも床下には空間を設けるのが常識となっているが、乾燥したアメリカ西海岸ではその必要が少ないのかもしれない。この床の安定感、重厚さ、そういったものが低域のタイトな響き、アメリカ西海岸のサウンドの秘密なのかもしれないと感じたところだ。
Old Neveのミキサーが鎮座するスタジオとは全く方向性の異なるサウンドではあるが、やはりここもApoogee Symphonyのサウンド。使い勝手はもちろん、そのサウンドキャラクターを確認するのに、これだけ異なった環境で聴き比べを行うことができるというのは、サウンドチューニングにとっても大きな意味を持っているのだろう。

📷リビングルームのような、開放感のある部屋に設置されたGenelecでの7.1.4chのスピーカーシステム。デスクは最小限のスペースにPC本体を含めて設置できるように設計されたカスタムデスクが置かれていた。アコースティックチューニングは最低限。音を聴きながらのチューニングの結果がこのような形で結実している。
最後に、片付いていないので、とかなり遠慮されていたのだが、ホームスタジオであればどのような環境になるか?ということをシミュレーションするためのミキシングルームを見せてもらった。ここでは、iLoudのスピーカーで7.1.4chが構築されている。イマーシブミキシングを行う上で、ミニマムな環境でのテストケースを検証しているということだ。このように、ユーザーの利用環境をシミュレートしながら、実際に作業をしてみてどうなのかというケーススタディを積み重ねていることがよく分かる。そして、次の制作環境としてターゲットとしているのが、すべてイマーシブ環境だということは特筆すべきポイント。アメリカでのイマーシブ制作の盛り上がりを強く感じずにはいられない。実際のところ、Bob Clearmountain氏へ過去に自身がレコーディングをおこなったヒットソングのイマーシブミキシング依頼が殺到しているということだ。このような新しいフォーマットへのムーブメントが感じられるのは本当に素晴らしい。過去作品のイマーシブミキシングも素晴らしいことだが、新譜、特にイマーシブを前提に制作された楽曲の盛り上がりも楽しみにしたい。
Apogeeの歴史、イノベーション、テクノロジーといったベースから、ユーザー目線での製品開発、イマーシブ時代の到来を感じさせるApogee Studioの進化。そのようなものを感じ取っていただけたのではないだろうか。この場で伝えたいことが数多く内容も多岐に渡ったが、このようなメーカー開発の現場での事例からも、アメリカでのDolby Atmos、イマーシブサウンドへの期待感が滲み出ていることが感じられる。是非ともこの感覚を共有していただければ嬉しいかぎりだ。
*ProceedMagazine2023号より転載
*記事中に掲載されている情報は2023年09月18日時点のものです。