«投稿
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

ROCK ON PRO PRESENTS Avid Creative Summit 2014 @SOUND INN 開催現地レポート!!

未来を紡ぐ百花繚乱のプロダクト、Network、Cloud、
あらゆる場所で私たちがつながる!
2014年5月15日、東京麹町に立地するSOUND INN Studio AにてROCK ON PRO presents AVID Creative Summitを開催、非常に多くのお客様にご来場頂きました。そのセミナー内容はほぼ全編をYou Tubeへすでに公開させて頂いていますが、ダイジェストにてその開催内容をレポートしていきます!

ROCK ON PRO presents AVID Creative SummitはAVIDのプロダクトを中心に、講師を招きお届けをしたセミナーセッションと、プラグイン・外部機器などを取り扱う協賛各社様によるブース展示で開催されました。ブース展示は総勢7社、それぞれ簡単にご案内するとM.I.D.様はSlate Pro RAVEN MTiを中心とした展示。このRAVENはRock oN店頭でご覧になった方も多いかもしれませんが、AES 2012での発表で世界中の注目を集めたタッチスクリーンを使った新しいDAW controller。ミキサーの操作だけでなく、編集操作もタッチスクリーンを使用してフィジカルに操作可能なプロダクト、会場でもその動作にお客様の注目が集まっていました。
MI7/Syntax Japan様はRMEを中心としたMADIのソリューション。すでに確立され、安定した技術であるMADIはその安定性とケーブル1本での64ch伝送という高い汎用性を併せ持ち、DAWのパワーが向上した現代だからこそユースフルな規格として脚光を浴びています。様々なコンバーター、MADI搭載Mic Preなどを展示していただきました。
TAC SYSTEM様はDirect Out Technologies社のMADI製品群。こちらの注目はもう一つの多チャンネル伝送技術として注目のAoIPであるRavennaとMADIのコンバーター。それぞれの特徴はありますが、相互につなぎ合わせることの出来るソリューションの登場はシステムアップの柔軟性を増すこと間違いありません。もう一つNTP Technologyも忘れてはいけません。こちらはDigilinkによるPro Toolsと直接接続も可能なMADI / Danteのコンバーターとなっており、様々な利用シーンに幅広く対応するプロダクトです。
BrainMusic様はいち早くAVID S6設置可能なAKA design社のスタジオデスクを展示。使い勝手の良さそうな機能性を持ったデスクにお客様からも多くのご反響を頂いています。
Formula Audio様はリバーブプラグインとして定番の地位を占めるAltiverbを開発するAudioEase社の製品群を展示。ご利用中のお客様も多く、現場レベルの質問が飛び交っていたのが印象的です。最近AAXに対応したのもTOPICでした。Media Integration 輸入事業部はWAVES,McDSP,Sonnox,SoundToy等様々な取扱プラグインを展示。その他にもEVE audioのスピーカー、輸入取扱いが開始されたばかりのLewittのマイクなど多彩な展示。AVID様はブース展示にもS6を持ち込んでいただき、S3Lと合わせて最新のコンソールプロダクトを展開。その製品詳細は、セミナー本編に譲ることとします。
Session#1はAVIDの製品群が中心となる「Eyes on AVID S6/S3/Protools Connect」定刻の開始時間にはすでにほぼ満員の盛況となりお客様の期待を感じながらのセッションスタートとなりました。先ずは、Avid APAC Director of Sales(Audio)のチャールズ・テタズ氏によるNAB 2014で発表となったAVID Everywhere、Pro Tools Cloudのご説明。通訳はAVID JAPANの三橋さんに行っていただきました。

AVID EverywhereはこれからAVIDの向かう将来、そしてAVIDが提案する未来のワークフローを表すメッセージ。AVIDはサーバー、NLE、DAWと今後ワークフローの中核となるプロダクトを持つ企業であり、これからは機能強化はもちろんだがワークフローの強化につながる『Cloud』『Archive』といった提案を行っていくということを表明しています。その一つがPro Tools Cloudであり、遠隔地の作曲家とミュージシャンがCloud Networkでつながり作業を共有していくというソリューション。ビデオチャット等のコミュニケーションツールがPro Toolsに組み込まれ遠隔地で同じセッションを共有し作業を行うことが出来るというまさに未来のワークフローを提案しています。NAB 2014ではステージ上でその実演も行われていたため、リリースまでもそれほど時間がかからないのではないかと感じさせる完成度を持った内容。
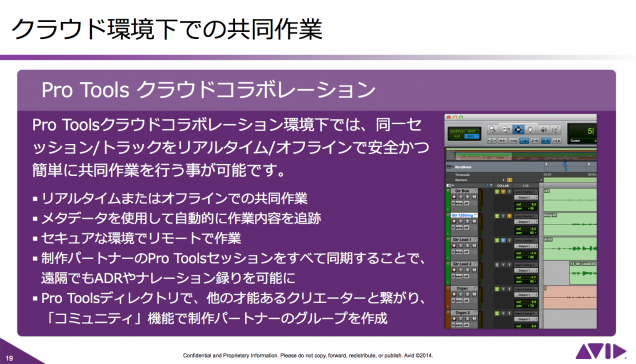
Pro Tools クラウド概要資料
NAB 2014で発表された事項の説明を引継ぎ、Avid Pro Audio Japan Sales Managerの常盤野 司 氏から『Archive』に関しての解説。ここでのトピックはPro Tools Sessionをパッキングする『PXF=Production eXchange Format』の発表。PXFはPro Toolsのセッションをアーカイブするためのフォーマットでレンダリングしたデータの保存や、フリーズトラック機能、セッションのプレビュー等アーカイブ向けの多数の機能を盛り込みます。また、Avidの他のアプリケーションとの共有、互換に関しても考慮して設計された、まさに次の世代へ『Archive』するための待ちに待ったフォーマットの登場です。過去のデータが開けなくなった、ということはこのPXFが解決をしてくれることとなるでしょう。
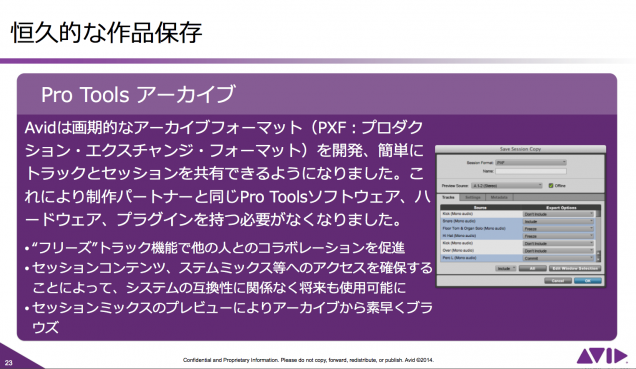
PXFファイル概要資料
そして、AVID Audio Aplication Specialist Daniel Lovell 氏とROCK ON PROのプロダクトスペシャリスト2名(洋介・赤尾)によるAVID S6を中心とするコンソールプロダクトの解説を行いました。Daniel氏は日本国内に常駐する初のAplication Specialist。このポジションは、次世代プロダクトの開発、バグフィックス、βテスト等を行うまさに開発チームの一員と言えるポジション。国内ユーザーの声が直接開発チームへと届けられる太いパイプが日本に置かれたと言っても過言ではありません。
セッション本編はS6の開発バックグラウンドにあるヒストリーの解説から。先ずはAVID ICONシリーズ。世界で最も成功したコンソール(なんと販売実績は5000台以上)となったICONはなぜここまで市場に受け入れられたのでしょうか?世界の音を取り扱う現場がTapeからDAWに取って代わられ、その背景から一番効率よくDAWを操作できるコンソールとしてICONは誕生し市場に受け入れられていきました。しかし、ユーザーからはもう少しコンパクトにならないか?モジュールで必要な部分だけを購入できないか?等多数の要望が寄せられていたのも事実です。もう一つのバックグランドヒストリーはAVID system 5。その登場はなんと1998年、すでにデビューから16年を経過したこのプロダクトはもちろん今でも現役です。今現在でも導入の話を聞くことができる現行製品。デジタル製品としては異例とも言える長寿の秘訣はどこにあるのでしょうか?それは、開発コンセプトの時点から既に先進的であったモジュール構造と、ソフトウェアベースのシステムにあると言えます。誕生当初、純粋なDigital Consoleであったsystem 5は2007年にHybridシステムと呼ばれる統合型のDAWコントロール機能を手に入れます。その特長はなんといってもLayout機能と呼ばれる、複数のDAWを同一の盤面に展開して操作可能という柔軟性。バックボーンにネットワーク構造を取り入れていたsystem 5だからこそ実現した機能であると言えるでしょう。
そして、ICON・system 5という大きな成功を納めた2つのプロダクトの血統を受け継いだ次世代型のコンソールが当日32fader仕様として展示したS6。Pro Tools専用設計だからこそ実現できたICONの高い親和性とコンソールメーカーが次世代のワークフローを考え実現したHybrid機能。これらの利点を全て盛り込み、ユーザーから得たフィードバックを活かし設計されたのがこのS6です。感覚的にフィジカルなコントローラーとして残さなければいけない部分(フェーダー、ノブ)と何度もボタンを押したり、メニューの階層を潜ったりするのではなく、スマートにタッチパネルでオペレーションを行い、これらをクリアに切り分けてコンパクトに再設計された製品。それぞれのモジュールは完全に独立しており、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なシステムアップが可能。もちろんソフトウェアベースの構成となっており、長期に渡りアップデートによる機能追加が行われ、system 5と同様に現場のニーズを満たし続ける製品となることでしょう。
また、今後予定されているS6のアップデート情報もここでは紹介していただきました。ICONで実現していたSpill Fader機能。これは1ボタンで、手元にGroupや、VCA masterなどを呼び出す機能。ICONからはもう一つ、プラグインパラメータをストリップのノブに展開可能なMAP機能。system 5の中心機能とも言えるLayout機能。非常に強力な追加が予定されています。これらはソフトウェアのバージョンアップで提供されます。今後も我々ユーザーの要望により、またワークフローの変化に追従し様々な更新が期待されます。
次のコーナーはS3Lを題材に、AVIDの持つ先進の機能をご説明。AVIDもAoIP=Audio over IPと呼ばれるネットワークオーディオの実現を果たしているメーカーの一つです。S3LではAVBと呼ばれる規格を採用、こちらも今後の展開が期待される技術です。そして、system 5、S6でも採用されるEuCon。DAWとコントローラーを接続するこのプロトコルもネットワークをベースとした非常に汎用性と柔軟性を併せ持った技術。S6&PT11の組合せではEuCon 3.0へとバージョンアップをしています。これによりS6の高度なVisual FeedBack、そしてDisplay Moduleに表示されるWaveformを実現しています。
最後のコーナーはこれからのソリューション、ワークフローをここまでにご紹介したAVIDのプロダクトとともに考えるというROCK ON PRO洋介からご提案のコーナー。音楽業界を考えると冒頭のPro Tools Cloudによるコラボレーションワークフローはまさに未来像でしょう。合わせて、AoIPによる柔軟なシステムアップ、Digital Mic等システムのデジタル化が大きな変革への道筋ではないでしょうか。これらの実現により作業環境から多くのストレスが排除され、より良い作業環境が成立するのではないでしょうか。
ポスト・プロダクションには、ファイルベース化による高効率化が求められると考えています。サーバーによるファイルシェアはもちろん、ファシリティーの共有による運用自体の効率化も求められる内容です。そのためには、KVM、Audio、Videoの回線にMatrixが必要となりますが、ここではそれらを実現するソリューションのご提案を行わせていただきました。
次は放送業界に向けたご提案として、作業の速度、確実性を求めたファイルベースでの高度に自動化されたソリューションワークフローのご提案。ここでキーワードとなるのがtranscoder。バックグラウンドで自動的に作業の工程を進めることが可能なエンジンを準備することで、作業効率の向上と確実性を確保することが可能です。最後に教育機関に向けたご提案。最新のソリューションワークフローを理解し運用が出来る人材の育成は今後の大きな課題。そのために必要な機材、ソリューションのご案内も行っているとお話をさせていただきました。
休憩を挟み行われた、セッション2は次世代の音響フォーマットであるDOLBY ATMOSの解説を、国内で初のダビングステージとなる東映株式会社デジタルセンターの畠山 宗之 氏とDOLBY JAPAN株式会社の中山 尚幸 氏にお話を頂きました。
先ずは中山氏よりDOLBY ATMOSがどのようなものなのか、どのようなスピーカー配置なのか、そしてその制作においてキーワードとなるBedとObjectの解説、必要なエンコーダーとしてRMUのご紹介をしていただきました。そして、畠山氏からはPro Tools上での設定などを含めてのATMOSミックス手法を詳細に解説、実際にスタジオのシステムと合わせてご紹介頂きました。使用されているモニターから、その配置、更には実際の制作工程を丁寧に追っていただき、まさに日々行われている現場でのワークフローを解説。
昨年秋のオープンから、まだ数名のエンジニアしか行ったことがないATMOSでのミキシング。その手法はまさに貴重な情報です。その詳細については是非とも公開されている動画をご覧頂きたいと思います。
最後に中山氏よりATMOSの世界市場での動向。このセミナー開催時点でATMOSでミックスされた作品は118作品以上、劇場は550以上、ダビングステージは55以上になっているとご紹介いただきました。
国内でも稼働中の劇場が6館、年内には10館以上になる予定であるとのコメントも。世界的にもATMOS作品は増え続けており5.1chフォーマットであるDOLBY Digitalの立ち上がりよりも速いペースで世界中に広がっているとのことです。ちなみに稼働中の映画館は関東では船橋、幕張、日本橋、平和島。関西では大阪、和歌山と各地に展開しています。
なお、立体音響ということでアクション等の派手な効果音などを想像される方も多いかと思いますが、ATMOSはあくまでも臨場感の向上を主眼に設計されたフォーマットであり、その高い臨場感を是非とも体感してもらいたいとお話を頂きました。今後続々とDolby ATMOS導入予定映画館が増えていきますので、是非とも一回体験をしていただきたいところです。
最後のセッションはエンジニア、ニラジ・カジャンチ氏をお迎えしてのボーカルレコーディングセッション。まずはニラジ氏のプロフィールのご紹介から。フィル・ラモーン氏を師徒してNew YorkのHit Soundでそのキャリアをスタート、ミックスよりもレコーディングが好きだとお話いただきました。そしてROCK ON Staffも知らなかったPro Toolsの便利なTIPSも。
まず初めのTIPSはどのようなレベルでレコーディングを行うのか、自身のRefernceをどのように設定するのかについてのお話。レコーディングにあたっては使用するアウトボードの美味しい部分を余すところ無く引き出すのがレコーディングのクオリティを上げる条件となります。様々な機材、また各々のノウハウもありますがニラジ氏はその経験からReferenceを-18dbに置いているとの事。ところが、デフォルトで設定されているProToolsのメーターにおける-18dbは不安になるほどの小さな振れ幅。またヘッドルームの確認も含めてレベル管理が非常に狭い範囲での確認となってしまい制作の効率を大きく損ないかねません。
そこでTIPSとなるのがProTools11より対応したメーターセッティング画面。Preferenceの右上にあるセッティングのPTメーターの0db表示を任意に設定可能となっており、ここを変更する事でレベル管理のしやすい表示を可能にします。
さらにその下に位置するColor Breakの設定を変更すれば、メーター表示色の切り替わる境目を変更する事が可能です。つまり、レコーディングの判断基準となるレベルの範囲を色分けすることができ、狙ったレベルの管理を一目で確認する事も可能。つまり、色の境目をハッキリさせてその範囲にレベルが振れていればOKという確実かつ簡潔なレベル管理方法が実現しています。
この手法でアウトボードが持つ一番のクオリティを確保したレコーディングを確実に行える事になります。それぞれの基準とするレベルはレコーディングを行う方それぞれのノウハウかと思われますが、それを管理する手法としてメーターの設定を行う事は、ジャンルを問わない応用範囲が広いTIPSと言えるのではないでしょうか。
セッティング自体はとてもシンプルなものですので、お手元のシステムでもすぐに導入する事ができます。多くの楽曲を集中的にミックス、そしてそのクオリティを確保するために効率を考慮して自身のワークフローにソフトウェアを適合させる。F1ドライバーがシートポジションを突き詰めるのと同じようなプロフェッショナルのこだわりを感じるTIPSでした。

続いて2つ目のTIPSとしてTrack Template機能の解説。数々のセッションを短期間に集中して行うというニラジ氏。しかしながら受け取るセッションによって含まれたセッティング環境も様々というのが実情です。スピーディーに自身のセッティングを行いセッションを円滑に進める事はエンジニアの抱えるストレスを大いに軽減することになります。
そこでニラジ氏が普段から行っているのがこの新規トラック作成時のTrack Templateに自身のプリセットを組み込む方法。自身のワークフローに沿ったプラグインやセンドなどが予め準備されたトラックを作成できるという非常に便利な機能です。
例えばプルダウンにあるFemale Vocalを選択すると写真のようにプラグイン、バスまでセッティングされたトラックが新規に作成されます。余計なオートメーションが残ってしまう事も無く、安心していつもの作業にすぐ取りかかれる。これはレコーディングセッションをスムーズに進める大きなポイントとなります。
実際の設定は、トラック作成、プラグインの挿し込み、バスの設定など自分のワークフローに沿った形で作り、これをFile→Export→Selected Tracks as New Sessionを選択。これをDocumentsフォルダ内のProTools→Track Presets→Audioのフォルダに格納します。Documents内のProToolsフォルダに保存しないといけないこのがポイントです。ちなみにTrack PresetsとAudioはデフォルトでは存在しませんので、この名前の通りに自分で作成することとなります。
そしてもう一作業が肝心です、セーブされたファイルは「〜.ptx」ですがこれを「〜.ptxt」に変更。この後表示されるポップアップでも「.ptxt」を選択します。拡張子にテンプレートを意味する「t」を加える事で新規トラック作成のプルダウンにテンプレートとして表示されるようになります。
これで設定は完了。再起動もすることなく、再度新規トラック作成をしてみると表示がされます。自身のシステムに設定をしておけばどのスタジオでも同じ環境・プラグイン・レイアウトでワークフローを即スタートする事ができます!ちなみに、1つのトラックだけではなく、複数のトラックを1つのテンプレートとして覚えさせることができるのでドラムのレコーディング用のチャンネル、ドラムマスターなどを覚えさせると非常に便利だとのこと。会場でも1名の方しかこの機能は知らなかったという非常にレアな機能。もちろんマニュアルにも載っていません。

そして注目のボーカルレコーディング。ゲストボーカリストにマヤ・ハッチさんをお迎えし、なんとコンソールの正面に設置されたマイクでヘッドフォン無しでレコーディング。セッション内ではスタジオ側でしたがコントロールルームでボーカルを録音するという想定。左右のスピーカーからの低域をキャンセルする位置へ狙ってマイクをセッティングすることで、ほとんどモニターと当たらないレコーディングが実現できるという実践。録音したトラックをソロにして再生も行いましたが、驚くほど少ないカブリで録音されていました。これには、会場のお客様もかなり驚かれた様子です。
やはり国内でのボーカルダビングといえば、遮音をきっちりとしたブースでヘッドフォンをしてというのが常識になっていますが、アーティストとのコミュニケーションなどを考えるとこの手法は是非とも試してもらいたい方法だと感じました。そして、更にかぶりをキャンセルする方法やマイクをセットするポイントの探し方などをご解説いただきました。
それ以外にも、Pro Tools 11になってそのサウンドの変化によりセレクトするアウトボードも変化したことや、お気に入りの機材の話などをしていただきました。非常に興味深いお話が満載のセッション。こちらも動画公開されていますので是非ともご覧ください。また、Web上でも改めて解説をアップ予定です!
3つのセミナーセッションの後には、懇親会を行わせていただきました。ブース展示をしていただいた各メーカーの方もご参加いただきアチラコチラで濃い内容の会話が飛び交っていたのが印象的。この記事をお読みの皆様も、動画を見てのご感想、ご質問お気軽にお寄せ下さい。出来る限りお答えします。また、末文になりましたが今回の開催にあたっては関係各社様より多大なるご協力、ご尽力を賜りました、誠にありがとうございました!
そして、この先のAvidソリューションはまさしくグローバルな規模感でEverywhereを実現していくことが実感できました、クリエイターの制作環境もProTools Cloudによって海を越えて行く、世界サイズでのコラボレーションが新たなミュージックシーンを作り上げて行くのかもしれません。可能性を更に拡げる未来を見据えたプロダクトの登場に期待で胸が沸き立ちます!今後もROCK ON PROでは皆様に有用なインフォメーションをもたらすイベントを開催して行きます!ご期待ください!
講師プロフィール
 ■1st Session
■1st SessionDaniel Lovell(ダニエル ラヴェル)氏(AVID)
Daniel James Lovell
Avid Audio Application Specialist
1979年6月16日 ニュージーランド、オークランド生まれ
1998年 Music and Audio Institute of New Zealand
Music Production and Audio Technology課程をMerit Passにて卒業
1999-2008年 Auckland AudioにAssistant-Engineerとして入社
その後Head Engineer and Technical Managerとなる。
2008年~ Freelance活動を開始、EngineeringとStudio Integrationを行う。
2009年~ Fairlight Japanに入社
Fairlight Japan Technical Support, Application Development and Testingとして活躍。
2012年~ Avid Technologyに入社
Avid Japan Application Specialistとして活躍の傍らFreelance Engineer and Sound Designerとしても活動を続けている。
 ■2nd Session
■2nd Session畠山 宗之 氏(東映株式会社)
2005年 東放学園音響専門学校 卒業
2005年 株式会社IMAGICAディオ 入社
TVCMの音声収録、MAスタジオエンジニアとして勤務。
2007年 株式会社ミディアルタエンタテインメントワークス 入社
映画作品におけるダビングスタジオエンジニアとして勤務。その他にもレコーディングやアニメーションのアフレコ等様々なジャンルのスタジオオペレートを担当。
2011年 東映株式会社 デジタルセンター 入社
映画作品におけるダビングスタジオエンジニア、リレコーディングミキサーとして勤務。2013年10月に完成稼働した、新ダビングステージ計画に携わる。
Pro製品営業部 コンテンツ技術担当 シニア・テクニカル・マネージャ
1983年レーザーディスク株式会社(後のパイオニアLDC)入社
レーザーディスクの品質管理やレーザービジョンフォーマット関連業務に従事。
その後DVDフォーマットやDVD-Video/Audioディスク制作を担当し、
2000年にDolby Japanに転職。コンテンツ制作に関する技術サポートと
Pro用製品のサポート、劇場音響調整を担当。
 ■3rd Session
■3rd SessionNeeraj Khajanchi(ニラジ カジャンチ)氏
マライア・キャリー、ボーイズIIメン、ジャヒーム、ヨランダ・アダムス、ケリー・ローランド、セリーヌ・ディオン、ランディー・ジャクソン、ボビー・バレンティノ、ティンバランドなどの海外一流アーティストをはじめ、Ai、中川翔子、三浦大知、福原美穂、ゴスペラーズ、伊藤由奈、鈴木雅之などの国内アーティストまでを幅広く手掛ける今最も多忙なレコーディング&ミキシングエンジニアの一人。
 ◎Guest Vocalist
◎Guest VocalistMaya Hatch(マヤ・ハッチ)
マヤ・ハッチ
1985年8月18日、アメリカ・ワシントン州・シアトル生まれ。 弱冠12歳にしてNHKのスタジオ収録に参加。13歳の時、TBS系列のオーディション番組「チャンスの殿堂!」に応募し、約14,000人の中から選び抜かれた4人のうちの ひとりとして6ヶ月間に渡り登場。国内外において数多くの賞を受賞。2009年「マイ・フーリッシュ・ハート」でデビュー。2010年BSフジの人気番組「Beポンキッキ」に、歌のお姉さんとしてレギュラー出演。これを機会にニューヨークから東京に拠点を移す。2011年ラックス・シャンプーのCM起用。そのCMソングが話題となり、ロングバージョン版「Grow Your Beauty」がEMIミュージック・ジャパンのコンピレーションアルバム「Jazz Now」に収録。2013年にはロン・カーターとの共演を果たし、現在はEXILE ATSUSHIのバックコーラスを務め、さまざまなジャンルを幅広くこなす本格的シンガーとして注目を集めている。




























