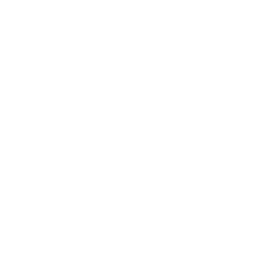«Works
Author
澤口 耕太
広範な知識で国内セールスから海外折衝、Web構築まで業務の垣根を軽々と超えるフットワークを発揮。ドラマーらしからぬ類まれなタイム感で毎朝のROCK ON PROを翻弄することもしばしば。実はもう40代。

株式会社角川大映スタジオ様 / 最新かつ最大規模のDolby Atmos Cinemaダビングステージ
『静かなる決闘』『大怪獣ガメラ』『Shall we ダンス?』といったヒット作が生みだされ、近年では高精細ディスプレイを使用したバーチャルプロダクション事業も手がける角川大映スタジオ。国内で唯一、自社に美術部を持つことでも有名な同スタジオだが、意外にもダビングステージの誕生は2011年と比較的最近のこと。このダビングステージにオープンから13年を経てついに大規模な改修が施された。待望のDolby Atmos Cinemaへの対応をはじめ、生まれ変わった本スタジオに込められた優れたノウハウを紐解いていきたい。
今回の角川大映スタジオダビングステージ改修においてもっともエポックメイキングな点といえば、何よりもDolby Atmos Cinemaへの対応ということになるだろう。国内では、東映デジタルセンター、グロービジョンに続く3部屋目のDolby Atmos対応ダビングステージの誕生になるが、デュアルヘッド72フェーダーのS6を備えた角川大映スタジオは現時点で最新かつ最大規模のDolby Atmosダビングステージということになる。Dolby Atmosへの対応にあたって新たに天井へのスピーカー設置が必要になるため、遮音壁の内側、スクリーン裏のフロントバッフルを除き、ほぼすべての内装意匠を解体してイチからの工事が実施されているほか、フロントLCRを除くすべてのスピーカー+サブウーファーもDolby社のレギュレーションに基づいて新規導入されるなど、まさに生まれ変わったと言って過言ではない大規模な改修となっている。

📷天井と壁面にずらりと並んだサラウンドスピーカー。「Dolby Atmos Theatrical Studio Certification Program Requirements」に基づいて、サイドが左右壁面に7本ずつ、ハイトが天井左右に7本ずつ、リアが背後壁面6本の合計34本のサラウンドに加え、サラウンド用サブウーファー4本が使用されている。
同じDolby Atmosといっても、家庭での視聴を前提とするDolby Atmos Homeと、映画館での視聴を前提とした制作となるDolby Atmos Cinemaでは、Dolby社のレギュレーションを満たすために求められるスピーカーシステムがまったく異なっている。ベッドチャンネルに対して1対1の関係でスピーカーを配置するDolby Atmos Homeに対して、Dolby Atmos Cinemaでは映画館と同様にディフューズ・サラウンドを使用することで面によるサラウンド環境の再生を行うということになる。家庭よりもはるかに広い映画館においては、視聴する位置による音響体験の差を極力なくすことが求められ、作品の音響制作に関わる最終段であるダビングステージでは、その環境を再現することが必須というわけだ。

📷ダビングステージのフロント、透過スクリーンの裏に設置されたLCRは既存のJBL 5742+サブウーファーJBL 4642Aを残している。LCR用のアンプはステージ裏に別途ラッキングされているのだが、今回の更新に伴い、スピーカーケーブルも試写室と同じBELDENに更新されている。
必要なスピーカーの本数はDolby社の「Dolby Atmos Theatrical Studio Certification Program Requirements」という文書に記されており、部屋の横幅と前後の奥行きに応じて、リアサラウンドとサイドおよびハイトスピーカーの本数が細かく指定されている。今回の角川大映スタジオの場合、サイドが左右壁面に7本ずつ、ハイトが天井左右に7本ずつ、リアが背後壁面6本の合計34本のサラウンドに加え、サラウンド用サブウーファー4本が使用されることとなった。ベース・マネージメント用に設置されたこれらのサブウーファーは天井の四隅から少し内側に入ったあたりに設置された。
既存流用となるフロントのJBL 5742に合わせ、サラウンドスピーカーもすべてJBLで揃えられている。基本的にはJBL 9310が採用されているが、カバーエリアの関係でハイトの一部にはJBL AM5212/00が使用されることになった。カバーエリアやスピーカーの設置角度に関してもDolby社の厳密な規定が存在しているのだが、このレギュレーションで興味深いのは、すべてのスピーカーをミキシングポイントとなる1点に向けるのではなく、一部のサラウンドスピーカーはCMA(Critical Mix Area)と呼ばれるミキシング作業をおこなうエリアの四隅または辺縁に向けるよう指定されている点だろう。このあたりも、シネマ制作ならではの仕様と言えるのではないだろうか。
もうひとつ、Dolby Atmos HomeとDolby Atmos Cinemaの大きな違いをあげるのであれば、ソフトウェア・レンダラーが異なっていることだ。シネマ・レンダラーでは、Cinema roomという、ディフューズ・サラウンドを構成するためのスピーカー・アレイ設定ウィンドウのほか、 レンダラー内部でベースマネジメントを行う機能が搭載されている。シネマ・レンダラーは市販されておらず、手に入れるにはそのダビングステージがDolby社の認定を受けなければならない。ベースマネジメントを除くEQ / Delayといった電気的な補正はBSS BLU-806。角川大映スタジオにとって使い慣れたAudio Architectを使用している。シネマ制作においては、Dolby Atmosだけではなく、従来の5.1や7.1サラウンド制作も当然存在する。そうしたフォーマットの違いごとにプリセットを作成し、作業内容に応じて切り替えて使用する形だ。
後に詳述するが、今回の角川大映スタジオのシステム構成はMTRX IIとDanteをフル活用した非常にシンプルなものになっている。A-Chainのすべての音声信号はMTRX IIからDante信号として1本のLANケーブルで出力され、ネットワークスイッチを介してB-Chainの入口となる2台のBLU-806に接続されている。ここで電気的な補正(スピーカーマネジメント)を施された音声は再度Danteネットワークへデジタルのまま送られ、RME M-32 DA Pro II-DでDA処理がおこなわれ ている(Dante 対応モデルは国内非取扱)。DAコンバーターは複数の機種を試したうえで、RMEが選ばれている。DAまでの経路において可能な限りフォーマット変換を避けシンプルなシグナルフローとすることで、個々のサウンドの解像度・明瞭度を向上させたいという想いが反映されたシステム構築となる。
DAされた音声は、Crown IT5000HDとDCi 8|600 DAからなるパワーアンプ群に送られる。フロントLCRとすべてのサブウーファーがIT5000HD、サラウンドスピーカーがDCi 8|600 DAという受け持ちだ。 ちなみにそれぞれ、IT5000HDはAES、DCi 8|600 DAはDanteでも接続されており、M-32 DA Pro II-Dをバイパスした信号を受け取ることが可能。万一、DAまでの経路に不具合があった場合にリダンダントとして機能させることが可能になっている。

📷マシンルームの様子。ダクトの下に見えているのが映写機NEC NC2000C。システムからの映像出しは作業に応じてEX Pro ToolsのVideo Trackと、Media ComposerとのSatellite Linkが併用されている。
もうひとつの大きな変更点は、AMS Neve DFC GeminiからAvid S6への音声卓の更新だ。素材の仕込み段階からすでに作業の中心となっているPro Toolsとの親和性の高さに加えて、今回の改修におけるテーマのひとつであるクリーンで解像度の高いより現代的なサウ ンドを目指すという方向性が大きな決め手になったようだ。そのS6は、国内のシネマ制作ではスタンダードとなりつつあるデュアルヘッ ド、72フェーダー、5ノブという仕様。日本音響エンジニアリング製作の特注デスクによって設置されている。そして、Dolby Atmos対応ということで、これも国内では多数の導入がある移動可能な特注ボックスに収められたJoystick Moduleを備え、さらに、国内初の導入となったPost Moduleが採用されている。

📷特注デスクに収められた72フェーダーのAvid S6。Master Moduleは盤面の中央に置かれている。一見シングルヘッドに見えるが、左側の離れた位置にふたつめのMaster Moduleが設置されている。
デュアルヘッドは1つのシステムにMaster Moduleが2基ある仕様(システムIDはMaster Moduleに紐づいているため、ライセンスとしては2つのシステムを1箇所で使用しているという形)。S6で1つのMaster Moduleが掴めるのは64フェーダーまでのため、72フェーダーという大規模な盤面を実現するにはデュアルヘッドの採用は必須となる。しかし、それよりも重要なのはデュアルヘッドを採用することで、S6の盤面を完全に2つの異なるエリアに分割することができるということだ。映画制作のダビングにおいてはひとつのシーンで同時に様々な音が鳴るため、セリフ、効果音、音楽のように、それぞれ各グループを担当する2〜3人のミキサーが同時に音声卓で作業をするということが一般的。デュアルヘッドを採用しておけば、どちらのMaster Moduleがどこまでのモジュール列を掴むのかがあらかじめ確定されるため、機能的にも視覚的にも各ミキサーが作業するフェーダーを明確に切り分けることができる。
2つのMaster Moduleの内の1つめは72フェーダーを構成する9モジュールを4:5に分割する位置、つまりサーフェスの中央に設置されているが、角川大映スタジオの大きな特徴は、2つめのMaster Moduleが72フェーダーから約1人分の作業スペースを隔てて離れた位置に設置されていることだ。センターのマスターフェーダーを挟んで左側には、セリフのミキサーが、右側には効果音のミキサーがという想定で構成が組まれている。
この、2つめのMaster Module付近はスタジオエンジニアの作業スペースとして想定されており、ここに国内初の採用となるS6 / S4 Post Moduleが並べて配置されている。このPost Moduleだが、その名称とは異なり、いわゆる国内で言うところのポストプロダクションというよりは映画ダビングに特化した機能を持ったモジュールだ。 モジュールにはトグル切り替えが可能なパドルが並んでおり、これでダバーへ流し込まれる各ステムの再生 / 録音をワンタッチで切り替えることができる。また、S6システムにPost Moduleが含まれていると専用のメーターを表示することができるのだが、このメーターではメインのアウトプットに加えて、 各プレイアウトからの出力を一覧で監視することができる。ちなみに、Post Moduleの前方に設置されたDisplay Moduleはデスクに直接挿さっているのではなく、イギリスのスタジオ家具メーカーであるSoundz Fishyが製作しているS6 Lowered Displayというアタッチメントを使用してデスクに埋め込まれている。デスクはその他モジュールが埋め込まれた部分と同サイズで製作されているので、例えばMaster ModuleとPost Moduleの位置を入れ替えるようなことも可能になっている。
今回のダビングステージ改修にあたっては、システム設計においても解像度の向上がひとつのテーマとなっている。そのための手法として検討されたのが、システムをシンプルにすることでシグナル・パスを最短化するというものだ。
AMS Neve DFC GeminiやEuphonix System 5といったDSPコンソールからAvid S6への更新においては、大きく分けてふたつの方針が考えられる。まずは、ミキサー用のPro Toolsシステムを導入し、S6を従来のコンソールと同じくミキサーとして使用する方法だ。プレイアウト用の各Pro Toolsからの信号はいったんミキサーを担うPro Tools MTRXに集約され、これに接続されたPro ToolsをS6で操作することでDSPコンソールを使用していた時と同じ、再生機→ミキサー→録音機、というワークフローを再現できるだけでなく、必要に応じてPro Tools内でのインボックス・ミキシングも活用することができるが、当然システム規模は大きくなり、その分信号経路も複雑になる。
角川大映スタジオが採用したのはもうひとつの方針、各プレイアウトPro Toolsが1台のMTRX IIを介しダイレクトにDubber Pro Toolsに接続される構成だ。システムの構成をシンプルにすることで 、音声信号は異なる機器間での受け渡しや、それに伴うフォーマット変換によるロスを最小限に抑えながら、最短経路のみを通ってB-Chainまで到達することができる。
ダビングステージに限らず音声を扱うスタジオの機器構成にあたっては、いくらシグナル・フローをシンプルにしたいといっても、Pro Toolsからの信号だけを出せればよいわけではなく、ハードウェア・エフェクターや持ち込み機材などの外部機器との接続、メーターやヘッドホンへの出力などの様々な回線が本線の音声信号系統に加えて必要となる。そうした多数のデジタル信号を同時に扱うことを可能にしているのがPro Tools MTRX IIだ。初代MTRXではDanteがオプション扱いだったため、ダビングステージのような大規模なシステムを初代MTRXで実現しようとした場合は、オプションカード・スロットをほかの拡張カードと取り合いになってしまうという課題があった。どうしても2台のMTRXが必要になってしまう。MTRX IIでは初代でオプション扱いだったDante I/O(256ch)とSPQ機能が本体に標準搭載されたことで、7基のDigilink I/O CardでPro Tools接続したとしても、その上でMADI 3系統(本体1系統、オプションカード2系統)とDante 256chという豊富な数の回線を外部とやり取りすることができたというわけだ。
角川大映スタジオでは、プレイアウトとしてDialogue、Music、SE-1、SE-2、EX、そしてレコーダーとしてDubberが1台からなる合計6台のPro Toolsシステムが運用されている。すべてMac Proによるシステムで、EXがHDX2仕様、その他はすべてHDX3仕様となっており、HDXカードからDigiLinkケーブルで1台のMTRX IIに直接接続されている。DialogueとDubberがHDX2枚分(128ch)、Music・SE-1・SE-2がHDX1枚分(64ch)ずつ、MTRX IIのオプションスロットに換装された7枚のDigilink I/O Cardにつながっており、EXはMTRX II本体の2基のDigiLink ポートに接続されている。MTRX IIの残り1基のオプションスロットにはMADIカードがインストールされており、オンボードのMADIポートと合わせて、RME製 MADI-AD / DA / AESコンバーターを介してアナログ / デジタルのパッチに上がり、アウトボード、持ち込み機器の接続用のトランク回線として使用されている。DanteはB-Chainへの送り出しのほか、TASCAM ML-32Dを介してメーター送りなどの回線として使用されている。
MTRX IIのもうひとつの特徴が、国内では2023年秋頃からリリースされているThunderbolt 3モジュールだ。オプションカード・スロットとは別に用意されたスロットに換装することで、Mac-MTRX II間で256chの信号をやり取りすることが可能になる。Thunderboltと聞くと思わず「MTRX ⅡがNative環境でも使える!」という発想になりそうだが、今回のシステム設計においては、RMUの接続をPro Toolsが接続されているMTRX Ⅱへダイレクトに接続することができるということになり、RMU用のAudio I/Fが不要になる。つまり、RMUを含めたすべてのPCがダイレクトに1台のMTRX IIに接続することができる、ということになる。
RMU含め7台のPCからの640chの信号と、ユーティリティーのDante、MADIの320chという信号を1台で取り扱っていることとなる。すべてをこのMTRX IIに集約することで、非常にシンプルなシステム構築となっていることがおわかりいただけるだろう。
各Mac Proには、持ち込み機材用の入出力やヘッドホンアウトを確保するためのI/Oも接続されているが、ダビング作業における音声信号の本線としては、5台のプレイアウトと1台のDubber、そしてRMUという7台のMacが1台のMTRX IIに集約されており、そして、 このMTRX IIからDante1回線ですべてのアウトプットがB-Chainへと出力されている。スペックとして理解はしていたが、実際に現場で動いているところを目の当たりにすると、MTRX IIの柔軟性と拡張性の高さに改めて驚かされる。
今回のダビングステージ改修にあたって、角川大映スタジオがこだわったもうひとつの点が同期系統の刷新だ。このダビングステージでは、24fpsだけではなく23.97fpsなどの様々なフレームレートを持った動画素材を扱う機会があり、音声ファイルにしてもダイアログは48kHz、音楽は96kHzなど複数のサンプリング周波数の素材を同時に扱う場面は多い。こうした状況となる中、多数の機器へ異なるフォーマットの同期信号を1箇所で管理できるようなグランドマスターが求められていた。
そこで採用されたのが、Brainstorm DXD-16。国内では放送局への導入が多い機材だが、ハウスシンクのマスターとしてだけではなく、GPSクロックを受けてのPTP出力が可能ということから中継現場で採用されるケースも多い。受けのMTRX II、出しのDXD-16とでも言うべきか、音声システムにおけるMTRX IIと同様、DXD-16もあまりにも多機能・高機能であるため、その特色を簡潔に解説することは難しい。GPSクロック、PTP v1/v2、10MHz、Video Reference、WC、マスターにもスレーブにもなれるなど、およそクロックに求められる機能はすべて備えていると言っても過言ではない。
実は今回の改修における機材選定にあたっては、B-Chainの音質に大きな影響を与えるDAコンバーターはもちろんだが、マスタークロックの試聴デモも実施されている。国内で入手できるほとんどのマスタークロックを試聴した結果、DXD-16が選ばれたというわけだ。ワークフローの効率化と解像度の向上を高い次元で両立したいという強い熱意を感じるエピソードではないだろうか。国内で入手できるPTP対応機器の場合、GPSシグナルが必須という機器が多く、自身で同期信号を生成するジェネレーターとしての機能を持たないものが多いのだが、DXD-16は自分自身がマスタージェネレーターとなることが可能で、角川大映スタジオではその精度をさらに上げるために内部の発信機をOCXOにグレードアップするオプションを追加している。
角川大映スタジオのダビングステージではこのDXD-16のインターナルOCXOをマスターとして、10MHz、1080p/24fps・NTSC/29.97fpsのVideo Reference、48kHz AES、96kHz WCの全信号を同時に出力しており、DanteネットワークのPTPマスターとしての機能も担っている。
このダビングステージで特徴的なのは、音質の向上を意図して10MHz信号が大きく活用されているところだろう。DXD-16は16個の各出力から同時に異なるフォーマットの同期信号を出力できるのだが、そのうちの半数である8系統を10MHzに割いている。1つはパッチに上がっており、もう1系統はBrainstorm DCD-24に接続、システムへのWCはここで再生成して分配されている。そして、残る6系統はすべてAvid Sync Xにダイレクトに接続され、各Pro Toolsシステムの同期を取っている。SYNC HDからSync Xへの進化において、この10MHz信号への対応は非常に大きなポイントだ。10MHzでPro Toolsシステムの同期を取るというのは、システム設計の段階で今回角川大映スタジオが大きなポイントとしていたところだ。
今回の改修にあたっては、Dolby Atmos Cinema対応や音の解像度向上といったサウンド面だけではなく、居住性の高さも追求されている。内装工事と音響施工を担当したのは日本音響エンジニアリング。 ダビングステージというと、黒やチャコールといった暗い配色の部屋をイメージすることが多いと思うが、生まれ変わった角川大映スタジオのダビングステージは非常に明るく開放的な雰囲気に仕上げられている。作品によっては1、2週間こもるということも珍しくないということで、長期間にわたる作業になっても気が滅入ることのない居心地のよい空間にしたかったのだという。「和モダン」をコンセプトにデザインされた部屋の壁面には日本伝統の組子細工を取り入れた照明が配されており、暖かな色合いは訪れる者をやさしく迎え入れてくれるようだ。壁面に灯りがあることで圧迫感のない開放的な空間を演出するとともに、日本音響エンジニアリングによれば、組子構造が透過面となることで結果的に音響的な寄与もあったそうだ。
Avid S6の設置は特注デスクによるもので、こちらも日本音響エンジニアリングによる製作。フェーダー面とデスク面が同じ高さになるようにS6が埋め込まれている形で、すでに述べた通り2つめのMater Moduleが離れたアシスタント席に設置されているのが特徴だ。この特注デスクは木材のもともとの色合いを生かしたナチュラルなカラーで、従来のイメージと比べるとかなり明るい印象を受ける。こうしたところにも、明るくあたたかな空間にしたいという強い想いを感じる。
角川大映スタジオには以前のダビングステージと建築面で同じ構造の試写室があるのだが、試写室には客席があるため、以前のダビングステージに比べて少し響きがデッドになっており、音の明瞭度やサラウンドの解像度という点でダビングステージよりも優れているように感じていたという。今回の改修にあたって、この響きの部分を合わせたいというのも音響における角川大映スタジオの希望だったようだ。
今回はDolby Atmosへの対応ということで、従来は存在しなかった天井へのスピーカー取り付けが必要であり、加えてDolby Atmosに最適な音響空間にするためにスクリーンを含むフロント部分以外は遮音層の内側はほぼすべて解体、吸音層もイチからやり直しということで工事の規模は大きかったが、却って音響的な要望には応えやすかったようだ。明瞭度を向上させつつも必要以上にデッドにならないよう、低域のコントロールに腐心したということで、壁面内部の吸音層の一部にAGSを使用するなどの処置が施されている。壁の内部にAGSが使用されている例は珍しいのではないだろうか。

📷株式会社角川大映スタジオ ポストプロダクション 技術課 竹田直樹 氏(左)、同じく山口慎太郎 氏(右)。システム設計においては主に竹田氏が主導し、現場での使いやすさや内装デザインなどは山口氏が担当された。
文字通り最新のテクノロジーをフル活用しシンプルな機器構成で大規模なシステムを実現しているマシンルームとは裏腹に、居住性を重視した和モダンな内装となった角川大映スタジオダビングステージ。待望の国内3部屋目となるDolby Atmos Cinema対応も果たした本スタジオで、これからどのような作品が生み出されるかが楽しみだ。それだけでなく、Dolby Atmos Cinema制作のためのダビングステージが増えるということは、国内におけるDolby Atmos作品の制作を加速させるという意味も持つ。今回の改修が国内のコンテンツ産業全体へ与えるインパクトの大きさも期待大だ。
*ProceedMagazine2024-2025号より転載
*記事中に掲載されている情報は2024年12月09日時点のものです。