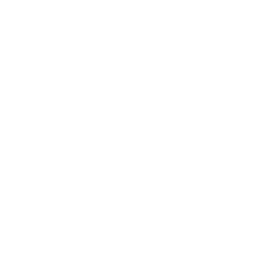«投稿
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

Sound Design のベース DOLBY ATMOS 普及の鍵となるスタジオが完成 〜 beBlue AOYAMA 〜
東京・青山という都内屈指の立地に世界各国で導入が進む Dolby Atmosへ対応したMAスタジオが誕生した。THX pm3認証も得た環境でCPU ベースのレンダリングエンジンによるDolby Atmos 環境とホームシアター用RMUを使用したリマスタリング環境を実現可能としたシステムは、将来へも布石した先進のスタジオと言える。今回の導入事例では数々のアイデアが詰め込まれたシステムの詳細に迫りたい。
有限会社ビー・ブルー様は名古屋に本拠地を持つ、主に映像作品のサウンドデザイン(選曲・音楽制作も含む)を行っている会社である。物語の始まりは「東京にスタジオを作りたい」という構想を、THX pm3認証に沿ったプランニングで数多くのスタジオ構築に実績がある染谷 和孝 氏に語ったところから始まる。東京には2chのMA スタジオも5.1chのMA スタジオも多数存在する。新しくスタジオを作るとなると同じようなコンセプトのスタジオを作っていたのでは成り立たない。そこでしっかりとした個性を持ったスタジオを作るには明確に差別化されたコンセプトが必要となる。
その答えを見つけるターニングポイントとなったのが東映株式会社でのDolby Atmos対応のダビングステージを視察した際のこと、Dolby Atmosというキーワードの実際を見る事によってこれまでの計画は一つの方向に向かって急激に走り出していくことになる。元々のコンセプトとしてTHX pm3の認証とシーリングスピーカーは導入したい考えであったが、そのシーリングがDolby Atmosに出会って大きな化学反応を起こし、今回のコンセプトに「小規模スタジオでのDolby Atmos」という一つの目標が出来たとも言える。しかし、まだその時点では「Local Renderer」の正式リリースの声は聞けず、結果的にはリリースを想定しての船出となった。また、その新しいチャレンジと言えるDolby Atmosのシステムアップだが、やはり予算との擦り合わせは大きな課題となる。果たしてDolby Atmosの導入コストの規模感はどうなるのか、ベースとなる音響を整えた環境は構築できるのか、新しいコンセプトとの折り合いは有限会社ビー・ブルー様にとってもこだわりを持って臨む新たな試みとなった。
前述のように当初はDolby Atmosの構想はなく、7.1chの整えられたレギュレーションに基づいたMAとしてコンセプトを考えていたとのことである。5.1chであればしっかりと調整が行き届いた設備もあるが、7.1chとなると整った環境を探す事も難しい。その一方で、Blu-rayやゲームコンテンツなどは既に7.1chがベーシックとなっており、7.1chの設備をきちんと整える事は充分な意味を持つ。また、MAと言えば48kHzがデフォルトとなりデジタルでシステムが組まれていることも多いため、ハイレゾ(96kHz以上)への対応も差別化を図る上で重要なコンセプトとなっていた。この7.1chとハイレゾ制作というベーシックプランにDolby Atmos対応が加わってスタジオのプランは試行錯誤を繰り返して行くことになる。
そして2014年春、ついにLocal Rendererの大まかな情報を得ることが出来た。それまでのDolby Atmos制作環境はシネマ用のダビングステージ向けシステムしか用意されていなかったが、このLocal Renderer の登場により中小規模のスタジオでも視聴環境が整備できればDolby Atmosの導入が可能となる。つまり、この発表によって初めてDolby Atmos作品の事前作業(プリミックス)への希望が明らかになり、スタジオ構築の方向性も定まっていく。例えば、完成後の設備追加では環境整備(音響調整)が難しいDolby Atmosフォーマットのスピーカー配置など、そのプランニングが一気に現在の完成形へと固まっていった。ちなみにLocal RendererとはDolby社が提供するPro Tools用プラグインで、Dolby AtmosのレンダリングをCUPベースで行うことができ、ダビングステージに持ち込む効果音等のサウンドデザインをニアフィールドDolby Atmosモニター環境で行うことができる製品である。
しかしながら、この2014年春の時点の情報では、Dolby社のLocal Rendererに関しては技術発表の段階であり、明確なリリース時期や本当にリリースが果たされるのかも不透明な状況。その中でもスピーカー配置などハードウェア的な準備がなければDolby Atmosの導入も難しくなってしまうため、アコースティックデザイナーである株式会社ソナの中原氏による緻密な音響設計が行われ、先行して設備を準備しLocal Rendererの登場を待つということとなった。
結果的にこのLocal Rendererの発表タイミングはbeBlue様にとって「非常にラッキーだった」と代表の青木氏も強調されていた。シーリング(天井)のスピーカーに関しては躯体の補強など様々な追加要素が必要となり、既存スタジオにシーリングを追加するハードルは高いと言える。これが設計段階からシーリングを見込んでプランニングが出来たのもLocal Rendererの開発が有限会社ビー・ブルー様にとって絶妙のタイミングで行われたからに他ならない。もしその開発が半年遅かったらDolby Atmos用のスピーカー構成にはなっていなかった可能性もあったとのこと。このほかにもDolby Atmos ホーム用のRMU(Rendering and Mastering Unit)の提供が開始したのもまさにスタジオの工事期間中。このRMUは シネマ用のプリントマスターから、ホームシアター用にDolby Atmos ミックスをリマスタリングするDolby Atmos ホームにとってのまさに心臓部、そのアジアでの1号機がこのスタジオに導入されている。このスタジオのプランニング、工事の進行と共にキープロダクトが発表されていくという非常なラッキーを携えてスタジオは完成していくこととなった。
「ファイナルミックスの完成度は、8割以上がプリミックスの出来次第だと思っている」と染谷氏は語る。このスタジオではDolby Atmosの事前作業とプリミックスを行ってもらい、ダビングステージで完成度の高いファイナルを作ってもらいたいという思いがあるとのこと。この設備を活用してプリミックスをじっくりと行ってもらいたいというのが大きなコンセプトの一つである。この実現にはLocal Rendererの存在は非常に大きなものとなった。CPUベースのレンダリングエンジンでDolby Atmosの環境を実現することを可能とするこのシステムは、コスト的にも規模感としてもコンセプトにフィットした。
そして、もう一つのコンセプトはDolby Atmos ホーム用のRMUの登場によりもたらされた。今後コンテンツの増加が予想されるDolby Atmos ホーム用のコンテンツ制作拠点として存在することも意義が大きい。さらに今後はBlu-ray用のオーサリング、リマスター等の作業も見込んでいる。もちろん現時点ではDolby Atmosの仕事だけでスタジオのスケジュールが埋まるとは考えてはおらず、MONOから7.1chの仕事まで全部がしっかりと行えるよう細かな設計されている。Dolby Atmosに特化したスタジオではなく、車のギアのように切り替えることでモードが変わり全てに対応できる環境というのが目的としてあった。その点をこのstudio 0(ゼロ)ではDolby AtmosとTHX pm3いうコンセプトの軸を与えることで差別化、機能性の明確化を行っている。
Dolby Atmosに関してまさにBlu-ray Discの発売が始まり大きな局面に差し掛かっているが、ここで非常に大切な作業が生まれる。染谷氏はSONY PCL時代に「なぜCDにはマスタリングがあるのにDVDにはないのか?」ということを提唱した。DVDこそコーディング(非可逆の圧縮)が行われそのサウンドが変質する可能性はCDなどよりも圧倒的に高い。エンジニアにとってスタジオで作った音とパッケージに収録される音の変化は自身で確認を行うべきなのに、なぜDVDにはマスタリングが無いのかが不思議で仕方が無かったとのこと。SONY PCLでは自身の携わった作品のエンコードまで責任をもって作業を行うことが出来る設備とワークフローを確立してきた。DVDに必須コーデックとして採用されたDolby DIGITALに代表される非可逆圧縮での音質や音量の変化が、どのような特性や仕組みで生じているかをつかむ必要があった。マスタリングの必要性は圧縮によるものだけではなく、映画作品の民生用パッケージ化では音響処理を施した大空間施設での再生を目的とした音声信号を、家庭に設置されたホームシアターに最適な状態にマスタリングする目的もある。
そしてDolby Atmosでも同じことが言える。シネマ用のDCPに収録されるDolby Atmos音声と民生用に提供されるDolby Atmos ホームではコーデックや収録再生の仕組みに違いがあり、マスタリングの重要性はこれまでの5.1chや7.1ch以上に大きい。Blu-rayではDolby Atmos音声収録のために可逆圧縮であるDolby TrueHDや非可逆圧縮であるDolby Digital Plusを選択することが可能であり、それらのコーデックに用意された様々なパラメータは適切に設定する必要がある。さらに映画用Dolby Atmosもまた多くのスピーカーを設備し音響処理を施した大空間施設での再生を目的としているため、ニアフィールドモニターが基本となるDolby Atmosホーム環境での再生音場確認及びマスタリングは、コンテンツ配給のワークフローになくてはならない。そしてもっとも重要なことは、Dolby Atmosホームのマスターファイルを作成する工程であるということ。このマスターファイルが後工程のエンコード処理における素材ファイルとなる。Dolby Atmos ホームの詳細は、別途本号で特集をしているのでそちらを是非とも参考いただきたい。
新たなコンセプトへのチャレンジということもあり、今回導入のシステムについても特色がある。まずはスタジオの全景でも存在感のあるYAMAHA NUAGEだがこの点はプロダクトの可能性にかけた導入、国内の製品であるアドバンテージを活かして、メーカーには多くの要望に前向きに取り組んでもらったという。その結果、特筆すべきPro Tools 2式とのリレーションなどのほか、今回のスタジオのコンセプトとして必須となる機能の数々が実現している。
また、このセレクトではコストメリットも得られる。今や1000万円のコンソールやコントローラーも高価に感じてしまうが、そのような中での選択は非常にコストを重視した。もちろん多くの予算があれば、大好きなSSL等の大型コンソールの選択となるはずだが、何を選択しどんな機能を満たしていくのか?という部分を重視して考え抜かれている。今回の導入で必須機能となったのは7.1chに対応したマルチチャンネルのモニターコントロール。大型コンソールであればもちろん実現可能だが、それに変わるコンソールは何があるのかを考えると選択肢が殆ど無い。そのような現状の中で浮上したのがDAWをミキシングエンジンとして取り扱うYAMAHA NUAGE。この製品であればNuendoが今後も拡張することで対応フォーマットは順次追加され、もちろん現時点で7.1chへの対応は言うまでもない。更にモニター補正として導入されているDME64との連携により実現されている機能も多い。Atmos対応のモニターシステムとの連動を考えた結論がNUAGE導入であった。そのNUAGEエンジンが実際に何を行っているのかというと、Pro Tools2台とMedia Composerで構成されるStellite Linkからの信号を受け、NUAGE I/Oを利用した、ダイレクトモニタリング機能により出力している。もちろんNuendoのユーザーがスタジオを使う場合には、DAWとしても利用可能なシステムアップとなっている。
もう一つ、B-Chainにコストを掛けるという点もコンセプトに基づく。スタジオの音響をしっかりとした設備にという重要なコンセプトを実現するためにB-Chainの充実は必須となる。DAWなどは後からの更新も可能だが、スピーカーへと導かれるB-Chian部分は音響設計と密接に結びつくため後からの変更が難しい部分だ。具体的には補正用に3台のDME64とMini-YGDAIシリーズのMY8-LAKEカードを使用している。ここもYAMAHA製品を使用しNUAGEを含めたトータルでのシステムアップにつながっている部分。今回のシステムでYAMAHA製品が中核となっているのはメーカーとしての対応力にプランニングを進める上での大きな可能性を感じたことが大きなファクター、NUAGEの最新バージョンには染谷氏のアイデアも数多く含まれているとのことだ。
これまでの作業の中でも特にゲームの仕事はイン・ザ・ボックスのミックスを要求されることが多く、特に近年は作品のほぼ100%がそのとおりとなっている。以前は、コンソールミックスに対する慣れがあり、イン・ザ・ボックスのミックスが上手く出来ない時期もあったとのこと。その時に試みたのがMackie Controlだけでのミックス。この作業をひたすら行いコンソールでもイン・ザ・ボックスでも優れたミックスを行えることを目指して研鑽を重ねた時期もあったとのこと。C300時代にはHUIモードが登場しコンソール側でも同様の作業を行うことが可能となった。イン・ザ・ボックスでもコンソールミックスでもクライアントのオファーに柔軟に対応できるような準備を行っていた。そのような経緯もあり、NUAGEでのHUIミックスには大きな違和感はなく、スタンドアローンのコンソールではないことのデメリットはほとんど感じないとのことだ。すでにコンソールとコントローラーの境界線が希薄になっているということを感じる一幕である。もちろんラージコンソールの優位性は誰よりも熟知している。マスターセクションのつくり、感触の良さ、豊富なマトリクス、人間工学に則った優れた設計。優れたメリットがあることは認めるが、残念ながらイン・ザ・ボックスでのミックスがクライアントから求められる現場においては、NUAGEのようなHUIミックスなどを考慮するべきだとの意見をいただいた。
発想の転換によりNUAGEの魅力は大きく広がる。Nuendo専用という意識を外して優れたHUIコントローラーとすると、また違った魅力が見えてくる。Pro Toolsをコントロールすることの出来るNuendoという柔軟性に富んだミキシングエンジンを持つコントローラー。そのような捉え方をすればPro Toolsユーザーにとってもメリットが大きい、新しいコントローラーとしてのNUAGE像が見えるのではないか。エンジニアがコントローラーとして求めるのは、ほとんどがフェーダーである。もちろん、プラグインのコントロールやセンドのアサインなど欲を言えば切りが無い。しかし、最も使用するのはどの機能なのかを考えればHUIでも対応ができるという発想に至るのではないだろうか。限られた予算を有効活用するための非常にシンプルな切り分けがここにはある。
室内音響に関してはTHX pm3の認証を得ている。従来の日本のTHX pm3スタジオにはインストールされていないシーリングチャンネルやLw,Rw等のAtmosに特徴的なスピーカーの配置に関しても、設計段階からTHX、Dolby、SONAによる詳細なディスカッションが行われており、最終的には3社にとっても妥協のないスピーカーレイアウトがstdio 0(ゼロ)では実現されている。最終的にはそれら全てのスピーカーを含んだモニター調整がTHXのスタッフにより実施されており、優秀な成績でTHX pm3の認証を得ている。特筆すべきは、ベースマネージメント無しで、全チャンネル20Hz〜20kHzの広帯域再生を可能とし、更にTHX pm3の承認を実現しているという点。基本的にはベースマネージメントの使用が前提となるTHX pm3規格をそれ無しで取得できるほど、室内音響的に低域の制御ができているということだ。音楽系のミキサーに敬遠されがちなベースマネージメントが無いということで、是非とも音楽ミックスでもこの部屋を活用してもらいたいとのことだ。筆者もこの部屋で行われた音楽用のDolby Atmosミックスを是非とも聴いてみたいところだ。
◎染谷氏とサラウンドテクノロジーの歩み
染谷 和孝 氏
有限会社 ビー・ブルー
サウンドデザイナー/ミキシングエンジニア
1963年東京生まれ。東京工学院専門学校卒業後、(株)ビクター青山スタジオ、(株)IMAGICA、(株)イメージスタジオ109、ソニーPCL株式会社を経て、2007年(株)ダイマジックのスタジオ設立に参加。2014年より有限会社 ビー・ブルーに所属を移し、サウンドデザイナー/リレコーディングミキサーとして活動中。2006年よりAES(オーディオ・エンジニアリング・ソサエティー)「Audio for Games部門」のバイスチェアーを務める。また、2014年9月よりAES日本支部監事を担当。
染谷氏がサラウンドに触れたのは30年以上も前のこと。アナログハイビジョン時代に「銀河の魚」のサウンドデザインとサラウンドミックスを担当したときに遡る。それをきっかけにInterBEEの国際シンポジウムなどにも参加するようになる。そこで元NHK制作技術センター長の沢口氏との大きな出会いもあり、それが全てのスタートになったとのこと。
サラウンドには黎明期から関わりがあるが、一貫してその根底には「サウンドデザイン」という概念があり、その発展の礎となっている。「サウンドデザイン」との出会いは、ProSound誌に掲載されていたSkywalker Soundの記事だとのこと。当時はInterBEEにSkywalker Soundからエンジニアが参加しており、様々なきっかけから徐々に交流が始まり、Skywalker Soundへの訪問など研鑽を積み重ねてはいたが、なかなかサラウンドの部屋を作ることは出来なかった。
次の契機となったのは1999年にロスで行われたSurround 2000というイベント、ここではTHX pm3と出会うことになる。このイベントはまさにSONY PCL の改装を決定する時期に重なっていた、当初はステレオの部屋を作るという方針であったが、このイベントと前後してサラウンドの部屋を作る計画が進行、スタジオのコンセプトを詰めるために自費で2週間サンフランシスコに行き、THX社とSkywalker Soundを見学して回った。そこで体験したサウンドは「音の消え際が聞こえる」と表現されるほどの繊細さ。今まで聞こえなかった音が聞こえるという体験することとなる。
その当時はまだITU-Rなどを始めとする様々なサラウンド再生基準が取り上げられ、その優位性が語られている段階であったが、その中から明確なレギュレーションに守られたTHX pm3選択した。信頼性の高い音響特性を持ったスタジオを構築し、アジア初のTHX pm3スタジオとなった。その後も染谷氏はTHX pm3の認証を得た世界標準の音響特性を持ったスタジオを数多く創り上げている。
Dolby Atmos採用に踏み切った染谷氏のポリシーの中には「真のブルーオーシャンを目指さなければいけない」ということが有る。真のブルーオーシャンを構築するためには、クローズドに全てを秘密にしてはならないと考えているというのも非常に新鮮なコメントとして聞こえた。現代を生き抜くためにはこのスタジオで得た知識・情報を開示し、それを共有する仲間が増える事が最も大切な要素。新しいことを始める為の仲間探しが今まさに始まったところだとコメントを頂いている。もう一つ「マイノリティーからマジョリティーへ」という言葉も頂いた。このスタジオ、そしてDolby Atmosが共に羽ばたくためにはマジョリティーになることは大切なこと。マイノリティーのままではなく、普及も進んで行かなければ意味がなくなってしまう。次に続くスタジオ・エンジニアの存在はなくてはならないもの、エンジニアリングのテクニックに関しても同様に隠すのではなく伝えることで、業界全体が豊かになるのであれば、その方が重要な事だとの考えも伺えた。
インタビューを終えて感じるのは、明確なコンセプトのもと、限られた予算を必要な部分に十分にかけた染谷氏のこだわりと考えが非常にわかりやすくスタジオに存在していたこと。また、最新の機材ソリューションの結晶のようなシステムとなっているが、突飛な存在とはならずに違和感なくそのシステムへ入っていける間口の広さも感じる。Dolby Atmos対応だからといってステレオやモノラルの作業のことを切り捨てずに「ギアチェンジ」出来るというコンセプトがしっかりと息づいているように感じた。染谷氏のコンセプトを受け、東映株式会社に続き国内2例目となるDolby Atmosの室内音響を設計された株式会社ソナ、アジア初となるDolby Atmos ホームシステムを設計した株式会社レアルソニード、そして機材のバージョンアップ等様々なソリューション面でのバックアップを行ったヤマハ株式会社、各社の持つ技術が非常に高いレベルで結実している。今後このスタジオから創りだされる作品に、早く出会いたいと強く感じた取材であった。