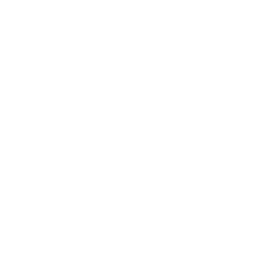«投稿
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

Virtual Circuitry Modeling技術によるオーディオエフェクトの開発 ~ADD-ON EFFECTシリーズからPorticoプラグインエフェクトの開発まで~ Part.1

ヤマハ株式会社では以前よりデジタルミキシングコンソールやMotifXFのようなシンセサイザーのエフェクト信号処理技術としてアナログ回路をデジタルでエミュレーションする自社技術、VirtualCircuitryModeling技術(以下VCM技術)を採用し、その音楽的な音質によって高い評価を得て来た。このたびヤマハとスタインバーグ社はRupertNeveDesigns社(以下RND社)との協業によりVST規格によるエフェクトプラグインソフトウェア、Portico 5033と5043を発売した。
そこで本稿では、VCM技術とはどう言うものかをデジタルミキシングコンソール用のエフェクト「OpenDeck」を例に説明するとともに、RND社とのソフトウェアエフェクト開発の経緯とPorticoプラググインフェクトについて紹介する。
- 1.VCM技術の歴史
当社における物理モデル技術(自然の音響現象や電子回路の挙動をソフトウェアなどによりモデリング・エミュレーションすることにより楽音合成やオーディオエフェクト処理を行う技術の総称)による製品の系譜は1993年のVL1/VirtualAcousticSynthesizer(以下VA音源)まで遡ることができます。当時、物理モデル概念による電子楽器商品は他にほとんど例がなく、VL1は実質的に世界で最初の商用物理モデルミュージックシンセサイザーでした。VL1での物理モデルは音響現象のモデリングを行っていたのでVA音源と言う技術名称を与えていました。
通称「K’Lab」の設立は実質的にはVA音源の開発を始めるための開発チームの編成を行った1987年と言うことになります。当時はK’sLabと言う呼称はありませんでしたが、筆者の一人(国本)はこの時から現在までヤマハの中での物理モデルによる電子楽器開発・オーディオ信号処理開発をまとめる立場であり続けています。
VL1においてもエフェクト部は部分的に電子回路モデリングによる原理を採用しており、その後も物理モデル概念による電子楽器、VP1(弦楽器の物理モデルに基づく)、AN1x(アナログシンセサイザーの物理モデル)、EX5/7(VL、ANのアルゴリズムとそれ以外にも物理モデルのアイデアを盛り込んだシンセサイザー)などの開発を経ながらヤマハ・K’sLabの中で物理モデル技術が育まれていきました。2004年に発売されたデジタルミキシングコンソール用オーディオエフェクト(ADD-ONエフェクトシリーズ)からVCMと言う技術呼称が与えられるようになり、スタジオで使用されるようなアナログのアウトボードエフェクトやギターアタッチメントなどの物理モデル技術によるデジタルでの再現によって様々なオーディオエフェクト処理が開発・製品化されるようになって来ました。現在ではシンセサイザーMotifXS/XFやエレクトリックピアノCPシリーズなどにも多数のVCM技術によるエフェクトが搭載されています。
次章では当初デジタルコンソール用追加エフェクトとして発売し、この度VSTプラグインエフェクトとしても発売することになったVCMエフェクトの中から、「OpenDeck」について技術や開発過程を紹介することでVCM技術について概観します。
[図1]VA音源とVCM技術が搭載されたCP1

[図2]VCMエフェクトも追加搭載可能なデジタルミキサーPM5D

- 2.VCM技術とOpenDeckの開発
OpenDeckの開発を始めた当初、ヤマハ・K’sLabではVCM技術によりアナログの電子回路をソフトウェアでモデリングすることで音の良いコンプ、音の良いEQを再現できるようになりつつあり、これらについては言わば「つぼは押さた」と言える状況でした。そして、次のターゲットを探していてテープへの録音再生のエミュレーションと言う課題に行き着きました。アナログ録音時代の音楽制作の環境や手順を考えるとき、マイクロフォン、ミキシングコンソール、アウトボードエフェクトと並んで録音再生機が大きな位置を占めるのは論を待ちません。当時の状況を今思えば、磁気テープに録音、再生すると言う作業は沢山の楽器を録音したり、全く別のタイミングで録音した複数のオーディオソースを再生・ミックスするための「必要悪」のようなものでした。しかし、テープの録音再生によりいい具合に歪んだりコンプ感が付与されたりにじんだ音になった楽器やヴォーカルの音、こうしたものは当時の楽曲、商業音楽の持つ音楽性の核のようなものでした。それゆえ今日でもリズムトラックだけはアナログのテープに一回「プリント」してからDAWに取り込む、と言ったエンジニアリング手法はデジタル技術中心の現在の音楽制作では一種「ポピュラーな裏技」として定着した感すらあります。
図3にテープレコーダーでの録音・再生の原理を示します。このようなテープへの録音・再生のモデリングはテープへの録音再生機が作られていた当時に基本的には分かっていました。(それなしに録音再生機を作れる訳はないのです)そのモデルのデジタルでの実現は、VCM技術を用いることで、録音アンプから録音ヘッドで起きている現象の再現や、磁気テープからの再生と再生ヘッド以後のNAB規格などで規定される再生EQアンプなどの特性の再現など、要素としては色々あるものの難しいものではありませんでした。したがって図3はアナログテープでの録音・再生原理でありで、かつVCM技術によってOpenDeckに作りこまれたテープレコーダーのモデルのブロック図的表現でもあります。
[図3]テープレコーダーの録音再生原理とOpenDeckでのモデル

モデルが出来上がれば測定です。残念ながら開発の当時(2002年頃)においても録音スタジオではデジタルのDAWによる録音再生が主流になって来ており、状態の良いアナログのプロフェッショナルなレコーダーはどんどん減りつつありました。それに加えてアナログのレコーダー特有のアジマスやEQの調整に長けたエンジニアもまた減りつつある状況もありました。こうした状況の中、音楽的に優れたアナログのレコーダーを最高のメンテナンスの状態でキャプチュアー(測定)できた我々は幸運だったと言えます。
VCM技術によるモデリングでは録音アンプも再生EQも個別にコンポーネントで再現しているので、録音と再生の機種を変えるのは簡単でした。よくコンポーネントレベルでのエミュレーションをしているという話しをVCM技術の説明ではしております。実際にはマクロレベルのコンポーネントとデバイスレベルのコンポーネントのエミュレーションと言う対立した概念があり、必要に応じた「ミクロ」さのレベルでのエミュレーションをしています。つまりアンプ単位で十分ならアンプをコンポーネントとしてエミュレーションし、ダイオードやトランジスターのレベルのコンポーネントのエミュレーションが必要ならそれを採用する。一般的にはモデリングによるエフェクトと言いながら一番上の「オーディオエフェクト」と言う一番「マクロ」な塊をいきなりエミュレーションしてコンポーネントのレベルには降りてないものが普通ですが、ヤマハ・K’sLabのVCM技術ではケースバイケースで効率とクオリティーによってどのレベルのエミュレーションを行うかを吟味して決めています。
開発としてみると難しかったのは、テープへの着磁やその磁場からの信号の再生の過程が非常に曖昧であり測定が難しいこともあり、モデリングが完成してもそこに実際のテープレコーダーの特性を入れ込む過程が曖昧にしか見えてこないことでした。何を持って必要な「特性」とし、どこにその「特性」のためのパラメーターを入れ込めばいいのか?そして出来上がったモデリングのパラメーターはどうやって物理的な特性と言うより音楽的なサウンドをリアルのテープレコーダーに近づけて行き、それにより実機のような音楽性が得られるようにするのか。開発を始めるとはたと考え込むところが多々ありました。
結局、こうした問題は人間技で解決されて行きました。特性データを技術的に咀嚼してモデルに入れ込む我々信号処理技術者の技とコンサルティングエンジニアの耳の能力を頼りにした膨大な時間をかけた調整作業によって、最終的には4機種のプロフェッショナルレコーダーを参考にした4つのデータセット、Swiss70/Swiss78/Swiss85/America70にまとめられました。特性的に本物と同じものになることよりも必要なのは音楽的な機能性が同じことであり、原器の音の「おいしいところ」がデジタルでも再現されることを目標にチューニング作業が進められました。
一つの例として録音から再生までの振幅周波数特性を示します。
[図4]4種のテープレコーダーの録音再生振幅周波数特性

[図5]OpenDeck上の4種のパラメーターセットの録音再生振幅周波数特

図4は現実の4種のアナログテープレコーダーの録音再生特性です。図5にはそれらをVCM技術のOpenDeckにおいて再現した様子を示します。振幅周波数特性の細部までが再現されています。(実際のOpenDeckではテープによる録音再生過程の様々な非線形性もモデリングしていますので、このデータはOpenDeckの特性のごく一部をとらえたものとお考え下さい)
最終的にはコンサルティングと評価の役割でプロジェクトに参画いただいた遠山淳氏をして「次世代への貴重なライブラリー」となっていると言っていただける出来になりました。VCM技術によって、リズム楽器などをまとめるのに重要な役割を果たす「テープコンプ感」のみならず、録音バイアスを本来の設定からづらすことによる倍音の制御など、様々な音作りができるプラグインエフェクト「OpenDeck」が完成しました。録音と再生のレコーダーを個別に選ぶことができる機能も好評価でした。スタジオでの音楽制作ではトラックダウンの録音に使ったレコーダーとマスタリングスタジオでの再生に使われるレコーダーが違うことは普通であり、それが再現できることによる音楽の表現の幅は現場にも素直に受け入れられました。
こうしたVCM技術によるオーディオエフェクトはヤマハのデジタルミキサー用のADD-ON EFFECTSシリーズとして2004年に発売されました。この他にはComp276やEQ601のようにスタジオストリップ(当時)の赤川新一氏に監修をいただいたエフェクトもあります。これらもその音楽性によって非常に高い評価を得ています。図6はヤマハのデジタルミキサーの様々な情報を管理できるPC上のアプリケーションソフトウェアStudioManager上のOpenDeckとComp276です。
[図6]OpenDeckとComp276。アプリケーションソフトStudioManager上で

Virtual Circuitry Modeling技術によるオーディオエフェクトの開発Part.2: (RND社とのコラボレーション)に続く>>>