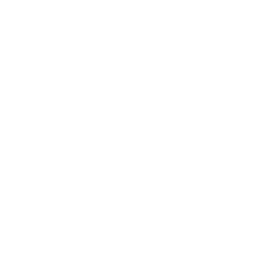«Works
Author
澤口 耕太
広範な知識で国内セールスから海外折衝、Web構築まで業務の垣根を軽々と超えるフットワークを発揮。ドラマーらしからぬ類まれなタイム感で毎朝のROCK ON PROを翻弄することもしばしば。実はもう40代。

TOHOスタジオ株式会社 様 / シネマサウンドの最進化形、東宝スタジオ ダビングステージ1
「七人の侍」「ゴジラ」シリーズなど、日本映画史に残る数々の作品を生み出してきた東宝スタジオ。同社のダビングステージ1が、待望のDolby Atmosへの対応を果たした。Dolby Atmos対応スタジオとしては国内最大、そして国内初のAMS NeveとPro Tools | S6のハイブリッド・コンソールなど、シネマサウンドを作り出すシステムの最進化形とも言えるその構成を紐解いていこう。
1932年に現在の世田谷区砧に誕生した東宝スタジオ。今回、Dolby Atmos化を果たした「ダビングステージ1」(以下、DB1)は、2003年から8年の歳月を費やして進められた「東宝スタジオ改造計画」の中核施設として2010年9月に完成した、フルデジタル対応の「ポストプロダクションセンター1」の中にある。このDB1は、ワーナー・ブラザーズのダビングステージを手がけたSalter社によって音響設計がおこなわれており、モデルとなったワーナー・ブラザーズのスタジオ9、10に基づいた設計が実現されているという。
今回のDB1更新では、サラウンドチャンネルとしては天井2列と両サイドが9本ずつ、リアが6本の合計42本、サラウンド用サブウーファー4本という構成が採用されている(スクリーンバックLCR、LFEは既存)。文字にしてしまうと淡白に感じるかもしれないが、これだけの本数を要する環境にはそうそうお目に掛かれるものではない。合計42本という数のスピーカーが必要になるくらいDB1の容積が大きいということである。
躯体間で天井高10.5m、内装仕上げ後のスクリーン最上部までが7.2m、ミキサー席から天井までが3m超という大きさは、Dolby Atmos対応の制作スタジオとしては日本最大となり(容積だけで考えると同社「ダビングステージ2」が国内最大)、長きにわたってビッグタイトルを生み出してきたダビングステージとしての堂々たる風格を感じさせる。映画作品における音響制作の最終段階として使用されることを考えると、何よりも部屋自体が実際に上映されるシアターと同等のサイズを持っているということは代えがたい強みであると言えるだろう。
特に、天井高を十分に確保することが困難な日本国内の建築においては、ドルビーのレギュレーションに記される角度でスピーカーを設置した場合に、ミキサー席とハイト・スピーカーの距離を十分に取ることが難しくなってしまう。無論、部屋自体が小さければハイト・チャンネルに限らず、すべてのスピーカーがミキサーから近く、反射も劇場とはかなり異ったものになっているわけだ。こうした場合、スピーカーに対してディレイやEQなどの電気的な補正を加えることになるのだが、やはり、部屋自体の容積を十分に取ることができているダビングステージの方が自然な音響環境を実現できるていることに間違いはない。
このようにもともと非常に高品質な音響を備えていたDB1、そのDolby Atmos対応に伴う内装工事においては、スピーカーレイアウトの大幅な更新を行なったうえで、従来の音響特性を保持することが至上命題となった。その実現のために、ドルビー社・ワーナーブラザーズスタジオとの緊密な連携と、内装工事を担当した日本音響エンジニアリングの力は不可欠だったと言えるだろう。B-Chainの大幅な規模拡大や照明のLED化といったアップデートを施しながらも、従来の音質を保持するため、Salter社が設計した側壁や天井の傾斜などの内装は従来通りの仕様が再現されている。完成したスタジオのクオリティについて、30年以上東宝スタジオでエンジニアを務める竹島氏は「細かな部分のブラッシュアップも含め、予想以上のクオリティに大変満足している」と言う。
それではシステム構成に目を向けていこう。まず、ダビングステージで大きな存在感を放っているのが、Avid Pro Tools | S6とAMS Neve DFC GeMiNiのハイブリッド・コンソールだ。このハイブリッド構成はハリウッドなどでは多くの事例があるが、国内ではこれが初めての採用となる。メインとなるのはPro Tools | S6だが、これは2022年に同社ダビングステージ2(以下、DB2)に導入されたのと同じ、デュアルヘッド、72フェーダーの構成となっており、Pro Tools | S6モジュールに並んで、DB1に従来から設置されていたDFC GeMiNiのマスター部分と16フェーダー分のモジュールが設置されている。デュアルヘッド、72フェーダー構成のS6は同社DB2、松竹映像センター、角川大映スタジオ ダビングステージに次いで4例目となり、ダビングステージにおけるPro Tools | S6のスタンダードな構成として定着しつつあると言えるのではないだろうか。
現代の音響制作においてPro Toolsを抜きにした制作が考えられない以上、やはりPro Toolsとの親和性が高いS6の利便性は非常に高いようだ。仕込み方にもよるが、現状S6ではプレイアウトPro Toolsからのステム出力を触ることが多いとのこと。その上で、個別トラックの調整が必要な場合はS6のスピル・フェーダー機能を使用するといった、柔軟な運用が魅力のようだ。また、DB2へのS6導入の際にも言及されていたことだが、オートメーションのデータがPro Toolsセッションとともに保存できることもワークフローの柔軟性を高めている。
一方でハイブリッド・コンソールという案は、こうしたPro Toolsのアドバンテージをブーストしつつも、従来のシネマサウンド、古き良きAMS Neveのサウンドもチョイスできるという選択肢を残すという意図があったようだ。ミキサーとして使用するというよりは、従来のNeveサウンドを得るためのアウトボードのような使用を想定しているとのこと。この十数年で、コンテンツは映像・音声ともにハイ・レゾリューション、ハイ・ダイナミクスレンジという方向性が急速に進展しながらも、特に音楽分野ではアナログレコードやカセットテープの持つ”味”が見直されるといった現象も起こっている。
Neveを通した時の唯一無二のあのサウンドは、やはり、ほかのシステムからは得難いものであると同時に、長きにわたってひとびとのイメージに染み込んだ「シネマサウンド」なのである。今回のハイブリッド・コンソールという構成には、そうした伝統的なサウンドを保存するという意味合いもあるのではないだろうか。
このハイブリッド・コンソールは既設DFC GeMiNiのフレームにS6モジュールを換装する形で設置されており、他のスタジオのS6とはまた違った存在感を放っている。これは、ハリウッドをはじめとしたシネマスタジオ向けにさまざまなスタジオ家具のソリューションを提供している、イギリスのHaddock Technical Furniture(旧 Flozen Fish Audio→Soundz Fishy)製のアタッチメントを使用することで、S6のバケットがDFC GeMiNiのフレームに収められている。Avid純正のシャーシの場合はバケット同士を直接連結することになるが、DB1の構成ではS6モジュール2列分をバケットごと取り出せるため、意外にもその部分を便利に感じているという。
今回のDB1の更新では、B-Chainに関連した部分以外のシステムは2022年に更新されたDB2のシステムを踏襲する形となった。これは、DB2におけるDFC2からS6への更新を中心としたA-Chainのシステム移行が大きな成功を収めたことに加え、運用面・音質面においてDB1とDB2で大きな違いが生じることを避けるという意図もあったという。DB1がDolby Atmos対応を果たしたからといって、5.1 / 7.1サラウンドの制作がなくなるわけではなく、そうした作品においてはDB1とDB2を行き来しながらの制作という状況も考え得る。その時に運用はもとより音質に大きな違いが出てしまっては、クライアントを混乱させてしまうことになるだろう。制作スタジオとして、どちらのダビングステージで完成させたミックスであっても、東宝スタジオで制作したことの安心感と安定したクオリティを提供するということだ。
DFC GeMiNiのようなデジタルミキサーからS6へコンソールをコンバートする場合、大きく分けてふたつの方針がある。ひとつは、Pro Toolsシステムとしての統合性をフル活用し、再生用のPro Toolsから直接レコーダー / ダバーPro Toolsに音声を入力するというもので、S6をPro Toolsのコントローラーと割り切り、ミックスはPro Tools内部でおこなう。もうひとつが、S6を従来同様の”ミキサー”として考え、再生用Pro Toolsと録音用Pro Toolsの間にミキシングエンジンとしてのPro Toolsを導入するという方針だ。東宝スタジオはDB1・DB2ともこの考え方でシステムを構築している。
一見、複雑にも見えるこのような構成を取ることのメリットは、やはり従来のシネマ・ワークフローを踏襲することができるという点だ。もちろん、Pro Toolsに慣れ親しんだ方であればミキサー用Pro Toolsをバイパスすることもできるし、ダイアログと音楽はダイレクトに、効果はミキサーを通して、などというハイブリッドなケースにも対応できる。さらに極端な例を挙げれば、再生用Pro Tools内部でオフラインバウンスしたステムを録音用Pro Toolsにペーストするようなワークフローも可能ということになる。先に更新されたDB2の運用を通して、この構成がどのような要望にも応えられる柔軟性を持ったシステムに仕上がっていることは実際の作業でも実証されているのだ。
再生用Pro Toolsはセリフ用(ダイアログ:D)、音楽用(ミュージック:M)、効果音用(エフェクト:E1/E2)の4台となり、すべてHDX2という仕様だ。先述のミキサー用Pro Toolsは大量のステムを受ける必要があるため、D+M Pro Tools用とE1+E2用にそれぞれHDX3構成のものが2台用意されている。そして、HDX2仕様の録音用(Dubber)Pro Toolsの合計7台のPro Toolsが稼働していることになる。
7台のPro ToolsシステムのI/Oには、すべてAvid Pro Tools | MTRX IIが導入されている。Pro Toolsは基本的にMADIで音声を後段へ出力しており、Dubber MTRXからのMADI出力は2台のRME M-32 DA Proでアナログ信号となりB-Chainへと送られる。メインの信号経路となるMADIは1系統ずつパッチ盤から取り出すこともでき、さらに、すべてのMTRX IIにはMADIに加えてAES/EBUモジュールが追加されておりこちらもパッチ盤に上がっている。個別の作品に応じて信号経路を変更したり、持ち込み機材を追加したりといった柔軟な運用が可能な構成になっている。
音楽用MTRX IIだけは32ch分のDAカードが追加されている。これは、音楽素材が96kHzで持ち込まれた場合を想定しての構成だ。96kHzの音声信号はMADIで伝送するとチャンネル数が半減してしまう上、どこかで映画マスターの48kHzに変換する必要がある。この場合に、MTRX IIでいったんDAした信号を M-32 DA Pro に入れ、そこで再度48kHzのMADI に変換してミキサー用 Pro Tools に信号を渡すという形になっている。96kHz→48kHzのコンバートをDD変換で済ませるのではなく、いったんアナログという連続数に戻してから信頼性の高いコンバータを使用して再度AD変換するという手順を踏むことで、デジタル領域での”縁切り”と音質の両立を意図した設計だ。
再生用Pro Toolsからパワーアンプの手前までのメインの音声信号経路はMADIが採用されているが、RMUやTrinnov PRC-2といったプロセッサーとの接続はDanteが活用されている。I/OがすべてMTRX IIなのであればPro Toolsシステム内部もDante接続で統一することも可能なはずだが、なぜDB1ではMADIをメインに採用しているのだろうか。もちろん、運用面・音質面でのDB2との連続性が考慮されているのは言うまでもないが、実はDB1でDanteが採用されている箇所は、一度設定したあと普段は触る必要のない系統に限定されている。それに対して、作品ごとに柔軟な経路変更が必要とされる可能性の高いPro Toolsシステム内はMADI接続、と用途に応じて明確に信号フォーマットが分けられているのである。
もし、信号経路をDanteで統一してしまうと、DB1のあらゆる信号をDante Controllerアプリケーションで管理しなければならなくなり、運用上のミスや混乱を招きかねない。複雑な経路変更が生じる可能性のある箇所を物理的なパッチでおこなうことにより、より迅速で正確な運用を可能にしているのである。とはいえ、Danteを活用したことでワイヤリングは想定していたよりもずっとスッキリと収まったという。今後、複雑なルーティングを物理的にコントロールできるソリューションのようなものが登場すれば、LANケーブル1本で128ch入出力できるという事実はより大きな恩恵を与えてくれるだろう。
Dubber Pro ToolsからMADIで出力された信号はM-32 DA Proでアナログに変換され、B-Chainへと渡される。アンプはすべてCrownで統一されており、スクリーンバックがIT 5000HD、サラウンドがIT4x3500HD。すべて、Audio Architect対応のモデルとなっている。スピーカーはすべてElectro Voice。シネマ用スピーカーといえばJBLがスタンダードだが、東宝スタジオでは30年以上前からスピーカーにはElectro Voiceを採用している。何もしなくとも自然にXカーブを描くようなJBLと比べてきらびやかな音色が特徴で、そのサウンドは同スタジオの個性の一部となっている。スクリーンバックにはEV Variplex II EX+EV TL880Dという組み合わせが3組設置されており、サラウンドはEVF-1152D/99が42本(ハイト2列x9本、両サイド9本ずつ、リア6本)、側壁にはサラウンドサブウーファー4本が埋め込まれている。このサブウーファーはユニットのみをElectro Voiceから取り寄せ、キャビネットは楽器音響によるカスタム製作だ。
改修前のサラウンドチャンネルは両サイド4本+リア4本の計12本だったことを考えると、かなり大規模なスピーカーレイアウトの変更となった。実は、今回導入されたEVF-1152D/99は改修前に設置されていた機種と比べて、ユニットの大きさこそ変わらないが、キャビネットが大幅にサイズダウンしている。もちろん、Dolby社の意見を聞きながら設計している以上、理論的には問題はないはずなのだが、サウンドの量感の部分で物足りなさを感じるのではないかということは、DB1が完成するまでは気になっていたそうだが、結果的には杞憂だったということで従来通りの重厚な質感が得られているという。
Dolby Atmos対応ダビングステージとしては、国内ではこれまで、東映デジタルセンター、グロービジョン、角川大映スタジオが存在していたが、DB1がこのタイミングでDolby Atmos対応に踏み切ったのは、近年、『ゴジラ-1.0』や『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』等、複数の作品がDolby Atmosで制作・公開されはじめたことが大きかったようだ。「Dolby Atmosを一度触るとそれまでの5.1や7.1には戻れない、と言う音響監督さんは多いです」と、TOHOスタジオ下總氏が言うように、Dolby Atmosというフォーマットの可能性が国内にも浸透してきたことの証とも言えるだろう。「ゴジラ」のような巨大生物が登場する特撮や、「鬼滅の刃」のようなアクションものは(無限城はその構造上、特に)、高さ方向への音響表現が最大限に生きる作品だったと言える。TOHOスタジオ竹島氏は「まさに、ゴジラがアトモスを連れてきてくれた」と話す。
それに加えて、東宝グループの新たな配給レーベル「TOHO NEXT」が扱うコンテンツの中に音楽作品の劇場上映が含まれていることも大きいだろう。ご存知の通り、国内では映画作品に先駆けて音楽制作の分野でDolby Atmosが浸透してきた。DB1も実際に、ライブコンサートのドキュメンタリー的な作品で使用される機会は非常に多いということだ。ライブコンサートのドキュメンタリー、という言い方をあえてしたが、近年のライブコンサート映像というのはドキュメンタリーとしての側面よりも音楽体験に力を入れる傾向が強い、それが意味するのは以前よりも音響クオリティ面が重視されるようになってきているということだ。そう考えれば、音楽映像作品の制作においてDB1が人気となるのも頷ける。単純に機器更新のタイミングに合わせて新しいフォーマットに対応する、ということではなく、グループ全体としての大きな戦略の一部としてのDolby Atmos対応ということで、今後、同社から数多くのDolby Atmos作品が生み出されることに期待できそうだ。
*ProceedMagazine2025-2026号より転載
*記事中に掲載されている情報は2025年12月29日時点のものです。