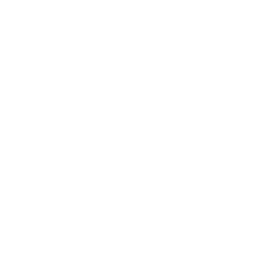«投稿
Author
ROCK ON PRO
渋谷:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1776 梅田:〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-4-14 芝田町ビル 6F 06-6131-3078

ROCK ON PRO REPORT !!/GAME AUDIOから劇伴まで、映像に音を付ける面白さ

GAME AUDIO業界でキャリアをスタートし、その活躍の場をTV、映画へと広げる光田氏に取材を行なった。ゲームコンソールの性能という縛りの中でつくり上げる時代から、自由な表現を駆使することのできる時代へとその変遷の中を歩んできた中で生まれたこだわり。そして、機器の進化に合わせてドラスティックに移り変わるGAME AUDIOの進化の歴史を感じられる内容となった。
 プロキオン・スタジオ 取締役 光田 康典
プロキオン・スタジオ 取締役 光田 康典
昭和47年(1972年)1月21日生まれ。山口県熊毛郡熊毛町(現・周南市)出身。
・スクウェア在籍初期に『半熟英雄』『ロマンシングサガ2』『聖剣伝説2』などのエフェクト音の制作に携わる。作曲家としてのデビュー作は『クロノ・トリガー』。その後『ラジカルドリーマーズ』『ゼノギアス』『クロノ・クロス』の楽曲制作を担当。
・スクウェアから独立後の主な作品は『ゼノサーガエピソード1』『イナズマイレブンシリーズ』など。『スマブラX』でもアレンジを担当している。
光田氏がGAME AUDIOの世界に飛び込んだのは、業界がまだ成長の課程にある1992年の事。1990年に任天堂よりSuper Famicomが登場した頃ということになる。なぜ、GAME AUDIOの業界に飛び込んだのかと聞くと、「学生の頃からエンターテイメントが好きだった」と。学生の当時のエンターテイメントは映画がその中心であり、全てであったと振り返る。GAMEはまだ、テーブルゲーム(インベーダー、パックマンなど喫茶店の机がゲーム機だった時代)。音楽など無く、ミサイルの発射音や、撃墜音、様々な効果音は今で言う『ピコピコサウンド』として鳴っていたが、映像と音声の融合によるエンターテイメントと言うよりは、純粋なGAMEのみのコンテツであった。そのような時代に、光田氏は映画をこよなく愛し、劇伴作家になりたいという夢を抱いていた。音楽系の専門学校に通い、作曲の手法を学びながらの就職活動。まさに時代は、変革の時代に突入していた時期である。
テーブルゲーム等のある、ゲームセンターは不良の行く場所というような風潮から、存在は知っているもののあまり触れることはなかった中、Family Computerから始まる家庭用のゲームコンソールは身近なものとして存在していた。ご承知のように、Family ComputerのGAMEには、音楽が付けられそのコンテンツを盛り上げていた。オープニングテーマがあったり、その音楽というものにも注目が集まった時代である。GAMEのサウンドトラック、オーケストラアレンジのCD等、GAMEからスピンアウトした音楽コンテンツが多数作られ始めた時代でもある。その進化、発展を見るうちに、その未来に秘められているエンターテイメント性に惹かれ、GAME AUDIOの業界への就職を決めた。
光田氏が就職をした会社が株式会社スクウェア(現:株式会社スクウェア・エニックス)。最初はシンセサイザープログラマや効果音なども担当をしたことがあったそうだが、基本的には、音楽の作曲作業が中心。元々、コンピューターが好きだったということもあり、入社3年目の1995年には代表作となる『クロノ・トリガー』に作編曲という形で関わっている。他にも音楽の評価の高い『ゼノキアス』等多くの作品に関わった後、1998年に独立しプロキオン・スタジオを立ち上げている。
プロキオン・スタジオは、プログラマーが所属しているという点が特筆すべき点。その成果として、DS用のKORG DS-1、M01D等ソフトウェアそのものとも言えるサウンドドライバーの開発など多彩な活躍をしている。それ以外にもiPhone App等も近年では積極的な開発を行なっている。元々は、作曲家の意図した音を再現し、再生するためのサウンドドライバーの開発を主眼としていたが、業界の進化とWwise、CRIのような優秀なMiddlewareの登場により、アプリ自体の作成の方向にシフトをしている。
今でもプログラマーがいるということで、プロキオン・スタジオでは楽曲の納品携帯は、プログラムに実装した状態で行うことがほとんどだということ。これは、通常であれば、WAVデータで納品をして実装は、各ゲーム会社が行なっていたところを鳴り方、サウンドの仕様まで含めて、確認を取るという一歩踏み込んだ制作受注の形態といえる。元々、ゲーム制作会社にいたからこそ、プログラマーが社内にいるからこそ実現しているビジネスだと感じる。更には、効果音を専門とするスタッフもいるので、GAME AUDIO全般を一括しての受注も可能だということだ。効果音と音楽の制作会社が別々である場合、どのような効果音を作ってくるのか?ゲーム音楽を作曲する際には非常に重要になるので、意思疎通ができていないと合わせるのが大変とも。それが、社内で全てを一元管理し連携することでクオリティの高い制作が実現するということもプロキオン・スタジオの大きな強みといえる。
プロキオン・スタジオの立ち上げ後は、GAME AUDIOはもちろんだが、アーティストのプロデュース、劇伴の作曲など多岐にわたる分野での活躍をされている。関わっているアーティストの代表は、『サラ・オレイン』。Wii用ソフト『ゼノブレイド』のエンディング「Beyond the Sky」でボーカルとしてサラを起用。2014年には「Fantasy on Ice」で安藤美姫が同曲で演技を行い話題となる。サラ自身も『関ジャニの仕分け∞』のカラオケ得点対決でMay.Jを破るなど話題の多いアーティスト。光田氏プロデュースによるアルバムをリリースしている。GAME AUDIO分野では、前述の『ゼノブレイド』、『大乱闘スマッシュブラザーズ』等多彩な活躍を続け、アニメ『イナズマイレブン』シリーズにも参加、劇場版、TV版、ゲームとマルチに楽曲の提供を行なっている。他にも、記憶に新しい2013年のアイソン彗星の特別番組、NHKスペシャル「宇宙生中継 彗星爆発 太陽系の謎」に楽曲を描き下ろしている。
GAMEとそれ以外で作曲に関して違いはあるのかとお聞きしたところ。特には変わりはないとのこと。オーダーに関してもM番表があり、それに合わせて作るという作業自体は同様。しかし、最近では、ゲームのほうが更に楽曲数が増える傾向にあるということ。アニメや、ゲームは実写と違い、全く音の無い世界に一から音をつけていく作業になる。その際には、音のない動画を何度も見返して頭のなかに音楽が流れ出すのを待つという手法をとっているということだ。どのような映像にもリズムがあり、音が含まれている。それを形にしているということだ。
作曲の手法をお伺いしている際に、『余韻』というキーワードにたどり着いた。他の話題の際にもお話をしていた言葉ではあるが、映像を何度も見返してその中にある音を探している際に、あまりにも説明されすぎている映像から音を導くのは大変に難しい。その映像の『余韻』、『間』という、音で表現を出来る部分があって欲しい。その映像の『余韻』に音で息吹を吹き込みたいという意思がそこからは感じられた。同様にその作品自体も『余韻』を含んで欲しい、ゲームであれば、プレイを終えたあとの余韻、CDであれば聴き終わった後に、映画であればカットの切り替えの余韻など。
たとえとして、CDデッキのピックアップのお話をしていただいた。CDが全て再生を終わった後に、読み取りのピックアップがホームポジションに戻る。その時にアクチュエーターが最速で動作をするために音がする。それがCDに収録された最終楽曲の『余韻』を台無しにしてしまうのが許せないという話だ。光田氏は関わったCDは可能な限り、最終楽曲の終わった後に10秒程度の無音を意図的に付け加えているということ。これにより、ピックアップの移動までの時間稼ぎをして”台無し”になることを防いでいるということ。このような『余韻』はプレイヤー、リスナーが想像をする余地を残すことで、その余韻は一層大きなものとなるのではないかと意見を頂いた。
黎明期を語るためには、光田氏にご教授いただいたゲームコンソールのスペックを確認する必要がある。Family Computerは1983年登場、8bit CPU(1.79MHz)動作で、音源部分はCPUに組み込まれた「パルス波」ジェネレーター2系統、「三角波」ジェネレーター1系統、ノイズジェネレーター1系統、DPCMと呼ばれる6BitのデルタPCM音源の合計5音。現代のシンセのスペックから考えると、これらのジェネレータを組み合わせて一つの音を作るの?と思ってしまうかもしれないが、この5音でゲームの中のBGMから効果音まで全てをまかなっていた。ゲームにとって重要な効果音用に音源をスタンバイさせると事実上利用できるのは2~3音。その中で作曲した楽曲をどのように再現するのか試行錯誤をしていたということだ。しかもその音源を鳴らすためには、MIDIのような汎用のものではなく、専用の言語にコンパイルをしたプログラムを使って再生をしていたということだ。シンセを制御し、発音をするための専用プログラムと想像してもらいたい。
次の世代としては、SUPER Famicomが1990年に登場する。このゲームコンソールの登場により、音源は世代更新を果たす。そのスペックは32kHzサンプリング/8チャンネル同時発音/16Bit PCMステレオ/DSPによるエフェクト処理と当時としても最高の音源が搭載された。1990年といえば、KORGであればM1の時代、WAVESTATIONが登場した年でもある。YAMAHAでは1989年にSY77が登場しPCMシンセが登場を始めた頃。RolandはDシリーズ。JVシリーズはまだ発売されていない。そんな時代に、家庭用ゲーム機に8チャンネル同時発音のPCM音源が搭載されたというのは革新的であった。しかし、そのメモリは64KBしかなく、その中にどのようにサンプルをロードするのかというのが、プログラマーの腕の見せどころ。搭載されたDSPを有効に活用し、その能力を引き出すテクニックが必要であった。効果音にチャンネルを割いたとしても、音楽用に従来比倍のチャンネルがアサイン可能ということで、まさに、GAME AUDIOの黎明期が訪れた頃である。とはいえ、内蔵音源にPCMサンプルを読み込ませ発音するという仕組みはプログラムそのもの。その当時もMIDIベースで作成した楽曲を専用のツールでコンパイルをしてプログラムとして実装を行なっていたということ。ROMカートリッジのデータ量の制約もあるので、制約の中で工夫を重ね、イメージを形にしてゆく作業であった。
光田氏は当時を振り返り、「まさにプログラマー同士でのメモリの奪い合い。それぞれにやりたいことを実現するために限られた制約の中でのコンソールの性能の限界への挑戦が日々続いていた。」とリアルなコメント。そのスペックの進化は、表にまとめてみたので見てもらいたい。実際に作曲家として思うがままに再生を出来るようになるのはPlay Station 3の登場まで待たなければならなかったという。更に時代を進めてみよう。
その後、1994年にPlay Stationが登場する。実は、SUPER Famicomに搭載された音源チップはSONY製のものであり、Play Stationに搭載された音源はその拡張版である。メモリは512KBに拡張され24チャンネルの同時発音が可能となっている。圧縮したサンプルを使えば1曲全体をサンプリングをして再生も技術的には可能であったが、コンテンツを提供するCD-ROMの容量の制限からなかなか実現する機会は少なかったとのこと。やはり、ゲーム本体のプログラム。3D再現のためのポリゴンデータ等他にも格納しなければならないデータは山のようにあったということだ。クオリティーを最大化するのであれば、CD-ROMなのでWAVのデータを格納し、プログラムとして音源に頼らずに再生するということも出来たそうだが、データ量の問題から実現は難しかったとのことだ。
更に、2000年にはPlay Station 2が登場。同じ系譜のチップが使用されメモリは2MBまで拡張される。同時発音数も48チャンネルと思いつくままに音を重ねることも出来るような仕様だ。しかし、この頃も、コンテンツの提供されるDVD-ROMの容量との戦いは続く。音声のみであれば、十分に思えるパッケージではあるが、高性能化したグラフィックエンジンに提供するためのデータ量は増加の一途をたどり、肝となる、オープニング、エンディング以外では、なかなか楽曲丸ごとをメディアから再生するということは出来なかったということだ。
そして、「思うように作曲した作品をそのままゲーム中に再生できる」Play Station 3の登場である。2006年に登場したこのゲームコンソールは、特定の音源を搭載しておらず、ゲームコンテンツ中の音声データを直接再生できるようになる。Nuendo 7のGame Audio Connect機能により注目をあつめるAudio Middlewareもこの世代になり始めてその必要性が強調される。コンテンツメディアもBlu-rayの世代となり、容量としてもやっと余裕が出る。特定の内蔵音源からの発音から、プログラムとして自由に音声再生が可能となるのは、まさにこの世代から。SUPER Famicomがその次代の最先端の音源を搭載してから15年かかって、次の世代へと進化を遂げている。逆に言えば、自由にGAME AUDIOとして表現ができるようになってまだ10年ということだ。
余談ではあるが、2004年という内蔵音源でのGAME AUDIO制作の終盤に登場したニンテンドーDSは、同時発音数16チャンネルのPCM音源が搭載され、プログラミングによりGAME AUDIOを作らなければならなかった。こうしてコンソールスペックを並べてみると、10年前の初代Play Stationよりもスペックの低い音源が搭載されているのがわかる。光田氏は、DSのサウンド開発のために、まさに10年前の製作用コンピューターを引っ張りだして作業をしたという回想をお話いただいた。
 |
 |
 |
 |
|
| メーカー | 任天堂 | SCE | 任天堂 | SCE |
| 機種名 | ニンテンドーDS | PlayStation Portable | ニンテンドー3DS | PlayStation Vita |
| 世代 | 携帯機第7世代 | 携帯機第7世代 | 携帯機第8世代 | 携帯機第8世代 |
| 発売日 | 2000/11/20 | 2000/12/11 | 2007/2/25 | 2007/12/16 |
| CPU | ARM946E-S 67MHz | PSP CPU(MIPS R4000 Core) | Nitendo 1048 0H ARM | ARM Cortex-A9 4-Core |
| 32-Bit RISC | 32-Bit RISC | 32-Bit RISC | 32-Bit RISC | |
| Co-Processer | ARM7TDMI 33MHz | Sony CXD1876 | PICA200 | PowerVR SGX543MP4+ |
| VRAM | 4MB | 32MB | FCRAM 128MB | 512MB |
| VRAM | 656KB | 4MB | – | 128MB |
| 音源名称 | – | – | – | – |
| 音源詳細 | 最大同時発音数:16チャンネル内8チャンネルをPSGに変更可能サンプリング周波数:32730Hz | 全てソフトウェアベースでの処理 | 全てソフトウェアベースでの処理 | 全てソフトウェアベースでの処理 |
コンソールの説明でも触れたが、それぞれのゲームコンソールに十分に仕事をさせるために、専用のPCM作成機(ハードウェアで存在していた:SONY製)そのデータを鳴らすためのPCM音源の制御プログラム。マルチサンプルはデータ量との兼ね合いで十分に行えず、ピッチシフトを活用しながら発音を制御し、楽曲を作り上げていく。譜面は完成されていたとしてもそれからの作業が非常に大変である。そして、その実装にあたっては、他の部門のプログラマーとも密接に連携を取らないと、出来たけれどもパッケージに収まらないなどという事態になる。
そしてこの黎明期には、ゲーム・サウンドトラックCDが多数登場している。今は、ほとんどお目にかからなくなっているが、ゲームに実装する段階で作曲家の意図した音楽からかなり引き算をしないと再現が出来ないということは創造に難しくないと思う。それをフルオーケストラなどで作曲されたありのままの形で再現をしたのがゲーム・サウンドトラックということだ。光田氏もサウンドトラックCDの作成時には、ゲームコンテンツ制作時のフラストレーションを全て吐き出し、思い通りの作品が作れたのでアレンジバージョンなどの制作は非常に気合が入ったということだ。人気作品では、コンテンツの発売以外にも、国内外を含めコンサートなども行われることも多々あるとか。ゲームからスピンアウトしたクラシック・コンサート。やりこんだゲームのシーンを回想しながらクラシックのコンサートで余韻を楽しむ。なかなか贅沢なひとときではないだろうか。
光田氏の立ち上げたプロキオン・スタジオには、プログラマーも参加をしている。これが強みであり、音源の実装まで自社で完結できるということだ。通常であれば、譜面を納品して終わるような作業も、ゲーム会社に所属をしていたというバックグラウンドと、自社でプラグラマーを抱えるということで、実装作業にまで関わっているというのが大きな特徴であると感じた。
現在、GAME AUDIOはコンソールの進化により、劇伴と同じように自由な表現が可能となっている。しかもプレイヤーの操作に従い、インタラクティブな変化を起こすような仕掛けを作ることも可能だ。学生時代から光田氏の求める最先端のエンターテイメントにGAME AUDIOがやっと追いついたということになるのかもしれない。映画に憧れスタートした光田氏、やはりその原点は、映画にあり、映像と音声によるエンターテイメントであり、その融合に因る化学反応なのではないだろうか。文字で伝えるのは非常に難しい部分もあるのだが、映像に対して音を付けるということは、映像に命を吹き込むような作業。映像に込められた感情を引き出すのも、殺すのも、音の役割。例えを出すと、銃を打つシーンに、リアルな銃声を付けるのか?バズーカの音を付けるのか?ビームライフルの音をつけるのか?それだけで、映像は、全く別のものに見えてくるはずである。直感的に受け取る情報量は、目よりも、音のほうが大きいと言われている。効果音は、その作品のリアリティーに、音楽は、感情、情景などの深みをもたせ、作品全体にリズムを生み出す。その作品にとって非常に重要な作業を行なっているということだ。

こだわりのログハウス
日本にも数件しか無いという、極太の材を使用したログハウスが光田氏のプライベートスタジオ。母屋とは、棟を変え独立したスペースが作業用に確保されている。ログハウス自体には、特殊な防音・遮音は施していないが大音量での作業を行なったとしても近隣からの苦情は無いということだ。まったく羨ましい限りである。ちなみにログハウスの材はパインの集合材。この部分は、ログハウスの材料として選択の余地はなかったそうだ。床材は無垢の材を利用した。その理由は、音というより防寒対策だと冗談半分におっしゃっていたのが印象的。床材の向きは、コンサートホール等同様に縦方向、無垢のあつみのある材を流すことは、旧来の音響建築と同様の手法だ。
話をしていても感じたのだが、内装に特別な吸音を行なっていないために響きはある。しかし、木の柔らかい響きのため耳障りでもなく、かえってここちの良い響きといえる環境だ。メインのスピーカーに使用しているADAM S3A-Hの後ろ側にVery-Qの吸音衝立、作業場所の椅子の頭上にウレタンの吸音材が設置されている以外に特別なことは何もない。これから、徐々にブラッシュアップをしていきたいと言われていたので、また数年後に、このスタジオの進化を確認に訪れてみたいと思わせる。

作業のメインはDigital Performer
メインのDAWはDP9を使われている。PC本体は、Mac Pro (黒)を使っているということだ。各種DAWを試してみているが、やはり、DPに戻ってきたということ。その最大の理由は、音源を立ち上げるのが軽いということが魅力ということだ。同じ数の音源を1台のPCで立ち上げた際に、Cubase、Pro Toolsでは開けない規模の楽曲が、DPであれば開くというなんとも魔法のようなことが起こる。この動作の軽さが最大の魅力だということだ。
他にもWinが1台、Mac Miniが1台有り、それぞれは音源再生用のマシンとしてVienna Ensamble Proがスタンバイしている。Mac Pro (黒)にしてから、CPUパワーが上がっているので出番が減っているということだ。メインのAudio InterfaceはApogee Ensamble Pro、他にもデータの受け渡し用にPro Toolsもある。

専用のショートカットアプリがiPadに!
ご本人が元々プログラマーもされていたいうことを感じたのがキーボードの横にあるiPadのAppを見せてもらった時。よく使うコマンドがマクロを組まれ、iPadに整然と並んでいる。「OSCulater」というアプリを利用して、プログラムを書いているということだが、とても便利そう。メインで使用しているDPとSibeliusのコマンドが並んでいるのだが、「右クリックをして、選択をして、数値を入力して、実行」
というような動作は単純なショートカットではどうにもならない。そのような動作も、このアプリでiPadの画面から1ボタンで実行しているのが印象的。これがないと仕事ができないという光田氏のコメントからもどれほど便利なのかが伺える。
スタジオは楽器が沢山!!!
周りを取り囲むギターに混じって、アイリッシュ・ブズーキや、マンドリン、ニッケルハルパ、そして様々な民族楽器。北欧から、アイルランドといったヨーロッパの北に位置する地方を中心に多くのコレクションが。これらの楽器のサウンドは、光田氏のCDの中で聞くことが出来る。書籍としても「ティン・ホイッスル」の教則本を出版したりと造詣が深い。

欲しい機能は自社開発!?
光田氏のプロキオン・スタジオで発売しているアプリを紹介していただいた。『Handy Harp』というこのソフトは、光田氏の企画のもと、グランド・ハープをiOSで再現をしてしまうというすぐれもの。グランドハープは複数のペダルによりスケールを瞬時に切替、美しい音色を表現する楽器だが、深く理解をしてなくとも、美しいグリスが楽しめる魅力的なアプリ。しかもWi-Fi MIDI経由でそのスケールノートはDAWにMIDIとして入力可能!!いちいち打ち込むのが非常に面倒なハープのグリスをこのアプリ一発で解決。ペダルが不慣れな方のために、通常のコードから選択することも可能と至れり尽くせりのアプリです。欲しい機能は自社で開発をしてしまうという環境が光田氏の会社の強みですね。
光田氏も自身の作品ながら、映像の魅力、作品に込められた感情を120%引き出すことに成功した際には、思わず感動してしまうことがある、ということだ。自身の作品でありながらも、このように客観的に喜び、そして光田氏のこだわりである『余韻』を受け取ることの出来る作品作りに関われるということはまさに作家冥利に尽きるのではないだろうか。
*記事中に掲載されている情報は2015年12月29日時点のものです。