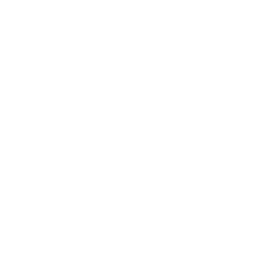Media
Media
2025/01/16
映画音響技術の基礎解説
映画のダビングとテレビにおけるMAは、同じくコンテンツ制作における音声の最終仕上げの段階となるが似て非なるもの。システム的な違いではなく、音響的な部分や視聴環境に求められる事柄の差異となると奥深く、全容を把握するためには整理整頓が必要だ。ここでは映画音響におけるXカーブ、センタースピーカー、ウォールサラウンド、フィルムに対するサウンドトラックといった、様々な特殊要素を技術的な側面から紐解いていきたい。
MA、ダビング、空間の違い
テレビの番組制作のためのMA室、昨今では配信番組など映像に音声を付けて仕上げる幅広い用途で活用されるスタジオだ。ここに求められるファクターは、音の正確性、解像度ということになるだろう。制作されたコンテンツはどのような環境で視聴されるかはわからないため、作品として100点満点の解答はないとも言えるのだが、そんな中でもMA室はリファレンスとなる環境であることが求められる。できる限り正確な音の再生を行うために、周波数特性、音の立ち上がり、強弱の再現、それらを実現するための吸音処理や反射音のコントロールなどを行い、音響設計をしっかりと行った環境を作り上げ、そこで作業を行うこととなる。
それでは、映画音響の仕上げに使われるダビングステージはどうだろうか?映画館での上映を前提に音響の仕上げが行われるダビングステージ。この空間に求められる要素は、どんな映画館で上映されたとしても再現がしっかりと行われるサウンド、ということになるだろう。映画館には上映用の規定があり、音圧に関しては-20dBfs = 85SPLという規定となる。そして、スクリーンの裏に設置されるL,C,R chのスピーカーに対しては、Xカーブと呼ばれる周波数特性に関わるカーブが存在する。ダビングステージはこれらを再現したスタジオであることが求められる。
また、映画館という大空間での再生を前提とするため、大空間での再生の再現というのも重要だ。MA室であれば、遠くても3m程度に設置されるスピーカーが、ダビングステージでは大きな部屋ともなると10mもの距離になる。そして、部屋が広いということは、直接音と間接音とのバランスがニアフィールドとは明らかに違った環境となる。ニアフィールドであれば、直接音が支配的にはなるが、10mも離れたスピーカーでは間接音も含めてその空間のサウンドになることはご想像いただけるだろう。
とはいえ、映画館ごとに間接音の状況は異なる。ダビングステージとしての最適解は、大空間らしいサウンドを保ちつつ、解像度、レスポンス、特性などの担保を行うという、相反した要素をはらむものになる。間接音があるということは、周波数や位相に対しての乱れが必然的に生まれる。リフレクションが加わるということはそういうことだ。ルーム・リバーブ的な要素が含まれると想像いただければイメージしやすいだろうか。その具合の調整がまさに音響設計の腕の見せどころだろう。スピーカーから飛び出したあとの音響建築的な部分での話になるため、機器の電気的な調整だけでは賄いきれないところ。まとめて言い換えれば、この間接音のコントロールがダビングステージのサウンドにおいて重要になるということだ。
Xカーブに合わせた空間調整
小空間で仕込んだ音を、大空間で再生したときに生じる差異。特に高域の特性の変化に関しては100年前にトーキーから光学録音へと映画が進化したころから問題視されている。アカデミーカーブ、Xカーブと言われるものが、まさにそれへ対処するために生み出されたものである。SMPTE ST-202としてその後標準化されるのだが、これらのカーブの求めるところとしては、測定機での周波数特性と聴感上の周波数特性を合わせるということがそのスタート地点にある。
この映画館における音響特性に関する研究は、まさにJBLとDolbyの歴史そのものでもある。再生機器側の性能向上、収録されるマスター音源のテクノロジー、それらの相互に及ぼしあう影響を、これまでの作品の再生とこれから生み出される作品の再生それぞれに対して最適なものとする100年に渡って継続されてきた歴史であり、この部分も興味深いストーリが数多く詰まっている。中でもDolbyの果たす役割は大きく、ノイズリダクションに始まり、フォーマットの進化、マスター音源の進化など、必然性を持って映画のサウンドフォーマットが形作られ継承されている。
スクリーンの透過特性(スクリーンの裏に置かれたスピーカーの高域成分は、サウンドスクリーンだとしても高域減衰が生じる)、低域よりも高域のほうが距離減衰量が大きいことによって、スピーカーから視聴位置が遠いために生じる高域減衰、空間が広いため間接音による干渉などにより生じる高域減衰。様々な要素によりダビングステージの容積に起因する高域減衰というものは、一般的なスタジオと比較しても多く生じる傾向にある。これは、映画館においても同様であり、その再現を求められるダビングステージでも同じように特性の変化が生まれる。
ダビングステージのスイートスポットにおける特性を測れば、当たり前のように高域の減衰した特性が出現する。しかし、これを電気的にフラットにしようとすることは間違いである。なぜなら、直接音に関してはスクリーンの透過特性、距離減衰の影響は受けるものの、ある程度フラットな特性が担保されているためである。反射音、間接音に起因する高域減衰(位相干渉等によるもの)を含めた特性をもとにフラットな特性を狙ってしまうと、結果的に高域が持ち上がった特性を作ることになってしまう。冒頭でも述べたように、大空間における直接音と間接音のバランスに依っており、大空間になればなるほど間接音の比重が大きくなり、高域が下がってくるということである。
お気付きかもしれないが、スイートスポットにおけるフラットな特性を電気的に補正して作ってしまうと、直接音としては高域の持ち上がった特性になるということである。これは、スイートスポットを離れた、特にスクリーンに近い位置での視聴時に顕著となる。直接音が支配的であり、高域の持ち上がったサウンドをダイレクトに聴いてしまうため、視聴体験に大きな影響を及ぼすことになる。
このような高域の持ち上がった特性とならないように、高域をロールオフしたターゲットカーブを設定し、それに合わせた音響調整を行うようにするのが、Xカーブに合わせた調整ということになる。厳密には劇場の座席数に応じたターゲットとなる周波数特性のカーブが設定されており、座席数の少ないものでは高域の減衰量が少なく、多くなれば減衰量が大きくなる、そのようなターゲットとなる特性が提示されている。
これらのターゲットカーブに関しては、ぴったりに周波数特性を合わせ込むということではなく、スピーカー単体としてフラットな特性で出力した際に、スクリーンや部屋などの影響を受けた上でターゲットカーブに収まっているかどうかを確認するところがあくまでもスタートポイントである。言い換えれば、許容誤差の範囲内に収まっているのであれば、それは想定通りの結果であり、それ以上の補正を行う必要はないということでもある。
小空間における映画作品の仕上げに関しては各所ご意見もあるところだろう。大空間における音響再現が行えていないということは確かにあり、それによって再現性が低いというご意見ももっともである。しかし、上記のようにXカーブの成立を紐解いて見ていくと、フラットな特性で作られた音源が空間の大小にかかわらず、ある一定の聴こえ方をするためのターゲットカーブ、とまとめられる。その視点から考えれば、フラットな特性を持ったスタジオで仕上げられた作品であれば、大空間に持っていったとしても一定の基準内での聴こえ方が担保されているので問題ないとも捉えることができる。
ただし、スクリーンの透過特性という物理的なフィルター分に関しては、やはり考慮する必要があると筆者は考えているが、どちらの意見も間違いではないし、ダビングステージといっても数多の映画館すべての再現となるわけではない。完璧な答えを得ることは難しいが、プロフェッショナルの仕事としてどこまでの再現を求めるのかという尺度になるのだろう。そして、これらのことを理解していれば、より良い作品、そしてバランスを作ることができるということでもある。
100年以上の歴史から、映画の音響に関するセオリーはできあがっている。こちらのほうが良いと言っても、一朝一夕に変わることができない過去との互換性や、大空間での平均化された視聴体験に対しての担保など要素を多彩に含んだテクノロジーの結晶体である。だからこそ映画というエンターテイメントのフォーマットは普遍的なものとして歴史を超えて受け継がれ、エンターテイメントの一つの形として存在し続けている。
映画の必須要素、センタースピーカー
次はセンタースピーカーについてを取り上げる。センタースピーカーはITU基準の5.1chにもあるので、それとは何が違うのかということからお話を進めたい。
映画におけるセンタースピーカーは、映画のサウンドトラックが登場した当初から存在する。その当時はモノラル再生環境、センタースピーカー1本からのスタートしたためである。映画館におけるセンタースピーカーが非常に重要であることは、ニアフィールドでのステレオミックスを中心に行っていると、なかなか気が付かないかもしれない。ステレオ作品であれば、センター定位はファントム・センターとして形作られる。しかし、映画館での視聴を想像して欲しい。きっちりとL,Rチャンネルのスピーカーの中心線に座ることができればよいが、1席でも左右にズレてしまうとファントムで作ったセンター定位はズレてしまう。
ハード・スピーカーでのセンターチャンネルがあることで、劇場内どの席からでもスクリーン中央からのセンター定位を感じることができる。これが劇場におけるセンタースピーカーの重要性のほぼすべてと言っても過言ではない。そのため、映画サウンドトラックの進化の歴史は、モノラルの次は3ch(L,C,R ch)、そして初のサラウンドであるアナログ・マトリクス・エンコードを活用したDolby SR(L,C,R + Sround)、そしてDolby Digital (5.1ch)、Dolby Atmosへと進化している。順を追って見ていくと、センターチャンネルを中心に左右へ広がっていったということがおわかりいただけるのではないだろうか。
このようなことから、映画においてセリフの基本はハードセンターである。よほどのことがない限りこのセオリーを外すことはない。画面に二人登場人物がいるので少し左右にパンを振って、ということを思いつくかもしれないが、前述の通りでファントム定位を使用すると劇場に足を運んだユーザーは着席する座席の位置によって定位が変わってしまう。
そうであれば、やはりファントムではなくハードセンターで再生をする。これは、映画における普遍的なものとして受け継がれている。Dolby Atmosになりオブジェクトという新しい技術が採用され、ギミックとして左右の壁面からも点音源として再生を行うということが可能となり、これを活用した作品も見受けられるが、ストーリーテリングを行うダイアログに関しては、やはりハードセンターは外せない。これまでのチャンネルベース・ミキシングの手法を踏襲したうえで、オブジェクト・ミックスがあるというDolbyの判断は正しいと感じている。劇場での再生を念頭においたミックスだからこその要素となるわけだ。
皆さんは、そのセンターチャンネルがどこに設置されているかご存知だろうか。スクリーンの裏にあるため通常は目にすることのないスピーカーではあるが、その名の通りスクリーンのちょうど中心に設置されている。高さ方向としては、スピーカーの音響軸を高さ方向に3等分した上端から1/3の位置というのが設置基準である。高さ方向に関しては素直にスクリーンの中央とイメージしてしまうところかもしれない。なぜ1/3になったのかという理由を解説している文献を探すことはできなかったのだが、すべての客席に対して音を届けるために高さが必要であったとか、サラウンドスピーカーとの高さを揃えようと考えるとこれくらいがちょうどいいなど様々な推測がある。
ちなみにではあるが、サラウンドスピーカーはスクリーンバックのL,C,Rchと音響軸的に平面に収まるように設置されている。壁面のサラウンドスピーカーの並びをそのまま伸ばしたあたりに、スクリーンバックのスピーカーの音響軸があるということだ。逆に言えば、壁面のサラウンドスピーカーの設置位置は、スクリーンサイズによって上下するということでもある。スクリーンが大きければ音響軸は高くなり、サラウンドスピーカーアレイの設置位置も高くなるということだ。
ウォール・サラウンド
もうひとつ、ITU 5.1chとの大きな違いがサラウンドチャンネルに関してだ。ITUでは点音源での再生となるサラウンドチャンネルが、シネマフォーマットではウォール・サラウンドアレイと呼ばれる壁面に設置された複数のスピーカーで再生されることとなる。デフューズ・サラウンドとも呼ばれるこのシステムは、やはり劇場でどの座席であっても一定のサラウンド感を感じられるように、という意図のもとにその設置が考えられている。
しかし、面で再生されるこのサラウンドチャンネルは定位感のある再生には不向きであり、Dolby Digitalまでの作品ではもっぱら環境音や音楽のリバーブなどの再生に活用されていた。もちろん、これは空間を囲むという意味では大きな効果があり、没入感を高めるための仕組みとしては大きな成功を収めている。Dolby Digital以前のSRではマトリクス・エンコードの特性上、正面に対して位相差を持ったサウンドしか配置をすることができず、まさに音を後方にこぼすといったことしかできなかったが、Dolby Digitalになりようやくチャンネルがディスクリートとなり、イメージした音がそこに入れられるようになったという技術的な進化も大きい。
さらに、Dolby Atmosではオブジェクトが使用できるようになり、点音源としてのサラウンド・チャンネルの活用が可能となった。この進化は大きく、ウォールで再生するベッドチャンネルと点音源で再生するオブジェクト・チャンネルを使い分けることで、音による画面外の表現が幅広く行えるようになった。スタジオ設計側としては、サラウンドも全チャンネルフラットにフルレンジの再生を求められることとなり、サラウンドスピーカーの選定において従来とは異なるノウハウが求められるようにもなってきている。再生環境として求められるスペックが増えるということは、逆説的には再生できる表現の可能性が広がったということでもある。これは進化であり大いに歓迎すべきポイントである。
フィルムに対するサウンドトラック
これらの映画音響の歴史は、まさにサウンドトラックの進化の歴史そのものでもあり、互換性が考えられながら新しいものへと連なっている。フィルムを上映して映像だけを楽しむサイレント映画から、それにレコードを同時に再生することで音を付け加えるという試みへと進化するが、まったく同期がとられていないため、当時は雰囲気として音楽を流す程度といったことが主流だったそうだ。
また、当時は活動写真弁士と呼ばれる映画に対して解説を加える解説者がいた。少し脱線するが、活動弁士という文化は日本独自のもの。海外ではテキストで状況説明を加えることで、映像同士に連続性をもたせることでレコードでの音楽再生のみというものが主流だった。しかし、日本では映画以前より人形浄瑠璃における太夫と三味線や、歌舞伎における出語りなど、口頭で場面の解説を加える、今風に言えば解説ナレーションの文化があった。もちろん、落語に代表される話芸の文化が盛んだったこともこのバックボーンにはあったのだろう。当初は、幕間の場繋ぎとしての解説者だったものが、上映中にもそれを盛り上げるための語り部となり、独自の進化を遂げたというのは興味深いところである。
フィルムで上映される映像と音声の記録されたレコードなどの媒体を同期するということは当時の技術では難しく、いくつものテクノロジーが発明されては消えていくということを繰り返していた。フィルム上にサウンドトラックを焼き付けるというサウンド・オン・フィルム。具体的には、光学録音された音声トラックを映像フィルムに焼き付けるという手法により技術革新を迎えるのだが、光学録音自体の特許登録がなされた1907年から、ハリウッドメジャーが共通フォーマットとして互換性を持ったサウンド・オン・フィルム技術を採用する1927年までに、なんと20年もの歳月がかかっている。その間、レコード等の録音媒体を使用した同期再生のチャレンジも続けられたが、確固たる実績となる技術へとは発展しなかった。サウンド・オン・フィルムの光学録音技術は、映画がデジタル化されDCP(Digital Cinema Package)でのデータ上映になるまでのフィルム上映では普通に使われ続けていくこととなる。
無音のサイレント映画に対してトーキー映画と言われる、映画に音をつけるという技術は瞬く間に普及することになる。1927年にハリウッドで採用されたということは前述の通りだが、その移行は早く、ハリウッドで制作された最後のサイレント映画が1929年ということからも、たったの2年間で時代の主流を奪っている。日本国内は活動弁士という独自の文化があったため、1938年になっても国内制作の1/3の映画はサイレントのままであったということだ。活動弁士の職を奪うということもあるが、贔屓の活動弁士による上映を見るため(聴くため)に劇場に足を運ぶということもあったということだ。今となっては想像することしかできないが、日本における最初期の映画とは人形浄瑠璃などの視覚的なエンターテイメントがフィルムになったという感覚だったのではないだろうか。
トーキー映画が黎明期を迎えてからのサウンドトラックの歴史は、まさに光学録音の歴史と言える。光学録音とは今日DAWなどで表示される波形をフィルムに焼き付けるというものだ。非常に細いスリットに光を当ててその記録を行うというのがその始まりだ。
光の強弱はまさに音の強弱であり、電気信号に変換された音声の強弱を光としてフィルム上に記録するということになる。しかし、ノイズや周りへのこぼれ(光なので屈折や解析などで周辺に溢れてしまう)、高域再生不足、様々な問題に直面し、それを乗り越えるノイズリダクションや、多チャンネル化の技術となっていく。光学録音に対して大きくは、ノイズの低減と高域再生特性の改善がそのテーマとして、様々な方式が出現しては消えていくということを繰り返す。それと並行して磁気記録技術が確立され、映像フィルムに磁気を塗布し、そこにサウンドトラックを収録するということも行われた。これは1950年代頃から70年代にかけてであり、Cinerama、Cinema Scopeといったものがその代表である。フロント3ch、サラウンド1chという仕様が一般的であった。
Dolby Atmosへの道筋
このような様々な技術や規格が乱立する中で、業界の標準となり今でも活躍をしているのがDolbyである。ノイズリダクション技術が世界的に認められ、映画の光学録音の収録などでも活用されていたDolby。1976年に開発されたDolby Stereoはマトリクス・エンコードを活用した2chのサウンドトラックでフロント3ch、サラウンド1ch仕様の4chの再生を可能とする技術として瞬く間に世界の標準フォーマットとなる。少しややこしいのだが、Dolby Stereoは2ch音声の技術ではなく、マトリクス・エンコードされた4chサラウンドの技術である。2trの音声トラックの収録であったことからStereoと名乗ったのだろうが、今となっては少し誤解を招く名称である。
このDolby Stereoを世界中が注目するようになるきっかけとなった作品は「スター・ウォーズ エピソード 4 / 新たなる希望」である。このDolby Stereoの特徴となるのが、エンコードされた2chの音声トラックは、そのまま2chステレオで再生しても違和感なく聴くことができるという点。後方互換性を備えたフォーマットであったということは特筆すべきところだ。しかし、そのマトリクス・エンコードの特性から、サラウンドチャンネルに低域成分を加えることはできず、ディレイ処理もエンコード時に加わるため輪郭のあるはっきりとした音をサラウンドに配置することができなかった。とはいえ、このDolby StereoはDolby SR(Spectral Recording)として音響特性を改善させ、多くの映画館で採用されたまさに80年代の業界標準とも言えるフォーマットである。
アナログ時代の真打ちであるDolby Stereoの次の世代は、フィルムにデジタルデータを焼き付けることでその再生を行ったDolby Digitalの登場を待つこととなる。1992年に登場したDolby Digitalは圧縮された5.1chのディスクリート音声をフィルムに焼き付けつけるフォーマットである。しかも、Dolby Stereoの光学2trの音声トラックはそのままに、追加でのデータの焼き込みを可能としている。図版を見ると、パーフォレーションの隙間にQRコードのような図形データとして符号化されたものが書き込まれている。これを読み込み、5.1chの音声を取り出すフォーマットである。
Dolby Stereoの上映館でもDolby Digital上映館でも同一のフィルムで上映できるため、フィルム上映における標準フォーマットとして今日に至るまで標準フォーマットとして採用が続いている。映画館の5.1ch再生のスクリーンは、そのすべてがこのDolby Digitalでの上映と思って差し支えない。もちろん、1990年代にはそれに対抗するフォーマットとして非圧縮の5.1chで高音質を特徴としたDTS、大型スクリーン向けにフロントのチャンネル数を5chとした7.1chサラウンドのSDDS(Sony Dynamic Digital Sound)があった。残念ながら、DTSもSDDSも映画館向けのフォーマットとしては生き残ることができなかった。DTSに関しては、DTS-Xとしてイマーシブを引っ提げて再び映画館に戻ってくる動きもあるのでここは要チェックである。
2000年代半ばに、ネットやコンピューター技術の進化に合わせて映画館での上映が物理的なフィルムから、DCP(Digital Cinema Package)と呼ばれるデータでの上映に切り替わった。現在でも少ないとはいえフィルムでの上映を行っている劇場もあり、やはりフィルムの需要がゼロになったわけではなくDolby Digitalでの制作を行うことが今でも続けられているのだが、DCPであればフィルム上にサウンドトラックを記録するといった物理的な制約もなくなり、ほぼすべてがデータでの上映になっていると言っていい状況だ。
そして、DCPになったからこそ生まれたのが、データ容量が大きいDolby Atmosというフォーマットである。Blu-rayや配信ではDolby True-HDと呼ばれる技術により圧縮が行われているが、映画におけるDolby Atmos Cinemaは、Rendererで収録された最大128chのデータがそのまま収録され、Dolbyのフォーマットとしては初となる非圧縮での劇場上映を実現している。
まだまだ、歴史を紐解くと他のファクターも存在する映画音響に関する様々な特殊要素。ここではその代表とも言えるXカーブ、センタースピーカー、ウォールサラウンド、フィルムに対するサウンドトラックに触れたが、それらすべては大空間において座席に着席して視聴しているすべてのユーザーへより良い音響を届けるために考えられたものであるということを忘れてはならない。
スイートスポットでの視聴はあくまでも制作においての判断を行う場所であり、そこを離れても意図した音響設計が一定以上で再現できる環境構築のために100年の歳月が掛けられたノウハウである。映画の制作に携わることがなければなかなか足を踏み入れることのないダビングステージや映画の音響制作。そこでの考え方や、ノウハウは興味深いものが数多くある。今回の解説が映画音響以外でもサウンドに関わる方にとって何らかの刺激となれば幸いである。
*ProceedMagazine2024-2025号より転載
Media
2024/09/03
よくわかるAoIP臨時特別講座!「AES67ってなに?」〜AoIPのいま、未来を知る。〜
AoIP、ネットワークオーディオを採用した放送局やレコーディング現場では、従来の(メタル)ケーブルからイーサネットケーブルに取って代わり、IPパケットで音声信号を伝送することで大きなメリットを実現していますが、ご存知のとおりでいくつもの仕様やプロトコルが存在していて、一般ユーザーには若干わかりにくい状況であることは確かです。そして、購入したばかりだというAoIPであるAES67対応の機材を手に「これをしっかり知り尽くしたい!」と意気込んでいるのが今回の講座にやってきたMクン。そんなMクンにROCK ON PRO 洋介がネットワークオーディオの世界を紐解きます。
まずは、AoIPってなに?
Mクン:Dante、RAVENNA、AVB、いくつものオーディオネットワーク規格があって制作現場でも目にすることが多くなってきたんですが、その中でもAES67についてお話を伺いたいんです。
ROCK ON PRO 洋介:なるほど。ところでなんでまた今日はAES67?
Mクン:実はNeumannのスピーカー KH 150 AES67モデルとオーディオインターフェースのMT 48を購入したんです。AES67に対応した製品なんでせっかくなら使いこなしてAES67の恩恵に授かりたいな、と。まずは「AoIPってなに?」というところから教えてもらえませんか?
洋介:了解しました! AoIPは「Audio over Internet Protocol」の略で、TCP/IPベースのイーサネットを使ってオーディオ信号をやりとりする規格です。AoIPのメリットとしてどういうことがあるかというと、信号分配の際に分配器を必要とせず、汎用のイーサネットハブで1対多数のオーディオを含む信号を簡単に送れることです。もうひとつは、1本のケーブルで多チャンネルを送れることですが、多チャンネルオーディオ転送規格に関してはMADIがありますし、またずっと以前からはADATがありますよね。その中でもAES67が優れている点は、回線の通信速度が現在主流となっている1ギガビットイーサネットであれば256ものチャンネルを転送可能だということです。
Mクン:少ないケーブルで多チャンネル送れるというのは、経済的にも、設定や設置の労力的にもメリットですよね。
洋介:実は挙げられるメリットはまだあって、1本のケーブルで「双方向」の通信を行えるのも大きいメリットです。イーサネットケーブル1本に対し、In / Outの概念がなくなるので繋ぎ間違えもなくなりますよね。あとDante Connectが登場して、クラウドネットワークを介した世界中からの接続ができるようになってきているので、遠隔地とのやりとりも特殊な環境を必要とせず汎用の製品やネットワークを使えることでコストの削減を図ることができます。少し未来の話をすると、ダークファイバー(NTTが保有する光回線のうち使用されていない回線)を使えば、汎用のインターネット回線の速度を超えたデータ転送が遠隔地間でもローカルエリア上として行える可能性があります。例えば、東京と地方のオフィスを繋ぐ場合に物理的に離れていても両拠点は同じネットワーク上にいる状態にすることができてしまうんです。
Mクン:ダークファイバーを使って遠隔運用しているところはあるんですか?
洋介:ありますよ。放送業界が先行していて、離れた支局間でダークファイバーを引いている事例があります。例を挙げると、F1の放送では鈴鹿サーキットなど世界中のサーキットとドイツのデータセンター間でダークファイバーを繋げ、世界規模で実況放送を実現しています。では、ここからはAES67制定の経緯について話していきましょう。
📷身近な存在のオーディオi/FやスピーカーでもAES67対応製品がリリースされている。Mクンが購入したというこのKHシリーズ(右)とMT 48(左)の接続ではDAコンバーターも不要となるためシンプルなシステム構成に。
AES67策定の経緯
洋介:AES67の元になった規格は、2010年にMerging Technologies社とLAWO社が立ち上げた「RAVENNA」です。このRAVENNAをベースにして、AES(Audio Engineering Society)がAoIPの規格として制定したのがAES67です。AES67の規格はRAVENNAの仕様により汎用性を持たせる方向で策定されています。例えば、レイテンシーの最小値を大きくしたり、ストリーム数に関してはRAVENNAが最大128chに対し、AES67は8chまでといったように仕様を緩い方向に制定して汎用性を持たせています。
その後、SMPTE ST2110-30(ST2110は映画テレビ技術者協会(SMPTE)によって開発されたメディアをIP経由で移動させるための規格)という規格のオーディオパケット部分としてAES67が採用されます。SMPTE ST2110は、映像パケットとオーディオパケットを別々に送信するのが大きな特徴です。もうひとつ前のVoIP規格にSMPTE ST2022というものがあるのですが、これはSDIの信号をそのままパケットにして送信します。そこからより現代的な新しいテクノロジーを組み込んだIP転送を実現しようという目的で策定されたのがSMPTE ST2110です。オーディオ部分に関していうと、ST2110-30が非圧縮での基本的なAES67互換規格であり、さらにST2110-31になるとメタデータまで含めた通信ができるようになりました。こういったST2110の拡張とともにAES67も今後拡大していくと予想されてます。
Mクン:AES67のサンプリングレートは48kHz固定となっていますが、これは今後変わっていくのでしょうか?
洋介:恐らくですが、48kHzという仕様で一旦固定されたままになるのではないでしょうか。放送業界においては、現時点で一般的に多く使われているのが24Bit / 48kHで、ハイサンプルの需要がほぼなく、それ以上のスペックは必要ないと判断されているようです。このようにRAVENNAから派生したAES67ですが、放送業界、映像業界をバックボーンにして成長を続けています。一方、RAVENNAとDanteの違いを話すと、TCP/IPの規格としてDanteの方が1つジェネレーションが古い規格を一部使用しています。その代表がPTPで、DanteはPTP(Precision Time Protocol)のバージョン1を用いていて、RAVENNAやST2110の基礎技術はPTPのバージョン2です。このバージョン1と2には下位互換がなく、実際は別物というくらい違います。同一ネットワーク上にお互いを流しても問題ないのですが、上位バージョンが下位バージョンの信号を受けることができません。現在の普及具合でいうとDanteのほうが多いのですが、こういったことからDanteを採用しているメーカーは将来性に関して危惧を始めているところがあると聞いています。
PTPバージョン1と2の違い
Mクン:そのバージョン1とバージョン2の違いとは何でしょう?
洋介:ネットワークプロトコルの技術的に複雑な話になるので、ここでは深く立ち入りませんが、単純に互換性がないということだけ覚えておいてください。このPTPですが、TCP/IP通信プロトコルとしてそもそもの大きな役割はクロック同期です。AoIPもVoIPも動作原理上バッファーが必要であり、それによりレイテンシーが必ず発生します。これはIP伝送のデメリットのひとつとして必ず話題に挙がることです。なぜバッファーが必要かというと、ネットワーク経路上にはネットワークインターフェイス、イーサネットスイッチなど多くのデバイスが挟まり、遅延が発生するのは避けることができません。
その事実への対処法として、バッファーへパケットデータを溜め込み、各パケットが送出されるタイミングの同期を行なってデータを出す、という同期のためのタイムスタンプの役割を行うのがPTPです。これは、ワードクロックやビデオクロックといった動作とは異なります。PTPでは各々のパケットに番号札を振って順番を決めるようなイメージで、そのバッファー分の遅延が必ず発生することになります。
Mクン:なるほど。では、オーディオのワードクロックでは精度が高い製品を使えば、一般的に音も良くなると思うんですが、PTPに関しては音質に対して影響するものなのでしょうか?
洋介:音質に影響しないというのが一般的な解釈です。RAVENNAの信号を受け、出力はアナログオーディオの場合の機材にもワードクロックが搭載されているわけで、AD/DAプロセッサーの動作はワードクロックで制御されています。つまり、IPデータの部分とワードクロックが作用する部分は完全に分離されていることになるので音質には影響しない、というのが設計上からの帰結です。現在の主流は、PTPとワードクロックを同時に出力するグランドマスター機能を持った機材を用いてシステム全体の整合性を取っています。
少し話が脱線しますが、AoIPにおけるレイテンシーの問題はグローバルなインターネットを越えても、依然存在し続けることになります。ただし、どれだけレイテンシーが大きくなったとしても、送信順が入れ違いになったとしても、届いたパケットの順番はPTPのタイムスタンプの順に並べられ、順番は変わらないわけです。
長遅延、インターネットを超えての伝送などの際には、このPTPのマスタークロックの上位の存在として、皆さんがカーナビなどでも恩恵を授かっているGPS衛星の信号を活用します。GPS衛星は地球の上空20,000kmに、常時24機(プラス予備7機)が飛行しています。GPS衛星は地球上どこにいても、遮蔽物がない限り6機が視界に入るように運用されています。そして、運用されているGPS衛星はお互いに時刻の同期が取られています。ということは、このGPSの衛星信号を受けられれば、世界中どこにいても同期された同一タイミングを得ることができるわけです。普段、何気なく車のカーナビを使っていますが、同期に関しては壮大な動作が背後にあるんです(笑)。
Mクン:宇宙から同期信号が届いているんですね!そういった先進技術は、今後私たちのような音声技術を扱う業界にも恩恵があるんでしょうか?
洋介:例えば、現在話題のイーロン・マスクが率いるスターリンク社(アメリカの民間企業スペースXが運用している衛星インターネットアクセスサービス)からのデータをPTPマスターとして受け取れるようになれば、もっと面白いことが起こるかもしれないですね。一方でデメリットを挙げるとすれば、やはりどこまでもレイテンシーがつきまとうという点ですね。オーディオの世界ではマイクやスピーカーといったアナログ領域で動作する製品がまだ大部分を占めるので、「信号の経路上、どのタイミングでAoIPにするか」というのはひとつの課題です。マイク自体でDante接続する製品も出てきていますが、ハイエンド製品はまだ市場に出てきてないですよね。これから期待したいところです。
AoIP、レコーディング現場への導入状況は?
Mクン:AoIPの導入は放送業界が先行しているそうですが、レコーディング環境への導入状況はどうなんでしょうか?
洋介:レコーディングスタジオに関してはこれから普及が始まるかどうかといった状況です。大きなスタジオになると設備が建設時に固定されているものが多く、変更する機会がなかなかないということが関係していそうです。また、別の理由としてパッチベイの存在もあるかもしれません。現状使っているレコーディング機器の接続を繋ぎ変えるにあたって、これまで慣れ親しんだパッチベイから離れたくない、という心理もありそうです。まあ、パッチケーブルを抜き差しするだけですからね。
スタジオにはアナログ機器がたくさん存在しますが、AoIPが本当にパワーを発揮するのは端から端までをIPベースにした場合で、ここで初めてメリットが生まれます。一部にでも従来のアナログ機器が存在すると、そこには必然的にAD/DAコンバーター(アナログとAoIPの変換機)が必要になるので、コンバーターの分だけコストが必要になってしまいますよね。Dolby Atmosをはじめとするイマーシブオーディオのような多チャンネルを前提としたシステム設計が必要スタジオには需要があると思います。
Mクン:AoIPでシステムを組む場合、Danteを採用するにしろ、ST2110を採用するにしろ、それに対応した機材更新が必要ですが、どのプロトコルを採用しても対応できるように冗長性を持たせたシステムの組み方は可能ですか?
洋介:システム設計は個別のネットワークとして組まれているケースが多いですね。本誌でも事例として紹介しているテレビ大阪様ではオーディオのフロントエンド(インプット側)はDanteですが、コンソールのアウトや映像のスイッチャーはST2110という構成です。従来の銅線ベースの環境に比べるとシステム図が驚くほどシンプルで、機材数もとても少なくて済みます。放送業界ではフルVoIP化の流れが来ていて、新局舎など施設を一新するタイミングで、副調整室やマスターなど、全設備オールIP化の設計が始まっています。SMPTE ST2110のイーサネットのコンセントを至るところに設置し、局内どこからでも中継ができるシステムが組まれています。
Mクン:そういった大規模な更新のタイミングであれば、既存のアナログ機器を一新したシステムにリニューアルできるメリットがありますね。
洋介:そうですね。未来を見据えてAoIPやVoIPシステムでリニューアルできる大きなチャンスですね。
AES67のメリット
Mクン:話をAES67に戻すと、Danteに比べてAES67のメリットはどんなことがあるんでしょうか? また、対応した製品がますます普及していきそうですが、今後のAoIPはどうなっていくのでしょう?
洋介:まず、Danteについては普及が進んでいるものの、先ほど話したPTPバージョン1の問題が依然として残ります。DanteにもAES67互換モードがすでに搭載されているのですが、Dante Network上のすべての機器をAES67互換モードで動作させることはできず、ネットワーク上の1台のみをAES67互換モードで動作させてゲートウェイとして使うということになります。言い換えると、AoIP / VoIPのメリットであるすべての機器が常に接続されているという状況を作ることが難しいということでもあります。これは、先にもお話したPTPのバージョンの違いにより生じている問題であり、一朝一夕で解決できる問題ではないでしょう。一方、RAVENNAはAES67の上位互換であり、SMPTE ST2110の一部でもあります。放送局など映像業界でのSMPTE ST2110の普及とともに今後導入が進むことが予想されます。音声のみの現場ではDanteが活用され、映像も絡んだ現場ではRAVENNA、というように棲み分けが進むかもしれませんね。
Mクン:私は「AES67 ニアイコール RAVENNA」という認識だったので、ST2110という存在がその先にあるというのは知りませんでした。
洋介:ST2110があってのAES67なんですよね。逆に言うと、ST2110を採用している映像メーカーはAES67対応だったりしますね。
Mクン:なるほど。私が購入したNeumannのオーディオインターフェイスMT 48はAES67に対応しているんですが、「RAVENNAベースのAES67」という表記がされていて納得がいきました。同じく購入したNeumannのスピーカー、KHシリーズもAES67に対応しているんですが、そのメリットはどんなことでしょう?
洋介:RAVENNAはAES67の上位互換なので、RAVENNAと書かれているものはすべてAES67だと考えていいです。一番大きいのはレイテンシーの問題で、AES67は最低1msでそれ以下は難しいんですけど、RAVENNAはもっと短くできます。KHシリーズとMT 48を組み合わせればDAコンバーターいらずになる、というのが大きなメリットです。システム的にもシンプルで気持ちいい構成ですよね。最近の製品の多くは、スピーカー自体でADしDSP処理してアンプ部分に送るという動作なんですが、それなら「デジタルのまんまで良くない?」って思うんですよね(笑)。シグナルとしてシンプルなので。
AoIP普及のこれから
Mクン:これからサウンド・エンジニアの方は音の知識だけでなく、ネットワークの知識も必要になってきそうな感じですね。
洋介:うーん、どうでしょう? まずはブラウザ上で設定するルーティングの仕方、クロスポイントを打つということに慣れるということで良さそうです。そこから先は我々のようなシステム設計、導入を担当する側が受け持ちさせていただきますので。実際、DanteでもRAVENNAやAES67でも基本的に設定項目は全部一緒なので、もちろんGUIの見た目は異なりますが、汎用のTCP/IPベースのイーサネットの世界なのでひとつ覚えれば他にも通じる汎用性があります。
今後、AoIPの普及はさらに進むでしょう。現在はまだシステムの範囲が1部屋で完結しているスケールなのでAoIPを用いるスケールメリットはあまりないのですが、これからさらに外へと繋がっていくと大きく変わっていくはずです。すにで汎用のインターネットで映像や音声がやりとりできる世界になり、グローバルなインターネットで放送クオリティーの伝送が可能となっています。
放送局の場合だと、これまでサブでしか受けられなかった中継回線などが、イーサネットケーブルを引けばMA室でも受けられるようになります。こうなれば受けサブとしてMA室を活用するという使用用途の拡張が見込めます。従来は音声信号に加え、同期信号もすべてケーブルを引っ張らなければいけなかったものが、イーサネットケーブル1本で対応できるようになるのは革新的です。さらに、光ファイバーを導入できれば、同じケーブル設備を使って通信速度、使用可能帯域をアップグレードしていくこともできます、従来のメタル銅線では実現できないことですよね。
Mクン:今日は色々と興味深い話をありがとうございました!
いかがだったでしょうか、「なるほど〜!」連発となったMクンはAES67がどのようなものなのか、そしてAoIPのメリットや抱えている課題点など、オーディオのIP伝送がいま置かれている現状もしっかりと把握できたようです。これからの制作システム設計における大きなキーワードとなるAoIP。もちろんそのメリットは従来のワークフローを大幅に塗り替えていくでしょう、そしてそのシステムが与えるインパクトたるや如何なるものか!?その進展から目が離せませんね!
*ProceedMagazine2024号より転載
Media
2024/08/30
RIEDEL製品が支えるF1サーカスの舞台裏〜MediorNetで結ばれたIPグローバルネットワーク〜
IP伝送が拡げる可能性は我々が位置する音響の分野のみならず多岐にわたる。音や映像が必要とされる分野であればIP伝送によって従来のシステムにとって代わるワークフローのブレイクスルーが起こり得る。そのひとつが今回取材を行ったF1サーカスとも呼ばれる、世界規模のスポーツイベントにおけるRIEDELの取り組みだ。本誌では以前にもご紹介をしたが、あれから5年を経てそのバックボーンを支える技術、ソリューションはどれほど進化したのだろうか。
レースに欠かせない通信のマネジメント
2024年のF1カレンダーは大きく変わり、日本グランプリが例年の秋の開催から春開催へと移動された。これまでであれば、秋のレースはその年のドライバーチャンピオンが決まるころのレースであり、テクニカルサーキットして世界にその名を馳せる鈴鹿サーキットが最後の腕試しという側面もあったのだが、今年は桜の季節に開催されシーズンも始まったばかりということもあり、パドックは終始和やかなムードに包まれていた。今回取材に入ったのは木曜日。F1は金曜日に練習走行、土曜日に予選、日曜日に決勝というスケジュールとなっており、木曜日はレースデイに向けての準備日といったところ。その準備日だからこそ見ることができるレースの裏側も多く充実の取材となった。まずは、取材協力をいただいたRiedel Communicationsの各位に感謝を申し上げたい。
準備日とはいえ鈴鹿サーキットは、レースに向けた準備がしっかりと進められており、木曜日は恒例のパドックウォークが実施されるということで多くの観客が来場していた。パドックウォークは、レースデイには立ち入ることのできないパドックやメインストレートを歩くことができるイベント。入場券もレースが行われない日ということもあり安く設定されており、さすがにガレージの中までは入れないものの、レースでピットクルーたちがタイヤ交換などを行うその場に立てる、ということでこれを目当てに来場される方も多数。また、この日はメインスタンドも開放されていてサーキットの好きなところに行けるのもパドックウォークの魅力。もちろん、レースデイの高揚感まではないものの、鈴鹿サーキットでF1の雰囲気を味わいたいということであれば、この木曜日の来場にも価値がある。
📷レース前の木曜日に開催されたパドックウォーク。メインストレートも一般開放され賑わいを見せるこの写真の中に、RIEDELの回線敷設スタッフが数日間かけて仕込んだアンテナほかの機材も多数あるのがお分かりになるだろうか。既に木曜のこの段階で準備万端となっているわけだ。
前置きが長くなってしまったが、まずRIEDELのF1における立ち位置を確認しておこう。RIEDELはFIA(F1を主催する国際自動車連盟)から業務依頼を受けて、F1における通信全般をマネージメントしている。通信全般とひとことで言ってもF1会場で取り扱われている通信は膨大な量となる。各チームのインカム、オフィシャルからの無線連絡、ドライバーとのコミュニケーションなどの音声通信。それに、各車6台ずつの車載カメラ映像、審判用にも使われるコースの監視用のカメラ(鈴鹿サーキットでは20台以上がコース脇に設置された)、F1レースカーから送られてくるテレメトリーデータ(エンジン情報、燃料残量、タイヤ温度、ドライバーの操作など車に関するデータ)など多種多様。もちろん、その種類の多さから必然的にデータボリュームも非常に大きなものとなる。
コミュニケーションのメッシュを運用する
📷インカムがずらりと並んだピット内。よく見るとスタッフ個人ごとに名前が記されている。
なぜ、RIEDELがF1の運営に関わるようになったのかという部分にも触れておきたい。RIEDELはMotorola製トランシーバーのレンタル会社としてスタートした。単に機材をレンタルするということだけではなく、イベント会場などで活用されるトランシーバーのグループライン設計や、運営、無線電波の管理なども行い今日に至っている。
F1会場でも各チームへ120台前後のトランシーバーがレンタルされ、その管理運営を行っているということだ。残念ながらチームスポンサードの兼ね合いもあり全20チーム中17チームへの提供となっているとのこと。本来であれば全チーム一括での運営が望ましいのは確かであるが、他の無線機器メーカーなどがスポンサーとなってしまった場合はその限りではないようだ。しかしながら、RIEDEL以外のトランシーバーを使用しているチームの回線もRIEDELがデータを受取りして一括での運営管理を行っていることには変わりない。そのため、各チーム内でのグループラインなどの構築のためにRIEDELから最低1名ずつのスタッフが帯同しているそうだ。これは、それぞれのチーム事情を汲み取り、最適な運用を行うと同時に、チーム間の情報機密などへも配慮した対応だと思われる。
運用は大きく変わらないものの、トランシーバー自体についてはRIEDELのベストセラー製品でもあるBoleroの導入が進んでいるということだ。従来のトランシーバーでは2チャンネルの送受信。チャンネル数がさらに必要なマネージャークラスのスタッフは、2台のトランシーバーを併用し4チャンネルの運用を行っていて、腰の両サイドに2台のトランシーバーをぶら下げたスタイルは、チームの中心人物である証とも言えたのだが、Boleroを使えば1台のベルトパックで6チャンネルの送受信が可能となる。やはりこれば評価が高い、各チームからBolero導入へのリクエストも多く寄せられているそうだ。
各チームで多少の違いはあるのだろうと想像するが、現場で話を聞いたインカムの送受信先を図にして掲載しておく。ドライバーと会話ができるスタッフは最低限とし、レーシングディレクター(監督)がドライバー、ピットクルー、ガレージのそれぞれへ指示を行うことでレースを進行するというのが基本。そのやりとりを聞くだけのスタッフもいれば、発信を行えるスタッフも必要となり、複雑にコミュニケーションのメッシュが構築されている。
さらに、サーキット外のスタッフもこのコミュニケーションに参加する。世界各国にある各チームのヘッドクォーターへと必要な回線が送られ、車の情報などを監視して現場のスタッフへ適切な指示がリアルタイムに出されているということだ。また、回線が送られるのはヘッドクォーターだけではない。例えば、Visa Cash App RB Formula One Team であれば、ヘッドクオーターがイタリアのファエンツァ 、エンジン開発拠点は日本のホンダ・レーシングといったように分かれており、それぞれの国で別のコントロールルームからエンジンの様子などを監視している。
取りまとめると、各チームではサーキットに80名程度、それ以外のヘッドクオーターや各開発拠点に100名以上という人員体制でレースマネージメントが行われているということ。1台のレーシングカーを走らせることには想像以上に数多くのスタッフが関わっている。なお、RIEDELは各チームのヘッドクオーターまでの接続を担当しており、ヘッドクオーターから先の各開発拠点への通信はそれぞれのチームが独自にコミュニケーション回線を持っているということだ。
年間24戦を支えるRIEDELのチーム編成
F1の運営に関わっているRIEDELのスタッフは、大きく3つのチームに分けられている。1つが実際のレースデイの運営を行うテクニカルチーム。それ以外の2チームは、事前に会場内でのワイヤリングを主に請負う回線敷設チームだ。テクニカルチームは基本的に水曜日の現地入り、木曜日にチェック、金曜日からのレースデイという流れだが、回線敷設チームは決勝日の10日程度前に現地に入り、サーキット各所へのカメラの設置、無線アンテナの設営など機材コンテナが到着したらすぐにチェックが行えるよう準備を行っているということ。また、決勝が終わったら撤収作業を行って速やかに次のサーキットへ向かわなければならない。レースは3週連続での開催スケジュールもある。よって交互に世界中を飛び回れるよう回線敷設は2チームが編成されているが、それでもかなり過密なスケジュールをこなすことになる。
ちなみに、すべてのケーブル類は持ち込みされており、現地での機材のレンタルなどは一切行われない。これは、確実性を担保するための重要なポイントであり、今後も変えることはありえないと言っていたのは印象的。質実剛健なドイツ人らしい完璧を求める考え方だ。
セーフティーカーに備えられた通信システム
今回の取材は木曜日ということもあり、レースカーの走行はなくセーフティーカーによるシステムテストが行われていた。セーフティーカーには、F1のレースカーと全く同様の車載カメラ、テレメトリー、ラップ等の計測装置が搭載されており、これらを使って各種テストを行っている。なんと、今回はそのセキュリティーカーに搭載されたこれらの機器を見せていただく機会を得られたのでここで紹介しておきたい。
F1で今年使われているセーフティーカーはAMG GT。そのトランクルームに各種データの送受信装置、データの変換装置が備え付けられている。こちらと同じ機器がレースカーにも備えられ、レースカーに車載された6台ものカメラの映像データも車上で圧縮され無線で送信されている。アンテナもインカム用のアンテナと、それ以外のデータ用のアンテナ、さらには審判用の装置、これらもレースカーと同様だ。
これらはF1レースカーの設計の邪魔にならないようそれぞれが非常にコンパクトであり、パッケージ化されていることがよく分かる。ちなみに、トランクルームの中央にある黒い大きなボックスは、セーフティーカーの灯火類のためのボックス(赤色灯等など)であり、こちらはレースカーに搭載されず、その左右の金色だったりの小さなボックス類が各種計測装置である。右手の金色のボックス類がカメラの映像を圧縮したりといった映像関連、左側がテレメトリーとインカム関連だということだ。
📷システムテストに用いられていたセーフティーカーの様子。トランク内にレースカーと同様の機材が積み込まれている。ルーフ上には各種アンテナが据えられており、そのどれもがレースカーに搭載することを前提にコンパクトな設計がなされている。
航空コンテナの中に設置されたサーバーラック
📷ラックサーバーが収められているという航空コンテナ。このコンテナごと世界各地のF1サーカスを巡っていく。
それでは、実際に用いられている通信の運用について見ていこう。それぞれのチームの無線チャンネル数は各チーム6〜8チャンネル前後、そこへオフィシャルの回線やエマージェンシーの回線などを加え、サーキット全体では200チャンネル前後の無線回線が飛び交っている。これらの信号はすべてIP化され、ネットワークセンターと呼ばれるバックヤードのサーバーラックへと送られている。これらすべての回線は不正のチェックなどにも使用されるため、全回線がレースデイを通して記録されているとのこと。また、サーキットに持ち込まれたサーバーでの収録はもちろん、RIEDEL本社にあるサーバールームでも併せて収録が行われるような仕組みになっている。なお、サーキットに持ち込まれたサーバーはあくまでもバックアップだそうだ。レース終了とともに次の会場への移動のために電源が落とされパッキングが始まってしまうからである。
2019年にもこのネットワークセンターのサーバーラックを見せてもらったのだが、このラックに収まる製品は大幅に変わっていた。まず取り上げたいのは、インカムの総合制御を行うための機器がAll IP化されたことに伴い、最新機種であるArtist 1024の1台に集約されていたことだ。従来の最大構成機種であったArtist 128は、その機種名の通り128chのハンドリングを6Uの筐体で行っていたが、Artist 1024はたった2Uの筐体で1024chのハンドリングを可能としている。このスペックによって予備回線のサブ機までをも含めてもわずか4Uで運用が事足りてしまっている。ラックには従来型の非IPの製品も収まっているが、これらは機材の更新が済んでいないチームで使用されている機器の予備機だということ。3本のラックの内の1本は、予備機材の運搬用ということになる。
他には、テレメトリー・映像データ送信用のMediorNet、多重化された電源、現地のバックアップレコーディング用のストレージサーバーといったところ。前回の取材時には非常に複雑なシステムだと感じたが、2024年版のラックはそれぞれの機器がシンプルに役割を持ち動作している。それらの機器のことを知っている方であれば、ひと目見て全貌が(もちろん、概要レベルだが)把握できるくらいにまでスリム化が行われていた。
📷数多くのインカム回線をハンドリングするArtist 1024。見ての通りArtist 1024を2台、わずか4Uでの構成だ。
これらのラックは、飛行機にそのまま積めるように航空コンテナの中に設置されている。コンテナは2台あり、回線関連の機器が収められたコンテナと、もう1台がストレージサーバー。航空輸送を行うということで、離陸、着陸のショックに耐えられるようかなり厳重な仕掛けが行われていたのも印象的。コンテナの中でラックは前後方向に敷かれたレールの上に設置され、それがかなりのサイズのダンパーで前後の壁面と固定されている。基本的に前後方向の衝撃を想定して、このダンパーでその衝撃を吸収しようということだ。2024年は24戦が世界各地で予定されており、そのたびに飛行機に積まれて次のサーキットへと移動される特殊な環境である。着陸のたびにダメージを受けることがないよう、これまでの経験を活かしてこのような構造を取っているということだ。
●RIEDEL MediorNet
2009年に登場した世界初となるFiber-BaseのVoIPトランスポート。さらにAudio、GPIO、もちろんRIEDELインカムの制御信号など様々な信号を同時に送受信できる。ファイバーケーブルを使った長距離伝送という特長だけではないこの規格は、世界中の大規模イベントのバックボーンとして使われている。本誌でも取り上げたF1以外にも、世界スポーツ大会、W杯サッカー、アメリカズカップなどが代表的な事例となる。ひとつのトランスポートで現場に流れるすべて(と言ってしまっても差し支えないだろう)の信号を一括で送受信することができるシステムである。
自社専用ダークファイバーで世界中へ
これらのコンテナ・ラックに集約された回線は、RIEDEL Networkの持つダークファイバー回線でRIEDEL本社へと送られる。RIEDEL NetworkはRIEDELのグループ会社で、世界中にダークファイバーの回線を持ち、その管理運用を行っている。その拠点まではそれぞれの国の回線を使用するが、世界中にあるRIEDEL Networkの回線が接続されているデータセンターからは自社回線での運用となる。各国内の回線であれば問題が起きることはそれほど多くない、それを他国へ送ろうとした際に問題が発生することが多い。そういったトラブルを回避するためにも自社で世界中にダークファイバーを持っているということになる。
また、RIEDEL本社の地下には、核シェルターに近い構造のセキュリティーレベルが高いデータセンターが設置されている。ここで、F1のすべてのデータが保管されているそうだ。各チームからのリクエストによる再審判や、車載カメラ、コースサイドのカメラ、各チームの無線音声などすべての情報がここに保管されている。FIAから直接の依頼を受けて業務を行っているRIEDELは、さながら運営側・主催者側のバックボーンを担っているといった様相だ。
ちなみに、F1のコントロールセンター(審判室)は、リモートでの運営となっている。RIEDEL本国に送られた回線は、ヨーロッパに設置されたコントロールセンター、そして、各チームのHQへと送られている。まさにRIEDEL本社がF1サーカスのワールドワイドのハブとなっているということだ。一旦レースの現場でデータを束ねて、確実なファシリティ、バックボーンのある本社拠点へ送る。それを必要なものに応じて切り出しを行い、世界中へを再発信する。世界中を転戦するF1サーカスならではの知恵と運用ノウハウである。
ちなみに、我々が楽しんでいるTVなどの中継回線は、コースサイドの映像などが会場で共有され、中継用の別ネットワークとして運営されているということだ。前回取材時の2019年はこの部分もRIEDELの回線を使ったリモートプロダクションが行われていたが、サーキット内での回線分岐で別の運用となっていた。これらの設備を見ることはできなかったが、サーキット内に中継用のブースがあるような様子はなく、RIEDELのスタッフもそのような設備がサーキット内に準備されているのは見たことがないということだったので、リモートプロダクションでの制作が行われているのは確かなようであった。別のネットワークを通じて行われるリモートプロダクション、2024年度の放映権を持つのはDAZNだが、どのようなスキームで制作されているのか興味が尽きないところだ。
総じてみると、2019年と比較してもシステムのコンパクト化、コロナを乗り越えたことによるスタッフの省力化、リモートの活用範囲の拡大などが随所に見られた。そして、バックボーンとなる回線のIP化が進み、Artist 1024のような大規模ルーターが現実のものとして運用されるようになっている。目に見える進化はそれほど大きくないのかもしれないが、そのバックボーンとなる技術はやはり日進月歩で進化を続けている。
IPによる物理回線のボリュームは劇的に減っており、要所要所は一対のファイバーケーブルで賄えるようになっている。ある意味、この記事において写真などで視覚的にお伝えできるものが減っているとも言えるのだが、これこそがIP化が進展した証左であり次世代のシステム、ソリューションの中核が現場に導入されているということに相違ない。
10年以上も前から一対のファイバーケーブルで、映像・音声・シリアル通信まで送受信できるシステムを提案しているRIEDEL。やっと時代が追いついてきているということなのだろうか。F1のような世界規模の現場からのリクエストで制作され鍛え上げられてきたRIEDELの製品。国内でも活用が多く見られるインカムは、RIEDELの持つテクノロジーの一端でしかない。トータルシステムとして導入して本来のバリューを発揮するRIEDELの製品群。今回のような事例から次世代のシステム・ソリューションにおけるヒントを見つけていただければ幸いである。
*ProceedMagazine2024号より転載
Media
2024/08/09
N響「第9」、最先端イマーシブ配信の饗宴。〜NHKテクノロジーズ MPEG-H 3D Audio 22.2ch音響 / NeSTREAM LIVE / KORG Live Extreme〜
年末も差し迫る2023年12月26日に行われた、NHKホールでのNHK交響楽団によるベートーヴェン交響曲第9番「合唱つき」のチャリティーコンサート。 その年の最後を飾る華やかなコンサートと同時に、NHKテクノロジーズ(NT)が主催する次世代を担うコンテンツ配信技術のテストだ。次世代のイマーシブ配信はどのようになるのか、同一のコンテンツをリアルタイムに比較するという貴重な機会である。その模様、そしてどのようなシステムアップが行われたのか、壮大なスケールで行われた実験の詳細をレポートする。
●取材協力
・株式会社NHKテクノロジーズ
・株式会社クープ NeSTREAM LIVE
・株式会社コルグ Live Extreme
3つのイマーシブオーディオ配信を同時テスト
まずは、この日に行われたテストの全容からお伝えしたい。イマーシブフォーマット・オーディオのリアルタイム配信実験と言ってもただの実験ではない、3種類のフォーマットと圧縮方式の異なるシステムが使われ、それらを比較するということが行われた。1つ目は、次世代の放送規格としての8K MPEG-H(HEVC+22.2ch音響MPEG-H 3D Audio *BaselineProfile level4)の配信テスト。2つ目がNeSTREAM LIVEを使った、4K HDR(Dolby Vision)+ Dolby Atmos 5.1.4ch@48kHzの配信テスト。3つ目がKORG Live Extremeを使った、4K + AURO-3D 5.1.4ch@96kHzの配信テストだ。さらに、NeSTREAM LIVEでは、HDR伝送の実験も併せて行われた。イマーシブフォーマットのライブストリーム配信というだけでも興味深いところなのだが、次世代の技術をにらみ、技術的に現実のものとして登場してきている複数を比較するという取り組みを目にすることができるのは大変貴重な機会だと言える。
全体のシステムを紹介する前に、それぞれのコーデックや同時配信されたフォーマットなどを確認しておきたい。22.2chは、次世代地上デジタル放送での採用も決まったMPEG-H 3D Audioでの試験、NeSTREAM LIVEは、NetflixなどストリーミングサービスでのDolby Atmos配信と同一の技術となるDolby Digital Plusでの配信、KORG Live ExtremeはAURO-3Dの圧縮技術を使った配信となっている。圧縮率はNeSTREAM LiveのDolby Digital Plusが640kbps、次にMPEG-Hの22.2chで1chあたり80kbps。Live Extremeは10Mbps程度となっている。
映像についても触れておこう。22.2chと組み合わされるのは、もちろん8K HEVCの映像、NeSTREAM LIVEは同社初のチャレンジとして4K Dolby Visonコーデックによる4K HDR映像の配信テストが合わせて行われた。KORG Live Extremeは、4Kの動画となっている。次世代フォーマットであるということを考えると当たり前のことかもしれないが、各社イマーシブと組み合わせる音声として4K以上の動画を準備している。KORG Live Extremeでは、HPLコーデックによる2chバイノーラルの伝送実験も行われた。イマーシブの視聴環境がないという想定では、このようなサブチャンネルでのバイノーラル配信というのは必要なファクターである。ちなみに、Dolby Atmosであれば再生アプリ側でバイノーラルを作ることができるためこの部分に関しては大きな問題とならない。
IPで張り巡らされたシステムアップ
📷仮設でのシステム構築のため、長距離の伝送を絡めた大規模なシステムアップとなっている。DanteのFiber伝送、Riedel MediorNet、OTARI LightWinderが各種適材適所で使われている。また、できるかぎり信号の共有を図り、チャンネル数の多いイマーシブサウンド3種類をうまく伝送し、最終の配信ステーションへと送り込んでいるのがわかる。実際のミックスは、22.2chのバランスを基本にそこからダウンコンバート(一部チャンネルカット)を行った信号が使われた。
それでは、テストのために組み上げられた当日のシステムアップを紹介したい。NHKホールでのNHK交響楽団によるベートーヴェン交響曲第9番「合唱つき」のチャリティーコンサートは、ご存知の通り年末の恒例番組として収録が行われオンエアされている。その本番収録のシステムとは別に今回のテスト配信のシステムが組まれた。マイクセッティングについても、通常収録用とは別に会場のイマーシブ収録のためのマイクが天井へ多数準備された。ステージ上空には、メインの3点吊り(デッカベースの5ポイントマイク)以外にもワイドに左右2本ずつ。客席上空には22.2chの高さ2層のレイヤーを意識したグリッド上の17本のマイクが吊られていた。
📷客席上空に吊り下げられたマイク。田の字にマイクが吊られているのが見てとれる。これは22.2chのレイヤーそのものだ。NHKホールは放送局のホールということもあり、柔軟にマイクを吊ることができるよう設計されている。一般的なホールではなかなか見ることができない光景である。
マイクの回線はホール既設の音響回線を経由して、ホール内に仮設されたT-2音声中継車のステージボックスに集約される。ここでDanteに変換されたマイクの音声は、NHKホール脇に駐車されたT-2音声中継車へと送られ、ここでミックスが作られる。この中継車にはSSL System Tが載せられているおり、中継車内で22.2ch、Dolby Atmos準拠の5.1.4chのミックスが制作され出力される。ここまでは、KORG Live Extremeが96kHzでのテストを行うこともあり、96kHzでのシステム運用となっている。
22.2chと5.1.4ch@48kHzの出力は、MADIを介しRIEDEL MediorNetへ渡され、配信用のテスト機材が設置されたNHKホールの配信基地へと送られる。もう一つの5.1.4ch@96kHzの回線はOTARI Lightwinderが使われ、こちらもNHKホールの配信基地へと送られる。ホールの内外をつなぐ長距離伝送部分は、ホールから中継車までがDante。中継車からホールへの戻りは、MediorNetとLightwinderというシステムだ。それぞれネットワークケーブル(距離の関係からオプティカルケーブルである)でのマルチチャンネル伝送となっている。
📷T-2音声中継車とその内部の様子。
ホールの配信基地には22.2ch@MPEG-H、NeSTREAM LIVE、Live Extremeそれぞれの配信用のシステムがずらりと設置されている。ここでそれぞれのエンコードが行われ、インターネット回線へと送り出される。ここで、NeSTREAM LIVEだけは4K HDRの伝送実験を行うために、AJA FS-HDRによる映像信号のHDR化の処理が行われている。会場収録用のカメラは8Kカメラが使われていたが、SDRで出力されたためHDR映像へとコンバートが行われ、万全を期すためにカラリストがその映像の調整を行っていた。機械任せでSDRからHDRの変換を行うだけでは賄えない部分をしっかりと補正、さすが検証用とはいえども万全を期すプロフェッショナルの仕事である。
このようにエンコードされ、インターネットへと送出されたそれぞれのコーデックによる配信は、渋谷ではNHK放送センターの至近にあるNHKテクノロジーズ 本社で受信して視聴が行われるということになる。そのほか渋谷以外でも国内では広島県東広島芸術文化ホールくらら、海外ではドイツでの視聴が行われた。我々取材班は渋谷での視聴に立会いさせていただいたが、他会場でも問題なく受信が行えていたと聞いている。
📷上左)NHKホールの副調整室に設置された3つの配信システム。写真中央の2台並んだデスクトップのシステムは、KORG Live Extremeのシステムだ。上右)こちらが、NeSTREAM LIVEのDolby Atmos信号を生成するためのラック。ここでリアルタイムにDolby Digital Plusへとエンコードが行われる。下左)8K+22.2chを制作するためのPanasonic製レコーダー。8K 60Pの収録を可能とするモンスターマシンで収録が行われた。下右)NeSTREAM LIVEで使われたHDRの信号生成のためのラック。最上段のAJA FS-HDRがアップコンバートのコアエンジン。
それぞれに持つ優位性が明確に
実際に配信された3種類を聴いてみると、それぞれのメリットが際立つ結果となった。イマーシブというフォーマットの臨場感、このポイントに関してはやはりチャンネル数が多い22.2chのフォーマットが圧倒的。密度の濃い空間再現は、やはりチャンネル数の多さに依るところが大きいということを実感する。今回の実験では、ミキシングの都合からDolby Atmos準拠の5.1.4 chでの伝送となった他の2種の倍以上のチャンネル数があるのだから、この結果も抱いていたイメージ通りと言えるだろう。もう一つは、圧縮率によるクオリティーの差異。今回はKORG Live Extremeが96kHzでの伝送となったが、やはり低圧縮であることの優位性が配信を通じても感じられる。NeSTREAM LIVEについては、現実的な帯域幅で必要十分なイマーシブ体験を伝送できる、現在のテクノロジーレベルに一番合致したものであるということも実感した。その中でDolby Visionと組み合わせた4K HDR体験は、映像のクオリティーの高さとともに、音声がイマーシブであることの意味を改めて感じるところ。Dolby Vision HDRによる広色域は、映像をより自然なものとして届けることができる。それと組み合わさるイマーシブ音声はより一層の魅力を持ったものとなっていた。
前述もしているが、それぞれの配信におけるオーディオコーデックの圧縮率は、NeSTREAM LIVEのDolby Digital Plusが640kbps、次にMPEG-Hの22.2chが1chあたり80kbps。Live Extremeは10Mbps程度となっている。このように実際の数字にしてみると、NeSTREAM LIVEの圧縮率の高さが際立つ。640kbpsに映像を加えてと考えると、現時点ではこれが一番現実的な帯域幅であることは間違いない。
ちなみに、YouTubeの執筆時点での標準オーディオコーデックはAAC-LC 320kbpsである。言い換えれば、NeSTREAM LIVEはこの倍の帯域でDolby Atmosを配信できるということである。KORG Live Extremeにおける96kHzのクオリティーは確かに素晴らしかった、しかし10Mbpsという帯域を考えると多数へ行なわれる配信の性格上、汎用的とは言い難い一面も否めない。しかしながらプレミアムな体験を限定数に、というようなケースなど活用の可能性には充分な余地がある。22.2chのチャンネル数による圧倒的な体験はやはり他の追従を許さない。8K映像と合わせてどこまで現実的な送信帯域にまで圧縮できるかが今後の課題だろう。22.2ch音響を伝送したMPEG-H 3D Audioは任意のスピーカーレイアウトやバイノーラル音声に視聴者側で選択し視聴することができる。22.2ch音響の臨場感を保ったまま、視聴者の様々な環境で視聴することが可能となる。AVアンプやサウンドバー、アプリケーションなどの普及に期待したい。
このような貴重な実験の場を取材させていただけたことにまずは感謝申し上げたい。取材ということではあったが、各種フォーマットを同時に比較できるということは非常に大きな体験であり、他では得ることのできない大きな知見となった。伝送帯域やフォーマット、コーデックによる違い、それらを同一のコンテンツで、最新のライブ配信の現場で体験することができるというのは唯一無二のこと。これらの次世代に向けた配信が今後さらに発展し、様々なコンテンツに活用されていくことを切に願うところである。
*ProceedMagazine2024号より転載
Media
2024/01/02
株式会社Cygames 大阪サウンドフォーリースタジオ様 / 正解は持たずにのぞむ、フォーリーの醍醐味を実現する自社スタジオ
「最高のコンテンツを作る会社」をビジョンに掲げ、妥協のないコンテンツ制作に取り組む株式会社Cygames。ProceedMagazine 2022-2023号では大阪エディットルームの事例として、Dolby Atmos 7.1.4chに対応した可変レイアウトとなるスタジオ2部屋が開設された様子をご紹介したが、それとタイミングを同じくしてフォーリースタジオも大阪に設けられた。ここではそのフォーリースタジオについてレポートしていきたい。
同時期に3タイプのスタジオ開設を進める
Cygamesでは、スマートフォン向けのゲームタイトルだけではなく、コンシューマー系のタイトル開発にも力を入れている。近年のゲームはプラットフォームを問わず映像や音の表現が飛躍的に向上しており、フォトリアルで写実的な映像に合わせたサウンドを作る場面が増えてきた。効果音の制作については、それまでは外部のフォーリースタジオを借りて作業を行っていたが、効率性を考えれば時間や手間が掛かってしまうという制約があった。また、ゲーム作品では、例えばキャラクターの足音一つとっても多くの動作音があるだけでなく、ファンタジーの世界特有の表現が必要である。土、石畳、レンガ等といった様々な素材の音を既存のライブラリから作り上げるのは容易ではなく、完成度を上げていくことは中々に難しい作業だが、フォーリースタジオを使って収録した効果音は、生音ならではの音の良さに加え、ゲームによく馴染む質感の音に仕上がることが多かったという。
やはり自社のスタジオがあればより効率的に時間を使い、かつクオリティを高める試行錯誤も行えるのではないか、という思いを抱いていたところ、Cygamesのコンシューマーゲーム開発の拠点がある大阪でモーションキャプチャースタジオの設立計画が立ち上がったことをきっかけに、建物のスペック等を考慮してフォーリースタジオも同じ場所に設置する形でスタジオ設置に向けて動きだした。以前ご紹介した、MAスタジオの用途を担う大阪エディットルーム開設プロジェクトと合わせると、同時期に2つのサウンドスタジオ開設を進めるという大きなプロジェクトになったそうだ。
制約はアイデアでポジティブに変換する
フォーリースタジオを開設するための要件としてまず挙げられるのは部屋の高さと広さ。通常のレコーディングとは異なって物を振り回したりすることも多いフォーリー収録ではマストな条件となる。天井が低ければ物が当たってしまうのではないかという演者の不安とストレスを低減するため、部屋の中央付近の天井を一段高くする工夫が取り入れられている。広さについてもフォーリー収録時の演技をする上で充分なスペースを確保しているが、加えて壁の反射音の影響が強く出てしまわないよう、床やピットを部屋の真ん中に寄せて配置し、壁からの距離が取れるレイアウトを実現できた点も広さを確保できたメリットだ。
また、スタジオ内の壁面にはぐるりと木製のフローリングが敷かれ、そこも材質の一つとして使用できる。中央には大理石やコンクリート、水を貯められるようなピットが用意され多様な収録に対応できる環境が整えられた。一方、スタジオの広さがある故に反響をどのようにマネジメントするのかは大きな課題となっていたようだ。そこで取られた特徴的な対策だが、壁面の反射を積極的に発生させつつルームモードを起こさないように処理した上で、むしろその反響を収録での選択肢として活かせるようにしたそうだ。もちろん、部屋の外周に沿って用意されたカーテンによって反射面を隠し、反響をダンピングして抑えていくこともできる。さらに、日本音響エンジニアリングの柱状拡散体を設置してアコースティックも整えられており、当初は弊害と考えていた反響音を逆に利用することで、収録できる音の幅を拡げている。
施工は幾度と重なる打ち合わせやシミュレーションを経て行われたのだが、それでも予想できない不確定な要素も出てきたそうだ。例えば、このスタジオの特徴でもある天吊りマイク。天井に取り付けられた金属製のパイプに特型のマイクスタンドを引っ掛けて固定する仕様になっているのだが、実際に収録を行うとパイプに響いているのか、音声信号にノイズを感じることが出てきた。イメージ的にはドラムのオーバーヘッドを立てるイメージに近く、ドラムは音量が大きいためそれほど気になりはしないが、フォーリーの収録となると微細なノイズでも大きく感じることが多くなる。試行錯誤した結果、天吊りマイクスタンドを取り付ける際に固定ネジを締めすぎないようにすることでノイズを軽減できることがわかった。そのほかにも、部屋の天井から高周波の金属音が鳴っているようで調査したところ、空調のダクトが共振していることが判明。金属のダンピングを見直して解決したそうだ。細かな調整だが、このような積み重ねこそが収録のクオリティーアップには必要不可欠であるとのことだ。
📷ダンピングが見直されたという天吊りマイクブーム
集中環境とコミュニケーションの両立
スタジオのコンセプトで重要視している要素として、ストレスフリーであることが必要であると考えているそうだ。ブースとコントロールルームのスタッフの間で意思疎通がストレスなく行われなければ作業効率も落ちてしまい、認識の齟齬も起きがちだ。社内スタジオで自由に使える環境とはいえ、クオリティを高めるトライアンドエラーの時間まで削ってしまっては本末転倒になってしまう。
ところが、このスタジオはブースとコントロールルームが完全にセパレートされており、お互いの姿を確認できるようなガラス面も設けられていない。
一見するとコミュニケーションを妨げる要素になりそうだが、ガラス面を設けないことで演者が集中して演技に取り組める環境を整えられたという。演者にとって、人の目線があると気になって集中力の妨げになることもある。外部のスタジオでは収録の様子をクライアントがコントロールルームから見守るといったことも多いが、このスタジオは社内スタッフでの利用が主となるため、必ずしもコントロールルームから演者を直視できる必要はない。ただし、その分だけコミュニケーションを重視したシステムプランが採用された。
スタジオ内にはフォーリー収録用とは別に天吊りマイクが仕込まれており、コントロールルームからスタジオ内の音を聴くことができ、トークバックと両立できるようなコミュニケーションの制御も行なっている。映像カメラも各所に設置されており、コントロールルーム内のディスプレイにスタジオ内の様子が映され、その映像も各ディスプレイに好きなように出せるスイッチャーが設置されており、オペレーターの好みに合わせて配置することが可能となっている。コントロールルームとブースをアイソレーションすることによって演者が集中できる整った環境と、コミュニケーションを円滑にさせるシステムプランをしっかり両立させている格好だ。
正解を持たずに収録する、トライする機材
📷コントロールルームには左ラックにPUEBLO AUDIO/JR2/2+、右ラックに TUBE-TECH/HLT2Aが収められコンソールレスな環境となっている。
このスタジオではスタッフが持ち込みPCで収録することも想定されており、各種DAWに対応できるシステムが必要であった。シンプルかつシームレスにシステムを切り替えられ、コミュニケーションシステムとも両立させる必要がある。それをシステムの中核に Avid MTRXを据えることで柔軟な対応を実現している。また、「収録段階からの音作りがしっかりできるスタジオにしたい」というコンセプトもあり、アウトボード類の種類も豊富に導入された。コンプレッション、EQはデジタル領域よりもアナログ機材の方が音作りの幅が拡がるということだけではなく、その機材がそこにあるということ自体がスタッフのクリエイティビティを刺激する。スタッフが自宅で録るのではなく、「このスタジオで録りたい」という気持ちが起こるような環境を整えたかったそうだ。
そうして導入された機材のひとつが、PUEBLO AUDIO/JR2/2+。フォーリースタジオではごく小さな音を収録することが多く、ローノイズであることが求められる。過去の現場での実績からもこの機種が際立ってローノイズであることがわかっており、早々に導入が決まったようだ。また、ミキサーコンソールが無くアウトボードで補完する必要があったため、TUBE-TECH/HLT2AがEQとして据えられている。HLT2Aは繊細なEQというよりは極端なEQでサウンドを切り替えることもできるそうで、極端にローを上げて重たい表現ができないか、逆にローを切ってエッジの効いた表現はできないか、といった試行錯誤を可能にする。このほか、ヴィンテージ機材ならではのコンプレッション感が必要な場面も増えてきていることから、NEVE 33609Cも追加で導入されている。今後も機材ラインナップは充実されていくことだろう。
はじめからこういう音が録りたいというターゲットはあっても、正解を持たずに収録していくという工程がフォーリーの醍醐味だという。その中で誰でも使いやすい機材を選定するということを念頭に置き、スタッフからのリクエストも盛り込んでこれらの機材にたどり着いたそうだ。
スタジオは生き物、その成長を期待する
📷何よりもチームワークの良さが感じられた収録中の一コマと、気合いが込められた渾身の一撃も収録!!
こうして完成をみたスタジオであるが、S/Nも良く満足した録音が行えているそうだ。また、5.1chリスニングが可能となっている点もポイント。開発中のタイトルにコンシューマー作品が多く、サラウンド環境が必要なことに加え、映画のようにセンターの重要度が高いことから、ファントムセンターではなくハードセンターで収録したいという要望に沿ったものだ。また、映像作品やゲーム資料を確認しながらすぐに収録することができるため、フォーリーアーティストに映像作品の音を聴かせてクリエイティブへのモチベーションをアップしてもらいながら制作を進める、という点も狙いの一つだ。もちろん、自社スタジオとなったことで時間を気にせずクオリティの向上を目指せることが大きく、求める方向性をより具体化させて収録できるメリットは計り知れない。
今後について伺うと、スタジオは生き物であり、収録できるサウンドの特徴も次第に変わっていくと考えているそうだ。導入する資材が増えればそれが吸音や反射になって音も変わる。ピットについても使用していく経年変化でサウンドにも違いが出てくる。高域が落ち着いたり、もう少し角が取れてきたりと、年月を積み重ねてどのように音が変わっていくのかがすごく楽しみだと語っていただいた。
📷今回お話を伺った、サウンド本部/マネージャーの丸山 雅之氏(左)、サウンド本部/サウンドデザインチーム 村上 健太氏(中央)、妹尾 拓磨氏(右)。
目の前の制約はアイデアでポジティブに変換する、考え抜かれたからこそ実現できたメリット。そして、それを活かしたフォーリー収録には正解を持たずにのぞむ。ここに共通するのは先入観を捨てるということではないだろうか。先入観を「無」にしたならば、そこにあるのは創るというシンプルかつ純粋な衝動のみである。クリエイティブの本質を言い得たような、まさにプロフェッショナルの思考には感銘を受ける。今後もこのスタジオが重ねた年月は成長となって作品に反映されていくのだろう、フォーリー収録された素材がゲームというフィールドで表現されエンターテインメントを高めていくに違いない。
*ProceedMagazine2023-2024号より転載
Media
2023/07/27
株式会社コジマプロダクション様 / 新たな世界を創り出す、遥かなる航海のためのSpaceship
日本を代表するゲームクリエイター・小島 秀夫氏が2015年に立ち上げた株式会社コジマプロダクション。2016年には第1作目となるタイトル「DEATH STRANDING」を発表し、2019年に待望のPS4Ⓡ版が発売されるやいなや、日本をはじめ世界各地から称賛の声があがり、米国LAで行われたThe Game Awards 2019では8部門にノミネートされ、クリフ役を演じたマッツ・ミケルセンのベスト・パフォーマンス賞を含めると3部門で賞を獲得、世界的なビッグタイトルとしてのポジションを確立した。その後も数々の受賞歴や昨年末の「DEATH STRANDING 2(Working Title)」発表など、ここ最近も話題が絶えないが、実はその裏でオフィスフロアの移転が実施されていたという。フロア移転のプロジェクトがスタートしたのは2020年の1月ごろ、昨年12月に新フロアでの稼働が開始され、サウンド制作についての設備も一新された。今回はTechnical Sound Designerの中山 啓之氏、Recording Engineer永井 将矢氏に、移転計画の舞台裏や新スタジオのシステムについて詳細にお話を伺うことができたのでご紹介していこう。
📷エントランスゲートを通った先に待ち受けている真っ暗な部屋。足元に伸びる一筋の光に導かれるまま進んだ先には、無限に続く白の空間。中央にはコジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」が力強く佇んでいる。ちなみにこの名前は、オランダの歴史学者ホイジンガが提唱した「ホモ・ルーデンス」(遊ぶ人)に由来しているそうだ。こうした人間の遊び心を刺激するような演出がオフィス内随所に施されていた。
Spaceship Transformation
今回のスタジオ設計のプランニング開始は2021年3月ごろと2年ほど遡る。"Spaceship Transformation"という壮大なコンセプトとともに、事業規模の拡大に伴うフロア移転が社内で伝えられ「それに見合ったスタジオを作れないか?」と、社内で協議するところからスタートしたそうだ。ゲーム制作の「何百人ものスタッフが膨大な創造と作業と時間をかけながら、ひとつのゲーム作品を作り上げていく過程」を「広大な空間を進んでいく宇宙船の航行」として置き換えてみると、制作を行うオフィスフロアはまさに宇宙船の船内やコックピットであり、そこは先進的な技術やデザインで満たされた空間であるべきだろう。勝手ながらな推察ではあるが、こう捉えると"Spaceship Transformation"が意図するところも伝わってくるのではないだろうか。
こうしたコンセプトを念頭に置きながらも、現場スタッフの頭の中には、具体的な業務への思慮が常にある。予算や法律上の問題をはじめ、各所で定められたルールなどの制約がある中で、想定される業務をしっかりとこなせるスタジオを作るというのは、やはり一筋縄ではいかなかったそうだが、しっかりと万が一に備えた冗長性や、将来に向けた拡張性を持たせるような工夫がなされたそうだ。
Rock oN (以下、RoC):本日は宜しくお願いします。まず、お二人の普段の業務内容を伺えますでしょうか。
中山 啓之 氏 (以下、中山):音の制作(サウンドデザイン)を中心にやりつつ、チームのマネジメント業務も行なっています。私は設立後半年経った頃に入社したのですが、その頃からメディア・インテグレーションにはお世話になっています。
RoC:ありがとうございます!個性的なスタッフばかりですみません…(汗)。
永井 将矢 氏 (以下、永井):私はレコーディングエンジニアとして入社したのですが、ちょうど移転の話が始まったタイミングだったため、入社から最近にかけてはスタジオの運営、管理業務を行っています。今後は音声収録の作業がメインになっていく予定です。
RoC:お二人は元々どのようなきっかけでゲームという分野のサウンド制作に携わるようになったのでしょう。
中山:子供の頃からゲームに興味を持っていたのですが、パソコンやFM音源が出始めたころにいわゆる"チップチューン"にどっぷりハマりまして(笑)。そこから趣味がどんどん広がっていく中でゲームサウンドの世界に行き着きました。当時、PC88というパソコンにYM2203というFM音源チップが載っていて、それを使ってパソコンから音を出すところから始まり、音楽を作ったり、効果音を作ったりということを色々やっていました。
RoC:チップチューンというと、やはり同時発音数の制限などもあったり?
中山:FM音源が3つとSSG(矩形波)が3つくらいだったんですけど、そこからPCが進化していって鳴らせる音も増えていって。その後、MIDIが出てきたのでシーケンサを買って、シンセサイザーを買って、というコンピュータミュージックの王道を進んできたという感じです。
永井:私は、新卒時にゲーム業界も興味はあったんですが、映画好きだったこともあってポスプロの道へ進むことにしました。最初はいつまで続けられるか不安だったのですが、収録やミックスをやっているうちにその楽しさに気づき、結果的に7年半ほどやっていました。当時はほとんど吹き替えの仕事が中心だったのですが、仕事の幅を拡げたいなと考えていたところにちょうどいいタイミングでコジマプロダクションでのレコーディングエンジニアの募集があったんです。自分が好きなゲームを制作している会社ということもあって「これはぜひやりたい!」ということで応募しました。
RoC:"Spaceship Transformation"が今回のフロア移転全体のコンセプトとのことですが、そうした大きなテーマの下で、現場レベルでのこだわりやテーマは何だったのでしょうか?
中山:音声収録やMAといった様々な業務が想定される中で、例えば内装デザインなどがそうですが、「会社としての方向性に合わせつつも必要な業務に対応したスタジオを作りたい」というのがありました。とは言え、無尽蔵に場所があるわけでもないですし、予算との兼ね合いもあるので、その中でベストを尽くせるように、まずは必要な部屋数や規模の検討、「こういうことをやりたい」という提示からスタートしました。
RoC:最初の構想は、やはり業務内容などから逆算していって決められたのでしょうか?
中山:今回の場合ですとこのコントロールルームとそれに隣接したレコーディングブース、EDITブースいくつか…というプランから一番最初の「妄想」が始まりました(笑)。そのプランを本当に一枚のテキストページに落とし込んで、それから紆余曲折が始まった格好です。
永井:一応「妄想」通りにはできた感じです(笑)。
RoC:内装も全体的に統一感があり、かなりこだわられていますよね。
中山:基本コンセプトとして、弊社のコーポレートカラーである黒と白をベースにしたデザインを念頭に細部を決めていきました。我々はデザインについては素人ですが、いくらCG技術が発展したとしても、実際に目にするとイメージと異なる部分がどうしても出てくるとは思います。そうした部分は不安でもあり、ワクワクした部分でもありました。
📷カフェテリアの半分は近未来的なデザインのカウンター、もう半分はカフェのような落ち着いた雰囲気の空間演出となっている。サウンドセクションのロビーはソファとテーブルが融合し、照明と対になったデザインがなされている。ラウンジはまさに映画のワンシーンで使われていそうな意匠で、フロアの各所が一度目にしたら忘れられない印象的なデザインとなっていた。また、用途に応じて背景を黒・緑・青の3色に変更できるスタジオも用意されており、映像コンテンツの収録も行うことができる。
RoC:スタジオ稼働に至るまで山ほどタスクがあったかと思いますが、中でも苦労されたポイントはどこでしたか?
中山:共用のオフィスビルなので、当然全てを好き勝手にやるわけにはいかず、消防法やビル管理上のルール、配管や防音構造、荷重の制限など、これまで全く知識がなかったことについて考えながら進める必要があった点です。そうした部分は施工をご担当いただいたSONAさんやビルの管理会社さんなど、色々な方々から知見をいただいて、針の穴を通すような調整をやりつつ進めていきました。
永井:今回は建築上の都合でピットを掘ることができなかったので、施工会社の方々にとっては配管が一番頭を悩まされたのではないかと思います。
中山:やはりピットではないので一度配管を作ってしまうと、後から簡単に変更ができなくなってしまいます。そういうこともあり、配線計画はかなり綿密に行いました。予備の配線も何本か入れてもらっているので、今後の拡張性にも対応しています。それから、バックアップの面については力を入れています。収録中に万が一メインのMacがトラブルを起こしても、MTRX経由で常時接続されているサブ機にスイッチして継続できるように用意してありますし、さらにMTRXについても代わりのI/Oを用意してあるので、すぐに収録が再開できるようになっています。インハウスのスタジオですが、商用スタジオ並みのバックアップシステムを実現しています。
永井:商用スタジオだと複数部屋あったりするのでトラブルが発生したら別の部屋で対応をするということもできますが、そういった意味ではここは一部屋しかないので「何かあった時に絶対何とかしなきゃいけない!」となりますから、色々なシチュエーションを考えてすぐに対応できるようにしています。
理想的なスペースに組んだ7.1.4chのDolby Atmos
📷株式会社ソナのデザインによる音響に配慮された特徴的な柱がぐるりとコントロールルームを取り囲み、その中へ円周上にGenelec 8361Aが配置されている。スクリーンバックにはL,C,R(Genelec 8361A)とその間にサブウーファーGenelec 7370APを4台設置し音圧も十分に確保された。
RoC:機材選定はどのように進めていったのでしょうか?
中山:最初の計画を立てた時に、一番最初に挙げたのは「スクリーンを導入したい!」ということでした。弊社に来られる方は、海外からのお客様や映画関係の方など多種多様にいらっしゃいます。そうしたみなさまにご視聴いただくことを想定すると、小さな液晶画面だと制作の意図が伝わらなかったり、音響の良さを伝えるのが難しかったり、ということがこれまでの経験上ありましたので、スクリーンの設置はぜひとも実現したいポイントでした。併せて、今後主流になっていくであろう4K60pの投影と、それに応じたサウンド設備をということも外せないところでした。その規格に対応させるために、映像配線はSDI-12Gを通してあります。
RoC:今回、コントロールサーフェスにAVID S4を選ばれた理由は何だったのでしょう?
中山:MAの作業の直後に音声収録を行い、その後の来客時にティザーをご覧頂いて、という事も弊社では多くありますので、素早くセッティングを切り替えられるデジタル卓を候補としました。加えて、Pro Toolsのオペレーションが中心ということもあるので、Avid S6、S4か、もしくはYamaha のNuageかという選択肢だったのですが、サイズなども色々検討した結果でAvid S4になりました。S4でもS6と遜色ない機能がありますので。
RoC:特注のアナログフェーダーが組み込まれているのは、まさにこだわりポイントですね!
永井:S6もそうですが、S4はレイアウトを自由に変えられるのが利点ですね。
RoC:MTMとAutomationモジュールが左右に入っているパターンは他ではあまり見ない配置ですが、実際S4を導入して良かったと思うところはありますか?
永井:キーボードの操作も多いので、この配置にしていると手前のスペースを広く取れるのでいいですね。あとは、モニターコントロール周りです。前職でも触れたことはあったのですが、今思えばそこまで使いこなせてなかったなと。DADmanでのソースやアウトプットの切り替えは結構やりやすいなと改めて思いました。最初に操作方法を教わった後は、自分で好きなようにカスタマイズしています。「やりたい」と思ったことが意外とすぐにできるというのは好感触でした。
📷Avid S4のオートメーションモジュール手前には特注の4chアナログフェーダーが収められている。これはスタジオラックに収められたAMS Neve 1073 DPXとMTRXのアナログ入力との間にパッチ盤を介して接続されており、頻繁に触れるであろうボリュームコントロールを手元でスムーズに行えるようにした実用を考慮したカスタムだ。また、マシンルームにはシステムの中枢となるAvid MTRXが設置され、MacProの他にも同ラックにはMac Studioをスタンバイし冗長性を確保している。
RoC:特に、カスタマイズが好きな方にはハマりますよね!スピーカーはGenelecの同軸スピーカー8361A / 8351Bを中心に、4台の7370APを加えた合計15台で構成されています。なぜこの構成になったのでしょう?
中山:スピーカー選定の段階で「Dolby Atmosに対応させよう」というのはありました。かつ、スクリーンバックから鳴らせるということ、あとは部屋のサイズに対して十分な音圧を出せるか、というところがポイントでした。そういった部分から考えていくと自ずと選択肢は絞り込まれていきました。当初は同じGenelecのS360Aで検討していたのですが、角度を変えて上に置いたり横に置いたりすることを考えると、リスニングポジションの関係もあって、最終的に同軸スピーカーの方がいいのではないかという方向に落ち着きました。
📷トップのスピーカーはGenelec 8351Bを4台設置、半球の頂点にあたる部分など各所に配線があらかじめ敷設され、将来の増設も想定されている。
永井:音質面でもすごく素直な音で、クリアで分離がよく音色ひとつひとつが聴き取りやすく感じました。今回、SONAさんに音響調整をお願いしていて私も立ち会ったのですが、デスク前方のプロジェクターが格納されている部分が床からの反射を防ぐ構造になっており、その影響もあってか低域が溜まらずクリアに聴こえるようになっています。
📷デスク前方の傾斜部分の下には、4K60p対応の超短焦点プロジェクターが収められているのだが、こちらは床からの反射音を軽減させる音響調整パネルとしての役割も担っている。
中山:何となく、これも宇宙船のようなデザインに見えますよね。
RoC:確かに、スタートレック感がありますね!
中山:来社されたお客様にも、そのような感想を頂いた事がありました。雰囲気・デザイン的にもそういった要素を色々含めています。
RoC:ウーファーはスクリーンバックに4台となっていますね。
中山:はい、LCRスピーカーのLとC、RとCの間に上下に2台ずつGenelec 7370APが設置されています。最初は2台だけの想定だったのですが、調整していくうちに音圧が足りないかも、ということで、最終的に2台追加することになりました。リスニングポイントからスピーカーまでも3.6mほどあって、天井高も2.7mと高く取れています。サラウンドスピーカーの上下や天井中央にも後からスピーカーを追加できるようにしていて、これからの拡張性も確保しています。
RoC:サラウンドやイマーシブの制作において理想的な半球状の配置になっていますよね。実際にスタジオが稼働しはじめて、周囲からの反応はいかがでしたか?
中山:「すごい」と言ってもらえる機会が多くて嬉しいですね。エンジニアの方からは「音の立ち上がりが速い」という声もあり、好評な意見をいただけていて願ったり叶ったりです(笑)。「妄想」していたスタジオがきちんと実現できたかなという印象です。
永井:いい評判をいただけて本当によかったです。こちらからコンセプトを伝えてなくても「宇宙船みたい」と言ってくれる方もいてデザイン面でも良かったなと。加えて、制作だけではなくプレゼンや海外とのコミュニケーションにも対応できるようにしたので、他部署のスタッフからも「居心地良く仕事ができる」といった声がありました。
RoC:スタジオが取り合いになったりはしないですか?
中山:まだそこまではいってないですが、いずれそうなってくるかもしれませんね(笑)。
📷コントロールルームに隣接したレコーディングブースは、実面積よりも広々とした開放感を感じさせ長時間の使用にも耐えうる快適な空間となっている。また、フロアのカーペット裏には、コンクリートやレンガ、大理石など、材質の異なる床材が仕込まれておりフォーリー収録も行うことができる。
📷Sound Editing Room はA / Bの2部屋が用意されており、いずれもGenelec 8331A + 7360Aで構成された7.1chのモニター環境が構築されている。入出力にはFocusrite Red 8 Line、モニターコントローラーには同R1が用意されており、ここでも拡張性を確保しつつもコンパクトな機材選定がなされている。また、スピーカースタンドとデスクが一体化された設計により、機材の持ち込みなどシチュエーションに応じた活用がフレキシブルに行えるようになっていることもポイントだ。
聴く人の心を動かすようなサウンドを
現在、ゲーム制作においては、映画と同じくサラウンドでの制作が主流となっており、そこからダウンミックスでステレオが作られるとのこと。ゲーミングPCのスペックの向上やバーチャルサラウンド対応ヘッドホンのラインナップが拡充し、手頃な価格でそのサウンドを楽しめる環境が整ってきており、着実にその裾野は広がっているのではないかということだ。これはイマーシブサラウンドについても同様で、一番最初の計画ではイマーシブ対応については検討されていなかったが、天井高が十分取れることが分かった段階で、今後の需要増にも備えてDolby Atmosへの対応を決めたそうだ。
現在、ゲーム制作においては、映画と同じくサラウンドでの制作が主流となっており、そこからダウンミックスでステレオが作られるとのこと。ゲーミングPCのスペックの向上やバーチャルサラウンド対応ヘッドホンのラインナップが拡充し、手頃な価格でそのサウンドを楽しめる環境が整ってきており、着実にその裾野は広がっているのではないかということだ。これはイマーシブサラウンドについても同様で、一番最初の計画ではイマーシブ対応については検討されていなかったが、天井高が十分取れることが分かった段階で、今後の需要増にも備えてDolby Atmosへの対応を決めたそうだ。
RoC:Dolby Atmosのようなイマーシブ対応をすることで、ゲームサウンドの分野でも従来からの変化を感じましたか?
中山:一般のユーザーの方々へどこまでイマーシブ環境が拡がるかということもありますが、ゲームサウンドは3D座標で処理されているものが多いので、イマーシブと相性も良く、今後チャレンジしていきたいです。
永井:ポスプロ時代にもイマーシブについては興味を持っていましたが、やはりゲームは親和性が高いように思います。プレイをしている自分がその場にいるような演出も面白いと思いますし、今後突き詰めていくべきところだと思います。
RoC:それこそチップチューンの時代は、同時発音数など技術的な制約が大きい中での難しさがあったと思いますが、今後は逆に技術的にできることがどんどん増えていく中での難しさも出てくるのでしょうか?
中山:次々と登場する高度な技術のひとつひとつに追いついていくのはなかなか大変ですが、しっかりとその進化に対応して聴く人の心を動かすようなサウンドを作っていきたいですね。
世界的な半導体不足の影響や、高層オフィスビルならではのクリアすべき課題など、大小様々な制約があった中で、現場の要件をクリアしつつコジマプロダクションとしてのコンセプトを見事に反映し完成された今回のスタジオ。Dolby Atmos制作に対応済であることはもちろん、将来的にスピーカーを増やすことになってもすぐに対応できる拡張性や、インハウスのスタジオながら商用スタジオ並みのバックアップシステムも備えており、現時点だけではない制作の将来像も念頭に置いた綿密なシステムアップが行われた。ついに動き出したこの"Spaceship"がどのような新たなる世界へと導いてくれるのか、遥かなる航海がいよいよ始まった。
*ProceedMagazine2023号より転載
Media
2023/01/18
株式会社カプコン bitMASTERstudio 様 / 圧倒的なパフォーマンスと理想的なアコースティック
バイオハザード、モンスターハンター、ロックマン、ストリートファイター、魔界村など数多くの世界的ヒットタイトルを持つ世界を代表するゲームメーカーである株式会社カプコン。そのゲーム開発の拠点である大阪の研究開発ビル。ここにゲームのオーディオを制作するためのミキシングルームがある。効果音、BGMなどを制作するクリエイター、海外で収録されたダイアログや楽曲、それぞれに仕上がってきたサウンドのミックスやマスタリングを行うためのスペースとなるが、そのミキシングルームが内装からの大改修により新しく生まれ変わった。
度重ねた更新と進化、理想のアコースティック
カプコンのbitMASTERstudio が設けられたのは2006 年のこと。ゲームではカットシーンと呼ばれるムービーを使った演出ができるようになるなど、コンソールの進化や技術の進化により放送・映画と遜色たがわないレベルの音声制作環境が求められてきていた時期である。そして、ステレオからサラウンド、さらにはイマーシブへと技術の進歩によりリファレンスとしての視聴環境への要求は日々高まっていく。
こうしたゲーム業界にまつわる進化の中で、カプコンbitMASTERstudio も時代に合わせて更新が行われていくこととなる。PlayStation2 の世代ではステレオ再生が基本とされる中で、DolbyPro Logic 2 を使ったサラウンドでの表現にも挑戦。PlayStation3 /Xbox の登場以降はDolby Digital が使用できるようになり、5.1chサラウンドへの対応が一気に進むことになる。ゲームにおける音声技術の進化に関しては興味が尽きないところではあるが、また別の機会にまとめることとしたい。
2006年にbitMASTERstudioが誕生してから、次世代のスタンダードをにらみ、ゲーム業界の先を見据えた更新を続けていくこととなる。今回のレポートはまさにその集大成とも言えるものである。改めてbitMASTERstudioの歩みを振り返ってみよう。設備導入当初よりAvid Pro Tools でシステムは構築されており、この時点ではDigidesign D-Control がメインのコンソールとして導入されていた。その後、2009 年に2 部屋目となる当時のB-Studio が完成、こちらにもDigidesign D-Control が導入される。2013 年にはA-Studio の収録用ブースを改修してProTools での作業が行えるようシステムアップが行われ、2015 年にはA-Studio のコンソールがAvid S6 へと更新された。
こうして更新を続け、その時点での最新の設備を導入し続ける「bitMASTERstudio」の大きな転機が、2018年に行ったB-studioの内装から手を加えた大規模な改修工事である。ゲームにもイマーシブ・オーディオの波が訪れ、その確認をしっかりと行うことができる設備の重要性が高まってきているということを受け、いち早くイマーシブ・オーディオ対応のスタジオとしてB-stduioが大改修を受けて生まれ変わった。その詳細は以前にも本誌でも取り上げているので記憶にある方も多いのではないだろうか。金色の衝立のようなスピーカースタンドにぐるっと取り囲まれた姿。一度見たら忘れられないインパクトを持つ部屋だ。
この部屋は音響施工を株式会社ソナ(以下、SONA)が行った。この部屋における音響設計面での大きな特徴は、物理的に完全等距離に置かれたスピーカー群、これに尽きるだろう。物理的にスピーカーを等距離に設置をするということは現実的に非常に難しい。扉などの導線、お客様の座るソファー、そもそもの壁の位置など、様々な要素から少なからず妥協せざるをえない部分が存在する。B-studioでは衝立状のスタンドを部屋の中で理想の位置に設置することで完全等距離の環境を実現している。これは、アコースティック的に理想となる配置であり、そこで聴こえてくるサウンドは電気的に補正されたものとは別次元である。この経験から今回のA-studioの改修にあたっても、前回での成功体験からSONAの施工で内装変更とそれぞれのスタジオのイマーシブ化を実施している。
📷 25年に渡りカプコンのサウンドを支えるエンジニアの瀧本氏。ポスプロで培ったサウンドデザイン、音による演出などのエッセンスをゲーム業界にもたらした。
圧倒的なパフォーマンスを求めたスピーカー群
今回の更新は、A-studioおよびそのブース部分である。前述の通りでブースにもPro Toolsが導入され、Pro Toolsでの編集を行えるようにしてあったが、やはり元々は収録ブースである。そこで今回は、ブースとの間仕切りの位置を変更し、ブースをC-studioとしてひとつのスタジオとして成立させることとなった。それにより、A-studioの部屋は若干スペースを取られることになったが、マシンルームへの扉位置の変更を行いつつ、スピーカーの正面を45度斜めに傾けることでサラウンドサークルの有効寸法に影響を与えずに部屋を効率的に使えるような設計が行われた。なお、この部屋は研究開発ビルのフロアに防音間仕切りを立てることで存在している空間である。その外壁面には手を加えずに内部の間仕切り、扉の位置などを変更しつつ今回の更新は行われている。
📷 スタジオ配置がどのように変更されたかを簡単な図とした。間仕切りの変更といっても、かなり大規模な改修が行われたことがわかる。
それではそれぞれのスタジオを見ていこう。まずは、旧A-studio。こちらはDubbing Stageと名称も新たに生まれ変わっている。なんといっても正面のスピーカー群が初めに目を引くだろう。旧A-studioでは、MK社製のスピーカーがこの部屋ができた当初のタイミングから更新されることなく使用されてきた。その際にスピーカーはスクリーンバックに埋め込まれていたのだが、今回はスクリーンバックではなく80 inchの巨大な8K対応TVへと更新されたことで、すべてのスピーカーのフェイスが見えている状態での設置となった。正面に設置されたスピーカーは、一番外側にPMC IB2S XBD-AⅡ、その内側にPMC 6-2、さらに内側にはサブウーファーであるPMC8 SUBが2本ずつ、合計4本。センターチャンネルにPMC 6-2という設置である。
PMC IB2S XBDはIB2SにスーパーローボックスとしてXBDを追加した構成。2段積みで1セットとなるスピーカーである。これはステレオ作業時に最高の音質でソースを確認するために導入された。カプコンでは海外でのオーケストラなどの収録によるBGMなど、高品位な音源を多数制作している。せっかくの音源をヘッドホンやPCのスピーカーで確認するだけというのは何とも心もとない。クリエイター各自の自席にも、Genelec 8020で5.1chのシステムは設置されているが、それでもまだまだスピーカーサイズは小さい。しっかりとした音量で細部に渡り確認を行うためにもこのスピーカーが必要であった。
📷 ダブルウーファー、3-wayで構成されたPMC6-2。PMCのサウンドキャラクターを決定づけているATLのダクトが左に2つ空いているのがわかる。新設計となるスコーカーとそのウェーブガイドもこのスピーカーのキーとなるコンポーネント。
この IB2S XBDが選定されることになった経緯は2019年のInterBEEまで遡ることとなる。この年のInterBEEのPMCブースにはフラッグシップであるQB1-Aが持ち込まれていた。4本の10 inchウーファーを片チャンネル2400wという大出力アンプが奏でる豊かな低域、そして1本辺り150Kgという大質量のキャビネットがそれを支える。解像度と迫力、ボディー、パンチのあるサウンド。文字としてどのように表現したら良いのか非常に難しいところであるが、あの雑多なInterBEEの会場で聴いても、その圧倒的なパフォーマンスを体感できたことは記憶にある。このQB1-Aとの出会いからPMCのスピーカーに興味を持ち、導入にあたりPMCのラインナップの中からIB2Sを選定することとなる。しかし、IB2S単体ではなくXBD付きの構成としたということは、やはりQB1-Aを聴いたときのインパクトを求めるところがあったということだろうか。
📷 PMC QB1-Aがこちら。迫力ある存在感もさることながら、このスピーカーから再生されるサウンドは雑多なInterBEEの会場で聴いても際立ったものであった。ここでのPMCとの出会いから今回の更新へとつながったと考えると感慨深い。
6本のサブウーファーが同時駆動するシステムアップ
📷 天井にも4本のPMC6-2が設置されている。天井からの飛び出しを最低限とするため半分が埋め込まれ、クリアランスとリスニングポイントまでの距離を確保している。
サラウンド、イマーシブ用のスピーカーには、PMCの最新ラインナップであるPMC6-2が選ばれている。当初はTwo-Twoシリーズが検討されていたということだが、導入のタイミングでモデルが切り替わるということで急遽PMC6シリーズの試聴が行われ、PMC6-2に決定したという経緯がある。その際にはPMC6との比較だったということだが、ローエンドの豊かさやボリューム感、スコーカーによる中域帯の表現力はやはり PMC6-2が圧倒したようだ。それにより、天井に設置するスピーカーも含めてPMC6-2を導入することが決まった。天井部分はひと回り小さいスピーカーを選定するケースも多いが、音のつながりなどバランスを考えると同一のスピーカーで揃えることの意味は大きい。この点はスピーカー取り付けの検討を行ったSONAでもかなり頭を悩ませた部分ではあったようだが、結果的には素晴らしい環境に仕上がっている。
📷 音響へのこだわりだけでなく、意匠にもこだわり作られたサラウンド側のPMC6-2専用スタンド。フロントの三日月型のオブジェと一体感を出すため、ここにも同じコンセプトのデザインが奢られている。
サラウンド側のスピーカースタンドは、SONAの技術が詰まった特注のもの。特殊なスパイク構造でPMC6-2をメカニカルアース設置しており、スピーカーのエンクロージャーからの不要な振動を吸収している。スタンドの両サイドにはデザイン的に統一感を持った鏡面仕上げのステンレスがおごられ、無味乾燥なデザインになりがちなスピーカースタンドにデザイン的な装飾が行われている。近年ではあまり見ないことだが「気持ちよく」作業を行うという部分に大きな影響を持つ部分だろう。
サラウンド用のLFEはPMC8 SUBが4本導入された。設置スペースの関係からPMC8 SUBが選ばれているが、実際に音を出して85dBsplのリファレンスでの駆動をさせようとすると、カタログスペック的にも危惧していた点ではあったがクリップランプが点いてしまった。そこで、サブウーファー4本という構成にはなるがそれを補えるように IB2S XBDのXBD部分を同時に鳴らすようにシステムアップされている。結果、都合6本のサブウーファーが同時に駆動していることになり、XBDボックスと同時に鳴らすということで余裕を持った出力を実現できている。6本ものサブウーファーが同時に鳴るスタジオは、さすがとしか言いようがないサウンドに包まれる。
これらのスピーカーは部屋の壁面に対して正面を45度の角度をつけて設置が行われた。従来はマシンルーム向きの壁面を正面にして設置が行われていたが、角度をつけることで多数のスピーカー設置、そしてTVモニターの設置が行われる正面の懐を深く取ることに成功している。そして正面の足元には、そのスピーカーを美しく演出する衝立が設置された。足元をスッキリと見せるだけではなく色の変わる照明をそこに仕込むことで空間演出にも一役買っている。ちょっとした工夫で空間のイメージを大きく変化させることができる素晴らしいアイデアだ。天井や壁面に設置された音響調整のためのパネルはピアノブラックとも言われる鏡面仕上げの黒で仕上げられている。写真ではわかりにくいかもしれないが、クロスのつや消し感のある黒と、この音響パネルの光沢黒の対比は実際に見てみると本当に美しい。影で支える音響パネルが、過度の主張をせず存在感を消さずにいる。
Avid MTRXを中心にシステムをスリム化
📷 Dubbing Stageに導入されているAvid S6 M40は16フェーダー仕様。右半分にはウルトラワイドディスプレイがコンソール上に設置されている。キーボードの左にトラックボールが置かれているのはサウスポー仕様。この部屋を使うエンジニア3名のうち2名が左利きのため民主主義の原則でこの仕様になっているそうだ。
📷 ラックの再配置を行ったマシンルーム。3部屋分の機器がぎっしりと詰まっている。この奥にPMCのパワーアンプ専用のアンプラックがある。
作業用のコンソールに関しては、前システムを引き継いでAvid S6-M40が設置された。これまでは、SSL Matrixを収録用のサブコンソールに使ったりといろいろな機器が設置されていたが、今回の更新では足元のラックを残してそれらはすべて撤去となり、スッキリとしたシステムアップとなった。収録を行う作業の比率が下がったということ、そしてPro Toolsや開発コンソールといったPCでの作業ウェイトが大きくなってきているということが、システムをスリム化した要因だということだ。このシステムを支えるバックボーンは、Avid MTRXが導入されている。これまで使ってきたAvid MTRXはB / C-studio用に譲り、追加で1台導入してこの部屋の専用機としている。社内スタッフ同士での共有作業が中心であったため、機材をある程度共有するシステムアップで運用してきたが、メインスタジオとなるDubbing Stageの機器は独立システムとして成立させた格好だ。
主要なシステムの機器としては、このAvid MTRXとPro Tools HDXシステム、そして持ち込まれた開発PCからの音声を出力するためのAVアンプとなる。開発用PCからはゲームコンソールと同様にHDMIでの映像 / 音声の出力が行われ、これをアナログ音声にデコードするためにAVアンプが使われている。音響補正はAvid MTRX内のSPQモジュールが使われ、PMCスピーカー側のDSPは利用していない状況だ。ベースマネージメント、特に6本のサブウーファーを駆動するための信号の制御や処理がMTRXの内部で行われていることとなる。
同軸で囲む、新設された銀の部屋
📷 Dynamic Mixing Stage - SILVER。GOLDと対となるSILVERの部屋。写真で並べて見るとそのコントラストがわかりやすいだろう。スピーカーはKS Digital、デスク正面には、LCRにC88、サブウーファーとしてB88が合わせて5台設置されている。コンソールはAvid S1が導入されている。
もう一つの新設された部屋である、旧ブースとなるスペースを改修したDynamic Mixing Stage - SILVERをご紹介したい。旧B-StudioにあたるDynamic Mixing Stage - GOLDはその名の通り「GOLD=金」をデザインのテーマに作られている。そしてこちらのSILVERは「SILVER=銀」をデザインのコンセプトとして作られた。ほかの2部屋が黒を基調とした配色となっているが、こちらのSILVERは白がベースとなり音響パネルは銀色に仕上げられているのがわかる。
📷 サラウンド側のスピーカー。音響パネルで調整されたこだわりのスピーカー設置が見て取れる。この音響パネルが銀色に仕上げられており、GOLDの部屋と同様に深みのある色で仕上げられている。
スピーカーから見ていこう。こちらの部屋にはKS Digitalのスピーカーが選定された。GOLDの部屋はGenelec the ONEシリーズ、DubbingはPMCとそれぞれの部屋であえて別々のメーカーのスピーカーが選ばれている。同一のメーカーで統一してサウンドキャラクターに統一感を持たせるということも考えたということだが、様々なキャラクターのスピーカーで確認できるということも別のベクトルで考えれば必要なことだという考えからこのようなセレクトとなってる。また、多チャンネルによるイマーシブ・サラウンド構築において同軸スピーカーを選択するメリットは大きい。特にSILVERのような容積が少なく、サラウンドサークルも小さい部屋であればなおさらである。その観点からも同軸であるKS Digitalの製品がセレクトされている。正面のこれらのスピーカーはSONAのカスタム設計によるスタンドでそれぞれが独立して設置されている。こちらもすべてのスピーカーがメカニカルアース設置され、これだけ密接していても相互の物理的干渉が最低限になるように工夫が凝らされている。物理的な制約のある中で、可能な限り理想的な位置にスピーカーを自然に設置できるように工夫されていることが見て取れる。
SILVERのシステムは、AVID Pro Tools HDX、I/OはGOLDと共有のAVID MTRXが使われている。コントローラーは部屋のサイズからもAvid S1が選ばれている。シグナルのフロントエンドとなるAD/DAコンバーターはGOLDと共有ではなく、それぞれの部屋ごとにDirectout Technologies ANDIAMOが導入されている。このコンバーター部分を部屋ごとに持つことでトラブル発生時の切り分けを行いやすく、シンプルな構築を実現している。
Avid S4へ更新された金の部屋
📷 Dynamic Mixing Stage - GOLD。以前本誌でも取り上げさせていただき、大きな反響があったカプコンにとって最初のイマーシブ対応スタジオだ。
部屋の内装、スピーカーなどに変更は加えられていないが、同時にDynamic Mixing Stage - GOLDのコンソールが同じタイミングで更新されている。これまで使われていたAvid S3からAvid S4へとグレードアップだ。これによりAvid S6が導入されているDynamic Dubbing Stageとの操作性の統一も図られている。やはり、同一メーカーの製品とはいえS3とS6では操作性がかなり異なりストレスを感じることが多かったようだ。S6ならばできるのに、S6だったらもっとスムーズに作業ができたのに、ということがS4へ更新を行うことでほとんどなくなったということだ。ただし、フェーダータッチに関してだけはS6と共通にしてほしかったというコメントもいただいた。制作作業において一番触れることが多い部分だからこそ、共通した仕様であることの意味は大きいのではないだろうか。
📷 今回の更新でコンソールがAvid S4へと更新、カスタム設計の机にユニットが埋め込まれてる。これはスピーカーにかぶらないようにというコンセプトからによるもので、ディスプレイが寝かされていることからも設計のコンセプトが感じられるだろう。
GOLDのAvid S4は製品に付属する専用シャシーを使わずに、カスタム設計となったデスクへの埋め込みとしている。デスクトップのシャシーであるS4は、普通の机にそのまま設置するとどうしても高さが出てしまう。シャシーごと埋め込むというケースは多いのだが、今回はモジュールを取り出してデスクに埋め込むという手法が用いられた。S6ではこれまでにも実績のあるカスタマイズだが、S4でのカスタムデスクへの埋め込みは初の事例である。これは今後スタジオの更新を考えている方にとって参考となるのではないだろうか。
スピーカーでサウンドを確認する意義
📷 デザイン性の高い空間の居住性と、音響のバランスを高いレベルで整えることに成功し、そのコンセプトやここに至る経緯を色々とお話いただいた。GOLDの部屋で実現した理想の音環境をそれ以外の2部屋でも実現できたと語っていただいた。
すべてのスタジオを7.1.4chのイマーシブ対応としたカプコン。これまでにもレポートした検聴用の2部屋と合わせて、しっかりとしたチューニングがなされた7.1.4chの部屋を5部屋持つこととなる。
ゲームではもともとが3Dで作られているのでイマーシブに対しての親和性が高い。どういうことかと言うと、ゲーム(3Dで作られているもの)は映像や中で動くキャラクター、様々な物体すべてが、もともとオブジェクトとして配置され位置座標などを持っている。それに対して音を貼り込んでいけば、オブジェクトミックスを行っていることと一緒である。
最終エンコードを行う音声のフォーマットが何なのか、Dolby Digitalであれば5.1chに畳み込まれ、Dolby True HDであればDolby Atmos。最終フォーマットに変換するツールさえ対応していれば、ゲームとして作った音はもともとが自由空間に配置されたオブジェクトオーディオであり、すでにイマーシブであるということだ。逆にゲーム機から出力するために規格化されたフォーマットに合わせこまれているというイメージが近いのではないだろうか。
そう考えれば、しっかりとした環境でサウンドを確認することの意味は大きい。ヘッドホンでのバイノーラルでも確認はできるが、スピーカーでの確認とはやはり意味合いが異なる。バイノーラルはどうしてもHRTFによる誤差をはらむものである。スピーカーでの再生は物理的な自分の頭という誤差のないHRTFによりサウンドを確認できる。自社内にスピーカーで確認できるシステムがあるということは本当に素晴らしい環境だと言えるだろう。
ゲームにおいて画面外の音という情報の有用性を無意識ながらも体験をしている方は多いのではないだろうか。仮想現実空間であるゲームの世界、そのリアリティーのために重要な要素となるサウンド。世界中のユーザーが期待を寄せるカプコンのゲームタイトルで、そのサウンドに対するこだわりは遥かなる高みを見据えている。
📷 今回の取材にご協力いただいた皆様。左下よりカプコン瀧本和也氏、スタジオデザイン・施工を行ったSONA土倉律子氏、SONA井出将徳氏、左上に移りROCK ON PRO前田洋介、PMCの代理店であるオタリテック株式会社 渡邉浩二氏、ROCK ON PRO森本憲志。
*ProceedMagazine2022-2023号より転載
Media
2022/12/28
ファシリティの効率的活用、Avid NEXIS | EDGE
コロナ禍になり早くも3年が過ぎようとしています。その最中でも、メーカー各社はリモートワークに対応するために様々なワークフローを紹介していますが、Avidでも今年の始めに新たにリモートビデオ編集のフローを実現するシステムNEXIS EDGEを発表し、満を辞して今秋リリースされました。
クラウド?オンプレ?
Avidではこれまでもリモートでのビデオ編集やプレビューをする製品が各種あり、ポストプロダクションのニーズに合わせて、システムを構築できるようにラインナップも取り揃えられています。例えば、Avid Edit On Demandでは、ビデオ編集ソフトMedia ComposerやNEXISストレージをすべてクラウド上に展開し、仮想のポストプロダクションを作ることが可能です。クラウドでの展開は時間や場所を問わず利用できること、使用するソフトウェアの数やストレージの容量の増減を簡単に週・月・年単位で設定し、契約することができ、イニシャルコストがほとんどないことがメリットと言えます。
今回紹介するAvid NEXIS EDGEは先で述べたEdit On Demandのクラウド構築とは異なり、サーバー購入の初期投資が必要になります。クラウド化の進みとともに、CAPEX(設備投資)からOPEX(事業運営費)へという言葉が最近よくささやかれ、今どきオンプレのサーバーは流行らないのでは?という見方はあるかもしれませんが、ポストプロダクション業務としてビデオ編集をする上で、すべてをクラウド上で編集することが必ずしも正解だとは言い切れません。それは、映像データの適切な解像度での再生、正確な色や音のモニタリングに対してクラウド上のシステムではできないこともあるからです。
Avid NEXIS EDGEは、会社内にサーバーを置くオンプレミスでのメディアサーバーシステムとなります。Avid NEXISストレージサーバーを軸にしたシステムとなり、メディアサーバーに加えてWindowsサーバーを追加します。ソフトウェアとしては、Media Composer Enterpriseが最低1ライセンス必要になります。Media Composer EnterpriseライセンスはDP(Distributed Processing)ライセンスが含まれており、プロキシを作成するために使用されます。DPは日本語では分散レンダリングと言われ、ネットワーク上にあるひとつまたはそれ以上のワークステーションを使用して、レンダリングやトランスコード、コンソリデートといったメディア作成の処理を行うことで、編集システムのCPUを使用せずに時間のかかるプロセスを外部で行うことができる機能です。
NEXIS EDGEが持つメリット
📷 NEXIS EDGE Webブラウザのユーザーインターフェース 素材の検索と編集
NEXIS EDGEの特徴は大きく分けて2つあります。1つ目は、NEXIS環境において社内のLAN環境と、汎用のインターネット回線を用いるリモートアクセス機能を簡単に切り替えできることです。つまり、遠隔地にいてもオンプレにあるNEXISサーバにアクセスすることができ、サーバー内にあるシーケンス、ビン、クリップを閲覧、再生、編集することができるのです。クラウドサービスを使用しなくてもクラウドと似た環境を構築することができ、メディアを様々な場所にコピーして分散させずに、オリジナルのメディアを1つの場所に置いて使うことができます。
2つ目は、高解像度メディアとそこから生成されたワーク用のプロキシメディアのメタデータが完全に一致して作られることです。そのため高画質のクリップを用いて編集をしても、プロキシメディアで編集をしても、シーケンスにはどちらのメディアも完全にリンクしており、再生ボタンの切り替えで再生させたいメディアを簡単に選ぶことができます。このシステムでプロキシを作成し、使用することの優位性がいくつかあります。汎用のインターネット回線を介して使用できることがその一つです。そしてプロキシメディアはデータ量も少なくダウンロードするにも時間がかからないため、ダウンロードをしたメディアを使用することができます。いったんメディアをコピーしてしまえば、その後インターネットを接続していなくても、ダウンロードをしたメディアで編集をすることができ、その編集されたビンやシーケンスは、ネットワークのある環境に戻せば、NEXISサーバー内にあるメディアにすぐにリンクすることができます。また、プロキシメディアの優位性はリモート環境で使用することだけではありません。LAN環境でもそのメディアを使うことで、ネットワークの帯域を節約することができます。
ストレージ内のメディアにアクセス
ご自身が社内ではない場所にいる場合、社内にあるNEXISメディアサーバーへアクセスするには通常のNEXISクライアントのリモート機能を使い、アクセス権で管理されたワークスペースをマウントします。Media Composerはプロジェクトの作成画面で、Remote Avid NEXISにチェックを入れて起動します。
📷 NEXISへのリモートアクセス
ビンに表示されているクリップは、プロキシメディアがあるクリップなのかどうかが一目で分かります。プロキシメディアがない場合には、メディア作成権のあるユーザーがMedia Composerからプロキシメディアを生成させることもできます。プロキシの生成は前述したDPが機能するPCで行うため、Media Composerで作業をしているエディターは編集作業をそのまま続けることができ、プロキシが作成された順にそのメディアを使うことができます。この分散レンダリングは、バックグラウンドでレンダリングを行うDP Workerと呼ばれるPCの数で、プロキシ生成やトランスコード等のタスクを分けることができます。そのためDP Workerの数が多ければ処理も早くなります。また、スタジオ内にあるMedia Composerが使用されていなければ、そのシステムもDP Workerとして使うこともできます。
📷 分散レンダリングでプロキシを作成するメニュー
リモートで接続したMedia ComposerからNEXISストレージ上のメディアを再生するときは、そのメディアの解像度を選択します。NEXISストレージ上にあるクリップには、高画質メディアとプロキシメディアの2つのメディアがリンクされており、Media Composerでどちらのメディアを再生するかを選択することができるため、NEXISストレージに接続されている環境に合わせてメディアを再生できます。
📷 再生のための解像度の選択
みんなでコラボ
NEXIS EDGEへのWebアクセスツールでは、クリップやビンへのアクセスはもちろんのこと、簡単なビデオ編集、クリップまたはシーケンスへマーカーやコメントなどを付ける機能があります。アシスタントからプロデューサーまでコンテンツに関わるすべての人々が、簡単な操作で編集作業を効率的に、そして円滑に共有することができます。一方、そのためにメディアの管理にはいっそう気を使わなければなりませんが、そんなときにもNEXIS EDGEではビンロックの機能によるシーケンスやクリップの保護、視聴や編集機能の有無など、ユーザー単位でシステムの機能を制限することができます。
さらに、NEXIS EDGEのPhonetic Indexオプションを使用することで、クリップ内の音声トラックからのキーワード検索をすることができ、素材クリップとそのキーワード箇所を素早く見つけることができます。この機能はWebクライアントでも、Adobe Premiere Proクライアントでも利用することができます。
SRT対応で機能アップ、Media Composer 2022
📷 Media Composerユーザーインターフェース クリップアイコンがオレンジ表示になっている時はプロキシメディアがリンクされている。
今年になり5Gが本格的に普及し、汎用のインターネット回線を使ってのワークフローは今後も増えていくことが期待されます。Media Composerはバージョン2022.4でSRT(Secure Reliable Transport)に対応しました。SRTは以前の本誌でも何回かご紹介したことがありますが、マルチメディア伝送のプロトコルです。2012年にカナダに本社を置くHaivision社によって開発されました。非常に強力な暗号技術を採用し、高い安全性とパケットロスのリカバリ、高画質であることが特徴で、2017年にオープンソース化され、同時に組織化されたSRT Allianceによる推進のもと、今では世界の多様なメーカーによって採用・開発・実装が行われています。コロナ禍で最初は戸惑っていたWeb会議も日常的になりましたが、環境によって回線速度が異なるため、そういったツールでの画質や音質は最低限に抑える必要があり、とてもリアルタイムでのプレビューチェック向きとは言えません。それを回避するためにYouTubeなどを使用することもありますが、設定ミスから意図せず動画が公開されてしまうというリスクはなくなりません。
📷 SRTの設定画面
そういった問題を解決できるのがMedia ComposerでのSRT送信です。Media Composerは内部でSRTのソフトウェアエンコードを行い、リアルタイムでインタネット越しにタイムラインを送信します。SRTを送信するにはMedia Composer内のH/Wボタンから設定を行い、シーケンスを再生するだけです。それを受け取るには、SRTデコーダーを備えたアプリケーションやハードウェアが必要になりますが、フリーのHaivision Playerや VLC Player等を使っても受信することが可能です。そのため、インターネット回線さえあればMedia ComposerのタイムラインをSRTでプレビューできます。例えば、遠方のクライアントに対してプレビューをする時など、前もってファイル転送サービスでファイルを送ったり、YouTubeの限定公開を使うためにファイルをアップロードしたりすることなく、ZoomなどのWeb会議システムで会議をしつつ、タイムラインをプレビューすることができます。そして、プレビュー中に直しがあってもファイルを書き出し直し、そのファイルのアップロードやダウンロードをし直すことなく、まるで編集室で立ち会っているかのようなコニュニケーションを取ることが可能です。
また、10月にリリースされたMedia Composer 2022.10では、Multiplex-IO機能が搭載されました。この機能は、シーケンスをスタジオでモニタリングしながら、同時にSRTやNDIをストリーミングさせることができるため、以前のようにどちらかに接続先を切り替える必要がなくなります。
より良い作品を作ることに必要とされるのが「どんな作品を作るのかという共通の認識」を持つことだとしたら、一番大切なのはコミュニケーションです。スタジオでの立ち合い編集などで時間を共有させてのコミュニケーションも大事ですが、ライフスタイルの変化によって場所も時間も共有できない時には、それを可能にするツールを使ってみてはどうでしょう。NEXIS Edgeはリモート・ビデオ編集を可能にする製品ではありますが、単に在宅作業を促進するためのものではありません。この製品はそう簡単には増やせない編集室の代わりに、場所を選ばない方法で編集作業を可能にするものなのです。
*ProceedMagazine2022-2023号より転載
Media
2022/12/26
株式会社Cygames様 / 大阪サウンド部 エディットルーム〜妥協ないコンテンツを生み出していく、7.1.4ch可変レイアウト2スタジオ
2011年、第一弾タイトル「神撃のバハムート」を皮切りに、これまで「グランブルーファンタジー」、「Shadowverse」、「プリンセスコネクト!Re:Dive」、「ウマ娘 プリティーダービー」などのゲームタイトルをリリースしてきた株式会社Cygames。その中でも、コンシューマー・ゲーム機向けのコンテンツ制作を主に行う大阪拠点においてDolby Atmos 7.1.4chに対応したスタジオが同時に2部屋開設された。まだまだフォーマットも定まらず過渡期だというゲーム制作のイマーシブ分野において、進取の取り組みが始まった大阪Cygamesサウンド部 エディットルームをご紹介していく。
2つのエディットルーム
大阪Cygames サウンド部エディットルーム(以下、大阪エディットルーム)は梅田中心部、交通アクセスもよく大阪Cygamesの第一拠点の近くに位置する。今回新設された大阪エディットルームはDolby Atmos対応のスタジオが2部屋という構成となり、大阪Cygamesにおけるリスニングスタジオとして機能することになる。Cygamesの東京拠点では、既にエディットルーム(以下、東京エディットルーム)が6部屋稼働しているが、大阪Cygamesで制作中である「GRANBLUE FANTASY: Relink」がサラウンド対応コンテンツとなり、同じようなスタジオの必要性を感じていたことからプロジェクトが開始されることとなった。
現状、スマートフォン向けコンテンツではステレオが基本となっており、コンシューマー機等でのゲームについてはサラウンド対応といったところで、ゲームにおけるイマーシブオーディオについてはどのようなフォーマットがスタンダード化していくのか今後の動向を窺っている状況にあるという。イマーシブオーディオに注目し始めたきっかけはMicrosoftがWindowsとXBOXでDolby Atmosをサポートしたことだったそうだ。コンシューマー・ゲーム機からの視点ではSony PlayStationはHDMIからのイマーシブ系の実出力には対応せず、バイノーラル系の技術で進むなど、大手を振ってこれからはDolby Atmosとは言えない状況ではあるが、現時点ではDolby Atmosがもっともスタンダードに近い存在であり、まずはそれに取り組むことが必要であるとのこと。さらには、Sonyから360 Reality Audioも発表されたため過渡期は引き続きとなるが、新たな規格が登場してくるとそれだけイマーシブオーディオが織りなすゲームの世界がどのように発展するのか期待も高まる。
すでに、5.1chのコンテンツを制作しているが再生環境が整っている家庭はまだ少なく、作り上げたサウンドがプレイヤーに伝わっているのだろうかという歯痒さを感じているそうだ。それでも、イマーシブオーディオという素晴らしいコンテンツを見過ごすわけにはいかないので、5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmosを取り入れ妥協することなくゲーム開発に挑戦し続ける。こういった取り組みにも「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンが見えてくる。
📷 エディットルーム A
📷 エディットルーム B
そして、今回竣工したのがこのエディットルームだ。こちらはインゲームでサラウンドを正確にリスニングすることが主な用途となっており、エディットルームA/Bという同じDolby Atmos 7.1.4ch対応の2部屋を設置することで、同時に作業ができるよう運用面での効率化が図られている。なお、エディットルームA/Bでは異なったオペレートデスクが設置されており、ルームAは固定デスク、ルームBは可動式デスクとなっている。ここにエディットルームの個性が隠されており、ルームBのデスクを移動することによりルームAはコントロールルーム、ルームBは収録スタジオのレイアウトに可変することができる。そのため、主な目的はリスニングとなってはいるが、ナレーションなども収録できるシステムを備えており、マイクプリアンプなどアウトボード系の機材も充実したラインナップが用意された。
📷 一見だけすると全く同じ部屋の写真に見えてしまうのではないだろうか、左ページが大阪Cygames エディットルームA、右ページが同じくエディットルームBの様子となる。両部屋をつなぐ窓の位置、そしてデスクとラックの形状をよく見るとお互いが連携している隣り合ったスペースであることがわかる。また、本文中でも紹介した通り、エディットルームBを収録スタジオとして使用できるようにBのデスク・ラックは可動式とされており、ナレーション収録など作業のシチュエーションによっては上図のように役割を変化させて制作を進行することができる仕組みだ。
基準となる音場
東京エディットルーム竣工時、様々なブランドのモニタースピーカーの比較試聴を行い、GENELEC The Onesシリーズを採用した。元々GENELECには高低音が強調されるようなイメージを持っていて、本命のブランドではなかったというが、The Onesシリーズを試聴した際にそのドンシャリというネガが消え、非常に良いイメージに変わったとのこと。また同軸スピーカーならではの定位感も高く評価を得ている。その流れを汲み、大阪CygamesエディットルームでもGENLEC 8331AWが採用される運びとなった。
大阪CygamesのスピーカーキャリブレーションはMTRX SPQスピーカープロセッシングを採用している。PCなどの機材が全て常設であるため、竣工時に日本音響エンジニアリングによる音響調整を行い、サウンド部スタッフ全員が同じ環境でモニタリングできるスタジオを作ることができた。なお、先立って稼働している東京エディットルームではGENELEC GLMを採用して音響調整を行なっており、PCやオーディオI/Fなど機材を持ち込むことが可能で、言わばフリースペースのような感覚で使用できるようになっている。そのため、GLMで手軽にオートキャリブレーションできるというメリットを活かしているが、状況によりリファレンスが変わるため、基準となる音場の必要性を感じていたそうだ。今回の大阪エディットルームではPCほかの機材を常設設備にして音響調整を重要視した理由がここにある。
📷 GENELEC 8331AW、Cygamesのコーポレートカラーであるホワイトのモデルをセレクト、ハイトスピーカーとして天井に吊られている。写真下はGENELEC 7350APM。スピーカーシステムと部屋のサイズを考慮し、8インチのサブウーファーが設置されている。
システムの柔軟性
大阪エディットルームでのメインDAWはOM Factory製Windowsマシンで稼働するSteinberg Nuendoとなっている。ゲームの開発環境がWindowsベースとなるため、Windows用DAWとして安定しているNuendoに信頼感があること、また、Nuendoに備えられた「Game Audio Connect」でミドルウェアのWwiseと連携できることは、膨大な音声ファイル数となるゲームのサウンド制作においては大きなメリットとなる。
一方、東京・大阪の各スタッフが使用しているDAWソフトウェアは多種多様で、スタッフ本人の意向に沿ったソフトウェアをそれぞれ導入しているとのこと。Avid Pro Tools、Apple Logic Pro、Steinberg Cubase、PreSonus Studio One、中にはAbleton Liveを使っているスタッフもいるそうだが、スタジオでの作業用として、また社外とのやり取りのためにPro Toolsは共通項。大阪のサウンド・デザイン・チームでは、ゲームサウンド制作に長年携わり、WindowsでNuendoという環境に慣れ親しんだ方が多く、今回のメインDAWについてもNuendoが採用されたのはごく自然な流れだったようだ。
📷 エディットルームAのカスタムオペレートデスク。ノンリニア編集に適するようフリースペースの広い形に設計されている。正面左手はRUPERT NEVE DESIGNS/SHELFORD CHANNEL、George Massenburg Labs / 2032、Empirical Labs/Distressor (EL-8)、Eventide/H9000 Harmonizerを、右手にはVertigo Sound/VSM-2 Full、SPL/Stereo Vitalizer MK2-T (model 9739)がマウントされている。直接操作することが少ないOM Factory製のDAW用PCやAVID Pro Tools|MTRX などは足元に収納されている。
なお、エディットルームでの中核となっているのがAvid MTRXとなっている。もちろんMTRXはProToolsで使用するイメージが強いのだが、多機能なオーディオルーティングやコンバーターとしての顔を持っており、NuendoをメインDAWとした大阪エディットルームでも中核機材として導入されている。今回の例では、各DAW PCに搭載されているYAMAHA AIC128-DからDanteで出された信号がMTRXに入り、スタジオ内のモニタースピーカー、コミュニケーション、アウトボードへアナログ信号で送信されている。また、持ち込みPCによるオペレートも想定しており、持ち込みPC用I/FにRME Fireface UFX+を設置。Fireface UFX+MTRX間はMADI規格が用いられている。
各サウンドデスクやエディットルームへの信号はDanteで張り巡らされており、スタジオ内でのルーティングはDADmanで行い、システム全体のルーティングはDante Controllerで行う、という切り分けがなされている。メインスピーカーのボリュームコントロールはNTP Technology MOM-BASEを用いてMTRXをリモートしているシステムとなっている。このシステムを実現するためという点でも、DAWを選ばず柔軟なシステムに対応するMTRXが選定される理由となった。
オペレートの多様性
今回新設の大きな要望として「4Kの画面をどこでも映せる、どこの4Kの画面でもどこにでも持っていける」、「どの音をどこでも聴ける」というテーマがあった。そのコンセプトに沿って、映像信号はADDERのKVMで、音声はDanteで、という役割分担が行われ、各サウンド部スタッフのデスクとエディットルームの音声および映像信号をやり取りするシステムが構築されている。すべてのデスクにKVMおよびDanteインターフェースが用意されており、各デスクで作業をしながらエディットルームの音声をリスニングしたり出力すると同時に、4Kの映像も映し出すことが可能となっているわけだ。
なお、その際HDMIにエンべデットされているDolby Atomsの信号をどのように各ルームとやりとりするのかが課題となっているのだが、配管の問題もあり実線を張り巡らせるのは現実的ではない。AVアンプを駆使してアナログ音声をデエンベデッドする構成もあるが、映像と音声のズレが発生しないかなど現在も検証を続けているところだ。また、映像と音声の垣根を超えるDante AV規格も選択肢の一つではあるが、現在の条件下でHDMIからDolby Atomsのチャンネル数を同時に転送することは難しいため、こちらはDante AV規格自体の発展に期待が寄せられる。ほかにも、機能拡張として各デスクでDolby Atomsをリスニングできる構想など、いまも将来に向けてスタジオ自体が成長し続けていると言えるだろう。
シンプルかつ多機能な機材レイアウト
竣工当時からの課題ではあったが、スペースの都合上でマシンルームを設けることができなかった。そこで、起動音が小さい機材はエディットルーム内に収納、スイッチングハブなどの起動音が大きい機材はスタジオ外にあるラックケースへ収納することで解決を図っている。結果的に、主だった機材がすべてスタジオ内で操作が可能で、ステータスなども目視確認ができるというメリットも生まれた。ここ近年の機器の進歩によって抑えられた起動音や、MTRXのオールインワン性を活かし必要最小限の機材構成としたからこそ実現できた機材レイアウトである。また、エディットルームAは常設のデスクとなる為、収録時でもストレスなく機材の操作ができるように手元にアウトボード系の機材が設置されている。メモや台本などを置けるスペースも広く、ノンリニア編集の理想的なオペレートスペースを作ることができている。
📷 起動音を考慮し静音ラックに収納され、スタジオ外に設置されたスイッチングハブ YAMAHA/SWR2310-10G。各エディットルームとサウンドデスク間を繋ぐDanteの信号処理を行う中核として機能している。また、左写真は別途に設けられたフォーリースタジオの様子だ。
施工にあたってはデザイン面も重要な要素となった。コーポレートカラーであるブラック / ホワイトを基調としたスペースからスタジオに入ると、内装にフローリングの床面やダークブルーを用いた落ち着いた空間が演出されている。オペレートデスクやスピーカースタンドもすべてカスタムオーダーとなっており、素材選びの段階から製作が行われたとのこと。特に、壁紙のカラーなどは大阪Cygamesが注力して開発している『GRANBLUE FANTASY: Relink』の空を意識した青が基調にされており、より制作しているコンテンツの世界観に没入して制作を進めることができそうだ。ゲーム開発ではどうしても自席でのデスクワークがメインとなるが、根本にはエディットルームをいっぱい使って楽しんで欲しい、リラックス感が感じられるように、という思いがあり、それがデザインに込められている。スタッフのモチベーションを上げるということも目的として重視されているということだ。
📷 右:株式会社Cygames サウンド部マネージャー 丸山雅之 氏 / 左:株式会社Cygames サウンド部サ ウンドデザイナー 城後真貴 氏
経験豊かなクリエイターによって一貫したクオリティでコンテンツ制作を進める大阪サウンド・デザイン・チーム。そのクオリティの基盤となるスタジオが新設されたことで、制作ワークは一層の飛躍を遂げることになるだろう。もちろん、ゲームサウンドにおけるイマーシブ制作といった観点でもここから数々のノウハウが生まれていくに違いない。ソーシャルゲームのみならずコンシューマー・ゲームの開発やアニメ制作、漫画事業など幅広い分野でコンテンツをリリースする株式会社Cygames。その「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンの通り、妥協ないコンテンツを生み出していくための拠点がここに完成したと言えるのではないだろうか。
*ProceedMagazine2022-2023号より転載
Media
2022/09/01
【MIL STUDIO技術解説】MIL誕生に寄せて〜鑑賞から体験へ 選択から多様の未来へ〜
チャンネルが少なくなければできないことがある。チャンネルが多くなければ分からないことがある。
オーディオの世界を支配するチャンネルとはいったい?
【技術解説】MIL誕生に寄せて〜鑑賞から体験へ 選択から多様の未来へ〜
中原雅考(株式会社ソナ / オンフューチャー株式会社)
📸 株式会社ソナ / オンフューチャー株式会社
中原 雅考 氏
芸術と工学の融合
スタジオと同じ音で作品を聴いてもらいたい。原音忠実再生といった希望は、多かれ少なかれ音響コンテンツ制作者にとっての願いだと思います。しかし、そのためには、ユーザーもスタジオと同じような環境にスピーカーを設置して作品を試聴しなければなりません。今や時代は多様化し、ユーザーの試聴環境は2chかサラウンドかといった単純な選択肢ではなくなっています。ともすれば、この作品はこのように聴いて欲しいといった制作者の強いこだわりが、ユーザーに対しての不用意な圧力になってしまうかもしれません。本来、作品には自由な表現が与えられるべきだと思いますが、オーディオでは、2ch、5.1ch、7.1.4chなど再生チャンネルの形式によって異なる流儀が要求されてしまいます。そのような制限は、工学が芸術を支配しているような関係にも見えてしまいます。
素晴らしい技術をもったエンジニアがスタジオでつくり出す音は最高です。その素晴らしさを多くのユーザーに伝えたいと思い、スピーカーの設置方法、調整方法、部屋の音響のことなどを様々な場面で伝えてきました。しかしそれは、ユーザーにとっては「高級な鮨屋で食べ方を指導されながらおいしさを味わっている」ような世界かもしれません。どうやら、今一度オーディオと出会った頃のユーザー体験に立ち返る必要がありそうです。工学による芸術の制限を緩和すべく、より一層の芸術と工学の融合を目指して…
誰もが気軽に良さの分かるオーディオ再生とは?
作品やユーザー(聴取者)が主役になるためのオーディオとは?
「モノ」「ステレオ」
Media
2022/09/01
完全4π音響空間で描く新たな世界の始まり。〜フォーマットを越えていく、MIL STUDIO〜
MIL=Media Integration Lab。絶えず時代の流れの中から生まれる、我々Media Integrationのミッション。創造者、クリエイターと共に新しい創造物へのインスピレーションを得るために、昨今の空間オーディオ、3Dサウンド、多彩なフォーマット、様々な可能性を体験し、実感する。そのためのスタジオであり、空間。2021年にオープンしたライブ、配信、エキシビジョンといった皆様とのまさに「ハブ」となる空間「LUSH HUB」に続き、次世代の音響、テクノロジーと体験、共有するための空間としてMILは誕生した。43.2chのディスクリート再生で実現した下方向のスピーカーを備えた完全4π音響空間。研究と体験、そこから得られるインスピレーション。それを実現するためのシステム、音響、これらをコンセプト、テクノロジー、音響など様々な切り口からご紹介していきたい。一つの事象に特化したものではないため、掴みどころがなく感じるかもしれない。しかしそれこそが次のステップであり、新しい表現の始まりでもある。
「4π」での感覚で描かれた音楽を
まずは、MIL(ミル)のコンセプトの部分からご紹介していきたい。長年2chで培われてきた音楽の表現。それは今後も残ることになるが、全く異なった「4π」での感覚で描かれた音楽が主体となる世界が新たに始まる。私たちはそのターニングポイントにあり、このMILは「進化し続けるラボ」として今後誕生するであろう様々なフォーマット、3Dの音響を入れるための器、エンコーダー、デコーダーなど様々なテクノロジーを実際に再生し体験し共有することができる。
そのために、特定のフォーマットにこだわることなく、可能性を維持、持続できる空間として設計がなされた。音響面に関しては、このあとのSONA中原氏の解説に詳細を譲るが、物理的な形状にとらわれることなく、今後進化を続けるように運営が行われていく予定である。スピーカー、音響パネルなどは、簡単に入れ替えられるようなモジュール構造での設計がなされており、かなり深い部分からの変更が可能だ。
また、MILならではの特徴として居住性にこだわった、というところは大きいだろう。各研究施設の実験室、無響室のような環境の方が、より正確な体験が行えるのかもしれない。しかしそのような空間は、まさに「Lab」であり、生み出された作品を「視聴」ではなく「検証」する場という趣である。もちろんそこに意味はあるし、価値もある。しかし、MILでは、作品自体をエンターテイメントとして受け取り、住環境にもこだわりゆっくりと楽しむことのできる環境を目指している。ユーザーの実際に近い環境での「検証」が可能であり、「視聴」を行うというよりコンテンツ自体を楽しむという方向での実験、というよりも体験が可能だ。このあとにも紹介する様々なプロセッサー、ソフトウェアを駆使して、いろいろな音環境でリラックスした環境で様々なコンテンツの視聴を行うことができる。
居住性にこだわりつつも、オーディオ、そしてビジュアルのクオリティーに妥協は無い。そのコンテンツ、作品の持つ最高の魅力を体感するために、最善と思われるオーディオとビジュアルのクオリティーを導入している。オーディオに関しては、水平よりも下方向にもスピーカーを配置した、現時点での音響空間のゴールとも言える4π空間再現による真の360イマーシブ環境を実現している。そのスピーカーにはFocal CIの3-Way Speakerを採用している。多チャンネル、イマーシブの環境では同軸のスピーカーが採用されることが多い。もちろん、2-way、3-wayといったスピーカーよりも物理的に点音源としてオーディオを出力する事ができる同軸スピーカーのメリットは大きい。しかし、設置の条件とサウンド・クオリティーを満たす同軸のユニットがなかったために、MILでは音質を重視して3-Way採用に至っている。スピーカー選定に際しては、ユニット自体の音圧放射の特性を調べ上げ、マルチチャンネルにふさわしいものを選定している。その測定の模様はこれまでの本誌にて株式会社SONA執筆の「パーソナル・スタジオ設計の音響学」に詳しい。
この部分に疑問のある方は、ぜひともMILで実際のサウンドを確認してほしい。イマーシブサウンド以降、立体音響=同軸スピーカー。この組み合わせは正しい回答ではあるが、絶対ではないということを知っていただけるはずだ。ビジュアルに関しても、最新の8K60P信号に対応したプロジェクター、そしてEASTON社のサウンドスクリーンの導入と抜かりはない。最新のテクノロジーを搭載した機材を順次導入していく予定である。多彩なフォーマットの体験の場として、またその体験を通しての学習の場として、あるいは創造の場としても今後MILを活用していく予定である。今後の情報発信、そして様々なコラボレーションなどに期待していただきたい。
📸 右写真にてご紹介するのはMIL STUDIOの設計・施工を手がけた株式会社ソナの中原 雅考 氏。後述となる同氏の技術解説も是非ご覧いただきたい。
43.2ch、4π空間をFocalで包む
ここからは、MILにおけるシステムの特徴についてご紹介していきたい。何はともあれ、この大量のスピーカーが興味の焦点ではないだろうか。スピーカーは水平方向に30度刻みで等間隔に配置される。高さ方向で見ると5層。12本 x 5層=60本。それに真上と真下の2本が加わる。現状のセッティングでは、中下層は水平面のスピーカーのウーファーボックスが設置され、下方向も半分の6本のスピーカーを設置、真下もスタンバイ状況ということで、実際には43chのディスクリートスピーカー配置となっている。それに2本の独立したサブウーファーがある。これで43.2chということだ。
📸 L,C,R chは、上から1000 IW 6、1000 IW LCR UTOPIA、HPVE1084(Low Box)が収まる。間の床にあるのがSUB 1000F(LFE)である。
これらのスピーカーはFocal CI社の最新モデルである1000シリーズがメインに使われている。正面の水平面(L,C,R ch)には同シリーズのフラッグシップである1000 IWLCR UTOPIAが設置されている。Focalではラインナップを問わず最上位モデルにこの「UTOPIA」(ユートピア)というネーミングが与えられる。CI=Custom Install、設備用、壁面埋め込み型ということで設置性重視とも捉えられ、音質が犠牲になっているのでは?と感じられる方もいるかもしれないが、同社が自信を持ってUTOPIAの名前を与えているだけに、このモデルは一切の妥協が感じられない素晴らしいサウンドを出力してくる。
それ以外の水平面と上空のTop Layerには1000 IW LCR 6が採用されている。機種名にLCRと入っていることからもわかるように、メインチャンネルを担当することを想定した3-way+1 Pussive Radiatorを搭載したモデル。Hight Layerには1000 IW 6という2-wayのモデルが設置されている。1000シリーズは、FocalのProfessionalラインで言うところのSolo 6 Be、Twin 6 Beといったラインナップに相当する。同社のアイコンとも言えるベリリウムツイーター、'W'コンポジットサンドウィチコーンを搭載した製品である。すでに高い評価を得ているFocal Solo 6 Beと同等のユニット構成のモデルが1000 IW 6。そう考えれば、そのスピーカー群のクオリティーが想像しやすいのではないだろうか。
📸 L,C,Rch以外のスピーカースタンド。上から1000 IW 6、1000 IW LCR 6、HPVE1084(Low Box)が収まる。
ベリリウムで作られたインバーテットドーム・ツイーターのサウンドは、すでに語られ尽くしているかもしれない。その優れた反応速度、濁りのないピュアな響き、Focalのサウンドキャラクターを決定づけているとも言えるサウンド。そのクオリティーをMILではマルチチャンネル、イマーシブ環境として構築した。Focal CIの1000シリーズは、クローズドバックで厚さはわずか10cm程しかない。その特徴もこのような多チャンネルのスピーカー設置を行う際には大きなメリットとなっている。今後、追加で天井にスピーカーを設置したいといった要望にも柔軟に対応できることだろう。
床下のBottom Layerのスピーカーには300シリーズが採用されている。これは物理的な問題が大きく、300 IWLCR 6がサイズ的に合致したということでこの選択肢となった。この300シリーズは、Focal Professionalで言えばSHAPEに当たるラインナップ。ユニットも同等の製品が使われている。物理的なサイズの制約があったといえ、採用できる限りで最良の選択を行っている。このモデルは300シリーズ内でのフラッグシップとなる。1000 IWLCR 6と比べると一回り以上も小さなモデルだが、ダブルウーファーにより十分な量感のあるサウンドを再生することができる。独立したLFE用のサブ・ウーファーに関してだけは、民生のラインナップであるSUB 1000 Fが採用された。これは、ユニットの整合性を取るための選択であり、Middle Layerのウーファーユニットと同一のサウンドキャラクターを得るための選択である。見ての通り、ユニット自体は全く同一のユニットである。
📸 床下に埋め込まれた300 IW LCR 6。現在は6本が設置されているが、それ以外の箇所もキャビネットは準備されている。
📸 天井に専用設計されたリング状のスピーカーキャビネット。ユニットは1000 IW LCR 6が収まる。
イヤーレベルにあたる、Middle Layerのスピーカーには、全てサブ・ウーファー用のユニットが加えられ、3-way + 1 sub。2.1chシステム的に表記するならば、1.1chのような構成となっている。音色面で支配的になるイヤーレベルのスピーカーユニットに関しては、フルレンジとしての特性を持たせるためにこのような構成をとっている。1000 IWLCR 6で低域が不足するというわけではまったくない。このモデルは、カタログスペックとしても48Hz(-3dB)からとかなりワイドレンジでの再生が可能な製品である。これにサブ・ウーファーを組み合わせることで25Hzからのフラットな特性を持たせることに成功している。
まだまだ、イマーシブ・サウンドで制作されたコンテンツはイヤーレベルに多くの主要なサウンドを配置する傾向にある。5.1chサラウンドなどとのコンパチビリティーや、これまでの制作手法などを考えれば当たり前のことではあるし、主役となるサウンドをあえて高さを変えて配置するということに、今後もそれほど大きな意味が持たされるということは無いだろう。そういったことを鑑みてもイヤーレベルのスピーカーをこのような奢った仕様にするということは間違いではない。
FIR補正、55ch分のパワーアンプ、1300mのケーブル
Focal CIのスピーカーは、全てパッシブである。そのため、このチャンネルと同数分のパワーアンプを準備することとなる。結果、必要なパワーアンプのチャンネル数はなんと55chにものぼった。2chステレオ仕様のアンプで準備をするとしたら28台が必要ということになるが、それほど多くのアンプを設置する場所は確保できないため、主要なスピーカーを4chパワーアンプとして、それ以外をInnosonix MA32/Dという2U 32chアンプを採用することとした。
主要スピーカーとは、イヤーレベルのMiddle Layerのスピーカー群であり、クロスオーバーを組む必要があるそのサブ・ウーファーの駆動用となる。これだけでも24本のスピーカーの駆動が必要であるため、4chアンプをアサインしても6台が必要となった。この6台には、Lab.Gruppen D20:4Lが採用されている。この製品は、アンプ内部にLAKE Processerが搭載されており、クロスオーバー、補正のEQなどをFIR Filterで行うことができる高機能モデルである。クロスオーバーがFIRでできるメリットの解説は専門家に任せることとするが、クロスオーバーで問題となる位相のねじれに対して有利であると覚えておいてもらえればいいのではないだろうか。
📸 Lab.Gruppen D20:4L
それ以外のスピーカーを担当するInnosonix MA32/DもオプションでDSP Processer、FIR Filterを搭載することが可能であり、MILではそれらのオプションを搭載したモデルを導入している。これらのアンプにより、スピーカーの補正はFIRとIIRの双方を駆使することができ、より高度なチューニングを可能としている。また高さごとの各レイヤーのアンプの機種を統一することもできているので、それぞれの音色に関しての差異も最小限とすることに成功している。
📸 Innosonix MA32/D
アンプとスピーカーの接続には、ドイツのSOMMER CABLEが採用された。ELEPHANT ROBUSTという4mm2 x 4芯のOFCケーブルが採用されている。同社の最上位のラインナップであり太い芯線により高い伝導率を確保している。芯線を太くしつつ外径は最低限にすることが重要なポイントであった、引き回しを行うケーブルの本数が多いため、その調整を行うために多くの苦労のあったポイントである。ちなみにMILで使用したスピーカーケーブルの総延長は実に1300mにも及ぶ。
これらのアンプまでの信号は再生機器から、全てDanteで送られる。多チャンネルをシンプルに伝送しようとすると選択肢はDanteもしくはMADIということになる。今回のシステムでは、パワーアンプが両機種ともにDanteに対応していたために、Danteでの伝送を選択した。クリティカルなライブ用途ではないために2重化は行っていないが、ケーブルはできる限り高品位なものをと考え、Cat8のケーブルでマシンラックからアンプラックまでを接続している。また、Dante用のEthernet SwitchはPanasonicのPoE対応の製品を選択。今後のシステム拡張時にも柔軟に対応できる製品をピックアップしている。
Avid MTRXで43.2chを一括コントロール
ここまでで、B-Chainにあたる部分がDanteとパワーアンプ内のDSPで構成されていることをお伝えしてきたが、本システムで一番苦労したのがここからご紹介する、モニターコントローラー部分だ。まず、必要要件として43.2ch(将来的には62.2ch)の一括ボリューム制御ができる製品であることが求められる。これができる製品を考えるとAvid MTRXの一択となる。Avid MTRXのモニター制御部分であるDADmanは、最大64chの一括制御が可能、まさにちょうど収まった格好だ。
そして、MILの環境で決まったフォーマットを再生する際に、どのチャンネルをどのスピーカーで鳴らすのか?この設定を行うのがなかなか頭を悩ませる部分だ。Dolby Atmos、SONY 360Reality Audio、AURO 3D、22.2chなど様々なフォーマットの再生が考えられる。一段プロセッサーを挟んだとしても特定のフォーマットでの再生という部分は外せない要素だ。まずは、SONA中原氏とそれぞれのフォーマットごとにどのスピーカーを駆動するのが最適か?ということを話し合った。そこで決まったスピーカーの配置に対し、各フォーマットの基本となるチャンネルマップからの出力がルーティングされるようにモニターセットを構築していった。こうすることで、再生機側は各フォーマットの標準のアウトプットマッピングのまま出力すればよいということになる。
この仕組みを作ることでシグナルルーティング・マトリクスを一箇所に集中することに成功した。DADman上のボタンで、例えばDAW-Atmos、DAW-AURO、AVamp-Atmos、、、といった具合にソースをセレクトすることし、バックグラウンドで適切にシグナルルーティングが行われる仕掛けとしている。後で詳しく説明するが、再生系としてはDAWもしくは、AVampデコードアウト、SPAT Revolutionのプロセッサーアウトの3種類。それぞれから様々なフォーマットの出力がやってくる。これを一つづつ設定していった。そしてそれらのボタンをDAD MOMのハードボタンにアサインしている。
このようにしておくことでDADmanのソフトウェアの設定に不慣れな方でも、その存在を意識することなくソースセレクトのボタンを押してボリュームをひねれば適切なスピーカーから再生されるというシステムアップを実現している。なお、Avid MTRXはあえてスタンドアローンでの設置としている。もちろんPro ToolsのAudio I/OとしてDigiLinkケーブルで直結することも可能だが、様々なアプリケーションからの再生を行うことを前提としているため、MTRXはモニターコントローラーとしての機能にのみ集中させている。
市販コンテンツからマスター素材まで対応の再生系
📸 プロジェクターはJVC DLA-V90R。「8K、LASER、HDR」と現時点で考えうる最高スペックを持つフラッグシップモデル。EASTONのサウンドスクリーンと組み合わせて最高の音とともに映像にもこだわった。
次に再生側のシステムの説明に移ろう。市販のメディア、コンテンツの再生のためにPanasonic DMR-ZR1(Blu-ray Player)、Apple TVが用意されている。これらのHDMI出力はAV Amp YAMAHA CX-A5100に接続され、このアンプ内でデコードされプリアウトより7.1.4chで出力される。このAV Ampは近い将来STORM AUDIO ISP Elite MK3へと更新される予定だ。この更新が行われれば、更に多チャンネルでのデコードが可能となり、MILのさらなるクオリティーアップへとつながる。このSTORM AUDIOはAURO 3Dの総本山とも言えるベルギー、ギャラクシースタジオ、Auro Technologies社が立ち上げたAV機器ブランドであり、AURO 3Dの高い再現はもちろん、Dolby Atmos、DTS:X pro、IMAX Enhancedといった最新の各種フォーマットに対応している。更に24chものアナログアウトを備え、Dolby Atmosであれば最大11.1.6chという多チャンネルへのデコードを行うことができる強力なAV Ampである。本来は、各スピーカーの自動補正技術なども搭載されているが、MILでは、すでにSONAによりしっかりとスピーカーの調整が行われているのでこの機能は利用しない予定である。このAV Ampの系統では、Apple TVによる各種オンデマンドサービス(Netflix等)の視聴、Apple Musicで配信されている空間オーディオ作品の視聴、Blu-ray Discの視聴を行うこととなる。
📸 映像再生用のPlayerはPanasonic DMR-ZR1が奢られている。4K Ultra Blu-ray対応はもちろん、22.2chの受信(出力時はDolby Atmosに変換)機能などを持つ。
📸 AV ampとして導入を予定しているSTORM AUDIO ISP Elite mk3。Dolby Atmos、Auro 3Dといった市販のコンテンツの魅力を余すことなく引き出すモンスターマシンだ。
もう一つの再生システムがMac Proで構築されたPCからの再生だ。これは各マスターデータやAmbisonicsなどメディアでの提供がなされていない作品の視聴に使われる。現在スタンバイしているソフトウェアとしては、Avid Pro Tools、Virtual Sonics 360 WalkMix Creator™、SONY Architect、Dolby Atmos Renderer、REAPERといったソフトになる。ここは、必要に応じて今後も増強していく予定だ。
📸 Avid Pro Tools
📸 Dolby Atmos Renderer
📸 360 WalkMix Creator™
📸 SONY Architect
📸 REAPER
Dolby Atmos、ソニー 360 Reality Audioに関して言えば、エンコード前のピュアな状態でのマスター素材を再生可能であるということが大きなメリット。配信にせよ、Blu-ray Discにせよ、パッケージ化される際にこれらのイマーシブ・フォーマットは圧縮の工程(エンコード)が必要となる。つまり、Dolby Atmosでも360 Reality Audioでも、マスターデータは最大128chのWAVデータである。さすがにこれをそのままエンドユーザーに届けられない、ということは容易に想像いただけるだろう。Dolby Atmosであれば、Dolby Atmos Rendererの最大出力に迫る9.1.6chでのレンダリング、360 Reality AudioはMILのスピーカー全てを使った43chの出力が可能である(360 Reality AudioはLFEのチャンネルを持っていないため43chとなる)。特に360 Reality Audioの再生は他では体験ができない高密度でのフルオブジェクトデータのレンダリング出力となっている。オブジェクト方式のイマーシブフォーマットの持つ高い情報量を実感することができる貴重な場所である。
REAPERでは、MILの4π空間を最大限に活かす7th orderのAmbisonicsの再生ができる。7th Ambiの持つ4π空間の音情報を43chのスピーカーで再生するという、まさにMILならではの体験が可能だ。現状のセットアップでは、IEM AllRADecoderを使用してのチャンネルベースへのデコードを行っているが、他のソフトウェアとの聴き比べなども行うことができる。この部分もこれからの伸びしろを含んだ部分となる。各フォーマットのレンダリングアウト(チャンネルベース)を一旦7th Ambiに変換して43chに改めてデコードすると言った実験もREAPER上で実施することが可能だ。
それ以外に、Stereo音源の再生のためにiFI Audio Pro iDSDが導入されている。これは、DSD / DXD / MQA / PCM192kHzなど各種ハイレゾ素材の再生に対応したモデル。イマーシブ・サウンドだけではなくステレオ再生にも最高のクオリティーを追い求めたシステム導入が行われている。
スピーカーの仮想化、FLUX SPAT Revolution
📸 視聴空間としてではなく、ラボとして様々なフォーマットの変更を担うのがFLUX:: Spat Revolutionだ。OM FactoryでSPATの動作に最適にチューンされた、カスタムWindows PC上で動作をさせている。実際にMILで利用しているSpat Revolutionのスクリーンショットを掲載しているが、Dolby Atmosの入力をMILの43.2chにアサインしているのがこちらとなる。それ以外にも22.2ch、Auro 3DなどをMILのデフォルトとしてプリセットしている。
この2つの再生系統の他に、Core i9を搭載したパワフルなWindows PCがFLUX SPAT Revolution専用機として準備されている。これは、それぞれの再生機から出力されたレンダリングアウトに対し様々なプロセスを行うものとなる。具体例を挙げるとDolby Atmosであれば、理想位置から出力された際のシュミレーションを行ったりということになる。MILのTOPレイヤーは仰角34度であるため、Dolby Atmosの推奨設置位置である仰角45度とは11度ほど差異が出ている。これをSPAT上で仰角45位置へと仮想化するということである。水平面に関しても、実際に物理的なスピーカーが設置されていない水平角100度、135度という推奨位置へと仮想化することなる。
スピーカーの仮想化というと難しそうだが、シンプルに言い換えればパンニングを行うということになる。SPAT Revolutionでは、このパンニングの方法が選択できる。3Dのパンニングとして一般的であるVBAP=Vector-Based Amplitude Panningに始まり、DBAP=Distance-Based Amplitude Panning、LBAP=Layer-Based Amplitude Panning、SPCAP=Speaker-Placement Correction Amplitude PanningといったAmplitude Pan系のものと、KNN=K Nearest Neighbourが選択できる。これらは今後のバージョンアップで更に追加されていくと見込んでいるのだが、3Dパンニングのタイプを切り替えて聴き比べができるのもSPAT Revolutionならではの魅力だ。水平面であれば、シンプルなAmplitude Panで問題は無いが、3D空間に対しては、垂直方向のパンニング、立体空間に定位させるための係数の考え方の違い、など様々なファクター、計算をどのように行うのかというところに多様なメソッドが考えられており、SPAT Revolutionを用いればこれらの聴き比べができるということになる。更にMILでの実践はできないが、SPATにはオプションでWFS=Wave Field Synthesisも用意されている。
📸 SPATを動作させるOM Factory製カスタムWindows PC
SPAT Revolutionは一般的なChannel-Baseの音声だけではなく、Scene-Baseの音声の取り扱いも可能である。具体的には7th order Ambisonics、バイノーラル音声の扱いが可能ということになる。これらScene-Baseのオーディオデータはさすがに直接の取り扱いというわけではなく、一旦Channel-Baseにデコードした上でSPATの自由空間内で各種操作が行えるということになる。ここで挙げたような3D Audioのミキシングのための様々な考え方は知っておいて損のないことばかりである。今後技術解説としてまとめた記事を掲載したいところである。
映像系統に関しては、AV ampに一旦全てが集約されInputセレクターとしても活用している。選択されたソース信号は、プロジェクターVictor DLA-V90Rに接続される。このモデルは、8k60p信号の入力に対応したハイエンドモデルである。これが、120inchのEaston E8Rサウンドスクリーンに投影される。PCの操作画面はKVM MatrixとしてAdder DDX10で制御され、1画面を切り替えて操作が行えるようにシステムアップされている。
以上が、MILにて導入された各機器である。文章としてはボリュームがあるが、実際にはAV amp以外は全てDanteでの接続のため、あっけないほどシンプルである。一本のEthernet Cableで多チャンネルを扱える、信号の分配など自由自在なルーティングが組めるDanteの恩恵を存分に活用したシステムアップとなっている。各機器がまさに適材適所という形で接続された、まさに次の世代への対応まで整えたと言っていい内容でシステムアップが行われたMILスタジオ。4πの空間再現、音を「MIL」という思いを込め実験施設とは異なった、じっくりと、ゆっくりと音を体験できる場となっている。
【LINK】MIL STUDIOの設計・施工を手がけた株式会社ソナの中原 雅考氏による技術解説
技術解説:MIL STUDIO
*ProceedMagazine2022号より転載
https://pro.miroc.co.jp/headline/proceed-magazine-2022/#.YxG8QezP0-Q
https://pro.miroc.co.jp/headline/360ra-info-2022/#.YxG72ezP0-Q
https://pro.miroc.co.jp/solution/360-reality-audio-360-walkmix-creator-proceed2022/
https://pro.miroc.co.jp/headline/comparison-of-atmos-360ra/#.YxG8EuzP0-Q
Media
2022/08/22
IP映像伝送規格 NDI®︎ + SRTで実現する!〜高品質、低遅延、利便性、3拍子揃った映像伝送を考察〜
汎用のインターネットを通じて高品質な映像信号の送受信が行える規格が登場し、InterBEEをはじめとする昨今の放送機器展示会でも大きな注目を集めている。例えば、これまで弊誌でも紹介してきたNDIでは、昨夏にリリースされたNDI 5より新たにNDI Bridge機能が追加され、2拠点間をインターネット越しにNDI接続することが可能となった。今回新たにご紹介するのはSRT = Secure Reliable Transport と呼ばれるプロトコルだ。その名の通り、安全(Secure)で、信頼性がある(Reliable)、伝送(Transport)ができることをその特徴とする。本稿では、今後ますます普及が見込まれる2つの規格の特徴についてご紹介するとともに、今年3月に同テーマで開催されたウェビナーのレポートをお届けする。
同一ネットワーク内で即座に接続確立 利便性のNDI
まずはNDIの特徴をあらためて確認しておこう。NDIとは Network Device Interface(ネットワーク・デバイス・インターフェース)の略称で、その名の通り、ネットワークで接続されたデバイス間で映像や音声をはじめとする様々な信号を送受信可能とする通信規格の一種だ。2015年9月のIBC Showにて米国NewTek社により発表されて以降、1年〜2年のスパンで精力的にメジャーアップデートが行われており、2022年現在は昨年6月に発表されたNDI 5が最新版となっている。このバージョンより、待望されていたインターネットを超えてのNDI接続を可能とするNDI Bridge機能が実装され、その裾野は着実に広がりを見せている。
SMPTE ST-2110が非圧縮映像信号のリアルタイム伝送を目的として策定されたのに対し、NDIは圧縮信号の低遅延 ・高効率伝送を前提とし、利便性を重視したような設計となっているのが大きな特徴だ。具体的には、例えば1080i 59.94のHD信号であれば100Mbit毎秒まで圧縮して伝送することにより、一般的なLANケーブル(ギガビットイーサネットケーブル)でも複数ストリームの送受信ができるというメリットを実現している。当然ながら10Gbイーサネットケーブルを使用すれば、より多くのストリームの送受信も可能だ。
NDIには、大きく分けると2つのバージョンがあり、スタンダードな"NDI"(Full NDI、Full Bandwith NDIとも呼ばれる)と、より高圧縮なコーデックを用いる"NDI | HX"というものが存在する。前者のFull NDIではSpeedHQと呼ばれるMPEG-2と似たような圧縮方式を採用しており、ロスレスに近い高品質ながら1フレーム以下の超低遅延な伝送が可能なため、海外では既にスポーツ中継などの放送現場で活用が始まっている。このNDI向けのソフトウェア開発キット(SDK)はオンラインで公開されており、個人の開発者でもロイヤリティフリーで使用することができる。
一方、後者のNDI | HXは、MPEG-2の2倍の圧縮率をもつH.264や、さらにその2倍の圧縮率をもつH.265といった圧縮方式を採用し、無線LANなど比較的帯域が狭いネットワークで安定した伝送を行うのに向いている。対応のスマートフォンアプリなども数多くリリースされており、スマホカメラの映像やスクリーンキャプチャーをケーブルレスで他のデバイスに伝送できる点が非常に便利だ。こちらのNDI | HXの使用に関しては、現在有償のライセンスが必要となっている。ちなみに、この"HX"というのはHigh Efficiency (高効率)を意味するそうだ。
また、NDIの利便性向上に一役買っている機能として、デバイス間のコネクション確立時に使用されているBonjour(ボンジュール)という方式がある。これは、あるネットワーク内にデバイスが接続された際、自身のサービスやホスト名を同一ネットワーク内にマルチキャストすることで、特に複雑な設定を行わなくとも他のデバイスからの認識を可能とする、Apple社開発・提供のテクノロジーだ。同じくBonjourを採用しているDante対応製品に触れたことがある人はそのイメージがつくだろう。
通常のDNS = Domain Name System においては、例えばDNSサーバなどの、ドメイン名とIPアドレスを変換する仕組みを提供するサーバーが必要となるが、このBonjourにおいては、mDNS = multicast DNSという方式を用いることで、デバイス同士の通信のみでホスト名の解決を行うことが可能となる。仮に、映像スイッチャーソフト等から、ホスト名ではなくデバイスのIPアドレスしか見ることができなかったらどうなるだろうか。「192.168.〇〇.〇〇〜」という数字がずらっと羅列されていても、それがどのデバイスか瞬時に把握することは困難を極めるだろう。そうではなく、「yamadataro-no-macbook.local」「yamadataro-no-iphone.local」といったホスト名が表示されることにより、我々人間にとって分かりやすく、使い勝手の良いインターフェースが実現されている。
やや話が逸れてしまったが、簡潔にまとめるとNDIの魅力は気軽に伝送チャンネルを増やせる柔軟性と、ネットワークに繋げばすぐホスト名が見えてくるという扱いやすさにある。SDKがオープンになっていることにより、vMixやWirecast、OBSなどの配信ソフトや、Media ComposerやDaVinci Resolve、Final Cut Proといった映像編集ソフトでも採用され、数あるVoIP規格の中でもまさに筆頭格とも呼べる勢いで放送・配信・映像制作現場での普及が進んでいる。弊社LUSH HUBの配信システムでも、NewTek TriCasterを中心としたNDIネットワークを構築しているが、従来のSDIやHDMIケーブルと比べ、LANケーブルは長尺でも取り回しが容易である点や、スマホカメラの映像を無線LANでスイッチャーに入力できる点は非常に便利だと感じており、個人的にもNDI導入を積極的にアピールしたいポイントとなっている。
セキュアかつ高品質低遅延な映像伝送を低コストで実現 品質重視ならSRT
SRTもNDI同様のマルチメディア伝送プロトコルの一種で、2012年にカナダに本拠地を置くHaivision社によって開発、翌2013年のIBC Showで初めて一般向けのデモンストレーションが行われた。SRTはSecure Reliable Transport (セキュア・リライアブル・トランスポート)の略称で、その名の通り、より安全(Secure)で、信頼性がある(Reliable)、伝送(Transport)ができることをその特徴とする。それまで遠隔地へ安全に高画質な映像伝送を行うための手段としては、衛星通信やダークファイバー(専用回線)を用いた方法が一般的だったが、伝送コストが高額となることが課題だった。その課題を解決するため、「汎用のインターネット回線を使ってセキュアで高品質な映像伝送したい」というニーズのもとにSRTは誕生した。2017年よりGitHubにてオープンソース化、同時期にSRT Allianceがスタートし、現在ではMicrosoftやTelestream、AVIDを含む500社を超えるメーカーがその開発に参加している。
それではSRTの技術的特徴を具体的に見ていこう。まず安全性に関する技術については、AES(Advanced Encryption Standard)と呼ばれる、世界各国の政府機関などでも採用されている非常に強力な暗号化技術を採用している。SRTの場合AES-128、AES-256に対応しており、付随する数字は暗号化に用いる鍵の長さのbit数を意味している。一般的な暗号化技術において、この鍵長が長いほど第三者による暗号解読が困難になる。仮にAES-256を使用した場合、2の256乗、10進数にしておよそ77桁にも及ぶということを考えると、AES暗号化の突破がいかに困難なことか、その片鱗をご理解いただけるだろう。この強力な暗号化が、通信だけでなく、伝送しているコンテンツそのものに対しても適用されるため、万が一通信パケットを盗聴されたとしても、その中身までは決して解読されることはないだろう。
信頼性については、パケットロスに対するリカバリ機能を備えていることにより、不安定なネットワーク状況下でもほとんどコマ落ちすることのない高品質な映像伝送を実現している。一体なぜそのようなことが出来るのか?その秘密は、低遅延な通信方式であるUDP(User Datagram Protocol)と、データの誤りを制御するためのARQ(Automatic Repeat reQuest [またはQuery] )と呼ばれる機能を組み合わせるという工夫にある。この工夫についてより理解を深めるには、まずはTCP/IPモデルにおけるトランスポート層に位置するプロトコル、TCP(Transmission Control Protocol)とUDPの違いについて触れておく必要がある。
●TCP、UDPって何?
TCPはコネクション型と呼ばれるプロトコルで、データ受信後にACK(アック)という確認応答を送信元に返すことで通信の信頼性を保証する仕組みになっている。そのような確認応答を行なったり、データが届かなかった場合に再送処理を行なったりするため、通信経路の品質が低い場合には比較的大きな遅延が生じるというデメリットがあるが、電子メールなど確実性が重視される用途で主に使われている。ちなみに一昔前まで普及していたAdobe Flash Playerでは、このTCPをベースとしたRTMP(Real Time Messaging Protocol)と呼ばれる通信方式が採用されている。
対するUDPはコネクションレス型のプロトコルで、TCPのように確認応答を返さず、データの再送も行わないため通信効率の面ではこちらが有利だ。いわばデータを通信相手に送りっぱなしにするようなイメージになる。パケットヘッダのサイズを比較しても、TCPは20バイト使うのに対し、UDPは8バイトと小さいため、そもそも送受信する情報量が少ない。ただし、通信経路の品質が低い場合には遅延こそ少なかれ、伝送するコンテンツ自体の品質の劣化が避けられないという欠点がある。そうした理由で、例えばライブ配信やIP電話やなど、確実性よりもリアルタイム性が重視される用途で使われることが多い。
簡単に言うとSRTでは即時性に優れたUDPをベースとしながらも、信頼性に優れたTCPのようなデータの再送要求の仕組みを上位層のアプリケーション層で上手く取り入れている。それが前述したARQである。一般的に、こうしたメディア伝送においては、送り手側となるエンコーダーと受け手側となるデコーダーのそれぞれに多少のバッファーが設けてあり、受け手側はそのバッファー内でパケットの並べ替えなどの処理を行った後、デコーダーにパケットを転送している。
従来型のRTMPでは下りのトラフィック帯域の低下を防ぐため、パケットを受け取るたびにACKを送り返すのではなく、シーケンス、つまり一連のパケットのまとまり毎に応答確認を行う。もしそのシーケンス内でパケットロスが生じていた場合、再度そのシーケンス丸ごと再送が必要となり、その分のタイムロスが生じてしまう。一方、SRTでは受け手側でパケットロスが判明した時点で、その特定のパケットのみを即座に送り手側に再送要求することができる。これが高画質低遅延を実現するための重要なポイントだ。無事に再送されてきたパケットはバッファー内で適切に再配置された後にデコード処理されるため、オリジナルの品質に極めて近い綺麗な映像を受信できるという仕組みだ。ちなみにこのバッファーのサイズは数ミリ秒〜数十秒の範囲で設定できるようになっているため、通信状況に合わせて変更が可能だ。
また、RTMPとSRTのもう一つの大きな違いはパケットヘッダーにタイムスタンプを持てるかどうかである。RTMPでは個々のパケット毎にはタイムスタンプが押されていないため、受信した各パケットを一定の時間内にデコーダーに転送する必要がある。 その際、不安定になりがちなビットレートを安定化させるために、ある程度のバッファを設定する必要が生じる。一方SRTでは、個々のパケット毎に高精度なタイムスタンプが押されているため、受信側で本来の信号特性そのものを再現できるようになる。これにより、バッファリングに要する時間が劇的に短縮されるというメリットもある。
まとめると、SRTの魅力は、従来の衛星通信や専用回線での通信と同レベルの、安全性が高く、極めて高品質な映像伝送を比較的低コストで実現できる点にある。活用が考えられるケースとしては、例えばテレビ番組の生中継などで、「汎用のビデオ会議ツールなどでは満足のいく品質が得られない、かといって衛星通信や専用回線ほどの大掛かりなシステムを構築する予算はない」といった状況に最適なソリューションではないだろうか。
Webiner Report !!
〜2拠点間を実際にSRTで接続しながら生配信するという初の試み〜
今年3月初旬、ROCK ON PRO とアスク・エムイーの共催にてウェビナー『NDI & SRT を活用した映像伝送 〜SRTで2拠点間をつないでみよう!〜』が開催された。本ウェビナーでは、渋谷区にある弊社デモスペース「LUSH HUB」と千代田区のアスク・エムイーショールーム「エースタ」間を、オンライン会議ツールZOOMおよびAJA社の高性能マルチチャンネルビデオエンコーダー BRIDGELIVEを使ってSRT接続し、両拠点からそれぞれのYou Tubeチャンネルで生配信するという、おそらく国内ウェビナー史上初となる試みが行われた。ウェビナー内ではNDIとSRTの概要説明のほか、インターネット越しのNDI接続を可能とするNDI Bridge や、NDIネットワーク内で音声のみの伝送を可能とするNDI Audio Direct の動作も紹介。それぞれの規格がどのような場面での使用に適しているか、またそれらを組み合わせることで生まれる利点についてのプレゼンテーションが行われた。
ROCK ON PRO & アスク・エムイー共催
NDI & SRT を活用した映像伝送 〜SRTで2拠点間をつないでみよう!〜
配信日:3月2日 (水) 16時〜17時
株式会社アスク アスク・エムイー/テクニカルサポート 松尾 勝仁 氏
株式会社リーンフェイズ アスク・エムイー/マーケティングマネージャー 三好 寛季 氏
株式会社メディア・インテグレーション ROCK ON PRO / Product Specialist 前田 洋介
●エースタ側配信
https://youtu.be/NK8AN1UsCRo
●LUSH HUB側配信
https://youtu.be/PzibZ3wKPDQ
●System:当日の接続システム
NDI Bridge、SRT、ZOOMを活用し、3拠点間のコミュニケーション、2拠点から同時配信という内容となる今回のウェビナーについて、まず、ROCK ON PRO 前田洋介より接続システムについての解説が行われた。やや複雑だが図にすると次のような形となる。(下図 )まず、講師陣がいる場所は渋谷のLUSH HUB、千代田区半蔵門のエースタ、そして今回リモート出演となった前田洋介が訪れているRockoN梅田の3拠点となる。3拠点間のコミュニケーションおよび音声の入力には汎用のツールとして使い勝手が良いZOOMを採用。さらに、LUSH HUBとエースタの2拠点間においては、AJA BRIDGE LIVEによるSRT接続とNewTek NDI Bridge接続が並行して確立されており、相互にSRTで高品位な映像伝送を行つつ、相手方のTriCasterの操作も可能となっている。その上で、両拠点からYou Tube Liveへの最終の配信エンコーディングが行われている。
●Digest1:NDIのメリット
まずはアスク・エムイー三好氏より、NDIについての解説が行われた。NDIの最大の特徴は、対応するデバイスやソフトウェア間で、映像、音声、制御などの様々な信号をWi-Fi接続やネットワークケーブル一本で伝送できてしまう点だ。SDK(ソフトウェア開発キット)が無償公開されていることもあり、対応するソフトウェアスイッチャーやスマートフォン向けのカメラアプリなども様々登場している。
●Digest2:NDI Tools
オンラインで無償配布されているNDI Toolsには、NDI信号をWebカメラのソースとして使えるWebcam InputやTriCasterを遠隔操作できるNDI Studio Monitor、インターネット越しのNDI接続を可能とするNDI Bridgeなどが含まれている。WIndows版の方が開発が早かったり、Final CutなどMac版にのみ対応しているソフトウェアもあるため、Win版とMac版でラインナップが異なっている。
●Digest3:NDI5から新たに追加されたNDI Bridge
NDI5から新たに追加された目玉機能の一つがNDI Bridgeで、これによりインターネット越しにNDI接続を行うことが可能となった。現時点ではWin版のみの対応となるが、遠隔地のNDIソースを受信したり、TriCasterやPTZカメラをソフトウェアパネル上からリモートコントロールしたりすることができる。実際にウェビナー内でこのデモンストレーションを行なっているシーンを是非ご覧いただきたい。LUSH HUBにいる松尾氏のPCから、半蔵門エースタのNDIソースが一覧となって表示されている様子が確認できる。さらに、TriCasterの画面に進むと、画面左上にKVMのボタンがあり、これをクリックすることでそのままTriCasterの遠隔操作が可能になるという驚きの手軽さだ。コロナ禍以降、ライブ配信の需要が急速に高まっており、配信のオペレーター不足なども懸念されるが、こうした機能を活用していくことで解決できる課題は山ほどあるだろう。
●Digest4:SRTとはどのようなものか
続いて、SRTに関する説明だ。SRT = Secure Reliable Transportの略称で、Haivision社が開発した。不安定なネットワーク環境でも高品質なライブ映像を実現することを目標に、変動するネットワーク帯域幅を考慮し、映像の整合性や品質を維持するための様々な機能が備わっている。NDI同様オープンソース化されているが、こちらはソフトウェアだけでなくハードウェアへの組み込みもロイヤリティーフリーとなっている。
●Digest5:NDIとSRTを併用するメリット
ここでNDIとSRTの違い、併用するメリットについて話題が移る。NDIは元々、単一ネットワーク内での利便性向上を重視して作られ、後からインターネット越えが可能となった。一方、SRTは開発当初から遠隔地への安定した映像伝送を目標として開発されている。したがって、これらを比較対象として同列に並べるのはそもそも誤りで、むしろ、適材適所で併用することで相乗効果を発揮できる。つまり、NDIとSRTを併用することで「品質をとるか利便性をとるか?」というトレードオフを打破できるわけだ。
●Digest6:実際にNDIとSRTを組み合わせると
その一例がまさに、先に説明した本ウェビナーのシステムそのものだ。NDI Bridgeを活用してカメラやスイッチャー等のリモートコントロールを行いつつ、配信用の映像本線はSRTを使って高画質を実現することができる。(図9)また、その上でZoomなどのオンライン会議ツールを併用すれば、2拠点間のコミュニケーションはもちろん、その場に不在の参加者との連絡も容易だ。
●Digest7:気になる実際の画質を比べてみる
やはり誰もが気になるのが実際の画質についてだと思われるが、ウェビナー中盤からSRT経由の映像、NDI経由の映像、そしてZoom経由の映像を横並びにした配置をご確認いただけるようになっている。左がSRTで受信している映像、中央がNDIで構築したLAN内の映像、右がZoomで受信している映像だ。残念ながら同じカメラで撮影している訳ではないため厳密な比較とは言えないかもしれないが、SRT経由の映像は、ZOOMと比べ、ローカルのNDIとほとんど遜色ない高画質な映像となっているのが確認できる。
日進月歩で発展し続けるIP映像伝送テクノロジーの中でも、本稿では特に注目すべき2つの規格、NDIとSRTについてご紹介した。従来のSDIにとって代わり、とことん利便性を追求したNDIと、衛星通信や専用回線にとって代わり、汎用のインターネットでも高品質低遅延での映像伝送実現を目指したSRT。これらについて議論されるべきなのは、「どちらを使うか?」ではなく、「どのように組み合わせて活用していくか?」という点である。今回我々がみなさんにご提案させていただいたシステムはあくまでほんの一例で、こうしたIP伝送テクノロジーを適材適所に活用することで、世界中の放送・配信の現場それぞれに特有の問題を解決できるのではないかという大きな可能性を感じている。技術的ブレイクスルーによる恩恵、そして新技術を積極的に取り入れ、既存の技術とうまく組み合わせていくことで、これまでなかなか避けられなかったトレードオフも、今後次々と打破されていくことを期待したい。
*ProceedMagazine2022号より転載
Media
2022/07/14
Avid Media Composer ver.2022.7リリース情報
日本時間 2022年7月8日未明、Avid Media Composer バージョン2022.7がリリースされました。有効なサブスクリプション・ライセンスおよび年間プラン付永続ライセンス・ユーザーは、MyAvidよりダウンロードして使用することが可能です。
Avid Media Composer 2022.7は主に機能改善を目的としてリリースされたバージョンです。
修正されたバグについては、Avid Download Centerから入手可能です。
では、Media Composer 2022.7の新機能について見ていきましょう。
Media Composer 2022.7の新機能
1. グループまたはマルチグループのサブクリップに対するマッチフレームの改善
グループまたはマルチグループクリップのサブクリップからマッチフレームをすると、以前のバージョンでは、元のグループクリップまたはマルチグループクリップがロードされていましたが、このバージョンからはサブクリップがロードされるようになりました。
2. 複数のディスプレイ構成に対応するカスタムワークスペースの追加
使用するディスプレイ数が異なる場合でも、様々なワークスペースを作成し、保存することができます。つまりMedia Composerは接続している複数のディスプレイ数に基づいてウィンドウやツールの位置を記憶することができるようになりました。
現在のディスプレイ構成と一致しないワークスペースに切り替えると、」「New monitor configuration」ウィンドウで、「Your workspaces were set up for a different number of monitors. Now that the number of monitors has changed, would you like to duplicate workspaces for the new configuration?」と表示されます。
「Yes」をクリックすると、新しいモディスプレイ構成に一致する既存のワークスペースが複製されます。「No」を選択すると、モニタ設定に一致しない状態で、現在のワークスペースのままになります。この場合、ウィンドウが正しく見えなくなることもあります。
3. Adobe PremireとDaVinci Resolveの新しいキーボードマッピングオプション
Media Composerの最新バージョンには、Adobe PremireとDaVinci Resolveのキーボードマッピングがデフォルトの設定として追加されます。
新しいキーボード設定がUser設定で見えない場合には、設定ファイルのユーザー設定からユーザー設定の更新をしてください。
4. Titler+のアンカーポイントでのテキスト揃え
Titler +でテキストの位置揃えを変更すると、アンカーポイントの位置を基準にしてテキストレイヤーがシフトするようになりました。
たとえば、テキストの位置揃えを「左揃え」に設定すると、アンカーポイントはレイヤーの左に配置されます(境界ボックスで示されます)。 位置揃え(左、中央、右)を切り替えると、テキストはそれに応じてこの同じアンカーポイントを中心にシフトします。
5. タイムラインメニューに「セグメントツールにフィラーを選択」が追加
「セグメントツールでフィラーを選択」オプションは、通常、タイムライン設定ウィンドウからアクセスできましたが、タイムラインメニューからもアクセスできるようになり、キーボードショートカットとしてマッピングできるようになりました。
6. ネストされたクリップのタイムラインクリップノートの表示
一番上のクリップにタイムラインクリップノートが含まれていないが、その下にネストされたセグメントにノードが含まれている場合、そのノートは一番上のセグメントにも表示されます。
7. デザイン性を向上させた新しい On/Off アイコン
このリリースでは、プロパティのオンとオフを切り替えるために使用される「enabler」が、より一貫したサイズと新しい見た目になりました。これより、より使いやすいインターフェース、そしてオンとオフとが把握し易くなりました。
Media Composerのご購入のご相談、ご質問などはcontactボタンからお気軽にお問い合わせください。
Media
2021/11/02
Sound on 4π Part 4 / ソニーPCL株式会社 〜360 Reality Audioのリアルが究極のコンテンツ体験を生む〜
ソニーグループ内でポストプロダクション等の事業を行っているソニーPCL株式会社(以下、ソニーPCL)。360RAは音楽向けとしてリリースされたが、360RAを含むソニーの360立体音響技術群と呼ばれる要素技術の運用を行っている。昨年システムの更新を行ったMA室はすでに360RAにも対応し、360立体音響技術群のテクノロジーを活用した展示会映像に対する立体音響の制作、360RAでのプロモーションビデオのMA等をすでに行っている。
独自のアウトプットバスで構成されたMA室
ソニーPCLは映像・音響技術による制作ソリューションの提供を行っており、360立体音響技術群を活用した新しいコンテンツ体験の創出にも取り組んでいる。現時点では映像と音声が一緒になった360RAのアウトプット方法は確立されていないため、クライアントのイメージを具現化するための制作ワークフロー構築、イベント等でのアウトプットを踏まえた演出提案など、技術・クリエイティブの両面から制作に携わっている。
この更新されたMA室はDolby Atmosに準拠したスピーカー設置となっている。360RA以前にポストプロダクションとしてDolby Atmosへの対応検討が進んでおり、その後に360RAへの対応という順番でソリューションの導入を行っている。そのため、天井にはすでにスピーカーが設置されていたので、360RAの特徴でもあるボトムへのスピーカーの増設で360RA制作環境を整えた格好だ。360RAはフルオブジェクトのソリューションとなるため、スピーカーの設置位置に合わせてカスタムのアウトプットバスを組むことでどのようなスピーカー環境にも対応可能である。360RACSには最初から様々なパターンのスピーカーレイアウトファイルが準備されているので、たいていはそれらで対応可能である。とはいえスタジオごとのカスタム設定に関しても対応を検討中とのことだ。
📷デスクの前方にはスクリーンが張られており、L,C,Rのスピーカーはこのスクリーンの裏側に設置されている。スクリーンの足元にはボトムの3本のスピーカーが設置されているのがわかる。リスニングポイントに対して机と干渉しないギリギリの高さと角度での設置となっている。
📷できる限り等距離となるように、壁に寄せて設置ができるよう特注のスタンドを用意した。スピーカーは他の製品とのマッチを考え、Neumann KH120が選ばれている。
360RAの制作にあたり、最低これだけのスピーカーがあったほうが良いというガイドラインはある。具体的には、ITU準拠の5chのサラウンド配置のスピーカーが耳の高さにあたる中層と上空の上層にあり、フロントLCRの位置にボトムが3本という「5.0.5.3ch」が推奨されている。フル・オブジェクトということでサブウーファーchは用意されていない。必要であればベースマネージメントによりサブウーファーを活用ということになる。ソニーPCLではDolby Atmos対応の部屋を設計変更することなく、ボトムスピーカーの増設で360RAへと対応させている。厳密に言えば、推奨環境とは異なるが、カスタムのアウトプット・プロファイルを作ることでしっかりと対応している。
ソニーPCLのシステムをご紹介しておきたい。一昨年の改修でそれまでの5.1ch対応の環境から、9.1.4chのDolby Atmos対応のスタジオへとブラッシュアップされている。スピーカーはProcellaを使用。このスピーカーは、奥行きも少なく限られた空間に対して多くのスピーカーを増設する、という立体音響対応の改修に向いている。もちろんそのサウンドクオリティーも非常に高い。筐体の奥行きが短いため、天井への設置時の飛び出しも最低限となり空間を活かすことができる。この更新時では、既存の5.1chシステムに対しアウトプットが増えるということ、それに合わせスピーカープロセッサーに必要とされる処理能力が増えること、これらの要素を考えてAudio I/OにはAvid MTRX、スピーカープロセッサーにはYAMAHA MMP1という組み合わせとなっている。
📷天井のスピーカーはProcellaを使用。内装に極力手を加えずに設置工事が行われた。天井裏の懐が取れないためキャビネットの厚みの薄いこのモデルは飛び出しも最小限にきれいに収まっている。
4π空間を使い、究極のコンテンツ体験を作る
なぜ、ソニーPCLはこれらの新しいオーディオフォーマットに取り組んでいるのであろうか?そこには、歴史的にも最新の音響技術のパイオニアであり、THX認証(THXpm3)でクオリティーの担保された環境を持つトップレベルのスタジオであるということに加えて、顧客に対しても安心して作業をしてもらえる環境を整えていくということに意義を見出しているからだ。5.1chサラウンドに関しても早くから取り組みを始め、先輩方からの技術の系譜というものが脈々と続いている。常に最新の音響技術に対してのファーストランナーであるとともに、3D音響技術に関してもトップランナーで在り続ける。これこそがソニーPCLとしての業界におけるポジションであり、守るべきものであるとのお話をいただいた。エンジニアとしての技術スキルはもちろんだが、スタジオは、音響設計とそこに導入される機材、そのチューニングと様々な要素により成り立っている。THXは一つの指標ではあるが、このライセンスを受けているということは、自信を持ってこのスタジオで聴いた音に間違いはないと言える、大きなファクターでもある。
📷デスク上は作業に応じてレイアウトが変更できるようにアームで取り付けられた2つのPC Displayと、Avid Artist Mix、JL Cooper Surrond Pannerにキーボード、マウスと機材は最小限に留めている。
映像に関してのクオリティーはここで多くは語らないが、国内でもトップレベルのポストプロダクションである。その映像と最新の3D立体音響の組み合わせで、「究極のコンテンツ体験」とも言える作品を作ることができるスタジオになった。これはライブ、コンサート等にとどまらず、歴史的建造物、自然環境などの、空気感をあますことなく残すことができるという意味が含まれている。自然環境と同等の4πの空間を全て使い音の記録ができる、これは画期的だ。商用としてリリースされた初めての完全なる4πのフォーマットと映像の組み合わせ、ここには大きな未来を感じているということだ。
また、映像とのコラボレーションだけではなく、ソニー・ミュージックスタジオのエンジニアとの交流も360RAによりスタートしているということだ。これまでは、音楽スタジオとMAスタジオという関係で素材レベルのやり取りはあったものの、技術的な交流はあまりなかったということだが、360RAを通じて今まで以上のコミュニケーションが生まれているということだ。ソニーR&Dが要素を開発した360立体音響技術群、それを実際のフォーマットに落とし込んだソニーホームエンタテイメント&サウンドプロダクツなど、ソニーグループ内での協業が盛んとなり今までにない広がりを見せているということだ。このソニーグループ内の協業により、どのような新しい展開が生まれるのか?要素技術である360立体音響技術群の大きな可能性を感じる。すでに、展示会場やイベント、アミューズメントパークなど360RAとは異なる環境でこの技術の活用が始まってきている。フルオブジェクトには再生環境を選ばない柔軟性がある。これから登場する様々なコンテンツにも注目をしたいところだ。
現場が触れた360RAのもたらす「リアル」
360RAに最初に触れたときにまず感じたのは、その「リアル」さだったということだ。空間が目の前に広がり、平面のサラウンドでは到達できなかった本当のリアルな空間がそこに再現されていることに大きな驚きがあったという。ポストプロダクションとしては、リアルに空間再現ができるということは究極の目的の一つでもある。音楽に関しては、ステレオとの差異など様々な問題提議が行われ試行錯誤をしているが、映像作品にこれまでにない「リアル」な音響空間が加わるということは大きな意味を持つ。報道、スポーツ中継などでも「リアル」が加わることは重要な要素。当初は即時性とのトレードオフになる部分もあるかもしれない。立体音響でのスポーツ中継など想像しただけでも楽しみになる。
実際の使い勝手の詳細はまだこれからといった段階だが、定位をDAWで操作する感覚はDTS:Xに近いということだ。将来的にはDAWの標準パンナーで動かせるように統合型のインターフェースになってほしいというのが、現場目線で求める将来像だという。すでにDAWメーカー各社へのアプローチは行っているということなので、近い将来360RAネイティブ対応のDAWなども登場するのではないだろうか。
もともとサラウンドミックスを多数手がけられていたことから、サウンドデザイン視点での試行錯誤もお話しいただくことができた。リバーブを使って空間に響きを加える際にクアッド・リバーブを複数使用し立方体を作るような手法。移動を伴うパンニングの際に、オブジェクトの移動とアンプリチュード・パンを使い分ける手法など、360RAの特性を色々と研究しながら最適なミックスをする工夫を行っているということだ。
3Dと呼ばれる立体音響はまさに今黎明期であり、さまざまなテクノロジーが登場している途中の段階とも言える。それぞれのメリット、デメリットをしっかりと理解し、適材適所で活用するスキルがエンジニアに求められるようになってきている。まずは、試すことから始めそのテクノロジーを見極めていく必要があるということをお話いただいた。スペックだけではわからないのが音響の世界である。まずは、実際に触ってミックスをしてみて初めて分かる、気づくことも多くある。そして、立体音響が普及していけばそれに合わせた高品位な映像も必然的に必要となる。高品位な映像があるから必要とされる立体音響。その逆もまた然りということである。
📷上からAntelope Trinity、Avid SYNC HD,Avid MTRX、YAMAHA MMP1が収まる。このラックがこのスタジオのまさに心臓部である。
📷ポスプロとして従来のサラウンドフォーマットへの対応もしっかりと確保している。Dolby Model DP-564はまさにその証ともいえる一台。
📷このiPadでYAMAHA MMP1をコントロールしている。このシステムが多チャンネルのモニターコントロール、スピーカーマネージメントを引き受けている。
ソニーPCLでお話を伺った喜多氏に、これから立体音響、360RAへチャレンジする方へのコメントをいただいた。「まずは、想像力。立体空間を音で表現するためには想像力を膨らませてほしい。従来のステレオ、5.1chサラウンドのイメージに縛られがちなので、想像力によりそれを広げていってもらいたい。この情報過多の世界で具体例を見せられてばかりかもしれないが、そもそも音は見えないものだし、頭の中で全方向からやってくる音をしっかりとイメージして設計をすることで、立体音響ならではの新しい発見ができる。是非とも誰もが想像していなかった新しい体験を作り上げていってほしい」とのことだ。自身もソニーグループ内での協業により、シナジーに対しての高い期待と360RAの持つ大きな可能性を得て、これからの広がりが楽しみだということだ。これから生まれていく360RAを活用した映像作品は間違いなく我々に新しい体験を提供してくれるだろう。
ソニーPCL株式会社
技術部門・アドバンスドプロダクション2部
テクニカルプロダクション1課
サウンドスーパーバイザー 喜多真一 氏
*取材協力:ソニー株式会社
*ProceedMagazine2021号より転載
Media
2021/10/26
Sound on 4π Part 3 / 360 Reality Audio Creative Suite 〜新たなオーディオフォーマットで行う4π空間への定位〜
360 Reality Audio(以下、360RA)の制作ツールとして満を持してこの4月にリリースされた360 Reality Audio Creative Suite(以下、360RACS)。360RAの特徴でもあるフル・オブジェクト・ミキシングを行うツールとしてだけではなく、360RAでのモニター機能にまで及び、将来的には音圧調整機能も対応することを計画している。具体的な使用方法から、どのような機能を持ったソフトウェアなのかに至るまで、様々な切り口で360RACSをご紹介していこう。
>>Part 1 :360 Reality Audio 〜ついにスタート! ソニーが生み出した新たな時代への扉〜
>>Part 2 :ソニー・ミュージックスタジオ 〜360 Reality Audio Mixing、この空間を楽しむ〜
全周=4π空間内に音を配置
360RACSのワークフローはまとめるとこのようになる。プラグインであるということと、プラグインからモニタリング出力がなされるという特殊性。最終のエンコードまでが一つのツールに詰め込まれているというところをご確認いただきたい。
360RACSは、アメリカAudio Futures社がリリースするプラグインソフトである。執筆時点での対応プラグイン・フォーマットはAAX、VSTとなっている。対応フォーマットは今後随時追加されていくということなので、現時点で対応していないDAWをお使いの方も読み飛ばさずに待ってほしい。Audio Futures社は、音楽ソフトウェア開発を行うVirtual Sonic社の子会社であり、ソニーとの共同開発契約をもとに、ソニーから技術提供を受け360RACSを開発している。360RAコンテンツの制作ツールは、当初ソニーが研究、開発用として作ったソフトウェア「Architect」のみであった。しかしこの「Architect」は、制作用途に向いているとは言えなかったため、現場から様々なリクエストが集まっていたことを背景に、それらを汲み取り制作に向いたツールとして新たに開発されたのがこの360RACSということになる。
それでは具体的に360RACSを見ていきたい。冒頭にも書いたが360RACSはプラグインである。DAWの各トラックにインサートすることで動作する。DAWの各トラックにインサートすると、360RACS上にインサートされたトラックが追加されていく。ここまで準備ができれば、あとは360RACS内で全周=4π空間内にそれぞれの音を配置していくこととなる。これまで音像定位を変化させるために使ってきたパンニングという言葉は、水平方向の移動を指す言葉である。ちなみに、縦方向の定位の移動を指す言葉はチルトだ。立体音響においてのパンニングにあたる言葉は確立されておらず、空間に定位・配置させるという表現となってしまうことをご容赦願いたい。
360RACS内で音像を定位させるには、画面に表示された球体にある音像の定位位置を示すボール状のポイントをドラッグして任意の場所に持っていけば良い。後方からと、上空からという2つの視点で表示されたそれぞれを使うことで、簡単に任意の場所へと音像を定位させることができる。定位をさせた位置情報はAzimuth(水平方向を角度で表現)とElevation(垂直方向を角度で表現)の2つのパラメータが与えられる。もちろん、数値としてこれらを入力することも可能である。
📷360RACSに送り込まれた各オブジェクトは、Azimuth(アジマス)、Elavation、Gainの3つのパラメーターにより3D空間内の定位を決めていくこととなる。
360RAでは距離という概念は無い。これは現時点で定義されているMPEG-Hの規格にそのパラメータの運用が明確に定義されていないということだ。とはいえ、今後サウンドを加工することで距離感を演出できるツールやなども登場するかもしれない。もちろん音の強弱によっても遠近をコントロールすることはできるし、様々な工夫により擬似的に実現することは可能である。ただ、あくまでも360RAのフォーマット内で、という限定された説明としては距離のパラメーターは無く、360RAにおいては球体の表面に各ソースとなる音像を定位させることができるということである。この部分はネガティブに捉えないでほしい。工夫次第でいくらでも解決方法がある部分であり、これからノウハウ、テクニックなどが生まれる可能性が残された部分だからだ。シンプルな例を挙げると、360RACSで前後に同じ音を定位させ、そのボリューム差を変化させることで、360RAの空間内にファントム定位を作ることも可能だということである。
4π空間に定位した音は360RACSで出力
360RACSはそのままトラックにインサートするとプリフェーダーでインサートされるのでDAWのフェーダーは使えなくなる。もちろんパンも同様である。これはプラグインのインサートポイントがフェーダー、パンよりも前の段階にあるということに起因しているのだが、360RACS内に各トラックのフェーダーを用意することでこの部分の解決策としている。音像の定位情報とともに、ボリューム情報も各トラックのプラグインへオートメーションできる情報としてフィードバックされているため、ミキシング・オートメーションのデータは全てプラグインのオートメーションデータとしてDAWで記録されることとなる。
📷各トラックにプラグインをインサートし、360RACS内で空間定位を設定する。パンニング・オートメーションはプラグイン・オートメーションとしてDAWに記録されることとなる。
次は、このようにして4π空間に定位した音をどのようにモニタリングするのか?ということになる。360RACSはプラグインではあるが、Audio Interfaceを掴んでそこからアウトプットをすることができる。これは、DAWが掴んでいるAudio Outputは別のものになる。ここでヘッドホンであれば2chのアウトプットを持ったAudio Interfaceを選択すれば、そこから360RACSでレンダリングされたヘッドホン向けのバイノーラル出力が行われるということになる。スピーカーで聴きたい場合には、標準の13ch(5.0.5.3ch)を始め、それ以外にもITU 5.1chなどのアウトプットセットも用意されている。もちろん高さ方向の再現を求めるのであれば、水平面だけではなく上下にもスピーカーが必要となるのは言うまでもない。
📷360RACSの特徴であるプラグインからのオーディオ出力の設定画面。DAWから受け取った信号をそのままスピーカーへと出力することを実現している。
360RACSの機能面を見ていきたい。各DAWのトラックから送られてきたソースは360RACS内でグループを組むことができる。この機能により、ステレオのソースなどの使い勝手が向上している。全てを一つのグループにしてしまえば、空間全体が回転するといったギミックも簡単に作れるということだ。4π空間の表示も上空から見下ろしたTop View、後方から見たHorizontal View、立体的に表示をしたPerspective Viewと3種類が選択できる。これらをの表示を2つ組み合わせることでそれぞれの音像がどのように配置されているのかを確認することができる。それぞれの定位には、送られてきているトラック名が表示されON/OFFも可能、トラック数が多くなった際に文字だらけで見にくくなるということもない。
360RACS内に配置できるオブジェクトは最大128ch分で、各360RACS内のトラックにはMute/Soloも備えられる。360RACSでの作業の際には、DAWはソースとなる音源のプレイヤーという立ち位置になる。各音源は360RACSのプラグインの前段にEQ/Compなどをインサートすることで加工することができるし、編集なども今まで通りDAW上で行えるということになる。その後に、360RACS内で音像定位、ボリュームなどミキシングを行い、レンダリングされたアウトプットを聴くという流れだ。このレンダリングのプロセスにソニーのノウハウ、テクノロジーが詰まっている。詳細は別の機会とするが、360立体音響技術群と呼ばれる要素技術開発で積み重ねられてきた、知見やノウハウにより最適に立体空間に配置されたサウンドを出力している。
Level 1~3のMPEG-Hへエンコード
📷MPEG-Hのデータ作成はプラグインからのExportにより行う。この機能の実装により一つのプラグインで360RAの制作位の工程を包括したツールとなっている。
ミックスが終わった後は、360RAのファイルフォーマットであるMPEG-Hへエンコードするという処理が残っている。ここではLevel 1~3の3つのデータを作成することになり、Level 1が10 Object 64 0kbps、Level 2が16 Object 1Mbps、Level 3が 24 Object 1.5Mbpsのオーディオデータへと変換を行う。つまり、最大128chのオーディオを最小となるLevel 1の10trackまで畳み込む必要があるということだ。具体的には、同じ位置にある音源をグループ化してまとめていくという作業になる。せっかく立体空間に自由に配置したものを、まとめてしまうのはもったいないと感じるかもしれないが、限られた帯域でのストリーミングサービスを念頭とした場合には欠かせない処理だ。
とはいえ、バイノーラルプロセスにおいて人間が認知できる空間はそれほど微細ではないため、できる限り128chパラのままでの再現に近くなるように調整を行うこととなる。後方、下方など微細な定位の認知が難しい場所をまとめたり、動きのあるもの、無いものでの分類したり、そういったことを行いながらまとめることとなる。このエンコード作業も360RACS内でそのサウンドの変化を確認しながら行うことが可能である。同じ360RACSの中で作業を行うことができるため、ミックスに立ち返りながらの作業を手軽に行えるというのは大きなメリットである。このようなエンコードのプロセスを終えて書き出されたファイルが360RAのマスターということになる。MPEG-Hなのでファイルの拡張子は.MP4である。
執筆時点で、動作確認が行われているDAWはAvid Pro ToolsとAbleton Liveとなる。Pro Toolsに関しては、サラウンドバスを必要としないためUltimateでなくても作業が可能だということは特筆すべき点である。言い換えれば、トラック数の制約はあるがPro Tools Firstでも作業ができるということだ。全てが360RACS内で完結するため、ホストDAW側には特殊なバスを必要としない。これも360RACSの魅力の一つである。今後チューニングを進め、他DAWへの対応や他プラグインフォーマットへの展開も予定されている。音楽に、そして広義ではオーディオにとって久々の新フォーマットである360RAは制作への可能性を限りなく拡げそうだ。
*取材協力:ソニー株式会社
*ProceedMagazine2021号より転載
>>Part 2はこちらから
https://pro.miroc.co.jp/solution/sound-on-4%CF%80-360ra-part-2/
>>Part 1はこちらから
https://pro.miroc.co.jp/solution/sound-on-4%CF%80-360ra-part-1/
Media
2021/10/19
Sound on 4π Part 2 / ソニー・ミュージックスタジオ 〜360 Reality Audio Mixing、この空間を楽しむ〜
国内の正式ローンチに合わせ、多数の邦楽楽曲が360RAでミックスされた。その作業の中心となったのがソニー・ミュージックスタジオである。マスタリングルームのひとつを360RAのミキシングルームに改装し、2021年初頭より60曲あまりがミキシングされたという。そのソニー・ミュージックスタジオで行われた実際のミキシング作業についてお話を伺った。
>>Part 1:360 Reality Audio 〜ついにスタート! ソニーが生み出した新たな時代への扉〜
2ミックスの音楽性をどう定位していくか
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ ソニー・ミュージックスタジオ
レコーディング&マスタリングエンジニア 鈴木浩二 氏(右)
レコーディングエンジニア 米山雄大 氏(左)
2021年3月23日発のプレスリリースにあった楽曲のほとんどは、ここソニー・ミュージックスタジオでミキシングが行われている。360RAでリリースされた楽曲の選定は、各作品のプロデューサー、アーティストに360RAをプレゼン、実際に体験いただき360RAへの理解を深め、その可能性に賛同を得られた方から制作にあたったということだ。
実際に360RAでミキシングをしてみての率直な感想を伺った。ステレオに関しての経験は言うまでもなく、5.1chサラウンドでの音楽のミキシング作業の経験も豊富にある中でも、360RAのサウンドにはとにかく広大な空間を感じたという。5.1chサラウンドでの音楽制作時にもあった話だが、音楽として成立させるために音の定位はどこの位置までが許容範囲なのか?ということは360RAでも起こること。やはりボーカルなどのメロディーを担うパートが、前方に定位をしていないと違和感を感じてしまうし、平面での360度の表現から高さ方向の表現が加わったことで、5.1chから更に広大な空間に向き合うことになり正直戸惑いもあったということだ。その際は、もともとの2chのミックスを音楽性のリファレンスとし、その音楽性を保ったまま空間に拡張していくというイメージにしたという。
360RAは空間が広いため、定位による表現の自由度は圧倒的だ。白紙の状態から360RAの空間に音を配置して楽曲を成立させるには、やはり従来の2chミキシングで培った表現をベースに拡張させる、という手法を取らないとあまりにも迷いが多い。とはいえ、始まったばかりの立体音響でのミキシング、「正解はない」というのもひとつの答えである。さらなる試行錯誤の中から、新しいセオリー、リファレンスとなるような音像定位が生まれてくるのではないだろうか。もちろん従来のステレオで言われてきた、ピラミッド定位などというミキシングのセオリーをそのまま360RAで表現しても良い。その際に高さを表現するということは、ステレオ・ミキシングでは高度なエンジニアリング・スキルが要求されたが、360RAではオブジェクト・パンの定位を変えるだけ、この簡便さは魅力の一つだ。
試行錯誤の中から得られた経験としては、360RAの広大な空間を広く使いすぎてしまうと、細かな部分や気になる部分が目立ってしまうということ。実際に立体音響のミキシングで直面することだが、良くも悪くもステレオミキシングのようにそれぞれの音は混ざっていかない。言葉で言うのならば、ミキシング(Mixing)というよりもプレイシング(Placing)=配置をしていくという感覚に近い。
また、360RAだけではなく立体音響の大きな魅力ではあるが、クリアに一つ一つのサウンドが聴こえてくるために、ステレオミックスでは気にならなかった部分が気になってしまうということも起こり得る。逆に、アーティストにとってはこだわりを持って入れたサウンド一つ一つのニュアンスが、しっかりとしたセパレーションを持って再生されるためにミックスに埋もれるということがない。これは音楽を生み出す側としては大きな喜びにつながる。このサウンドのセパレーションに関しては、リスナーである我々が2chに収められたサウンドに慣れてしまっているだけかもしれない。これからは、この「混ざらない」という特徴を活かした作品も生まれてくるのではないだろうか。実際に音楽を生み出しているアーティストは2chでの仕上がりを前提に制作し、その2chの音楽性をリファレンスとして360RAのミキシングが行われている。当初より360RAを前提として制作された楽曲であれば、全く新しい世界が誕生するのかもしれない。
実例に即したお話も聞くことができた。ゴスペラーズ「風が聴こえる」を360RAでミキシングをした際に、立体的にサウンドを動かすことができるため、当初は色々と音に動きのあるミキシングを試してみたという。ところが、動かしすぎることにより同時に主題も移動してしまって音楽性が損なわれてしまったそうだ。その後のミックスでは、ステレオよりも広くそれぞれのメンバーを配置することで、ステレオとは異なるワイドなサウンドが表現しているという。360RAでミキシングをすることで、それぞれのメンバーの個々のニュアンスがしっかりとクリアに再生され、ステレオであれば聴こえなかった音がしっかりと届けられるという結果が得られ、好評であったということだ。まさに360RAでのミキシングならではのエピソードと言えるだろう。
📷元々がマスタリングルームあったことを偲ばせる巨大なステレオスピーカーの前に、L,C,R+ボトムL,C,Rの6本のスピーカーがスタンドに設置されている。全てMusik Electornic Gaithain m906が採用され、純正のスタンドを改造してボトムスピーカーが据え付けられている。天井には天吊で同じく906があるのがわかる。
高さ方向をミックスで活用するノウハウ
5.1chサラウンドから、上下方向への拡張がなされた360RA。以前から言われているように人間の聴覚は水平方向に対しての感度は高いが、上下方向に関しては低いという特徴を持っている。これは、物理的に耳が左右についているということに起因する。人間は水平方向の音を左右の耳に届く時間差で認識している、単純に右から来る音は右耳のほうが少しだけ早く聴こえるということだ。しかし、高さ方向に関してはそうはいかない。これは、こういう音はこちらから聴こえている「はず」という人の持つ経験で上下を認識しているためだ。よって、360RAでの上下方向のミキシングはセオリーに沿った音像配置を物理的に行う、ということに向いている。例えば、低音楽器を下に、高音楽器を上にといったことだ。これによりその特徴が強調された表現にもなる。もちろん、逆に配置して違和感を効果的に使うといった手法もあるだろう。また、ステレオMIXでボーカルを少し上から聴こえるようにした「おでこから聴こえる」などと言われるミックスバランスも、物理的にそれを配置することで実現が可能である。これにより、ボーカルの明瞭度を増して際立たせることもできるだろう。
音楽的なバランスを取るためにも、この上下方向をサウンドの明瞭度をつけるために活用するのは有効だ、という経験談もいただくことができた。水平面より少し上のほうが明瞭度が高く聴こえ、下に行けば行くほど明瞭度は落ちる。上方向も行き過ぎるとやはり明瞭度は落ちる。聴かせたいサウンドを配置する高さというのはこれまでにないファクターではあるが、360RAのミキシングのひとつのポイントになるのではないだろうか。また、サウンドとの距離に関しても上下で聴感上の変化があるということ。上方向に比べ、下方向のほうが音は近くに感じるということだ。このように360RAならではのノウハウなども、試行錯誤の中で蓄積が始まっていることが感じられる。
📷天井には、円形にバトンが設置され、そこにスピーカーが吊るされている。このようにすることでリスニングポイントに対して等距離となる工夫がなされている。
📷ボトムのスピーカー。ミドルレイヤーのスピーカーと等距離となるように前方へオフセットして据え付けられているのがわかる。
理解すべき広大な空間が持つ特性
そして、360RAに限らず立体音響全般に言えることなのだが、サウンド一つ一つがクリアになり明瞭度を持って聴こえるという特徴がある。また、トータルコンプの存在していない360RAの制作環境では、どうしてもステレオミックスと比較して迫力やパンチに欠けるサウンドになりやすい。トータルコンプに関しては、オブジェクトベース・オーディオ全てにおいて存在させることが難しい。なぜなら、オブジェクトの状態でエンドユーザーの手元にまで届けられ、最終のレンダリング・プロセスはユーザーが個々に所有する端末上で行われるためだ。また、バイノーラルという技術は、音色(周波数分布)や位相を変化させることで擬似的に上下定位や後方定位を作っている。そのためトータルコンプのような、従来のマスタリング・プロセッサーはそもそも使うことができない。
そして、比較対象とされるステレオ・ミックスはある意味でデフォルメ、加工が前提となっており、ステレオ空間という限られたスペースにノウハウを駆使してサウンドを詰め込んだものとも言える。広大でオープンな空間を持つ立体音響にパンチ感、迫力というものを求めること自体がナンセンスなのかもしれないが、これまでの音楽というものがステレオである以上、これらが比較されてしまうのはある意味致し方がないのかもしれない。360RAにおいても個々の音をオブジェクトとして配置する前にEQ/COMPなどで処理をすることはもちろん可能だ。パンチが欲しいサウンドはそのように聴こえるよう予め処理をしておくことで、かなり求められるニュアンスを出すことはできるということだ。
パンチ感、迫力といったお話をお伺いしていたところ、ステレオと360RAはあくまでも違ったもの、是非とも360RAならではの体験を楽しんでほしいというコメントをいただいた。まさにその通りである。マキシマイズされた迫力、刺激が必要であればステレオという器がすでに存在している。ステレオでは表現、体験のできない新しいものとして360RAを捉えるとその魅力も際立つのではないだろうか。ジャズなどのアコースティック楽器やボーカルがメインのものは不向きかもしれないが、ライブやコンサート音源など空間を表現することが得意な360RAでなければ再現できない世界もある。今後360RAでの完成を前提とした作品が登場すればその魅力は更に増すこととなるだろう。
360RAならではの魅力には、音像がクリアに分離して定位をするということと空間再現能力の高さがある。ライブ会場の観客のリアクションや歓声などといった空気感、これらをしっかりと収録しておくことでまさにその会場にいるかのようなサウンドで追体験できる。これこそ立体音響の持つイマーシブ感=没入感だと言えるだろう。すでに360RAとしてミキシングされたライブ音源は多数リリースされているので是非とも楽しんでみてほしい。きっとステレオでは再現しえない”空間”を感じていただけるであろう。屋根があるのか?壁はどのようになっているのか?といった会場独自のアコースティックから、残響を収録するマイクの設置位置により客席のどのあたりで聴いているようなサウンドにするのか?そういったことまで360RAであれば再現が可能である。
この空間表現という部分に関しては、今後登場するであろうディレイやリバーブに期待がかかる。本稿執筆時点では360RAネイティブ対応のこれら空間系のエフェクトは存在せず、今後のリリースを待つこととなる。もちろん従来のリバーブを使い、360RAの空間に配置することで残響を加えることは可能だが、もっと直感的に作業ができるツール、360RAの特徴に合わせたツールの登場に期待がかかる。
360RAにおけるマスタリング工程の立ち位置
かなり踏み込んだ内容にはなるが、360RAの制作において試行錯誤の中から答えが見つかっていないという部分も聞いた、マスタリングの工程だ。前述の通り、360RAのファイナルのデータはLevel 1~3(10ch~24ch)に畳み込まれたオブジェクト・オーディオである。実作業においては、Level 1~3に畳み込むエンコードを行うことが従来のマスタリングにあたるのだが、ステレオの作業のようにマスタリングエンジニアにミックスマスターを渡すということができない。このLevel 1~3に畳み込むという作業自体がミキシングの延長線上にあるためだ。
例えば、80chのマルチトラックデータを360RAでミキシングをする際には、作業の工程として80ch分のオブジェクト・オーディオを3D空間に配置することになり、これらをグループ化して10ch~24chへと畳み込んでいく。単独のオブジェクトとして畳み込むのか?オブジェクトを2つ使ってファントムとして定位させるのか、そういった工程である。これらの作業を行いつつ、同時に楽曲間のレベル差や音色などを整えるということは至難の業である。また、個々のオブジェクト・オーディオはオーバーレベルをしていなかったとしても、バイノーラルという2chに畳み込む中でオーバーレベルしてしまうということもある。こういった部分のQC=Quality Controlに関しては、まだまだ経験も知見も足りていない。
もちろん、そういったことを簡便にチェックできるツールも揃っていない。色々と工夫をしながら進めているが、現状ではミキシングをしたエンジニアがそのまま作業の流れで行うしかない状況になっているということだ。やはり、マスタリング・エンジニアという第3者により最終のトリートメントを行ってほしいという思いは残る。そうなると、マスタリングエンジニアがマルチトラックデータの取扱いに慣れる必要があるのか?それともミキシングエンジニアが、さらにマスタリングの分野にまで踏み込む必要があるのか?どちらにせよ今まで以上の幅広い技術が必要となることは間違いない。
個人のHRTFデータ取得も現実的な方法に
ヘッドホンでの再生が多くなるイメージがある360RAのミキシングだが、どうしてもバイノーラルとなると細かい部分の詰めまでが行えないため、実際の作業自体はやはりスピーカーがある環境のほうがやりやすいとのことだ。そうとはいえ、360RAに対応したファシリティーは1部屋となるため、ヘッドホンを使ってのミキシングも平行して行っているということだが、その際には360RAのスピーカーが用意されたこの部屋の特性と、耳にマイクを入れて測定をした個人個人のHRTFデータを使い、かなり高い再現性を持った環境でのヘッドホンミックスが行えているということだ。
個人のHRTFデータを組み込むという機能は、360RACSに実装されている。そのデータをどのようにして測定してもらい、ユーザーへ提供することができるようになるのかは、今後の課題である。プライベートHRTFがそれほど手間なく手に入り、それを使ってヘッドホンミックスが行えるようになるということが現実になれば、これは画期的な出来事である。これまで、HRTFの測定には椅子に座ったまま30分程度の計測時間が必要であったが、ソニーの独自技術により耳にマイクを入れて30秒程度で計測が完了するということを筆者も体験している。これが一般にも提供されるようになれば本当に画期的な出来事となる。
📷Pro Tools上に展開された360 Reality Audio Creative Suite(360RACS)
「まだミキシングに関しての正解は見つかっていない。360RACSの登場で手軽に制作に取り組めるようになったので、まずは好きに思うがままに作ってみてほしい。」これから360RAへチャレンジをする方へのコメントだ。360RAにおいても録音をするテクニック、個々のサウンドのトリートメント、サウンドメイクにはエンジニアの技術が必要である。そして、アーティストの持つ生み出す力、創造する力を形にするための360RAのノウハウ。それらが融合することで大きな化学反応が起こるのではないかということだ。試行錯誤は続くが、それ自体が新しい体験であり、非常に楽しんで作業をしているということがにじむ。360RAというフォーマットを楽しむ、これが新たな表現への第一歩となるのではないだろうか。
>>Part 3:360 Reality Audio Creative Suite 〜新たなオーディオフォーマットで行う4π空間への定位〜
*取材協力:ソニー株式会社
*ProceedMagazine2021号より転載
https://pro.miroc.co.jp/solution/sound-on-4%CF%80-360ra-part-3/
https://pro.miroc.co.jp/solution/sound-on-4%CF%80-360ra-part-1/
Media
2021/10/12
Sound on 4π Part 1 / 360 Reality Audio 〜ついにスタート! ソニーが生み出した新たな時代への扉〜
ついに2021年4月16日に正式リリースとなった 360 Reality Audio(以下、360RA)。読み方は”サンロクマル・リアリティー・オーディオ”となるこの最新のオーディオ体験。これまでにも色々とお伝えしてきているが、日本国内でのリリースと同時に、360RAの制作用のツールとなる360 Reality Audio Creative Suiteもリリースされている。360RAとは一体何なのか?どのようにして作ればよいのか?まずは、そのオーバービューからご紹介していこう。
ソニーが作り出してきたオーディオの時代
まず最初に、ソニーとAudioの関係性を語らないわけにはいかない。コンシューマ・オーディオの分野では、常にエポックメイキングな製品を市場にリリースしてきている。その代表がウォークマン®であろう。今では当たり前となっている音楽を持ち歩くということを世界で初めて実現した電池駆動のポータブル・カセットテープ・プレイヤーである。10代、20代の読者は馴染みが薄いかもしれないが、据え置きの巨大なオーディオコンポや、ラジオとカセットプレイヤーを一体にしたラジカセが主流だった時代に、電池で動作してヘッドホンでどこでも好きな場所で音楽を楽しむことができるウォークマン®はまさにエポックな製品であり、音楽の聴き方を変えたという意味では、時代を作った製品であった。みんなでスピーカーから出てくる音楽を楽しむというスタイルから、個人が好きな音楽をプライベートで楽しむという変化を起こしたわけだ。これは音楽を聴くという体験に変化をもたらしたとも言えるだろう。
ほかにもソニーは、映画の音声がサラウンドになる際に大きなスクリーンの後ろで通常では3本(L,C,R)となるスピーカーを5本(L,LC,C,RC,R)とする、SDDS=Sony Dynamic Digital Soundというフォーマットを独自で提唱したり、ハイレゾという言葉が一般化する以前よりPCMデジタルデータでは再現できない音を再生するために、DSDを採用したスーパーオーディオCD(SACD)を作ったり、と様々な取り組みを行っている。
そして、プロフェッショナル・オーディオ(音響制作機器)の市場である。1980年代よりマルチチャンネル・デジタルレコーダーPCM-3324/3348シリーズ、Oxford R3コンソール、CDのマスタリングに必須のPCM-1630など、音声、特に音楽制作の中心にはソニー製品があった。いまではヘッドホン、マイクは例外に、プロシューマー・マーケットでソニー製品を見ることが少なくなってしまっているが、その要素技術の研究開発は続けられており、コンシューマー製品へしっかりとフィードバックが行われているのである。「制作=作るため」の製品から「利用する=再生する」製品まで、つまりその技術の入口から出口までの製品を揃えていたソニーのあり方というのは、形を変えながらも続いているのである。
PCM-3348
PCM-3348HR
Oxford R3
PCM-1630
このようなソニーとAudioの歴史から見えてくるキーワードは、ユーザーへの「新しい体験の提供」ということである。CDではノイズのないパッケージを提供し、ウォークマン®ではプライベートで「どこでも」音楽を楽しむという体験を、SDDSは映画館で最高の臨場感を作り出し、SACDはまさしく最高となる音質を提供した。全てが、ユーザーに対して新しい体験を提供するという一つの幹から生えているということがわかる。新しい体験を提供するための技術を、難解なテクノロジーの状態からスタイリッシュな体験に仕立てて提供する。これがまさにソニーのAudio、実際はそれだけではなく映像や音声機器にも共通するポリシーのように感じる。
全周(4π)を再現する360RA
ソニーでは要素技術として高臨場感音響に関しての研究が続けられていた。バーチャル・サラウンド・ヘッドホンや、立体音響を再生できるサラウンドバーなどがこれまでにもリリースされているが、それとはまた別の技術となる全周(4π)を再現するオーディオ技術の研究だ。そして、FraunhoferがMPEG-H Audioを提唱した際にこの技術をもって参画したことで、コンテンツとなるデータがその入れ物(コンテナ)を手に入れて一気に具体化、2019年のCESでの発表につながっている。CES2019の時点ではあくまでも技術展示ということだったが、その年の10月には早くもローンチイベントを行い欧米でのサービスをスタートさせている。日本国内でも各展示会で紹介された360RAは、メディアにも取り上げられその存在を知った方も多いのではないだろうか。特に2020年のCESでは、ソニーのブースでEVコンセプトの自動車となるVISION-Sが展示され大きな話題を呼んだが、この車のオーディオとしても360RAが搭載されている。VISION-Sではシートごとにスピーカーが埋め込まれ立体音響が再生される仕様となっていた、この立体音響というのが360RAをソースとしたものである。
360RAはユーザーに対して「新しい体験」を提供できる。機器自体は従来のスマホや、ヘッドホン、イヤホンであるがそこで聴くことができるサウンドは、まさにイマーシブ(没入)なもの。もちろんバイノーラル技術を使っての再生となるが、ソニーのノウハウが詰まった独自のものであるということだ。また、単純なバイノーラルで収録された音源よりも、ミキシングなど後処理が加えられることで更に多くの表現を手に入れたものとなっている。特にライブ音源の再生においては非常に高い効果を発揮し、最も向いたソースであるという認識を持った。
バイノーラルの再生には、HRTF=頭部伝達関数と呼ばれる数値に基づいたエンコードが行われ、擬似的に左右のヘッドホン or イヤホンで立体的音響を再生する。このHRTFは頭の形、耳の形、耳の穴の形状など様々な要素により決まる個人ごとに差異があるもの。以前にも紹介したYAMAHAのViRealはこのHRTFを一般化しようという研究であったが、ソニーでは「Sony | Headphones Connect」と称されたスマートフォン用アプリで、個々に向けたHRTFを提供している。これは耳の写真をアップロードすることでビッグデータと照合し最適なパラメーターを設定、ヘッドホンフォン再生に適用することで360RAの体験を確実にし、ソニーが配信サービスに技術提供している。
Sony | Headphones Connectは一部のソニー製ヘッドホン用アプリとなるが、汎用のHRTFではなく個人に合わせて最適化されたHRTFで聴くバイノーラルは圧倒的である。ぼんやりとしか認識できなかった音の定位がはっきりし、後方や上下といった認識の難しい定位をしっかりと認識することができる。もちろん、個人差の出てしまう技術であるため一概に言うことはできないが、それでも汎用のHRTFと比較すれば、360RAでの体験をより豊かなものとする非常に有効な手法であると言える。この手法を360RAの体験向上、そしてソニーのビジネスモデルとして技術と製品を結びつけるものとして提供している。体験を最大化するための仕掛けをしっかりと配信サービスに提供するあたり、さすがソニーといったところだ。
360RAはいますぐ体験できる
それでは、360RAが国内でリリースされ、実際にどのようにして聴くことができるようになったのだろうか?まず、ご紹介したいのがAmazon music HDとDeezerの2社だ。両社とも月額課金のサブスクリプション(月額聴き放題形式)のサービスである。ハイレゾ音源の聴き放題の延長線上に、立体音響音源の聴き放題サービスがあるとイメージしていただければいいだろう。視聴方法はこれらの配信サービスと契約し、Amazon music HDであればAmazon Echo Studioという立体音響再生に対応した専用のスピーカーでの再生となる。物理的なスピーカーでの再生はどうしても上下方向の再生が必要となるため特殊な製品が必要だが、前述のAmazon Echo Studioやサラウンドバーのほか、ソニーからも360RA再生に対応した製品としてSRS-RA5000、SRS-RA3000という製品が国内でのサービス開始とともに登場している。
また、Deezerではスマートフォンとヘッドホン、イヤホンでの再生、もしくは360RA再生に対応したBluetoothスピーカーがあれば夏にはスピーカーで360RAを楽しむことができる。スマートフォンは、ソニーのXperiaでなければならないということはない。Android搭載のデバイスでも、iOS搭載のデバイスでも楽しむことができる、端末を選ばないというのは実に魅力的だ。ヘッドホン、イヤホンも普通のステレオ再生ができるもので十分で、どのような製品でも360RAを聴くことができる。Sony | Headphones Connectの対象機種ではない場合はパーソナライズの恩恵は受けられないが、その際にはソニーが準備した汎用のHRTFが用いられることとなる。導入にあたり追加で必要となる特殊な機器もないため、興味を持った方はまずはDeezerで360RAのサウンドを楽しむのが近道だろうか。余談ではあるが、Deezerはハイレゾ音源も聴き放題となるサービス。FLAC圧縮によるハイサンプルの音源も多数あるため、360RAをお試しいただくとともにこちらも併せて聴いてみると、立体音響とはまた違った良さを発見できるはずだ。
そして、前述の2社に加えてnugs.netでも360 Reality Audioの楽曲が配信開始されている。360RAを体験していただければわかるが、立体音響のサウンドはまさに会場にいるかのような没入感を得ることができ、ライブやコンサートなどの臨場感を伝えるのに非常に適している。nugs.net はそのライブ、コンサートのストリーミングをメインのコンテンツとして扱う配信サービスであり、このメリットを最大限に活かしたストリーミングサービスになっていると言えるだろう。
欧米でサービスが展開されているTIDALも月額サブスクリプションのサービスとなり、すでに360RAの配信をスタートしている。サービスの内容はDeezerとほぼ同等だが、ハイレゾの配信方針がDeezerはFLAC、TIDALはMQAと異なるのが興味深い。この音質の差異は是非とも検証してみたいポイントである。TIDALはラッパーのJAY-Zがオーナーのサービスということで、Hip-Hop/R&Bなどポップスに強いという魅力もある。ハイレゾ音源は配信サービスで月額課金で楽しむ時代になってきている。前号でも記事として取り上げたが、ハイレゾでのクオリティーの高いステレオ音源や360RAなどの立体音響、これらの音源を楽しむということは、すでにSpotifyやApple Musicといった馴染みのある配信サービスの延長線上にある。思い立てばいますぐにでも360RAを楽しむことができる環境がすでに整っているということだ。
360RAを収めるMPEG-Hという器
360RAを語るにあたり、技術的な側面としてMPEG-Hに触れないわけにはいかない。MPEG-H自体はモノラルでも、ステレオでも、5.1chサラウンドも、アンビソニックスも、オブジェクトオーディオも、自由に収めることが可能、非常に汎用性の高いデジタルコンテンツを収める入れ物である。このMPEG-Hを360RAではオブジェクトオーディオを収める器として採用しているわけだ。実際の360RAには3つのレベルがあり、最も上位のLevel3は24オブジェクトで1.5Mbpsの帯域を使用、Level2は16オブジェクトで1Mbps、Leve1は10オブジェクトで640kbpsとなっている。このレベルとオブジェクト数に関しては、実際の制作ツールとなる360RA Creative Suiteの解説で詳しく紹介したい。
Pro Tools上に展開された360 Reality Audio Creative Suite(360RACS)
ここでは、その帯域の話よりもMPEG-Hだから実現できた高圧縮かつ高音質という部分にフォーカスを当てていく。月額サブスクリプションでの音楽配信サービスは、現状SpotifyとApple Musicの2強であると言える。両社とも圧縮された音楽をストリーミングで再生するサービスだ。Apple Musicで使われているのはAAC 256kbpsのステレオ音声であり、1chあたりで見れば128kbpsということになる。360RAのチャンネルあたりの帯域を見るとLevel1で64kbps/chとAACやMP3で配信されているサービスよりも高圧縮である。しかし、MPEG-Hは最新の圧縮技術を使用しているため、従来比2倍以上の圧縮効率の確保が可能というのが一般的な認識である。その2倍を照らし合わせればチャンネルあたりの帯域が半分になっても従来と同等、もしくはそれ以上の音質が確保されているということになる。逆に言えば、従来のAAC、MP3という圧縮技術では同等の音質を確保するために倍の帯域が必要となってしまう。これがMPEG-H Audioを採用した1点目の理由だ。
もう一つ挙げたいのはオブジェクトへの対応。360RAのミキシングは全てのソースがオブジェクトとしてミキシングされる。オブジェクトとしてミキシングされたソースを収める器として、オブジェクトの位置情報にあたるメタデータを格納することができるMPEG-Hは都合が良かったということになる。特殊な独自のフォーマットを策定することなく、一般化された規格に360RAのサウンドが収めることができたわけだ。ちなみにMPEG-Hのファイル拡張子は.mp4である。余談にはなるが、MPEG-Hは様々な最新のフォーマットを取り込んでいる。代表的なものが、HEVC=High Efficiency Video Coding、H.265という高圧縮の映像ファイルコーディック、静止画ではHEIF=High Efficiency Image File Format。HEIFはHDR情報を含む画像ファイルで、iPhoneで写真を撮影した際の画像ファイルで見かけた方も多いかもしれない。このようにMPEG-Hは3D Audio向けの規格だけではなく、様々な可能性を含みながら進化を続けているフォーマットである。
拡がりをみせる360RAの将来像
360RAの今後の展開も伺うことができた。まず1つは、配信サービスを提供する会社を増やすという活動、360RAに対応したスピーカーやAVアンプなどの機器を増やすという活動、このような活動から360RAの認知も拡大して、制作も活発化するという好循環を作り健全に保つことが重要とのこと。すでに世界中の配信事業者とのコンタクトは始まっており、制作に関しても欧米でのサービス開始から1年半で4000曲とかなりのハイペースでリリースが続いている。ほかにも、ライブやコンサートとの親和性が高いということから、リアルタイムでのストリーミングに対しても対応をしたいという考えがあるとのこと。これはユーザーとしても非常に楽しみなソリューションである。また、音楽ということにこだわらずに、オーディオ・ドラマなど、まずはオーディオ・オンリーでも楽しめるところから拡張を進めていくということだ。また、360RAの要素技術自体はSound ARなど様々な分野での活用が始まっている。
日本国内では、まさに産声を上げたところである360RA。ソニーの提案する新しい音楽の「体験」。立体音響での音楽視聴はこれまでにない体験をもたらすことは間違いない。そして改めてお伝えしたいのは、そのような技術がすでに現実に生まれていて、いますぐにでも簡単に体験できるということ。ソニーが生み出した新たな時代への扉を皆さんも是非開いてほしい。
>>Part 2:ソニー・ミュージックスタジオ 〜360 Reality Audio Mixing、この空間を楽しむ〜
*取材協力:ソニー株式会社
*ProceedMagazine2021号より転載
https://pro.miroc.co.jp/solution/sound-on-4%CF%80-360ra-part-2/
Media
2021/07/28
IPビデオ伝送の筆頭格、NDIを知る。〜ソフトウェアベースでハンドリングする先進のIP伝送〜
弊社刊行のProceedMagazineでは以前より音声信号、映像信号のIP化を取り上げてきた。新たな規格が登場するたびにそれらの特徴をご紹介してきているが、今回はNewtek社によって開発された、現在世界で最も利用されているIPビデオ伝送方式のひとつであるNDIを取り上げその特徴をじっくりと見ていきたい。IPビデオ伝送ということは、汎用のEthernetを通じVideo/Audio信号を伝送するためのソリューション、ということである。いま現場に必要とされる先進的な要素を多く持つNDI、その全貌に迫る。
一歩先を行くIPビデオ伝送方式
NDI=Network Device Interface。SDI/HDMIとの親和性が高く、映像配信システムなどの構築に向いている利便性の高い規格である。このIP伝送方式は、NewTek社により2015年9月にアムステルダムで開催された国際展示会IBCで発表された。そして、その特徴としてまず挙げられるのがソフトウェアベースであるということであり、マーケティング的にも無償で使用できるロイヤリティー・フリーのSDKが配付されている。ソフトウェアベースであるということは、特定のハードウェアを必要とせず汎用のEthernet機器が活用可能であるということである。これは機器の設計製造などでも有利に働き、特別にカスタム設計した機器でなくとも、汎用製品を組み合わせて活用することで製品コストを抑えられることにつながっている。この特徴を体現した製品はソフトウェアとしていくつもリリースされている。詳しい紹介は後述するが、汎用のPCがプロフェッショナルグレードの映像機器として活用できるようになる、と捉えていただいても良い。
フルHD映像信号をを100Mbit/s程度にまで圧縮を行い、汎用のEthernetで伝送を行うNDIはIBC2015でも非常に高い注目を集め、NewTekのブースには来場者が入りきれないほどであったのを覚えている。以前、ProceedMagazineでも大々的に取り上げたSMPTE ST2110が基礎の部分となるTR-03、TR-04の発表よりも約2ヶ月早いタイミングで、NDIは完成形とも言える圧縮伝送を実現した規格として登場したわけだ。非圧縮でのSDI信号の置換えを目指した規格であるSMPTE ST-2022が注目を集めていた時期に、圧縮での低遅延リアルタイム伝送を実現し、ロイヤリティーフリーで特定のハードウェアを必要とせずにソフトウェアベースで動作するNDIはこの時すでに一歩先を行くテクノロジーであったということが言える。そして、本記事を執筆している時点でNDIはバージョン4.6.2となっている。この更新の中では、さらに圧縮率の高いNDI HX、NDI HX2などを登場させその先進性に磨きがかけられた。
📷これまでにもご紹介してきた放送業界が中心となり進めているSMPTE 2022 / 2110との比較をまとめてみた。大規模なインフラにも対応できるように工夫の凝らされたSMPTE規格に対し、イントラネットでのコンパクトな運用を目指したNDIという特徴が見てとれる。NDIは使い勝手を重視した進化をしていることがこちらの表からも浮かんでくるのではないだろうか。
100Mbit/s、利便性とクオリティ
NDIの詳細部分に踏み込んで見ていこう。テクノロジーとしての特徴は、前述の通り圧縮伝送であるということがまず大きい。映像のクオリティにこだわれば、もちろん非圧縮がベストであることに異論はないが、Full HD/30pで1.5Gbit/sにもなる映像信号を汎用のEhternetで伝送しようと考えた際に、伝送路の帯域が不足してくるということは直感的にご理解いただけるのではないだろうか。シンプルに言い換えれば一般的に普及しているGigabit Ethernetでは非圧縮のFull HD信号の1Streamすら送れないということである。利便性という目線で考えても、普及価格帯になっているGigabit Ethernetを活用できず10GbEthernetが必須になってしまっては、IPビデオ伝送の持つ手軽さや利便性に足かせがついてしまう。
NDIは当初より圧縮信号を前提としており、標準では100Mbit/sまで圧縮した信号を伝送する。圧縮することでGigabitEthernetでの複数Streamの伝送、さらにはワイヤレス(Wi-Fi)の伝送などにも対応している。4K伝送時も同様に圧縮がかかり、こちらもGigabit Ethernetでの伝送が可能である。もちろん10GbEthernetを利用すれば、さらに多くのStreamの伝送が可能となる。放送業界で標準的に使用されているSONY XDCAMの圧縮率が50Mbit/sであることを考えれば、十分にクオリティが担保された映像であることはご想像いただけるだろう。さらにNDI HXでは20Mbit/sまでの圧縮を行いワイヤレス機器などとの親和性を高め、最新の規格となるNDI HX2ではH.265圧縮を活用し、NDIと同様の使い勝手で半分の50Mbit./sでの運用を実現している。
Ethernet Cable 1本でセットできる
代表的なNDI製品であるPTZカメラ。
次の特徴は、Ethernet技術の持つ「双方向性」を非常にうまく使っているということだ。映像信号はもちろん一方向の伝送ではあるが、逆方向の伝送路をタリー信号やPTZカメラのコントロール、各機器の設定変更などに活用している。これらの制御信号は、SMPTE ST2022/ST2110では共通項目として規格化が行われていない部分だ。
NDIではこれらの制御信号も規格化され、メーカーをまたいだ共通化が進められている。わかりやすい部分としてはPTZカメラのコントロールであろう。すでにNDI対応のPTZカメラはPoE=Power over Ethernet対応の製品であれば、Ethernet Cable1本の接続で映像信号の伝送から、カメラコントロール、電源供給までが行えるということになる。従来の製品では3本、もしくはそれ以上のケーブルの接続が必要なシーンでも1本のケーブルで済んでしまうということは大きなメリットだ。天井などに設置をすることが多いPTZカメラ。固定設備としての設置工事時にもこれは大きな魅力となるだろう。NDIに対応した製品であれば、基本的にNDIとして接続されたEthernetケーブルを通じて設定変更などが行える。別途USBケーブル等を接続してPCから設定を流し込む、などといった作業から解放されることになる。
📷左がリモートコントローラーとなる。写真のBirdDog P200であれば、PoE対応なので映像信号、電源供給、コントロール信号が1本のEthernet Cableで済む。
帯域を最大限に有効活用する仕組み
NDIの先進性を物語る特徴はまだある。こちらはあまり目に見える部分ではないが、帯域保護をする機能がNDIには搭載されている。これは前述のタリー信号をカメラ側へ伝送できる機能をさらに活用している部分だ。実際にスイッチャーで選択されていない(双方向で接続は確立されているが、最終の出力としては利用されていない)信号は、データの圧縮率が高められたプロキシ伝送となる。本線として利用されていない(タリーの戻ってきていない)カメラは、自動的にプロキシ伝送に切り替わり帯域の圧縮を防ぐということになる。これは本線で使用されていたとしても、PinP=Picture in Picture の副画像などの場合でも同様だ。画面の1/4以上で利用されている場合にはフルクオリティの出力で、1/4以下であればプロキシへと自動的に切り替わる。双方向に情報を伝達できるNDIはスイッチャーが必要とする時にカメラ側へフルクオリティー画像の伝送をリクエストして切り替える、この機能を利用しているわけだ。数多くのカメラを同一のネットワーク上に接続した場合にはその帯域が不安になることも多いが、NDIであればネットワークの持つ帯域を最大限に有効活用する仕組みが組み込まれている。
信号伝送の帯域に関しての特徴はほかにもあり、MulticastとUnicastの切り替えが可能というのもNDIの特徴だ。接続が確立された機器同士でのUnicast伝送を行うというのがNDIの基本的な考え方だが、スイッチャーから配信機材やレコーダーといった複数に対して信号が送られる場合にはMulticastへと手動で切り替えが可能となっている。もちろん、全ての信号伝送をMulticastできちんと設定してしまえば、特に考えることもなく全ての機器で信号を受け取ることができるが、実際のシステム上では設定も簡易なUnicastで十分な接続がほとんどである。イントラネットを前提とするNDIのシステム規模感であれば、Unicast/Multicast両対応というのは理にかなっている。AoIPであるDanteも同じく基本はUnicastで、必要に応じてMulticastへと変更できるということからも、イントラであればこの考え方が正しいということがわかる。
また、IP機器ということで設定に専門的な知識が必要になるのではと思われるかもしれない。NDIは相互の認識にBonjour(mDNS)を使っている、これはDanteと同様である。同一のネットワーク上に存在している機器であれば自動的に見つけてきてくれるという認識性の高さは、Danteを使ったことのある方であれば体験済みだろう。もちろん、トラブルシュートのために最低限のIPの知識はもっておいたほうが良いが、ITエンジニアレベルの高いスキルを求められる訳ではない。汎用のEthernet Switchに対応機器を接続することで自動的に機器が認識されていき、一度認識すればネットワーク上に障害が生じない限りそのまま使い続けることができる。
IPビデオ伝送ならでは、クラウドベースへ
非圧縮映像信号のリアルタイム伝送を目的として策定された SMPTE ST-2110との比較も気になるポイントだろう。SMPTE ST-2110はMulticastを基本とした大規模なネットワークを前提にしており、Video PacketとAudio Packetが分離できるため、オーディオ・プロダクションとの親和性も考えられている。各メーカーから様々な機器が登場を始めているが、相互の接続性など規格対応製品のスタート時期にありがちな問題の解決中という状況だ。NDIについてはすでに製品のリリースから6年が経過し高い相互接続性を保っている。
NDIはイントラ・ネットワーク限定の単一のシステムアップを前提としているために、大規模なシステムアップのための仕組みという部分では少し物足りないものがあるかもしれない。WWW=World Wide Webを経由してNDIを伝送するというソリューションも登場を始めているが、まだまだNDIとしてはチャレンジ段階であると言える。その取り組みを見ると、2017年には200マイル離れたスタジアムからのカメラ回線をプロダクションするといった実験や、Microsoft Azure、AWSといったクラウドサーバーを介してのプロダクションの実験など、様々なチャレンジが行われたそうだ。なお、こちらの実験ではクラウドサーバーまでNDIの信号を接続し、そこからYoutube Liveへの配信を行うということを実現している。つまり、高い安定性が求められる配信PCをクラウド化し、複数のストリーミング・サービスへの同時配信を行う、といったパワフルなクラウドサーバーを活用したひとつの未来的なアイデアである。このようなクラウド・ベースのソリューションは、まさにIPビデオ伝送ならではの取り組みと言える。業界的にもこれからの活用が模索されるクラウド・サービス、SMPTE ST-2110もNDIもIP伝送方式ということでここに関しての可能性に大きな差異は感じないが、NDIが先行して様々なチャレンジを行っているというのが現状だ。
NDIをハンドリングする無償アプリ
次に、NDIの使い勝手にフォーカスをあてていくが、キーワードとなるのは最大の特徴と言ってもいいソフトウェアベースであるということ。それを端的に表している製品、NewTekが無償で配布しているNDI Toolsを紹介していこう。
NDIを活用するためのアプリケーションが詰まったこのNDI Toolsは、Windows用とMac用が用意され9種類のツールが含まれている。メインとなるツールはネットワーク内を流れるNDI信号=NDIソースのモニターを行うNDI Studio Monitor。NDI信号が流れるネットワークにPCを接続しアプリケーションを起動することで、信号のモニターがPCで可能となる。SDIやHDMIのようにそれぞれの入力を備えたモニターの準備は不要、シンプルながらもIPビデオ伝送ならではの機能を提供するソフトウェアだ。次は、VLCで再生した映像をNDI信号としてPCから出力できるようにするNDI VLC Plugin。こちらを立ち上げれば、外部のVideo PlayerをPCを置き換え可能となる。そして、PCから各種テストパターンを出力するNDI Test Patterns。高価な測定器なしにPCでテストパターンの出力を実現している。ここまでの3点だけでも、最初に調整のためのテストパターンを出力し、調整が終わったらVLCを使ってVideo再生を行いつつ、最終出力のモニタリングをNDI Srtudio Monitorで行う、といったフローがPC1台で組み上げられる。IPビデオ伝送ならではの使い勝手と言えるのではないだろうか。
利便性という面で紹介したいのがNDI Virtual Input。これはWindows用となり、PCが参加しているネットワーク内のNDIソースをWindows Video / Audioソースとして認識させることができる。つまり、NDIの入力信号をウェブカメラ等と同じように扱えるようになるということだ。なお、Mac向けにはNDI Webcam Inputというツールで同じようにWEBカメラとしてNDIソースを認識させることができる。すでにZoom / Skypeはその標準機能でNDIソースへの対応を果たしており、IPベースのシステムのPCとの親和性を物語る。そして、NDI for Adobe CCは、Premier / After Effectの出力をNDI信号としてPCから出力、イントラネット越しに別の場所でのプレビューを行ったり、プレイヤーの代替に使ったりとアイデアが広がるソフトウェアだ。他にもいくつかのソフトウェアが付属するが、ハードウェアで整えようとすればかなりのコストとなる機能が無償のソフトウェアで提供されるというのは大きな魅力と言える。
NDI Tools紹介ページ
NDI Toolsダウンロードページ
NDIの可能性を広げる製品群
続々と登場している製品群にも注目しておきたい。まずは、Medialooks社が無償で配布を行なっているSDI to NDI Converter、NDI to SDI Converter。Blackmagic Design DecklinkシリーズなどでPCに入力されたSDIの信号をNDIとして出力することができる、またその逆を行うことができるソフトウェアで、IPビデオらしくPCを映像のコンバーターとして活用できるアプリケーション。有償のソフトウェアとしてはNDI製品を多数リリースするBirdDog社よりDante NDI Bridgeが登場している。こちらはソフトウェアベースのDante to NDIのコンバーターで、最大6chのDante AudioをNDIに変換して出力する。ステレオ3ペアの信号を3つのNDI信号として出力することも、6chの一つのNDIの信号として出力することもできる使い勝手の良い製品だ。同社のラインナップにはNDI Multiveiwというアプリケーションもある。こちらは、その名の通りネットワーク上のNDI信号のMultiview出力をソフトウェア上で組み立て、自身のDisplay用だけではなくNDI信号として出力するという製品。ソースの名称、オーディオメーター、タリーの表示に対応し、複数のMuliviewをプリセットとして切り替えることが行える。
また、BirdDog社は現場で必須となるインカムの回線をNDIに乗せるというソリューションも展開、SDI / HDMI to NDIのコンバーターにインカム用のヘッドセットIN/OUTを設け、その制御のためのComms Proというアプリケーションをリリースしている。このソリューションはネットワークの持つ双方向性を活用した技術。映像信号とペアでセレクトが可能なためどの映像を撮っているカメラマンなのかが視覚的にも確認できるインカムシステムだ。もちろん、パーティラインなど高度なコミュニケーションラインの構築も可能。ハードウェアとの組み合わせでの機能とはなるが、$299で追加できる機能とは思えないほどの多機能さ。どのような信号でも流すことができるネットワークベースであることのメリットを活かした優れたソリューションと言える。
今回写真でご紹介しているのが、Rock oN渋谷でも導入している NewTek TriCaster Mini 4K、NDI自体を牽引しているとも言えるビデオスイッチャーである。NDIのメリットを前面に出した多機能さが最大のアピールポイント。先述した接続の簡便さ、また、双方向性のメリットとして挙げたPTZカメラのコントロール機能では対応機種であればIRIS、GAINなどの調整も可能となる。そして、TriCasterシリーズはソフトウェアベースとなるためVideo Playerが組み込まれている、これもビデオスイッチャーとしては画期的だ。さらには、Video Recorder機能、Web配信機能などもひとつのシステムの中に盛り込まれる。肝心のビデオスイッチャー部もこのサイズで、4M/E、12Buffer、2DDRという強力な性能を誇っているほか、TriCasterだけでクロマキー合成ができたりとDVEに関しても驚くほど多彩な機能を内包している。
📷
NDIを提唱するNewTekの代表的な製品であるTriCasterシリーズ。こちらはTriCaster Mini 4Kとなる。コンパクトな筐体がエンジン部分、4系統のNDI用の1GbEのポートが見える。TriCasterシリーズは、本体とコントロールパネルがセットになったバンドルでの購入ができる。写真のMini 4Kのバンドルは、エンジン本体、1M/Eのコンパクトなコントローラー、そしてSpeak plus IO 4K(HDMI-NDIコンバーター)が2台のバンドルセットとなる。そのセットがキャリングハンドルの付いたハードケースに収まった状態で納品される。セットアップが簡単なTriCasterシリーズ、こちらを持ち運んで使用するユーザーが多いことの裏付けであろう。
すでにInternetを越えて運用されるNDI
イントラ・ネットワークでの運用を前提としてスタートしたNDIだが、すでにInternetを越えて運用するソリューションも登場している。これから脚光を浴びる分野とも言えるが、その中からも製品をいくつか紹介したい。まずは、Medialooks社のVideo Transport。こちらは、NDIソースをインターネット越しに伝送するアプリケーションだ。PCがトランスミッターとなりNDI信号をH.265で圧縮を行い、ストリーミングサイズを落とすことで一般回線を利用した伝送を実現した。フルクオリティの伝送ではないが、汎用のインターネットを越えて世界中のどこへでも伝送できるということに大きな魅力を感じさせる。また、データサイズを減らしてはいるが、瞬間的な帯域の低下などによるコマ落ちなど、一般回線を使用しているからこその問題をはらんでいる。バッファーサイズの向上など、技術的なブレイクスルーで安定したクオリティーの担保ができるようになることが期待されるソリューションだ。
BirdDog社ではBirdDog Cloudというソリューションを展開している。こちらは実際の挙動をテストできていないが、SRT=Secure Reliable Transportという映像伝送プロトコルを使い、インターネット越しでの安定した伝送を実現している。また、こちらのソリューションはNDIをそのまま伝送するということに加え、同社Comms ProやPTZカメラのコントロールなども同時に通信が可能であるとのこと。しっかりと検証してまたご紹介させていただきたいソリューションだ。
Rock oN渋谷でも近々にNewTek TriCasterを中心としたNDIのシステムを導入を行い、製品ハンズオンはもちろんのことウェビナー配信でもNDIを活用していくことになる。セットアップも簡便なNDIの製品群。ライブ配信の現場での運用がスタートしているが、この使い勝手の良さは今後のスタジオシステムにおけるSDIを置き換えていく可能性が大いにあるのではないだろうか。大規模なシステムアップに向いたSMPTE ST-2110との棲み分けが行われ、その存在感も日増しに高くなっていくことは想像に難くない。IP伝送方式の中でも筆頭格として考えられるNDIがどのようにワークフローに浸透していくのか、この先もその動向に注目しておくべきだろう。
*ProceedMagazine2021号より転載
Media
2021/05/31
音楽配信NOW!! 〜イマーシブ時代の音楽配信サービスとは〜
レコードからCDの時代を経て、音楽の聴き方や楽しみ方は日々変化を続けている。すでにパッケージメディアの販売額を配信の売上が超えて何年も経過している。最初は1曲単位での販売からスタートした配信での音楽販売が、月額固定での聴き放題に移行、その月額固定となるサブスクリプション形式での音楽配信サービスに大きな転機が訪れている。新しい音楽のフォーマットとして注目を集めるDolby Atmos Music、SONY 360 Reality Audio。これらの配信を前提としたイマーシブフォーマットの配信サービスがサブスク配信上でスタートしている。いま、何が音楽配信サービスに起こっているかをお伝えしたい。
目次
いよいよ風向きが変わってきたハイレゾ
バイノーラルという付加価値が始まっている
イマーシブは一般的なリスナーにも届く
1.いよいよ風向きが変わってきたハイレゾ
レコードからCDへとそのメディアが変わってから、音楽の最終フォーマットは44.1kHz-16bitのデジタルデータという時代がいまだに続いている。Apple Music、Spotify等のサブスクサービスも44.1kHz-16bitのデジタルデータの圧縮である。そんな現実を振り返ると、2013年頃にハイレゾ(High Resolution Audio)という言葉が一斉を風靡した際に48kHz-24bit以上(これを含む)の音源をハイレゾとするという判断は間違っていなかったとも感じる。逆に言えば、制作の現場でデフォルトとなっている48kHz-24bitというデジタルデータは、まだまだその音源を聴くユーザーの元へ届けられていないということになる。ハイレゾ音源に関しては、付加価値のある音源として1曲単位での販売がインターネット上で行われている。DVD Audioや、SACDなどハイレゾに対応したパッケージも存在はしたが、残念ながらすでに過去のものとなってしまっている。これらの音源は残念ながら一般には広く普及せず、一部の音楽愛好家の層への浸透で終わってしまった。
もちろん、その素晴らしさは誰もが認めるところではあるが、対応した再生機器が高額であったり、そもそも音源自体もCDクオリティーよりも高価に設定されていたため、手を出しにくかったりということもあった。しかし再生機器に関してはスマホが普及価格帯の製品までハイレゾ対応になり、イヤフォンやヘッドフォンもハイレゾを十分に再生できるスペックの製品が安価になってきている。
そのような中、2019年よりハイレゾ音源、96kHz-24bitの音源をサブスクサービスで提供するという動きが活発化している。国内ではAmazon Music HD、mora qualitasが2019年にサービス開始、2020年にはDeezerがスタート、海外に目を向けるとTIDAL、Qobuzがハイレゾ音源のサブスクサービスを開始している。多くのユーザーが利用するSpotifyやApple Musicよりも高額のサブスクサービスだが、ほぼすべての楽曲をロスレスのCDクオリティーで聴くことができ、その一部はハイレゾでも楽しめる。この付加価値に対してユーザーがどこまで付いてくるのか非常に注目度が高い。個人的には「一度ロスレスの音源を聴いてしまうと圧縮音声には戻りたくない」という思いになる。ハイレゾの音源であればなおのこと、その情報量の多さ、圧縮により失われたものがどれだけ多いかを思い知ることになる。あくまでも個人的な感想だが、すでにサブスクサービスにお金を支払って音楽を楽しんでいるユーザーの多くが、さらにハイクオリティーなサブスクサービスへの移行を、たとえ高価であっても検討するのではないかと考えている。
執筆時点では日本国内でのサービスが始まっていないTIDAL。Dolby Atmos、SONY 360 Reality Audio、ハイレゾすべてが聴き放題の配信サービスとなっており、ミュージシャンのJAY-Zがオーナーのサブスク配信サービスとしても有名である。Dolby Atmosを聴くためには、HiFiプランに加入してDolby Atmos対応の端末(下部製品が一例)を利用することとなる。
2.バイノーラルという付加価値が始まっている
今の音楽の楽しみ方は、スマホで再生をして、ヘッドフォンやイヤホンで楽しむ、といった形態が大部分となっている。音楽のヘビーユーザーである若年層の部屋には、ラジカセはもちろん、スピーカーの付いた製品はすでに存在していない状況にある。高価なハイレゾ対応のオーディオコンポで楽しむのではなく、手軽にどこへでも音楽を持ち出し、好きなところで好きな曲を楽しむというのがサブスクサービスの利用者ほとんどの実態ではないだろうか。
好きな音楽を少しでも高音質に楽しみたい。そんな願いを手軽に叶えてくれるのがハイレゾのサブスクサービスである。原盤が96kHz/24bitというのは、ここ数年の作品であれば存在しているものも多い。また海外からはデジタル・リマスター版として過去の名盤が多数ハイレゾフォーマットで登場している。
さらに、音楽の楽しみ方に次の時代がやってきている。Dolby Atmos MusicとSONY 360 Reality Audio(以下、Sony 360RA)という2つのフォーマット。イマーシブ(3D)の音源である。後方や天井にスピーカーを設置して聴くのではなく、バイノーラルに変換したものをヘッドフォンで楽しむ。フォーマットを作ったメーカーもそういった楽しみ方を想定し、ターゲットにして作ったものだ。そしてこれらのフォーマットは、ハイレゾサブスクサービスのさらなる付加価値として提供が始まっている。Dolby Atmos Musicであれば、Amazon Music HD、TIDAL。Sony 360RAは、Amazon Music HD、Deezer、TIDALで楽しむことができる。すべてを楽しもうというのであれば、両者とも対応のTIDALということになる。
表1 主要音楽配信サービス概要(2021年5月現在) ※画像クリックで拡大
(※1)2021年5月追記
2021年後半にはSpotifyが「Spotify HiFi」としていくつかの地域でロスレス配信に対応することを発表しました。さらには、2021年6月にはApple Musicがロスレスとハイレゾ、そして空間オーディオ(Apple製品におけるイマーシブフォーマットの呼称)への対応を発表しています。
ただし、さすがに最新のフォーマットということで少しだけ制約がある。特にDolby Atmosに関しては再生端末がDolby Atmosに対応している必要があるが、これも徐々に対応機器が増えている状況。高価なものだけではなく、Amazon Fire HDといった廉価なタブレットにも対応製品があるのでそれほどのハードルではない。Amazon Music HDでの視聴は執筆時点ではEcho Studioでの再生に限られているのでここも注意が必要だ。また、本記事中に登場するQobuz、TIDALは日本国内でのサービスは提供前の状況となる。
こちらは国内ですでにサービス提供されているAmazon Music HD。このサブスク配信サービスもDolby Atmos、SONY 360 Reality Audio、ハイレゾすべてが聴き放題。ただし、Dolby Atmos、SONY 360 Reality Audioを楽しむことができるのはAmazon Echo Studioのみという対応状況になる。
3.イマーシブは一般的なリスナーにも届く
これらのハイレゾサブスクサービスの展開により、手軽にイマーシブ音響を楽しむ土壌はできあがる。バイノーラルで音楽を楽しむということが普通になるかもしれない。もちろんハイレゾを日々聴くことの楽しみもある。ここで注目をしたいのは、ハイレゾの魅力によりハイレゾサブスクサービスを楽しみ始めたユーザーが、イマーシブも追加のコスト無しで聴けるという点だ。これまでのイマーシブは興味はあっても設備に費用がかかる、スピーカーも多数必要、設置ができない、そういったハードルを超えた先にある存在だった。それが、いま手元にあるスマホとヘッドフォンでサブスクサービスの範囲内で楽しめるということになる。映画館ですらDolby Atmosの特別料金が設定されているが、ハイレゾサブスクサービスにはそれがない。多くのユーザーがその楽しさに気づくことにより、より一層制作も加速することとなるだろう。
制作側の話にも触れておこう。Proceed Magazineでは、以前よりDolby Atmos、SONY 360RAを記事として取り上げてきている。
Dolby Atmosは、7.1.2chのBEDトラックと最大118chのObject Audioにより制作される。Dolby Atmos Musicでは、バイノーラルでの視聴が前提となるため、レンダラーに標準で備わるバイノーラルアウトを使って作業を行うこととなる。となると、最終の仕上げまでDolby Atmos Production Suiteで行えるということになる。Dolby Atmosの制作に対応したPro Tools Ultimate、NUENDOがあれば、Production Suiteの追加でDolby Atmos Musicの制作は始めることができる。
https://pro.miroc.co.jp/headline/daps-90day-trial/#.YK3ozZP7TOQ
SONY 360RAの制作ツールは執筆時点ではベータ版しか存在しない。(※2)まさに、ベータテスターのエンジニアから多くのリクエストを吸収し正式版がその登場の瞬間を待っている状況だ。360RAはベースの技術としてはAmbisonicsが使われており、完全に全天周をカバーする広い音場での制作が可能となる。すでにパンニングのオートメーションなども実装され、DAWとの連携機能も徐々にブラッシュアップされている。正式版がリリースされれば、いち早く本誌紙面でも紹介したいところだ。
(※2)2021年5月追記
360RA制作用プラグイン、360 Reality Audio Creative Suite (通称:360RACS)がリリースされました!
価格:$299
対応フォーマット:AAX、VST
対応DAW:Avid Pro Tools、Ableton Live ※いずれも2021年5月現在
https://360ra.com/ja/
さらなる詳細は次号Proceed Magazine 2021にてご紹介予定です。
←TIDALの音質選択の画面。Normal=高圧縮、High=低圧縮、HiFi=CDクオリティー、Master=ハイレゾの4種類が、対応楽曲であれば選択できる。Wifi接続時とモバイル通信時で別のクオリティー選択ができるのもユーザーに嬉しいポイント。※画像クリックで拡大
←TIDALがDolby Atmosで配信している楽曲リストの一部。最新のヒットソングから70年代のロック、Jazzなど幅広い楽曲がDolby Atmosで提供されている。対応楽曲は、楽曲名の後ろにがDolbyロゴが付いている。※画像クリックで拡大
ハイレゾサブスクサービスは、新しいユーザーへの音楽の楽しみを提供し、そのユーザーがイマーシブ、バイノーラルというさらに新しい楽しみに出会う。CDフォーマットの誕生から40年かかって、やっとデジタル・オーディオの新しいフォーマットが一般化しようとしているように感じる。CDから一旦配信サービスが主流となり、圧縮音声が普及するという回り道をしてきたが、やっと次のステップへの道筋が見えてきたと言えるのではないだろうか。これまでにも色々な試みが行われ、それが過去のものとなっていったが、ハイレゾというすでに評価を得ているフォーマットの一般化の後押しも得て、イマーシブ、バイノーラルといった新たなサウンドがユーザーにも浸透し定着していくことを願ってやまない。
https://pro.miroc.co.jp/headline/rock-on-reference-room-dolby-atmos/#.YLTeSpP7TOQ
https://pro.miroc.co.jp/solution/dolby-atmos-proceed2020/#.YLTeFJP7TOQ
https://pro.miroc.co.jp/headline/netflix-sol-levante-dolby-atmos-pro-tools-session-file-open-source/#.YLTd9ZP7TOQ
https://pro.miroc.co.jp/headline/pro-tools-carbon-proceedmagazine/#.YLTdn5P7TOQ
https://pro.miroc.co.jp/solution/mac-mini-ht-rmu/#.YLTen5P7TOQ
Media
2021/02/24
浜町 日々 様 / 〜伝統芸能が得た、テクノロジーとの融合〜
福井駅からほど近い浜町。福井の歓楽街といえば片町が有名だが、その片町と市内を流れる足羽川との間の地区が浜町である。古くから花街として賑わい、現在でも料亭が軒を連ね情緒あふれる街。国指定の登録有形文化財としても有名な開花亭や、建築家 隈研吾の設計によるモダンな建築も立ち並ぶ文化の中心地である。そんな浜町に花街の伝統的な遊びをカジュアルに楽しむことの出来る「日々」はある。今回はこのステージ拡張に伴う改修をお手伝いさせていただいた。
芸妓の技。日本の伝統芸能とテクノロジー。
ステージ奥のスクリーンをおろした状態での演目の様子。福井・浜町芸妓組合の理事長である今村 百子氏が伝統的な演目を披露し、背景には福井の風景が流れる。まさに伝統芸能とテクノロジーが出会った瞬間である。
日々は、福井・浜町芸妓組合の理事長でもある今村 百子氏が立ち上げたお店。お座敷という限定された空間で、限定された特別なお客様にしか披露されてこなかった芸妓の技。それを広く、カジュアルに楽しんでもらいたいという思いからスタートしている。バーラウンジのようなお店にステージがあり、そこで毎夜これまでお座敷でしか見ることができなかった芸妓さんたちの日本舞踊や、三味線、唄を楽しむことができる。
この日々のステージがこのたび拡張され、様々な催しに対応できるように改修が行われた。改修にはレコーディングエンジニアでもあり、様々な音楽プロデュースを行うK.I.Mの伊藤圭一氏が携わっており、コンセプトや新しい演目のプロデュースなどを行なっている。元々、日々にあったステージは非常に狭かった。「三畳で芸をする」という芸妓の世界、お座敷がそのステージであることを考えればうなずける。これを広げ、日本の伝統芸能だけではなく、西洋の芸能、最新のテクノロジーと融合させ新しいステージを作ろう、というのがそのコンセプトとなる。
普通に考えれば、クローズドな世界に見える日本の伝統芸能の世界だが、今村氏の持つビジョンはとてもオープンなものだ。2017年には全国の芸妓を福井に集め、大きなステージに50名近くの芸妓が集まり、それぞれに磨いた芸を披露する「花あかり」というイベントを行なっている。芸妓の技を広く、カジュアルに楽しんでもらいたいという考えを具現化したわけだ。このように新しいことへ果敢にチャレンジするスピリットを持った今村氏のイメージを具体化できるステージを作ろう、ということで伝統芸能とテクノロジーの融合というコンセプトがさらに詰められていくことになる。
無拍子である日本の伝統芸能に指揮者代わりの声やクリックを持ち込み、バックトラックに合わせて演奏をする。プロジェクターを使い、福井の映像とともに舞踊を披露する、そしてマイクで集音し拡声する。現代のステージ演出としては当たり前に聞こえることかもしれないが、「日本の伝統芸能を」という枕詞をつけた瞬間にハードルの高いチャレンジとなる。なんといっても無拍子である。様々な演出のきっかけを決めることだけでも困難なことだ。このような多くの課題を持ちながら、ステージの設計は進められていくこととなった。
スクリーンを上げると手作業で金・銀・銅をヘラで塗り重ねた四角錐のホリゾントが現れる(下部左)。和を意識する金と、幾何学的な造形。照明により、表情を変化させる建築デザイナー 大塚先生のアイデアだ。
透過スクリーンに浮かび上がる表現
ステージ天井部分にはホリゾントのスクリーンと透過型スクリーン用に2台の超短焦点型のプロジェクターを準備し、この位置からの投影を可能としている。
まずは、映像演出から見ていこう。ステージのホリゾントは、今回の改修の建築デザイナー、大塚 孝博氏による金の四角錐があしらわれている。一般的には、金屏風や松などが想像されるが、ここに幾何学的な金の四角錐とはなんとも粋である。日本の古来のデザインにも幾何学的な模様は多く使われているが、この四角錐は照明の当たり具合により変幻自在に表情を変える。金・銀・銅をヘラで塗り重ねており、一つ一つ反射の具合も異なる。これにより有機的な表情を得ている。
ここに映像との融合を図るわけだが、さすがにこの四角錐のホリゾントへプロジェクターで投影することはできないため、昇降式の大型スクリーンが吊られている。プロジェクターは超短焦点のレンズと組み合わせてステージ天井からの投写としている。これによりステージ上の人物は、ステージ後方1/3まで下がらなければ影が映らない。プロジェクターでの映像演出と、ステージ上での実演を組み合わせることを可能としている。
さらにステージには、透過型スクリーン(日華化学 ディアルミエ)が設置されている。この透過スクリーンに投影することで、ステージ上に人物を浮かび上がらせたり、視覚効果的に使ったりと様々な演出を行うことができる。例えば、笛を吹いている今村百子さんの映像を投影しながら、実際の今村氏がそれに合わせて三味線と唄を披露するという演目が行われている。周りを暗くすることで、ホログラム的に空間に浮かび上がっているような効果を得ることができている上、ホリゾントのプロジェクターとも同時使用が可能なため、演出の幅はかなり広い。
ステージ手前下手側に吊られた透過型スクリーン(日華化学 ディアルミエ)を使った演出、無拍子の笛に合わせるためにイヤモニでクリックを聴きながら演奏を行っている。また、透過型スクリーンはこのように歌詞を浮かび上がらせたりといった演出にも活用できる。空中にふわっと文字が浮かび上がったような幻想的な空気さえ感じる演出が可能だ。
スピーカーをイメージさせない音環境
音響としては、やはりスピーカーの存在をできるだけ目立たないようにしたいという要望があった。スピーカーが鳴っているというイメージを極力持たせないためにも大切なポイントだが、理想的な音環境を提供しようと考えると設計としては難しいものがある。結論から言えば、今回はステージプロセの上下にスピーカーを設置することとなった。上部は、視界よりも上の位置、下部はネットで覆い客席からは見えないように工夫してある。この上下のスピーカーの調整を行うことで、仮想音響軸をステージ上の演者の高さとするように調整を行っている。
音響ミキサーはYAMAHA TF-RACKを導入している。専門のオペレーターが所属するわけではないため、できるだけ簡単に操作できる製品としてこちらが選択された。接続されているソースは、2台のプロジェクターへそれぞれ映像を投影するために用意された映像プレイヤーからの音声、ステージ天井に仕込まれた2本のマイク、上下の袖にはマイクコンセントが設けられている。仮設の機器としては司会者などを想定したハンドマイクが用意されている。
ステージ天井のマイクはDPA 4017が選ばれた。コンパクトなショットガンタイプで、ステージの決まった位置に座ることが多い演者をピンポイントで狙っている。これらのソースは予めバランスを取り、演目ごとのプリセットとして保存、それを呼び出すことで専門でない方でもオペレートできるよう工夫が凝らされている。
映像に合わせた音声のバックトラックは、映像ファイルに埋め込むことで映像と音声の同期の問題を解消している。それらの仕込みの手間は増えるものの、確実性を考えればこの手法が間違いないと言えるだろう。天井マイクの音声にはリバーブが加えられ、実際の生の音を違和感なく支えられるよう調整が行われた。
プロジェクターの項でご紹介した笛を吹く映像に合わせて三味線と唄を歌うという演目では、演者の今村氏はイヤモニをつけてステージに上がる。無拍子の笛にクリックをつけた音声を聴きながらタイミングを図り演奏を行っているということだ。高い技術があるからこそできる熟練がなせる業である。呼吸を合わせ演奏を行う日本の伝統音楽の奏者にとって、これはまさに未知の体験であったことだろう。より良いステージのため、このようなチャレンジに果敢に取り組まれていることに大きな敬意を抱く。
マイクはステージ上での演奏を集音する為にDPA 4017を設置。音響および映像の再生装置はステージ袖のラックにまとめて設置され、専門ではない方もオペレートできるよう工夫が凝らされている。
ここまでに紹介したような芸妓の技を披露するということだけではなく、今後は西洋楽器とのコラボレーションや、プレゼン会場などの催しなど、様々な利用をしてもらえる、皆様に愛される空間になって欲しいとのコメントが印象的。日本の伝統芸能が、新たなスタイルを携えてこの福井の地から大きく羽ばたく、日々はその発信源になるステージとなるのではないだろうか。
前列左より、株式会社大塚孝博デザイン事務所 大塚孝博氏、浜町日々 女将 今村百子氏、株式会社KIM 伊藤圭一氏、後列左より:前田洋介、森本憲志(ROCK ON PRO)
*ProceedMagazine2020-2021号より転載
Media
2021/01/07
手軽に多拠点ストリーミング!〜ATEM Streaming Bridge
ATEM Streaming Bridgeは、ATEM Mini ProシリーズからH.264ストリームを受信して、SDI/HDMIビデオに変換するビデオコンバーター。ATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOからのEthenetダイレクトストリーミング信号を受け、SDI/HDMI対応機器にビデオ信号を送ることが出来ます。
つまり、離れた場所にある複数のATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOの映像を受け、手元のATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOでスイッチングしながらインターネットに配信を行うことが可能になります!
ローカルLANだけでなく、特定のポートを開放することでインターネット越しに信号を受けることも可能。世界中のATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOユーザーとコラボレーションしながらの多拠点ストリーミングが手軽に行えます。
セットアップ例
ATEM Streaming Bridgeを使用すると、ATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOからのダイレクト配信の配信先としてATEM Streaming Bridgeを指定することができるようになる。図のように、ひとつのビデオスイッチャーに信号をまとめることもできるし、SDI/HDMI対応のレコーダーへ入れてやることもできる。各カメラに1台ずつATEM Mini Pro / ATEM Mini Pro ISOを使用して、離れた場所にいるエンジニアにスイッチングをまるごと任せるような使い方も可能だ。
ATEM Streaming Bridge
販売価格:¥30,778(本体価格:¥ 27,980)
高度なH.264コーデックを使用しており、非常に低いデータレートで高品質を得られるため、ローカル・イーサネットネットワークで離れた場所にビデオを送信したり、インターネット経由で世界中に送信できます!放送局とブロガーがコラボレーションし、ATEM Mini Proを使ったリモート放送スタジオの国際的なネットワークを構築できると想像してみてください。(インターネット経由での受信には特定のポートを開放する必要があります。詳細は製品マニュアルをご参照ください。)
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design ATEM Mini Pro
販売価格:¥ 73,150(本体価格:¥ 66,500)
ATEM Mini Proで追加される機能は「本体からインターネットへのダイレクト配信」「マルチモニタービュー」「プログラム出力の外部SSDへの収録」の3つ。本記事の主旨に則ってオーディオクオリティを優先すると、ダイレクト配信機能は使用する機会がないため、各カメラの映像を確認しながらスイッチングをしたい、または、配信した動画を高品質で取っておきたいのいずれかに該当する場合はこちらを選択することになる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
販売価格:¥ 113,850(本体価格:¥ 103,500)
ATEM Mini Pro ISOで追加される機能は、ATEM Mini Proの全機能に加え、「全HDMI入出力信号を外部SSDに個別に保存」「スイッチングを施したタイミングをDaVinci Resolveで読み込めるマーカーの記録」の2つ。あとから映像を手直ししたり再編集したりしたい場合にはこちらを選択することになる。アーカイブ映像として公開する前に、本番中に操作を誤ってしまった部分を修正したり、リアルタイムで無料配信したライブを編集し後日有償で販売する、といったことが可能になる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Rock oN Line eStoreに特設コーナーが誕生!
Rock oN Line eStoreでは、カメラからスイッチャー、配信や収録向けのマイクなど、映像制作に関わる機材を集めた特設コーナーを新設している。本記事に挙げた個別の機材が購入できるのはもちろん、手軽なセット販売や、スタッフに相談できる問い合わせフォームなどもあるので、ぜひ覗いてみてほしい。
eStore特設コーナーへ!!>>
Media
2020/11/11
Roland V-600U~HD4K/HD混在環境でもハイクオリティなビデオ出力!
放送や映像制作と同じように、イベントやプレゼンテーションなどの演出も4K化が進んでいます。一方で、クライアントや演出者からは従来の HD 機材の対応も同時に求められている。
V-600UHDはそうした現場のニーズに合わせ、従来の HD 環境を段階的に 4K に対応させることが可能。全ての入出力端子にローランド独自の「ULTRA SCALER」を搭載。 この機能によりフル HD と 4K の異なる映像を同時に扱えるだけでなく4K と HD 映像も同時に出力できるため、従来の HD ワークフローの中に4K映像を取り込むことができる。
システムセットアップ
V-600UHD は HDMI(2.0対応)入力を 4 系統、12G-SDI 入力を 2 系統搭載し、PC とメディア・プレーヤーに加え、ステージ用にカメラを使用するようなイベントやライブコンサートに最適。すべての入出力に独自のスケーラーを搭載し、4KとHDを同時に入出力することができるため、両者が混在するシステムでも容易に運用が可能だ。
会場ディスプレイには4K映像を出力しながら、HDモニターやライブ配信用エンコーダー等従来の HD 表示デバイスへの出力も可能。エンベデッド・オーディオの入出力にも対応するほか、XLR入力2系統を備えオーディオミキサーからの出力をもらうこともできる。中規模〜大規模イベントのコアシステムとして高い実用性を誇る。
プロダクト
ROLAND V-600UHD
販売価格:¥ 1,408,000(本体価格:¥ 1,280,000)
HDR、フル・フレームレート 60Hz、Rec.2020 規格、DCI 4K(シネマ4K)解像度など先進のテクノロジーに対応し、高精細な映像を扱うことが可能。さらに、内部映像処理は 4:4:4/10bit に対応し、PC から出力された高精細な映像も鮮明に表示可能で、拡大した映像内の細かな文字も細部まで読み取ることができる。
「ROI(Region of Interest)機能」を使えば、1 台の 4K カメラの映像から必要な部分を最大 8 つ抽出することで、複数のカメラを用意するのと同じような演出が可能になる。スケーラー機能と併せてクロスポイントに割り当てることが可能。カメラの台数に頼ることなく、映像演出の幅を拡げることができる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
ROLAND UVC-01
販売価格:¥ 27,500(本体価格:¥ 25,000)
最大1920×1080/60pに対応するRoland純正のビデオキャプチャー/エンコーダー。Mac/Windowsに対応し、ドライバーのインストール不要、USBバスパワー対応など、普段使いにも便利な取り回しのよさが魅力だ。ほとんどのHDMIカメラやビデオスイッチャーに対応するため、WEB配信の機会が多いユーザーは持っておくと便利かも。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Rock oN Line eStoreに特設コーナーが誕生!
Rock oN Line eStoreでは、カメラからスイッチャー、配信や収録向けのマイクなど、映像制作に関わる機材を集めた特設コーナーを新設している。本記事に挙げた個別の機材が購入できるのはもちろん、手軽なセット販売や、スタッフに相談できる問い合わせフォームなどもあるので、ぜひ覗いてみてほしい。
eStore特設コーナーへ!!>>
Media
2020/11/11
ライブミキサーを使用して4K制作環境でWEB配信!
ついにiPhoneが5Gに対応し、大容量データの高速通信がモバイル環境でもいよいよ実現されつつある。テレビ放送やリアルイベントではすでに4Kの需要は高まっており、その波がWEB配信の世界にも押し寄せることが予想される。折しもコロナ禍の影響で映像配信事業の成熟は加速度的に高まっており、既存メディアと同等のクオリティが求められるようになるまでにそれほど長い時間はかからないだろう。
あらゆるライブイベントをプロ仕様のプログラムとして制作することが出来るビデオスイッチャー、Blackmagic Television Studio Pro 4Kを中心とした、4K対応WEB配信システムを紹介しよう。
システムセットアップ
4K対応ビデオスイッチャーであるATEM Television Studio Pro 4Kから、4K対応のビデオキャプチャーであるUltra Studio 4K Miniで配信用のフォーマットにファイルをエンコード。配信用のMac/PCに信号を流し込む構成だ。
ATEM Television Studio Pro 4Kはマルチビュー出力を備えているため、SDIインプットのあるモニターを使用して各カメラやメディアからの映像を監視しながら映像の切り替えを行うことができる。
図ではオーディオ部分を割愛しているが、ATEM Television Studio Pro 4Kにはオーディオインプット用のXLR2系統が備わっているほか、SDIにエンベッドされたオーディオ信号を扱うこともできる。Ethernet経由でMac/PCを繋ぎ、ATEM Control Softwareを使用すれば内部で音声ミキシングも可能なため、ミキサーからのアウトをATEM Television Studio Pro 4Kに入れ、映像と音をここでまとめることが可能。
オーディオクオリティにこだわるなら、小型のオーディオI/FやI/F機能付きミキサーを使用してミキサーからの信号を配信用のMac/PCに直接入力してもよい。手持ちのミキサーの仕様や求められる品質・運用に鑑みて、柔軟な構成を取ることができる。
キープロダクト
Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro 4K
販売価格:¥373,780(本体価格:¥339,800)
8系統の12G-SDI入力を搭載し、ハイエンドの放送用機能に対応したATEM Television Studioシリーズの中でも、ATEM Television Studio Proシリーズはプロ仕様の放送用ハードウェアコントロールパネルが一体化しており、追加のCCUにも対応。すべての入力系統に再同期機能を搭載しており、プロ仕様および民生用カメラで常にクリーンなスイッチングが可能。マルチビュー出力に対応しており、すべてのソースおよびプレビュー、プログラムを単一のスクリーンで確認できる。また、Aux出力、内蔵トークバック、2つのスチルストア、オーディオミキサー、カメラコントロールユニットなどにも対応。
ライブプロダクション、テレビシリーズ、ウェブ番組、オーディオビジュアル、そしてテレビゲーム大会のライブ放送などに最適で、カメラ、ゲーム機、コンピューターなどを接続するだけで簡単にライブスイッチングを開始できる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini
販売価格:¥125,180(本体価格:¥ 113,800)
UltraStudio 4K Miniは本来はThunderbolt 3に対応したポータブルなキャプチャー・再生ソリューション。Mac/PCにビデオI/Fとして認識される機能を利用して、4K対応キャプチャーカードとして使用することが可能だ。
最新の放送テクノロジーを搭載しており、4K DCI 60pまでのあらゆるフォーマットで放送品質の8/10-bitハイダイナミックレンジ・キャプチャー、4K DCI 30pまでのあらゆるフォーマットで12-bitハイダイナミックレンジ・キャプチャーを実現。SDカードリーダーを内蔵しているので、カメラメディアを直接コンピューターにマウントすることも可能だ。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design Blackmagic Web Presenter
販売金額:¥ 62,678(本体価格:¥ 56,980)
素材のみは4Kで録っておき、配信はHD品質でもOK、という方はUltraStudio 4K Miniの代わりにこちらを。
あらゆるSDIまたはHDMIビデオソースをUSBウェブカメラの映像として認識。Skypeなどのソフトウェアや、YouTube Live、Facebook Live、Twitch.tv、Periscopeなどのストリーミング・プラットフォームを使用したウェブストリーミングを一層高い品質で実現。Teranex品質のダウンコンバージョンに対応しているので、あらゆるSD、HD、Ultra HDビデオを、低データレートながらも高品質のストリーミングが可能な720pに変換する。
ドライバ不要で、ハイクオリティの内部エンコーダーとして動作する本機があれば、キャプチャデバイスとコンピューターの相性を気にすることなくWEB配信に集中できる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Rock oN Line eStoreに特設コーナーが誕生!
Rock oN Line eStoreでは、カメラからスイッチャー、配信や収録向けのマイクなど、映像制作に関わる機材を集めた特設コーナーを新設している。本記事に挙げた個別の機材が購入できるのはもちろん、手軽なセット販売や、スタッフに相談できる問い合わせフォームなどもあるので、ぜひ覗いてみてほしい。
eStore特設コーナーへ!!>>
Media
2020/11/11
ウェブキャスターで高品質配信!音楽演奏配信向けシステムセットアップ例
公共の場でのマスク着用と並んで、映像配信はウィズ・コロナ時代のひとつのマナーとさえ言えるほど急速にひとびとの生活に浸透している。もちろん半分ジョークだが、読者の半数は実感を持ってこのことばを迎えてくれることと思う。なにせ、このような記事を読もうと思ってくれているのだから、あなたも映像配信にある程度の関心があるはずだ。
さて、しかし、いざ自分のパフォーマンスを配信しようと思っても、どのような機材を揃えればいいのか、予算はいくらくらいが妥当なのか、というところで迷ってしまう方もいることだろう。(Z世代のミュージシャンは、そんなことはないのだろうか!?)
そこで、この記事では音楽の生演奏を前提に、低価格かつ高品質な映像配信を実現するシステムアップ例を紹介したいと思う。
システムセットアップ例
スイッチャーはATEM Miniで決まり!?
マルチカメラでの映像配信にこれから挑戦したいという方にぜひおすすめしたいビデオスイッチャーがBlackmagic Design ATEM Miniシリーズだ。4x HDMI入力やプロ仕様のビデオエフェクト、さらにはカメラコントロール機能までついた本格仕様でありながら価格破壊とも言える低価格を実現しており、スイッチャーを初めて導入するという方からコンパクトなスイッチャーを探しているプロフェッショナルまで、幅広くおすすめできるプロダクトだ。
ATEM Mini、ATEM Mini Pro、ATEM Mini Pro ISO、と3つのラインナップがあり、順次機能が増えていく。ATEM Miniでは各カメラ入力をモニターする機能がないため、バンド編成でのライブ配信などにはATEM Mini ProかATEM Mini Pro ISOを選択する方がオペレートしやすいが、弾き語りや小編成ユニットの場合はATEM Miniでも十分だろう。
ATEM Miniシリーズについての詳細はこちらの記事>>も参考にしてほしい。
オーディオI/F機能付きミキサーでサウンドクオリティUP!
ATEM Miniシリーズにはマイク入力が備わっており、ATEM Mini内部でのレベルバランスの調整も可能となっている。しかし、オーディオのクオリティにこだわるなら小型でもよいのでオーディオミキサーの導入が望ましい。ライブやレコーディングで使用できる一般的なマイクを使用することができるし、機種によってはオンボードのエフェクトも使用できる。必要十分な入出力数を確保できるし、なにより経由する機器を減らす方がクオリティは確実に上がる、とメリット尽くしだ。
音声系をいったんミキサーでまとめ、ATEM Miniからの映像信号とは別系統としてMac/PCに入力、OBSなどの配信アプリケーション内で映像と音声のタイミングを合わせるというシステムアップになる。
この時、ミキサーとオーディオI/Fを別々に用意してもよいが、最近の小型ミキサーの中にはUSBオーディオI/F機能を搭載したものも多く、「ウェブキャスター」と呼ばれるWEB配信を特に意識したプロダクトも存在する。
すでにミキサーやオーディオI/Fを所有しているなら足りない方を買い足すのがよいだろうが、これから配信に挑戦しようというならウェブキャスターなどのUSB I/F機能付きミキサーがうってつけのソリューションとなるだろう。チャンネル数、対応サンプリング周波数、マイク入力数など各モデルで特色があるため、自分に必要なスペックがわからない場合は気軽にRock oN Line eStoreに問い合わせてみてほしい。
おすすめI/F機能付きミキサー
YAMAHA AG-06
販売価格:¥ 19,800(本体価格:¥ 18,000)
ウェブキャスターという名称を広めた立役者とも言えるYAMAHA AGシリーズ。ループバック機能、ヘッドセット対応、2x マイク/ライン入力・1x 48Vファンタム電源を含む6入力、USB I/F機能、USBバスパワーなど、ウェブ動画配信に完全対応。さらに最大で192kHz/24bitというハイレゾクオリティのオーディオ性能を誇る。弾き語りや二人組ユニットだけでなく、バックトラックに合わせての演奏やトーク番組風の配信、ゲーム実況まで幅広く対応可能だ。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
ZOOM LIVETRAK L-8
販売価格:¥ 39,600(本体価格:¥ 36,000)
ジングルや効果音を鳴らせる6個のサウンドパッド、電話の音声をミックスできるスマートフォン入力、バッテリー駆動でスタジオの外にも持ち出せる機動力。ポッドキャスト番組の収録やライブ演奏のミキシングが手軽に行える、8チャンネル仕様のライブミキサー&レコーダー。内蔵SDカードに録音することが可能で、12chモデル、20chモデルの上位機種もランナップされているためバンドライブの動画配信にはうってつけだろう。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Presonus StudioLive AR8c
販売価格:¥ 55,000(本体価格:¥ 50,000)
ミュージシャン達がミュージシャンのために開発したハイブリッド・ミキサーであるStudioLive® ARcシリーズは、XMAXプリアンプ/EQ/デジタル・エフェクトを搭載したアナログ・ミキサーに、24Bit 96kHz対応のマルチチャンネルUSBオーディオ・インターフェース、SD/SDHCメモリー・カード録音/再生、そしてBluetoothオーディオ・レシーバーによるワイヤレス音楽再生機能を1台に統合。ラインアップは、8チャンネル仕様、12チャンネル仕様、16チャンネル仕様の3機種。レコーディングや音楽制作のためのCapture™/Studio One® Artistソフトウェアも付属し、ライブPA、DJ、バンドリハーサル、ホームスタジオ、ネット配信に理想的なオールインワン・ハイブリッド・ミキサーとなっている。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
YAMAHA MG10XU
販売価格:¥ 29,334(本体価格:¥ 26,667)
YAMAHAの定番アナログミキサーであるMGシリーズも、多くがUSB I/F機能を搭載している。WEB配信に特化した製品ではないが、高品位なディスクリートClass-Aマイクプリアンプ「D-PRE」搭載をはじめ、1ノブコンプ、24種類のデジタルエフェクトなど、本格的なミキサーとしての機能を備えており、クオリティ面での不安は皆無と言える。20chまでの豊富なラインナップも魅力。トークやMCではなく「おれたちは音楽の中身で勝負するんだ!」という気概をお持ちなら、ぜひこのクラスに手を伸ばしてほしい。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
SOUNDCRAFT Notepad-8FX
販売価格:¥ 14,900(本体価格:¥ 13,545)
ブリティッシュコンソールの老舗メーカーであるSOUNDCRAFTにもUSB I/F機能搭載のコンパクトミキサーがラインナップされている。全3機種の中で上位モデルであるNotepad-12FXと本機Notepad-8FXには、スタジオリバーブの代名詞Lexicon PRO製のエフェクト・プロセッサーを搭載!ディレイやコーラスも搭載しており、これ1台で積極的な音作りが可能となっている。ブリティッシュサウンドを体現する高品位マイクプリ、モノラル入力への3バンドEQ搭載など、コンパクトながら本格的なオーディオクオリティを誇っている。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
ALLEN & HEATH ZEDi-8
販売価格:¥ 19,008(本体価格:¥ 17,280)
こちらもイギリスの老舗コンソールメーカーであるALLEN & HEATHが送るUSB I/F対応アナログミキサーがZEDシリーズだ。ZEDi-8はコンパクトな筐体に必要十分で高品質な機能がギュッと凝縮されたようなプロダクトだ。2バンドのEQ以外にオンボードエフェクトは搭載していないが、定評あるGS-R24レコーディング用コンソールのプリアンプ部をベースに新設計されたGSPreプリアンプは同シリーズ32ch大型コンソールに搭載されているのと同じもの。長い歴史を生き抜いてきたアナログミキサー作りのノウハウが詰め込まれた一品と言えそうだ。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
あなたに最適なATEM Miniは!?
Blackmagic Design ATEM Mini
販売価格:¥ 39,578(本体価格:¥ 35,980)
4系統のHDMI入力、モニター用のHDMI出力1系統、プロクオリティのスイッチング機能とビデオエフェクトなど、プロクオリティの機能を備えながら圧倒的な低コストを実現するATEM Mini。コンピューターに接続してPowerPointスライドを再生したり、ゲーム機を接続することも可能。ピクチャー・イン・ピクチャー・エフェクトは、生放送にコメンテーターを挿入するのに最適。ウェブカムと同様に機能するUSB出力を搭載しているので、あらゆるビデオソフトウェアに接続可能。導入コストを低く抑えたい方にはおすすめのプロダクトです。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design ATEM Mini Pro
販売価格:¥ 73,150(本体価格:¥ 66,500)
ATEM Mini Proで追加される機能は「本体からインターネットへのダイレクト配信」「マルチモニタービュー」「プログラム出力の外部SSDへの収録」の3つ。本記事の主旨に則ってオーディオクオリティを優先すると、ダイレクト配信機能は使用する機会がないため、各カメラの映像を確認しながらスイッチングをしたい、または、配信した動画を高品質で取っておきたいのいずれかに該当する場合はこちらを選択することになる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
販売価格:¥ 113,850(本体価格:¥ 103,500)
ATEM Mini Pro ISOで追加される機能は、ATEM Mini Proの全機能に加え、「全HDMI入出力信号を外部SSDに個別に保存」「スイッチングを施したタイミングをDaVinci Resolveで読み込めるマーカーの記録」の2つ。あとから映像を手直ししたり再編集したりしたい場合にはこちらを選択することになる。アーカイブ映像として公開する前に、本番中に操作を誤ってしまった部分を修正したり、リアルタイムで無料配信したライブを編集し後日有償で販売する、といったことが可能になる。
Rock oN Line eStoreでのご購入はこちらから>>
Rock oN Line eStoreに特設コーナーが誕生!
Rock oN Line eStoreでは、カメラからスイッチャー、配信や収録向けのマイクなど、映像制作に関わる機材を集めた特設コーナーを新設している。本記事に挙げた個別の機材が購入できるのはもちろん、手軽なセット販売や、スタッフに相談できる問い合わせフォームなどもあるので、ぜひ覗いてみてほしい。
eStore特設コーナーへ!!>>
Media
2020/11/11
加速度的に進む普及、ATEM Mini Proが配信を面白くする
ATEM Mini Pro 価格:¥74,778(税込)
いま、注目を集めているのはオンライン・コラボレーションだけではない。音楽ライブ、ゲーム、セミナーなどの配信、特にリアルタイム配信の分野もまた、大きな注目を集め始めている。ここでは、そうしたライブ配信のクオリティアップを手軽に実現できるプロダクトとしてBlackmagic Design ATEM Mini Proを取り上げたい。
スイッチャーの導入で配信をもっと面白く
冒頭に述べたように、オンラインでのコミュニケーションを行う機会が格段に増えている。以前からゲームプレイの中継配信などがメディアにも取り上げらることが多かったが、ここのところではライブを中心に活動していたミュージシャンやライブハウスが新たにライブ配信に参入するケースも出てきた。もちろん普段の生活の中でもオンラインでのセミナー(所謂ウェビナー)や講義・レッスン、さらにはプレゼンの機会も多くなっているだろう。
その音楽ライブの配信は言うまでもなく、ゲーム中継やセミナー、会議やプレゼンでも、ふたつ以上の映像を配信できた方が表現の幅が広がり、視聴者や参加者により多くの事柄を伝えることができる。演奏の様子を配信する場面では、引きと寄りのアングルを切り替えた方が臨場感が増すし、音楽レッスンならフォーム全体と手元のクローズ映像が同時に見られた方がより分かりやすい。講義やプレゼンではメインの資料を大きく映しておいて、ピクチャインピクチャで講師の顔を映しておく、補足資料や参考URLなどを別PCで用意しておく、プロダクトをカメラで撮ってプレゼンする、など使い方を少し思い起こすだけでも数多くの手法が広がることになる。
こうしたニーズを満たすのがビデオスイッチャーと呼ばれるプロダクトになるのだが、現在、市場で見かけるスイッチャーのほとんどは業務用にデザインされたものになっている。サイズの大きいものが多く、また様々な機能が使用できる分だけ一見すると操作方法が分かりにくい場合もある。さらに、入出力もSDI接続である場合がほとんどであり、家庭向けのカメラとの使用には向いていない。そして何より高額だ。
しかし、昨年秋に発表されたBlackmagic Design ATEM Miniは、放送用のトランジションやビデオエフェクト機能を備えた4系統HDMI入力対応のスイッチャーでありながら、税込定価¥40,000を切るプロダクトとして大きな話題を呼んだ。今回紹介するATEM Mini Proは新たに発売された上位版にあたるプロダクトであり、ATME Mini にさらに機能を追加し、業務用途にも耐える仕上がりとなっている。どのような映像を配信したいかは個別のニーズがあるが、インターネットへマルチカムでの映像配信を検討中の方は必見のプロダクトだ。以下で、ATEM Mini、ATEM Mini Proのアドバンテージを概観していきたい。
HDMI 4系統に特化した映像入力
まず、ATEM Miniシリーズが手軽なソリューションである大きな理由は、HDMI 4系統のみというシンプルな入力であることだ。その他の入力系統を大胆に省略し、多くの家庭用カメラが対応するHDMIに接続を特化することで、十分な入力数を確保しながらコンパクトなサイズを実現している。これは、業務用カメラやSDI変換などの高額な機器が不要であるという点で、システム全体の導入費用を大幅に下げることにも貢献する。
外部オーディオ入力端子としてふたつのステレオミニジャックを備えているため、ダイナミックマイクを接続することも可能。画角との兼ね合いでカメラからのオーディオが使用しにくい場合でも、クリアな音質を確保することができる。2020年6月のアップデートで、コントロールソフトウェアで外部からのオーディオ入力にディレイを掛ける機能が追加され、画・音のずれを修正することも可能になった。
システムをコンパクトに
さらに、ATEM Miniシリーズの利点として配信システムに必要なデバイスの数を減らすことができるという点も挙げられる。スイッチャーを中心としてマルチカム配信システムの構成をざっくりと考えると、カメラやMac/PCなどの映像入力機器、スイッチャー、信号を配信に向いたコーデックにエンコードするキャプチャー/WEBキャスター、配信アプリケーションのインストールされたMac/PC、となる。
ATEM Miniはこのうち、スイッチャーとキャプチャーの機能を併せ持っている。Mac/PCからウェブカムとして認識されるため、配信用のMac/PCに接続すればそのままYouTube LiveといったCDNに映像をストリーミングすることができるのだ。それだけでなく、SkypeやZoomなどのコミュニケーションツールからもカメラ入力として認識されるため、会議やプレゼン、オンライン講義などでも簡単に使用することができる。上位機種のATEM Mini Proはこれに加えて、配信アプリケーションの機能も備えている。システムを構成するデバイスを削減できるということは、コスト面でのメリットとなるだけでなく、機材を持ち込んでの配信や、システムが常設でない場合などに、運搬・組み上げの手間が省略できるというアドバンテージがある。
ATEM Miniは図のようにスイッチャー、キャプチャーをひとまとめにした機能を持っているが、上位版のATEM Mini Proではさらに配信環境までカバーする範囲が広がる。まさにオールインワンの配信システムと言える内容だ。
つなぐだけ派にも、プロユースにも
デフォルトの設定では、ATEM Mini / ATEM Mini Proは4系統のHDMIに入力された信号を自動で変換してくれる。つまり、面倒な設定なしでカメラをつなぐだけで「とりあえず画は出る」ということだ。
しかし、ATEM シリーズに無償で同梱される「ATEM Software Control」は、これだけで記事がひとつ書けてしまうほど多機能で、クオリティにとことんこだわりたい場合はこちらから詳細な設定やコントロールを行うことも可能。スイッチングやオーディオレベルの操作は本体のパネルからも行うことができるが、コントロールソフトウェアを使用すれば、さらに追い込んだ操作を行うことが可能になる。このATEM Software Controlの各機能はDaVinci Resolveで培われた技術を使用しているため、オーディオ/ビデオ・エフェクトやメディア管理など、業務レベルに耐えるクオリティの仕上がりになっている。
しかも、ATEM Software Controlはネットワークを介して本体と接続できるため、離れた場所からのスイッチャー操作も可能。HDMIは長尺ケーブルを使用するのがためらわれるが、この機能を使用すればカメラ位置に左右されずにオペレーションするスペースを確保することができる。さらに、同時に複数のATEM Software ControlからひとつのATEM Mini / ATEM Mini Proにアクセスできるため、スイッチング / カメラ補正 / オーディオミキシング、など、役割ごとにオペレーターをつけるというプロフェッショナルな体制を取ることまでできてしまう。
ATEM Software Controlのコントロール画面。なお、オーディオパネルはMackie Control、KORG NanoKontrol、iCON Platform M+などの外部コントローラーに対応している。スペースに余裕が生まれた分、こうした機材を導入して音のクオリティアップで差をつけるのも面白いだろう。
ATME Mini VS ATEM Mini Pro
●CDNにダイレクトにストリーミング
ATEM MiniとATEM Mini Proのもっとも大きな違いと言えるのが、ATEM Mini Proでは本体を有線でインターネットにつなげば、ダイレクトにCDNに映像をストリーミングすることができるということだ。もちろん、ストリーミングキーを入力してやるためのMac/PCは必要になるが、一度キーを設定してしまえば本体から取り外しても問題ない。手元のスペースを節約できるだけでなく、安定した配信を行うためにスペックの高いMac/PCを新たに購入する必要がなくなるし、ストリーミングのように安定度が求められる部分をハードウェアに任せることができるのは大きな安心だ。省スペース、低コスト、高い信頼性、と、この機能の実装によって得られるメリットは非常に大きいのではないだろうか。ライブハウスなどによるビジネス用途ならATEM Mini Pro、すでに十分に高いスペックのマシンを所有しているならATEM Miniと、既存の環境に応じてチョイスするとよいのではないだろうか。
●マルチビュー対応
こちらもパワフルな機能。ATEM Mini ProにはHDMI出力が1系統しか搭載されていないが、一画面で全ての入力ソース、メディアプレイヤー、オーディオとON AIRのステータスを確認することができる。各モニターはタリーインジケーターを表示可能で、どのソースがオンエアされ、次にどのソースへトランジットするかを確認することができる。プレビュー機能も備えており、M/Eがどのようにかかるのかを事前に確認することも可能だ。これらすべてを一画面でモニターできるというコンパクトさと取り回しのよさは、まさに"Pro"という名にふさわしい機能追加と言えるだろう。
●外部デバイスへプログラムをレコーディング
ATEM Mini Proは、プログラムをH.264ビデオファイルとしてUSBフラッシュディスクにダイレクトに記録することができる。しかも、USBハブやBlackmagic Design MultiDockなどのプロダクトを使用すると、複数ディスクへの収録にも対応可能だ。ひとつのディスクがフルになると、自動で次のディスクに移行することで、長時間のストリーミングでも継続した収録を行うことができる。YouTube LiveやFacbook LiveではWEB上にアーカイブを残すことが可能だが、プログラムをその場で手元にメディアとして持っていられることは、ほかの場所で使用することなどを考えると大きなメリットとなるだろう。
実際の自宅からの簡易的な配信を想定したシステム例。ATEM Mini Proで取りまとめさえすれば配信への道は簡単に開けてしまう。音声の面でも48Vファンタム対応の小型ミキサーを使用すればコンデンサーマイクを使用することができる。HDMIアダプタを使用して、スマートフォンやタブレットをカメラ代わりに使うことも可能。別途、配信用のMac/PCを用意すれば、複数の配信サイトにマルチキャストすることもできる。
にわかに活況を呈するコンパクトビデオスイッチャーの世界。小さなスペースで使用でき、持ち運びや設置・バラシも手軽な上に、マルチカメラでの配信をフルHD画質で行うことを可能にするコンパクトスイッチャーをシステムの中心に据えることで、スマホ配信とは別次元のクオリティで映像配信を行うことが可能となる。特にATEM Mini / ATEM Mini Proを使用すれば、ほんの何本かのケーブルを繋ぐだけで、高品質な配信が始められてしまう。ぜひ、多くの方に触れてみてほしいプロダクトだ。
*ProceedMagazine2020号より転載
Media
2020/10/27
On Premise Server パーソナルなオンプレサーバーで大容量制作をハンドリング
Internetの発達に伴って進化を続けている様々なCloudベースのサービス。その一方で、コスト面も含めて個人の自宅でも導入できるサイズの製品も着実な進化を遂げているのがOn Premise(オン・プレミス=敷地内で)のサーバーソリューション。Cloudのように年額、月額で提供されるサービスと比較するとどのようなメリットがあるのか、オンプレのサーバーはNetwork上からどう活かされるのか、オンラインでの協業体制が求められる今だからこそパーソナルユースを視野に入れたエントリーレベルにおけるオンプレサーバー導入のいまを見ていきたい。
Synology Home Server
今回、取り上げる製品はSynology社のホームサーバー。ラインナップは1Drive(HDD1台)のコンパクトな製品からスタートし、1DriveでHDD無しのベアボーンが1万円前半の価格から入手できる。何かと敷居の高いサーバーソリューションの中でも、パーソナル領域におけるラインナップを充実させているメーカーだ。このホームサーバーの主な役割は、ローカルネットワーク上でのファイル共有サービス(NAS機能)と、Internetに接続されたどこからでもアクセス可能なOn Premiseファイル・サーバーということに集約される。
もちろんそれ以外にも、遠隔地に設置されたSynology製品同士での自動同期や、プライベートな音楽/動画配信サーバー機能、ファイルのバージョニング機能、誤って消去してしまったファイルの復元機能など多彩な機能を持ち、ローカルでのファイル共有に関しては汎用のNAS製品と同様に、Windows向けのSMB/NFS共有、MacOS向けのSMB/AFS共有が可能と、それぞれOSの持つ標準機能でアクセスができるシンプルな形式を持つのだが、今回はこのようなローカル環境でのサービスではなく、外出先でも活用ができるサービスに目を向けたい。
Synologyの設定画面。ブラウザでアクセスするとOSライクなGUIで操作できる。
コスト優位が際立つオンプレ
外出先で、サーバー上のデータを取り出せるサービスといえば、DropBox、OneDriveなどのCloudストレージサービスが思い浮かぶ。Synologyの提供するサービスは、一般向けにもサービスの提供されているCloudストレージと比較してどのような違いがあるのだろうか?
まず、SynologyのようなOn Premiseでのサービスの最大のメリットは、容量の大きさにあるだろう。本原稿の執筆時点で一般向けに入手できる最大容量のHDDは16TB。コスト的にこなれてきている8TBのモデルは2万円を切る価格帯で販売されている。これは1TBあたりの単価は¥2,000を切る水準となっており、容量単価のバランスも納得いくレベルなのではないだろうか。
これをCloud Stroageの代表格であるDropBoxで見てみると、1TBの容量が使える有償サービスは年額¥12,000となる。もちろん、機器の購入費用が必要ない、壊れるという心配がない、電気代も必要ない、などCloudのメリットを考えればそのままの比較はできないが、8TBという容量を持つ外出先から接続可能なOn Premiseサーバーの構築が4万円弱の初期投資で行えるということは、コストパフォーマンスが非常に高いと言えるだろう。また、4Drive全てに8TBのHDDを実装しRAID 5の構成を組んだとすれば、実効容量24TBという巨大な容量をNetwork越しに共有することが可能となる。大容量をコストバランスよく実現するという側面をフォーカスすると、On Premiseのメリットが際立ってくる。
利用している帯域など、ステータスもリアルタイムに監視が可能だ。
オンプレの抱える課題とは
このように単純に価格で考えれば、HDDの容量単価の低下が大きく影響するOn Premiseの製品のコストパフォーマンスは非常に高いものがある。その一方で、On Premiseが抱えるデメリットがあることも事実。例えばCloudサービスであれば、データはセキュリティーや防災対策などが万全になされたデータセンターに格納される。データの安全性を考えると自宅に設置された機器との差は非常に大きなものになるだろう。もちろん、Synologyの製品も2Drive以上の製品であればRAIDを構築することができるため、データの保全に対しての対策を構築することも可能だが、これは導入コストとトレードオフの関係になる。実例を考えると、ストレージの速度とデータの保全を両立したRAID 5以上を構築しようとした際には3 Drive以上の製品が必要。製品としては4Drive以上の製品に最低3台以上のHDDを実装する必要があり、初期導入コストは8万円程度が見込まれる。1TB程度の容量までで必要量が足りるのであれば、Cloudサービスの方に軍配があがるケースもある。必要な容量をどう捉えるかが肝要な部分だ。
また、On Premiseの製品は手元にあるために、突如のトラブルに対しては非常に脆弱と言わざるを得ない。前述のようにデータセンターとは比較にならない環境的な要因ではあるが、2〜3年おきにしっかりと機器の更新を行うことで、そういったリスクを低減することはできる。そのデータはどれくらいの期間の保持が必須なのか、重要性はどれほどのものなのか、保全体制に対しての理解をしっかりと持つことで、大容量のデータの共有運用が見えてくる。
オンプレをNetworkから使う
パッケージセンターには数多くのアプリケーションが用意されている。
Synology社のOn Premiseサーバーは、専用のアプリをインストールすることでInternet接続環境があればどこからでも自宅に設置されたサーバーのデータを取り出すことができる。また、DropBoxのサービスのように常時同期をさせることもできれば、特定のフォルダーを第三者へ共有リンクを送り公開する、といった様々なサービスを活用できる。設定もWebブラウザ上からGUIを使うシンプルなオペレーションとなっており、設定も極めて簡便。VPNを使用するというような特別なこともないため、迷うことなく自宅のサーバーからファイル共有を行うことが行えてしまう。ユーザーの専門知識を求めずに運用が可能な水準にまで製品の完成度は高まっていると言えそうだ。
ファイル共有のあり方は多様になっており、ユーザーの必要な条件に合わせてOn Premise、Cloudと使い分けることができるようになってきている。むしろ選択肢は多彩とも言える状況で、メリット、デメリットをしっかりと理解し、どれくらいのデータ量をハンドリングしたいのか、そのデータの重要性をどう考えるか、ユーザーの適切な判断があれば充実したパーソナルサーバー環境はすぐにでも構築、実現できてしまう。今後、ますます大容量となるコンテンツ制作のデータをどう扱えるのかは、パーソナルな制作環境にとっても重要な要素であることは間違いないだろう。それをどのようにハンドリングするかの鍵はここにもありそうだ。
*ProceedMagazine2020号より転載
Media
2020/09/24
Macのワークステーションが今後を”創る” 〜Apple Mac Pro Late2019〜
目次
序論
Apple Mac Pro Late2019概要
Mac Pro Late2019の各構成部品:CPU
Mac Pro Late2019の各構成部品:メモリ
Mac Pro Late2019の各構成部品:PCI Express拡張スロット
Mac Pro Late2019の各構成部品:GPU
Mac Pro Late2019の各構成部品:AfterBurner
考察
1:序論
各業界で注目を集めたApple Mac Pro Late2019は2019年6月に発表、同年12月より発売が開始された。同社CEO Tim Cook氏はWWDC2019の基調講演で「これまでに開発した中で最も強力なMac」と語り「すべてを変えるパワー」と広告される本機種。その驚異的なマシンスペックと拡張性などの紹介から前機種との比較などを通し、Macのワークステーションが作り得る未来への可能性を紐解いていく。
2:Apple Mac Pro Late2019概要
<↑クリックして拡大>
発表当初より、Apple Mac Pro Late2019は注目度も高く、既に発売されているためデザイン面など基本的な情報は皆さんご存知であろう。たださすがにMac Proの最新モデルともあり、オプションも多岐に渡るため構成部品とそのカスタマイズ域についてを別表にまとめるのでご確認いただきたい。また「これまでに開発した中で最も強力なMac」「すべてを変えるパワー」と称されるMac Pro Late2019だが、比較対象に直近3モデル:Mid2012・Late2013・Late2019を取り上げ、CPU / メモリ / GPU / ストレージ、周辺機器との接続性なども同様に別表に掲載する。それでは、次から各構成部品の紹介に移り、Mac Pro Late2019の内容を確認していく。
<↑クリックして拡大>
【特記事項】
・min maxの値:Apple公表値を基準とする。メモリなど3rdパーティー製品による最大値は無視する。
・CPU/GPU:モデル名を表記する。比較はベンチマークで行い後述する。
・メモリ/ストレージ:モデル名は表記せず、容量/動作周波数、容量/PCIe規格といった数値表記とする。
・数値の表記:比較を用意にする為、単位を揃える。(メモリ:GB、ストレージ:TB)
3:Mac Pro Late2019の各構成部品:CPU
Apple HPの広告で搭載CPUについては、”最大28コアのパワー。制限なく作業できます。”と称されている。このモデルではMac史上最多の最大28コアを搭載したIntel XeonWプロセッサを採用、8coreから28coreまで、5つのプロセッサをラインナップしたため、ニーズに合わせた性能を手に入れることができるようになった。CPUはコンピュータの制御や演算や情報転送をつかさどる中枢部分であるが、直近3モデル(Mid2012/Late2013/Late2019)のCPUパフォーマンスを比較し、その実力を見ていく。まずは以下のグラフをご覧いただこう。
図1. Mac Pro CPU(Multi-core)ベンチマーク比較
こちらのグラフは、モデルごとのCPUベンチマーク比較である。横軸左から、Mid2012(青)→Late2013(緑)→Late2019(オレンジ)と並び、各モデルの最低CPUと最高CPUにおける、マルチコアのベンチマーク値を縦軸に示した。ベンチマーク値はGeekBenchで公開されるデータをソースとしている。Late2019の最低CPUの値に注目しラインを引くと、旧モデル最高CPUの値をも超えていることがわかる。たとえ、Late2019で最低のCPUを選んだとしても、旧MacPROの性能を全て超えていくということだ。決して誇大広告でなく、「これまでに開発した中で最も強力なMac」と称される理由の一つだと分かる。数値で示すと以下表になる。参考までに、Single-Coreのベンチマーク値も掲載する。
表3. Late2019/最低CPU と 旧モデル/最高CPUのベンチマーク値
次に、Late2019最大値にもラインを引き、Late2019最低値との差分に注目する。この差分が意味するのは、ユーザーが選択できる”性能幅”である。ユーザーはこの範囲の中から自らの環境に合わせてMacPROをコーディネートしていくことになる。視覚的にも分かる通り、Late2013と比べても圧倒的に性能の選択幅が広くなっている事が分かる。
図2. Mac Pro Late2019 ベンチマーク性能幅
数値を示すと以下のようになる。Late2013と比較すると、約3倍もの性能選択幅があることが分かる。
表4. 性能選択余地の遷移
以上の比較から、旧MacProから乗り換える場合、”Late2019を買えばCPU性能が必ず向上する”ということが分かった。しかし、性能幅も広がった為、新たにLate2019を検討する方は自分に合うCPUを選択する必要がある。Late2013よりも長期的運用が可能だと噂され、CPUが動作速度の根幹であることを考えると、Mac Pro Late2019のCPUは少しオーバースペックなものを選択しても良いかもしれない。参考までに、現行MacのCPU性能比較もご覧いただきたい。なお、現行モデルの比較対象として以下モデルを追加した。iMac Pro Late 2017 / Mac mini Late 2018 / iMac 21.5inch Early 2019 / iMac 27inch Early 2019 / Mac Book Pro 16inch Late 2019(ノート型の参考)
図3. 現行MacとMacPro Late2019との比較
<↑クリックして拡大>
このグラフで注目するのは、Late2019のCPU最低値と16core XeonWの値である。まず、CPU最低値に注目すると、iMacのCPU値と交差することが分かる。また、16core XeonWの値に注目すると交差するCPUが存在しなくなることが分かる。故に、現行モデル以上の性能を求め、他にない性能を実現するには16core XeonW以上の選択が必要となる。また、ワークステーション/PCの性能はCPUのみで決まることではないので、購入の際にはメモリ、GPUや拡張性なども十分考慮していただきたい。
4:Mac Pro Late2019の各構成部品:メモリ
Apple HPの広告でメモリについては、"あなたが知っているメモリは、昨日のメモリです。”と称されている。ユーザーがアクセスできる12の物理的なDIMMスロットを搭載し、プロセッサと互換性のあるメモリであれば、将来的なアップグレードも可能だ。Mac Pro Late2019ではR-DIMMとLR-DIMMのメモリモジュールに対応しているが、同じシステムで2種類のDIMMを使うことはできないので容量追加には注意が必要である。LR-DIMM対応のCPU(24core以上のXeonW)を選択した場合、最大1.5TBの容量を実現する。
ワークステーション/PCの”作業机”と訳される事も多いメモリ。データやプログラムを一時的に記憶する部品であるが、CPU同様に直近3モデルと比較していく。まずは最小構成、最大構成の2種類のグラフをご覧いただこう。
図4. MacPro:メモリ最小構成での比較
図5. MacPro:メモリ最大構成での比較
表5.MacPro:メモリ最小構成での比較
表6.MacPro:メモリ最大構成での比較
横軸はCPU同様、Mac Pro Mid2012/Late2013/Late2019を並べている。縦軸左側はメモリ容量値で青棒グラフで示し、右側は動作周波数をオレンジ丸で示している。図4.最小構成のグラフに注目しメモリ容量を比較すると、おおよそモデル毎に倍々の推移が見られる。また、動作周波数に関しては2次曲線的推移が見られる。モデルの発展とともに、部品としての性能も格段に上がってきている事が分かる。図5.最大構成のグラフに関しては一目瞭然ではあるが、表6.最大構成のLate2019、メモリ容量の前モデル比に注目すると23.44という驚異的な数値を叩く。これもまた、「これまでに開発した中で最も強力なMac」と称される理由の一つだと分かる。
さて、購入検討時のメモリ問題であるが、こちらは後ほどアップグレードできる為、初めは低容量から導入し、足りなければ随時追加という方式が取れる。メモリで浮いた金額をCPUへ割り当てるという判断もできるため、予算を抑えながら導入も可能だ。ただし、CPUによるメモリ容量の搭載上限が決まり、メモリモジュールを合わせる事を念頭に入れ検討する事が重要だ。
5:Mac Pro Late2019の各構成部品:PCI Express拡張スロット
Mac Pro Late2019ではCPUの性能幅やメモリの拡張性に加え、8つのPCI Express拡張スロットの搭載が可能になった。Avid HDX Card や Universal Audio UAD-2 PCIe Cardを搭載してオーディオプロセスを拡張するも良し、加えて、GPU / AfterBurner(後述) / キャプチャボードを搭載し、グラフィック面を拡張しても良い。まさに、クリエイティブなユーザーの思いのままに、Mac Proの拡張が可能になったと言える。さらに、Mac Pro Mid2012と比べるとスロット数が倍になっていることから、PCIeによる機能拡張においても「これまでに開発した中で最も強力なMac」であると分かる。
写真を参考に、搭載可能なPCIeについて確認していこう。上から順に、ハーフレングススロット、シングルワイドスロット、ダブルワイドスロットと並ぶ。下から順に、スロットNo.が1-8までカウントされる。
それでは各種のスロットについて見ていこう。
○ハーフレングススロット:No.8
スロットNo.8には最大 x4 レーンのPCIeカードが搭載可能。ここには標準仕様でApple I/Oカードが既に搭載されており、Thunderbolt 3ポート× 2、USB-Aポート× 2、3.5mm ヘッドフォンジャック× 1を備える。このI/Oカードを取り外して他のハーフレングスPCIeカードに取り替えることもできるが、別のスロットに取り付けることはできないので、変更を検討する場合には注意が必要だ。
○シングルワイドスロット:No.5-7
スロットNo.5には最大 x16レーン、No.6-7には最大 ×8レーンのPCIeカードが搭載可能。スロットNo.5の最大 ×16レーンには、AfterBurnerはに取り付けることが推奨される。後述のGPUとの連携からであろうが、他カードとの兼ね合いから、AfterburnerをNo.5に取り付けられない場合は、後述のスロットNo.3へ、No.3とNo.5が埋まっている場合はスロット4へ取り付けると良い。
○ダブルワイドスロット:No.1-4
スロットNo.1,3,4には最大 x16レーン、No.2には最大 x8レーンのPCIeカードが搭載可能。スロットNo.1、No.4は2列に渡ってPCIeが羅列しているが、これは後述するApple独自のMPX Moduleを搭載する為のレーンになる。MPXモジュール以外で使用する場合は、最大 x16レーンのPCIeスロットとして使用できる。
6:Mac Pro Late2019の各構成部品:GPU
Apple HPの広告でGPUについては、"究極のパフォーマンスを設計しました。”と表現されている。業界初、MPX Module(Mac Pro Expansion Module)が搭載され、業界標準のPCI Expressのコネクタに1つPCIeレーンを加えThunderboltが統合された。また、高パフォーマンスでの動作のため、供給電力を500Wまで増やし、専用スロットによる効率的な冷却を実現している。500Wというと、一般的な冷蔵庫を駆動させたり、小型洗濯機を回したり、炊飯器でご飯を炊けたりしてしまう。また、Mac Pro Late2013の消費電力とほぼ同等である為、相当な量であるとイメージできる。話が逸れたが、GPUに関してもCPU同様に前モデルと比較していく。
図6. MacPro:GPU最小/最大での比較
こちらのグラフは、モデルごとのCPUベンチマーク比較である。横軸左から、Mid2012(青)→Late2013(緑)→Late2019(オレンジ)と並び、各モデルの最低GPUと最高GPUにおける、マルチコアのベンチマーク値を縦軸に示した。ベンチマーク値はGeekBenchで公開されるデータをソースとしているが、Mid2012に関しては有効なベンチマークを取得できなかった為、GPUに関してはLate2013との比較になる。また、AMD VegaⅡDuoは2機搭載だが、この値は単発AMD VegaⅡDuoの値となる。
表7.MacPro:GPU最小部品での比較
表8.MacPro:GPU最大部品での比較
部品単体であっても、前モデルからは最小でも2倍、最大では3倍のパフォーマンスを誇る。最大部品である。AMD Radeon Pro VegaⅡDuoはさらにもう一枚追加できるため、グラフィックの分野でも十分驚異的なスペックが実現できると言える。これも「これまでに開発した中で最も強力なMac」と称される理由の一つとなる。
7:Mac Pro Late2019の各構成部品:AfterBurner
Afterburnerとは、ProRes/Pro Res RAW ビデオファイルのマルチストリームのデコードや再生を高速化するハードウェアアクセラレータカードである。まず、AfterBurnerを導入するメリットを振り返ろう。ProRes や ProRes RAW のマルチストリームを8Kなどの解像度で再生するための演算をこのAfterBurnerに任せられる。逆にない場合、Mac Pro Late2019のCPUで演算を行うため、その負担分が編集作業に回せなくなってしまう。AfterBurnerによる外部演算を取り入れることによりCPUでは他の処理や映像エフェクトの演算に注力できる為、より複雑な3D、映像編集が可能となる。また、ProRes および ProRes RAW のプロジェクトやファイルのトランスコードおよび、共有が高速化する事もメリットの一つである。
AfterBurnerの対応するアプリケーションは、"ProRes または ProRes RAW のファイルを再生するApple製のアプリケーション”である。例えば、Final Cut Pro X、Motion、Compressor、QuickTime Player などで使用可能だ。その他、他社製のアプリが気になるところだが、"他社製の App のデベロッパが、Afterburner のサポートを組み込むことは可能”とのことなので、今後の対応に期待したい。
8:考察
Mac Pro Late2019の登場により、従来のMacからは考えられないようなスペックでワークステーションを導入する事が可能になったが、ハイスペックかつ消費電力も高いため、初期投資およびランニングコストも大きくかかってしまうというリスクもある。しかし、クリエイティブ以外に時間を割いていると感じているならば朗報である。例えば、レンダリング、プロキシファイル変換、変換によって生じるファイルマネジメントなどなど。Mac Pro Late2019の性能は、作品を完成させるまでの待機時間や面倒な時間を圧倒的に減らし、ユーザーのクリエイティブな時間をより多く提供してくれると考える。
従来機よりも早く仕事を終わらせ、次の仕事に取り掛かる、それを終えたらまた次の新しい仕事へと取り掛かる。サイクルの早い循環、クオリティの向上が、他者との差別化に繋がっていく。初期投資、ランニングコストなど懸念点も多いが、その分クリエイティブで勝負して稼いでいく、というスタイルへMac Pro Late2019が導いてくれるかもしれない。これからの時代の働き方を変え、クリエイティブ制作に革新が起きることを期待している。
*ProceedMagazine2020号より転載
Media
2020/08/19
株式会社ミクシィ 様 / 新たな価値は「コミュニケーションが生まれる」空間のなかに
都内5拠点に分かれていたグループ内の各オフィスを集約させ、2020年3月より渋谷スクランブルスクエアでの稼働を開始した株式会社ミクシィ。渋谷の新たなランドマークともなるこの最先端のオフィスビル内にサウンドグループのコンテンツ収録や、制作プロジェクトにおける外部連携のコミニュティの場を設けるべく、この機に合わせて新たなスタジオが完成した。オフィス移転によるサウンドグループの移転だけでもプランニングは膨大な労力を伴うものとなるが、加えて高層オフィスビルへのスタジオ新設という側面や、何より同社らしいコミュニケーションというキーワードがどのようにスタジオプランに反映されたのか見ていきたい。
スタジオの特色を産み出した決断
これまで、青山学院にもほど近い渋谷ファーストタワーに拠点を置いていたサウンドグループ。そこにも自社スタジオはあり、主にナレーション録りを中心とした作業を行うスペースとなっていた。もちろん、コンテンツ制作を念頭に置いた自社で備えるスタジオとしては十分に考えられた設備が整っていたが、あくまでオフィス内のスペースでありミックスを形にするという設計ではなかった。また、コンテンツ制作には演者、クリエイターからディレクター、企画担当者など社内だけでも多数の関係者が存在するため、スタジオでいかにコミュニケーションを円滑に進められるか、ということは制作進行にとって重要な課題となっていた。そこへ、各所に分散していたオフィスの集約プランが浮上する。
新しいオフィスは当時建設中であった渋谷スクランブルスクエア、その高層階にサウンドグループのスペースが割り当てられる。そもそも全社のオフィス機能集約となるため、移転計画の最初からフロアにおけるスペース位置、間取り、ドアや壁面といった要素はあらかじめ決められていたものであり、高層ビルにおける消防法の制約もあったそうだ。例えば、スタジオ壁に木材が貼られているように見えるが、実はこちらは木目のシートとなっている。壁面に固定された可燃物は使用できないための対応だが、質感や部屋の暖かさもしっかり演出されている。取材の最後に明かされるまで我々も気がつかなかったほどだ。
そして、今回スタジオ向けに用意されたのは大小の2スペース。そもそもにどちらの部屋をコントロールルームとするのか、またその向きは縦長なのか横長なのか、制約ある条件のもと安井氏と岡田氏が試行錯誤を繰り返す中で着眼したのは"コミニュケーション”という課題。
ミクシィ社としてこのスタジオがどうあるべきか、どういう価値を出すのが正しいのか。専属エンジニアがいる商業スタジオではない、コミュニケーションが生まれる環境とはどのようなものなのか。これにマッチすることを突き詰めて考えた結果、レコーディングブースの方を広くとる設計になり、また当初縦長で進めていたコントロールルームの設計も思い切って横長レイアウトに変えたそうだ。もちろん、音響的な解決を機材面や吸音で行う必要もあれば、ブース窓の位置やテレビの高さ、モニタースピーカーの配置など課題は数多くなったが、これをクリアしていくのも楽しみの一つだったという。そしてこれらのポイントの解決に芯を通したのが"コミニュケーション”が如何にいい形で取れるか、ということ。このレイアウト段階での決断がスタジオを特色あるものにしたのではないだろうか。
音でのコミュニケーションを促進させる最初のツール
前述の通り、こちらは商業スタジオではなくミクシィ社でのプロジェクトにおける制作拠点、またその外部との連携に利用できるスペースとして機能している。自社コンテンツでのボイス・ボーカル収録はもちろんのこと、同フロアにある撮影スタジオとも協業で、自社タレントとユーチューバーの楽曲カバーコラボレーション企画のPV制作や、渋谷公園通りにあるXFLAGストアでのインストアライブの配信コンテンツミックスなどがすでに行われており、多種多様なコンテンツの制作がすでにこちらで実現され始めている状況だ。企画案件の規模によってはクリエイターのワークスペースで完結できるものもあるが、このようなプロジェクトで多くの関係者との共同作業を可能にする拠点、というのが今回のスタジオに求められている要件でもある。社外のクリエイターが来てもすぐに使えるような機材・システム選定を念頭に置き、またそこから「コミュニケーションが生まれる」ような環境をどのように整えたのだろうか。それを一番現しているのがアナログミキサーであるSSL X-DESKの導入だ。
コントロールルームの特注デスクにはPro ToolsのIn the boxミキシング用にAvid Artist MixとアナログミキサーのX-DESKが綺麗に収められている。X-DESKにはAvid MTRXから出力された信号、また入力に対しての信号、さらにレコーディングルームからの信号と、コントロールルームに設置されているマイクプリなど様々なソースに対して臨機応変に対応でき、使用するスタッフによって自由に組み替えが可能になっている。ただしデフォルトの設定はシンプルで、基本的にはマイクプリから来ているマイクの信号と、外部入力(iPhoneやPC上の再生)がミキサーに立ち上がっており、内外問わずどんなスタッフでも簡単に作業を始めることができる仕様だ。
これは現場での作業を想定した際に、ギターでボーカルのニュアンスを伝えたいクリエイターもいれば、ブースでボーカリストの横に入ってディレクションするケースであったり、Co-Write(共作)で作業を行う場合など、共同作業がすぐに始めて立ち上げられて、バランスまで取れる環境を考えるとアナログの方が有利という判断。「音でのコミュニケーションを促進させる最初のツール」がアナログミキサーだということだ。
また、デスク左側にはMac miniを中心としたサブシステムが用意されている。こちらのMac miniにはNuendo/Cubaseもインストール、そのインターフェイスとなるRME Fireface UFX II も左側を向けてラッキング。これも来訪者がすぐさま使用開始できるように配慮されている部分だ。
セレクトされたコミュニケーションでの実用性
それでは、デスク右側のラックに目を向けたい。ラックの中でも特に存在感を放っているのが新型のMacProだ。2019年の夏頃から本格的にスタジオの設計を固め、機材選定も大方定まったところで中々導入時期を読めなかったのがこちらのMacPro。周知の通りで2019年末に突如として姿を現すことになったわけだが、このスタジオに導入されたのは、必須となるレコーディング作業だけに限らず、映像の編集も難なくこなせるであろう3.3GHz 12Core、96GBメモリ、SSD 2TBというスペック構成のもの。レンダリングが数多く走るなど負荷がかかる場面はまだあまりないようだが、意外にもその動作はかなり静粛とのことだ。
このラックではMac Proを筆頭に、ビデオ入力、出力の分配を担うBlack Magic Design SmartVideoHub。そしてAvid HDXからMTRXにつながり、MTRXからX-Deskや、各々ルーティングを細く設定できるバンタムパッチベイがある。Ferrofish PULSE16はMTRXからのDANTE Optionを有効活用し、ADATへ変換されBEHRINGER POWERPLAY16(CUE BOX)に繋がれている。その上にはAvid Sync HDがあり、マスタークロックとしてAntelope Audio Trinityがトップ段に設置されている。
また、モニタースピーカーについてはRock oN渋谷店舗にて十数のモニタースピーカーが比較試聴され、KS digital C8 Reference Rosewood(後に同社製のサブウーファーも導入)とAmphion One18が選ばれた。こちらは横長にしたコントロールルームのレイアウトを考慮してニアフィールドにスイートスポットがくる同軸のKS digitalと、バランスを重視してのAmphionというセレクトとなった。使用するスタッフによってナレーションでのボイスの部分にフォーカスしたり、あるいは楽曲全体を聴く必要があるなど、用途は制作内容によってそれぞれとなるためバランスの良さという共通項はありつつも、キャラクターが異なる2種類が用意された。
後席ソファー横にはデシケーターがあり、U87Ai、TLM67、C414 XLSなどが収められている。演者にもよるが特に女性の声優とTLM67がよくマッチするようで好まれて使用されることが多いそうだ。また、マイクモデリングを行えるSlate Digital VMSの姿も見える。こちらは試している段階とのことだが、ボイス収録の幅広さにも適用できるよう積極的に新たな技術も視野に入れているようだ。確実性あるベーシックな機材を押さえつつ、 新MacProやMTRXといった新しいプロダクトを導入し、かつコミュニケーションの実用性を図っているところが、こちらの機材セレクトの特色でありユニークなところと言えるだろう。
レコーディングブースを超えた多目的さ
大小のスペースのうち、広い方を割り当てたブースは主にナレーション録音が行われる。天井のバトンにはYAMAHA HS5Wが5ch分吊るされているのだが、用途としては5.1chサラウンドへの対応だけではなく、イベント向けの制作に効果を発揮するという。イベント会場では吊られたスピーカーから音が出るケースが多く、その環境を想定しての音作りを求められることが多いためだ。多様な企画を行うミクシィ社ならではのスピーカー環境の利用の仕方と言える。なお、センターにあるHS5Wの横にもパッシブモニター YAMAHA VXS5W(パワー・アンプはコントロールルームにYAMAHA MA2030aを設置)がTalkBack用の返しモニターとして設置されている。このようにヘッドフォンに返すのではなく、あえてモニターでTalkBackを送るというのは、コントロールルームとのコミニュケーションをよりよくするために考えられた発想だ。
また、コントロールルームのラックにあったBlackMagic Smart Videohub 12x12にて、ディスプレイモニターには映像の出力やPro Toolsメイン画面を切り替えにて映し出し可能、レコーディングブースでもミキシングも行えるようになっている。急ぎの案件ではブースとコントロールルームでパラレル作業を行い、作業部屋二つのようなスタイルでも使われるとのことだ。そして、壁面のパネルは演者の立ち位置を考慮して4面それぞれに配置されている。4人でのナレーションを録る場合や、さらに声優たちの個別映像出しにモニター出力用のSDI端子、CUE送り用のLAN端子。また、スタッフがブース内でPC/Macを持ち込み映像を見ながら打ち合わせをする場合に備えての社内LAN回線までもが備えられている。ミクシィという企業ではこの先にどんな制作物が発想されてもおかしくない、とのことで考えうる最大限の仕様が織り込まれた格好だ。スピーカーが吊るされたことにより、無駄なくスペースを広く保ち、録音はもちろんコントロールルームと並走したミキシングの機能まで兼ね備えている。単にレコーディングブースと呼ぶには留まらない特徴的な”多目的"スペースを実現している。
コミュニケーションを生み出す仕掛け
コミュニケーションを生み出すというコンセプトによって生み出された工夫はほかにもある。コントロールルームの後方にあるソファは通常はクライアント用と考えられそうだが、こちらは商業スタジオではないためこのスペースも立派に作業スペースとして成り立つ必要がある。そのためこのソファの内部2箇所に可動式のパネルが隠されている。クリエイターやプロデューサーがPC/Macを持ち寄り、その場で持ち込んだ素材(オーディオファイル)の確認や、映像の出力、もちろんディレクションも行えるようにモニターコントローラーとして採用されたGrace Design m905のTalkBackマイクのスイッチがアクセスできるようになっている。当初このアイデアは壁面や床面など設置位置に試行錯誤があったようだが、その結論はなんとソファの中。これによってスタジオのデザイン的な要素や機能面も損なうことなく、コミュニケーションを生み出す仕掛けが実現できている。
また、コントロールルーム正面からそのまま窓越しに演者とコミュニケーションが取れるようにというのが、レイアウトを横長に変更した大きな理由であったが、ブースへの窓はエンジニア席だけではなく、このソファからの視線も考慮されて位置が決定されている。窓位置はモニタースピーカーの位置決定にも関わるし、テレビの配置にも関わる。施行前から座席部分にテープでマーキングして両氏が念入りに試行錯誤を重ねたそうだ。
そして、このフロアにはサウンドスタジオのみではなく、連携して協業する撮影スタジオのほか、会議室、社員の休憩スペースからコンビニエンスストアまで整っている。インタビューを行った会議室や休憩スペースは遠く水平線まで見渡せる開放的なスペースで、集中した作業を行うスタジオ内と実に対照的。作業のON/OFFがはっきりとした環境で生まれるコミュニケーションも良好なものになりそうだ。
最後に話題となったのは、スマートフォンにおける5Gへの対応だ。
「まさに実用が始まったばかりとなる5Gの高速な通信は、端末に頼らなくとも大容量のコンテンツを成立させることができるかもしれない。もちろん、アプリやゲームも5Gの恩恵を受けてより高度な表現を提案することが可能になってくる。サウンドで言えばバイノーラルへの対応でキャラクターへの没入感をより深いものにできるかもしれない。5Gで何ができるのだろうか、提供されるインフラとはどのようなものだろうか、そして顧客へ提供できるサービスとはなんだろうか、このような着想から生み出されるのは各社の特色。そして何に強みを持ってコンテンツを作っていくのか、これによって整えるスタジオの環境も変わってくる。」
インタビュー時の両氏のコメントをまとめたものだが、やはり見据えているのはインフラやプラットフォームまで含めたエンタテインメントコンテンツそのものであるという点で、クリエイティブワークだけではない視野の広さが求められているということが感じられた。このスタジオが生み出すコミュニケーションの積み重ねが、5Gの可能性を引き出し、エンタテインメントの可能性を拡げていく。今後このスペースは従来のスタジオ以上の価値を生み出していくことになる、とも言えるのではないだろうか。
株式会社ミクシィ
モンスト事業本部
デザイン室 サウンドグループ
マネージャー
安井 聡史 氏
株式会社ミクシィ
コーポレートサポート本部
ビジネスサポート室
サウンドライツグループ
岡田 健太郎 氏
*ProceedMagazine2020号より転載
Media
2020/08/11
ゼロからはじめるDOLBY ATMOS / 3Dオーディオの世界へDIVE IN !!
2020年1月、CES2020にてお披露目された"Dolby Atmos Music"。映画向けの音響規格の一つであるDolby Atmosを、新たなる"3D"音楽体験として取り入れよう、という試みだ。実は、前年5月頃より"Dolby Atmosで音楽を制作しよう”という動きがあり、ドルビーは世界的大手の音楽レーベル、ユニバーサルミュージックとの協業を進めてきた。"Dolby Atmos"は元々映画音響用のフォーマットとして2012年に誕生している。その後、ヨーロッパを中心に対応劇場が急速に増え、海外では既に5000スクリーン以上、国内でもここ数年で30スクリーン以上に渡りDolby Atmosのシステムが導入されてきた。
また、映画の他にもVRやゲーム市場でもすでにその名を轟かせており、今回、満を持しての音楽分野への参入となる。Dolby Atmos Music自体は、既にプロオーディオ系の様々なメディアにて取り上げられているが、「Dolby Atmosという名称は聞いたことがある程度」「Dolby Atmosでの制作に興味があるが、日本語の情報が少ない」という声もまだまだ多い。そこでこの記事では、今のうちに知っておきたいDolby Atmosの基礎知識から、Dolby Atmosミックスの始めの一歩までを出来るだけ分かりやすい表現で紹介していきたい。
目次
コンテンツは消費の時代から”体験”の時代に 〜イマーシブなオーディオ体験とは?〜
まずは Dolby Atmosを体験しよう! / 映画、音楽、ゲームでの採用例
ベッドとオブジェクトって何!? / Dolby Atmos基礎知識
Dolby Atmos制作を始めよう / 必要なものは何?
自宅で始めるDolby Atmosミックス / Dolby Atmos Renderer × Pro Tools 2020.3【Send/Return編】
自宅で始めるDolby Atmosミックス / Dolby Atmos Renderer × Pro Tools 2020.3【CoreAudio編】
1.コンテンツは消費の時代から”体験”の時代に 〜イマーシブなオーディオ体験とは?〜
近年、"3Dオーディオ"という言葉をよく見かけるようになった。今のところ、その厳密な定義は存在していないが、古くからは"立体音響"や"三次元音響"といった言葉でも知られており、文字通り、音の位置方向を360度、立体的に感じられる音響方式のことを指す。その歴史は非常に古く、諸説あるがおよそ1世紀に渡るとも言われている。
点音源のモノラルに始まり、左右を表現できるようになったステレオ。そして、5.1、7.1、9.1…とその数を増やすことによって、さらなる音の広がりや奥行きを表現できるようになったサラウンド。と、ここまででもイマーシブな(*1)オーディオ体験ができていたのだが、そこにいよいよ、天井や足元といった高さ方向にもスピーカーが加わり、三次元空間を飛び回るような音の再生が可能になった。それぞれの方式は厳密には異なるが、3DオーディオフォーマットにはDolby Atmos、Auro-3D、DTS:X、NHK22.2ch、Sony360 Reality Audioなどといったものがある。
基本的に、これまでこうした3Dフォーマットのオーディオを再生するにはチャンネル数に応じた複数のスピーカーが必要だった。そのため、立体的な音像定位の再現性と、そうした再生環境の手軽さはどうしてもトレードオフになっており、なかなか世間一般に浸透しづらいという状況が続いていた。そこで、いま再注目を浴びているのが"バイノーラル(*2)録音・再生方式"だ。個人差はあるものの原理は単純明快で、「人間の頭部を模したダミーヘッドマイクで録音すれば、再生時にも人間が普段自分の耳で聞いているような立体的な音像が得られる」という仕組み。当然ながらデジタル化が進んだ現代においては、もはやダミーヘッドすら必要なく、HRTF関数(*3)を用いれば、デジタルデータ上で人間の頭側部の物理的音響特性を計算・再現してしまうことができる。
バイノーラル再生自体は全くもって新しい技術というわけではないのだが、「音楽をスマホでストリーミング再生しつつ、ヘッドホンorイヤホンで聴く」というスタイルが完全に定着した今、既存の環境で気軽にイマーシブオーディオを楽しめるようになったというのが注目すべきポイントだ。モバイルでのDolby Atmos再生をはじめ、Sonyの360 Rearity Audio、ストリーミングサービスのバイノーラル音声広告といった場面でも活用されている。
*1 イマーシブ=Immersive : 没入型の *2 バイノーラル= Binaural : 両耳(用)の *3 HRTF=Head Related Transfer Function : 頭部伝達関数
2.まずは Dolby Atmosを体験しよう! / 映画、音楽、ゲームでの採用例
では、Dolby Atmosは一体どのようなシーンで採用されているのだろうか。百聞は一見に如かず、これまでDolby Atmos作品に触れたことがないという方は、まずは是非とも体験していただきたい。
映画
映画館でDolby Atmosを体験するためには、専用設計のスクリーンで鑑賞する必要がある。これには2種類あり、一つがオーディオの規格であるDolby Atmosのみに対応したもの、もう一つがDolby Atmosに加え、映像の規格であるDolby Visionにも対応したものだ。後者は"Dolby Cinema"と呼ばれ、現時点では国内7スクリーン(開業予定含む)に導入されている。
Dolby Atmosでの上映に対応している劇場は年々増加していて、2020年4月現在で導入予定含む数値にはなるが、既に国内では 36スクリーン、海外では5000スクリーン以上にも及んでいる。 (いずれもDolby Atmos + Dolby Cinema計)当然ながら対応作品も年々増えており、ライブストリーミング等、映画作品以外のデジタルコンテンツも含めると、国内では130作品、海外ではその10倍の1300を超える作品がDolby Atmosで制作されている。いくつか例を挙げると、国内興行収入130億円を超える大ヒットとなった2018年の「ボヘミアン・ラプソディ」をはじめ、2020年のアカデミーでは作品賞を受賞した「パラサイト 半地下の家族」、同じく録音賞を受賞した「1917 命をかけた伝令」などといった作品がDolby Atmosで制作されている。
●Dolby Atmos採用映画の例
アイアンマン3 / アナと雪の女王 / ラ・ラ・ランド/ パラサイト / フォードvsフェラーリ / ジョーカー / 1917 命をかけた伝令 / ボヘミアンラプソディetc...
*Dolby 公式サイトよりDolby Atmos採用映画一覧を確認できる
ゲーム
Dolby AtmosはPCやXbox Oneといった家庭用ゲームの人気タイトルでも数多く採用されている。特に、近年流行りのFPS(First Person Shooter = 一人称視点シューティング)と呼ばれるジャンルのゲームでは、射撃音を頼りに敵の位置を把握しなければならない。そのため、Dolby Atmosを使った3Dサウンドの再生環境の需要がより高まってきているのだ。
※Windows PCやXbox OneにおいてヘッドホンでDolby Atmosを楽しみたい場合は、Dolby Access(無料)というアプリをインストールし、Dolby Atmos for Headphonesをアプリ内購入する必要がある。
●Dolby Atmos採用ゲームの例
Assassin's Creed Origins(Windows PC, Xbox One) / Final Fantasy XV(Windows PC ,Xbox One)Star / Wars Battlefront(Windows PC ,Xbox One) / ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN(Windows PC, Xbox One)
音楽
Amazon Echo Studio
そして2020年1月にCES2020で正式発表されたのが、このDolby Atmosの名を冠した新たな3Dオーディオ再生フォーマット、Dolby Atmos Musicだ。現時点で、国内ではAmazonが提供するAmazon Music HD内のみでサービスを提供しており、同社のスマートスピーカー”Amazon Echo Studio”を用いて再生することができる。アメリカでは音楽ストリーミングサービス"TIDAL"でもDolby Atmos Musicを再生することができ、こちらは対応するPCやスマホなどでも楽しめるようになっている。
ここまで、Dolby Atmosを体験してみて、皆さんはどのような感想を持たれただろうか? 当然ながら多少の個人差はあるにしても、映画であればその空間に入り込んだかのような没入感・豊かな臨場感を体験できたのではないだろうか。あるいは、人によっては「期待したほど音像が動き回っている感じが得られなかった」という方もいるだろう。しかし、それでDolby Atmosの魅力を見限るのはやや早計だ。なぜなら、この技術は、"作品の意図として、音を無意識に落とし込む”くらい自然にミックスすることを可能にしているからだ。それを念頭におき、もう一度、繊細な音の表現に耳を澄ましてみてほしい。
3.ベッドとオブジェクトって何!? 〜Dolby Atmos基礎知識〜
体験を終えたところで、ここからは技術的な側面と基礎知識を押さえていこう。ポイントとなるのは以下の3点だ。
● ベッド信号とオブジェクト信号
● 3次元情報を記録するメタデータ
● 再生環境に合わせてレンダリング
Dolby Atmosの立体的な音像定位は、2種類の方式を組み合わせて再現されている。 一つはチャンネルベースの信号 ー 5.1.2や7.1.2などあらかじめ定められたスピーカー配置を想定し、そのスピーカーから出力される信号のことを"Bed"と呼んでいる。例えば、BGMやベースノイズといった、あまり指向性が求められない音の再生に向いている。基本は音源とスピーカーが1対1の関係。従来のステレオやサラウンドのミックスと同じなので比較的イメージがつきやすいだろう。
劇場のように、一つのチャンネルが複数のスピーカーで構成されていた場合、そのチャンネルに送った音は複数のスピーカーから再生されることになる。
そしてもう一つはオブジェクトベースの信号 ー 3次元空間内を縦横無尽に動き回る、点音源(ポイントソース)の再生に適した方式だ。例えば、空を飛ぶ鳥の鳴き声や、アクション映画での動きのある効果音の再生に向いている。原理としては、3次元情報を記録するメタデータをオーディオとともに記録・伝送し、再生機器側でそれらを再生環境に合わせてレンダリング(≒変換)することで、再生環境ごとのスピーカー配列の違いをエンコーダー側で吸収できるという仕組みだ。
ある1点に音源を置いた時に、そこから音が聴こえるように、スピーカー送りを最適化するのがレンダラーの役割
Dolby AtmosのチャンネルフォーマットはBed 7.1.2ch(計10ch) + Object118ch(最大)での制作が基本となっている。この"空間を包み込むような音"の演出が得意なベッドと、”任意の1点から聞こえる音”の演出が得意なオブジェクトの両方を組み合わせることによって、Dolby Atmosは劇場での高い臨場感を生み出しているのだ。
4.Dolby Atmos制作を始めよう 〜必要なものは何?〜
Dolby Atmosはその利用目的によって、大きく2種類のフォーマットに分けられる。
まずは、一番最初に登場した映画館向けのフォーマット、Dolby Atmos Cinemaだ。これはまさにフルスペックのDolby Atmosで、先述した7.1.2chのBEDと118chのObjectにより成り立っている。このフォーマットの制作を行うためにはDolbyの基準を満たした音響空間を持つダビングステージでの作業が必要となる。しかも、劇場向けのマスターファイルを作ることができるCinema Rendering and Mastering Unit (Cinema RMU)はDolbyからの貸し出しでしか入手することができない。
もう一つは、Blu-ray やストリーミング配信向けのフォーマット、 Dolby Atmos Homeだ。実は、こちらの大元となるマスターファイル自体は Cinema 向けのものと全く同じものだ。しかし、このマスターファイルから Home 向けのエンコードを行うことで、128chのオーディオを独自の技術を活用して、できる限りクオリティーを担保したまま少ないチャンネル数に畳み込むができる。この技術によって、Blu-rayやNetflixといった家庭向けの環境でも、Dolby Atmos の迫力のサウンドを楽しめるようになった。こちらも、マスターファイルを作成するためには、HT-RMUと呼ばれるハードウェアレンダラーが必要となるが、HT-RMUは購入してスタジオに常設できるというのがCinemaとは異なる点だ。
●Dolby Atmos制作環境 比較表
※Dolby Atmos Production SuiteはWeb上、AVID Storeからご購入できるほか、Mastering Suiteにも付属している。
※Dolby Atmos Dub with RMUについてはDolby Japan(TEL: 03-3524-7300)へお問い合わせください。
●Cinema
映画館上映を目的としたマスター。ダビングステージでファイナルミックスとマスタリングを行う。Dolby Atmos Print Masterと呼ばれるファイル群をCinema Rendering and Mastering Unit (Cinema RMU)で作成。
●Home
一般家庭での視聴を目的としたマスター。ニアフィールドモニターによるDolby Atmosスピーカー・レイアウトにてミックスとマスタリングを行う。Dolby Atmos Master File(.atmos)と呼ばれるファイル群をHome-Theater-Rendering and Mastering Unit(HT-RMU)で作成。
Cinema用とHome用のRMUでは作成できるファイルが異なり、スピーカーレイアウト/部屋の容積に関する要件もCinema向けとHome向けで異なる。それぞれ、目的に合わせたRMUを使用する必要がある。ミキシング用のツール、DAW、プラグイン等は共通。
ここまで作品や概要を説明してきたが、そろそろDolby Atmosでの制作を皆さんも始めてみたくなってきただろうか?「でも、自宅に7.1.2chをモニターできる環境が無い!「やってみたいけど、すぐには予算が捻出できない!」という声も聞こえてきそうだが、そんな方にとっての朗報がある。Dolby Atmos Production Suiteを使えば、なんと ¥33,000 (Avid Storeで購入の場合)というローコストから、Dolby Atmos ミックスの最低限の環境が導入できてしまうのだ。このソフトウェア以外に別途必要なものはない。必要なものはスペックが少し高めのマシンと、対応DAW(Pro Tools、Nuendo、DaVinchi etc)、そしてモニター用のヘッドホンのみだ。
多少の制約はあるものの、ヘッドホンを使ったバイノーラル再生である程度のミックスができてしまうので、スタジオに持ち込んでのマスタリング前に自宅やオフィスの空き部屋といったパーソナルな環境でDolby Atmosの仕込みを行うことができる。次の項ではそのワークフローを具体的に紹介していく。
5.自宅で始めるDolby Atmosミックス 〜Dolby Atmos Renderer × Pro Tools 2020.3〜
ここからは最新のPro Tools 2020.3 とProduction Suiteを使って実際のDolby Atmosミックスのワークフローをチェックしていきたい。まず、大まかな流れとしては下記のようになる。PTとレンダラーの接続方法は、Send/Returnプラグインを使う方法とCore Audio経由でやり取りする方法の2種類がある。それでは順番に見ていこう。
1.Dolby Atmos Production SuiteをAvid Storeもしくは販売代理店にて購入しインストール。
2.Dolby Atmos Renderer(以後レンダラー)を起動各種設定を行う。
3.Pro Tools(以後PT) を起動各種設定を行う。※正しいルーティングの確立のため、必ずレンダラー →Pro Toolsの順で起動を行うこと。
4.PTの標準パンナーで3Dパンニングのオートメーションを書き込む。
5.Dolby Atmos RMU導入スタジオに持ち込む。
Send/Returnプラグインを使う方法
■Dolby Atmos Renderer の設定
● 左上Dolby Atmos Renderer → Preferences( ⌘+ , )で設定画面を表示
● Audio driver、External Sync sourceをSend/Return Plug-insに設定
● Flame rate、Sample rateを設定 ※PTの設定と合わせる
HeadphoneのRender modeをBinauralにすることで、標準HRTFでバイノーラル化された3Dパンニングを確認することができる。(※聴こえ方には個人差があります。)
■Pro Tools の設定
● 新規作成→プロジェクト名を入力→テンプレートから作成にチェック
● テンプレートグループ:Dolby Atmos Production Suite内”Dolby Atmos Renderer Send Return Mono(またはStereo)”を選択→ファイルタイプ:BWF
● 任意のサンプルレート、ビットデプス、I/O設定を入力→作成
● 設定 → ペリフェラル → Atmosタブ
● チェックボックスに2箇所ともチェックを入れる。
● RMUホストの欄には”MAC名.local”または”LOCALHOST”と入力。
接続状況を示すランプが緑色に点灯すればOK。一度接続した場合、次回からプルダウンメニューで選択できる。
編集ウィンドウを見てみると、英語でコメントが入力されたいくつかのトラックが並んでいる。
● まず、一番上の7.1.2Bedという名称のトラック ーここにBedから出力したい7.1.2の音素材をペーストまたはRECする。
● 次に、その下のObject 11という名称のトラック ーここにObjectから出力したいMonoまたはStereoの音素材をペーストまたはRECする。
● 上の画像の例では、任意の範囲をドラッグして選択、AudioSuite→Other→Signal Genetatorよりピンクノイズを生成している。
● このトラックは、画面左側、非表示になっている”SEND_〇〇_IN_ch数”という表記になっているAUXトラックに送られている。
● このAUXトラックにSendプラグインがインサートされており、パンなどのメタデータとともにレンダラーへと出力される。
試しに再生してみると、レンダラー側が上の画像のような状態になり、信号を受けているチャンネルが点灯している様子が確認できる。
赤丸で囲った部分をクリックしてアウトプットウィンドウを表示し、パンナーのポジションのつまみをぐりぐりと動かしてみよう。
すると、レンダラー内のオブジェクトが連動してぐりぐりと動くのが確認できる。
オートメーションをWriteモードにしてチェックすると、きちんと書き込んだ通りに3Dパンニングされているのが分かる。ここで、トラックの右端”オブジェクト”と書かれているボタンをクリックすると、”バス”という表示に切り替わり、その音はベッドから出力される。つまり、ベッドとオブジェクトをシームレスに切り替えることができるのだ。これは、例えば、映画などで正面のベッドから出力していたダイアローグを、”ワンシーンだけオブジェクトにして、耳元に持ってくる”といった表現に活用できそうだ。
さらにその右隣の三角形のボタンを押すごとに、” このトラックに書き込まれたメタデータをマスターとする ”( 緑点灯 ) か、” 外部のオブジェクトパンニング情報源からREC する ”( 赤丸点灯 ) か、” 何も送受信しない ”( 無点灯 ) か を選択できるようになっている。レンダラー内でレンダリングされた音は、ReturnプラグインからPTへと戻ってくる。あとは、各々のモニター環境に合わせてアウトプットしたり、RECをかけたりすることができる。
以上が、Send/Returnプラグインを利用した一連のルーティングのワークフローになる。今回はテンプレートから作成したが、もちろんはじめから好きなようにルーティングを組むことも可能だ。しかし、チャンネル数が多い場合はやや複雑になってくるので、初めての場合はまずはテンプレートからの作成をおすすめする。
CoreAudioを使う方法
はじめに、Core Audioを使う場合、Sync sourceをMTCかLTC over Audioから選択する必要がある。LTCを使う場合は、PTの130chまでの空きトラックにLTCトラックまたは、Production Suite 付属のLTC Generator プラグインを挿入→レンダラーからそのch番号を指定する。MTCを使う場合はIACバスをというものを作成する必要がある。(※IAC = Inter-application communication)
■IACバスの設定
● Mac →アプリケーション→ユーティリティ→Audio MIDI設定を開く
● タブメニューのウインドウ→IAC Driverをダブルクリック ※装置名がIACドライバなど日本語になっていた場合レンダラーでの文字化けを防ぐため”IAC Driver”など英語に変更しておくとよい
● +ボタンでポートを追加→名称を”MTC”(任意)に変更→適用をクリック
■Dolby Atmos Renderer 側の設定
● 左上Dolby Atmos Rendere → Preferences( ⌘+ , )で設定画面を表示
● Audio driverをCore Audioに設定
● Audio input deviceを”Dolby Audio Bridge”に設定 ※ここに”Dolby Audio Bridge”が表示されていない場合、Macのシステム環境設定→セキュリティとプライバシー内に関連するアラートが出ていないか確認。
● External Sync sourceをMTCに設定し、MTC MIDI deviceで先ほど作成したIAC Driver MTCを選択(またはLTC over Audioに設定しCh数を指定)
● Flame rate、Sample rateを設定 ※PTの設定と合わせる
● ヘッドホンでバイノーラルで作業する場合はHeadphone only modeを有効にすると、リレンダリングのプロセスなどを省くため、マシンに余分な負荷をかけることなく作業できる
■Pro Tools 側の設定
● 設定→プレイバックエンジンを”Dolby Audio Bridge”に。
● キャッシュサイズはできる限り大きめに設定しておくと、プレイバック時にエラーが発生しにくくなる。
● 設定→ペリフェラル→同期→MTC送信ポートを先ほど作成した”IAC Driver,MTC”に設定
● 設定 → ペリフェラル → Atmosタブ(Send/Returnの項目と同様だ)
● チェックボックスに2箇所ともチェックを入れる。
● RMUホストの欄には”MAC名.local”または”LOCALHOST”と入力。接続状況を示すランプが緑色に点灯すればOK。一度接続した場合、次回からプルダウンメニューで選択できる。
以上で、CoreAudio経由でのルーティングは完了だ。Send/Returnプラグインを利用する時のように大量のAUXトラックが必要ないため、非常にシンプルにセッティングを完了できる。また、ソフトウェアレンダラーでの仕込みから最終のマスタリングでRMUのある環境に持ち込む際にも、I/O設定をやり直さなくてよいという点もメリットの1つだろう。こちらも試しにオーディオ素材を置いて動作を確認していただきたい。
マルチチャンネルサラウンドやバイノーラルコンテンツへの需要は、日々着実に高まりつつあることが実感される。今回はゼロからはじめるDolby Atmosということで、Dolby Atmosとはどのようなものなのか、そしてDolby Atmosミックスを始めるためにはどこからスタートすればいいのか、という足がかりまでを紹介してきた。「思ったより気軽に始められそう」と、感じていただいた方も多いのではないのだろうか。
「一度体験すれば、その素晴らしさは分かる。ただ、一度体験させるまでが難しい。」というのが3Dオーディオの抱える最大の命題の命題かもしれない。これを解決するのは何よりも感動のユーザー体験を生み出すことに尽きる。そのために今後どのような3Dオーディオ制作ノウハウを蓄積していけるのか、全てのクリエイターが手を取り合って研鑽することが、未来のコンテンツを創り上げる第一歩と言えるのかもしれない。
*ProceedMagazine2020号より転載
Media
2019/02/07
Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL 様 / レジェンドの描いた夢が実現する、全方位型36.8chイマーシブステージ
早稲田大学を始め教育機関が集中する東京西早稲田、ここにArtware hubと名付けられた新しいサウンド、音楽の拠点となる施設が誕生した。この施設は、Roland株式会社の創業者であり、グラミー賞テクニカルアワード受賞者、ハリウッドロックウォークの殿堂入りも果たしている故 梯郁太郎氏(公益財団法人 かけはし芸術文化振興財団 名誉顧問)の生涯の夢の一つを現実のものとする「音楽の実験室、様々な音環境、音響を実践できる空間」というコンセプトのもと作られている。
この空間の名称であるArtware hubという名称は梯郁太郎氏の生んだ造語「Artware」がその根本にある。ハードウェア・ソフトウェアだけではなく、人間の感性に根ざしたアート感覚を持った映像、音響機器、そして電子楽器を指す「Artware」、それがつなぐ芸術家の輪、絆、共感を生み出す空間としての「hub」、これが掛け合わされているわけだ。そして、もう一つのキーワードである「共感」を生み出すために、多くの方が集える環境、そのパフォーマンスを共有できる環境として設計が行われた。まさにこの空間は、今までにない音響設備を備え、そのコンセプトに沿った設計によりシステムが構築されている。
1:すべて個別に駆動する36.8chのスピーカーシステム
まずは、その環境を実現するためにインストールされた36.8chというスピーカーシステムから見ていきたい。壁面に数多く設置されたスピーカーはTANNOY社のAMS-6DCが採用されている。これだけの多チャンネルシステムであると、スピーカーの構造は物理的に同軸構造であることが望ましい。Stereoであれば気にならないツイーターとウーファーの位相差の問題が、スピーカーの本数分の問題となりサウンドチューニングの妨げとなるからである。このスピーカーの選定には10種類以上の機種の聴き比べを行い、自然なサウンドが得られる製品がセレクトされている。音の飛び出し方、サウンドのキャラクターが単品として優れている製品もあったが、個性の強すぎない、あくまでもナチュラルなニュアンスを持った製品ということでセレクトは進められている。
これらのスピーカーを駆動するアンプはTANNOY社と同じグループ企業であるLab.Gruppen D10:4Lが9台採用された。合わせてサブウーファーには同社VSX 10BPを2本抱き合わせて4箇所に合計8本、こちらのアンプにはLab.Gruppen D20:4Lを2台採用。PA関係を仕事とされている方にはすでに当たり前になっているかもしれないが、SR用のスピーカーのほとんどが専用アンプとのマッチングを前提に設計されており、その組み合わせにより本来のサウンドを生み出すからである。このアンプは1Uのスペースで4chのモデルであるためこのような多チャンネルの個別駆動にはベストなセレクトとなっている。
前後の壁面のスピーカー。正面は「田」の字に9本配置されているのがわかる。
そして、皆さんの興味はこのスピーカー配置に集まるのではないだろうか?壁面にはセンターから30度間隔で12本のスピーカーが2レイヤー配置されている。一般に開放する施設ということで、入場者の邪魔にならない位置、具体的には2.5mの高さに下層のスピーカーは取り付けられている。上層は5mの位置となる。さらに写真ではわかりにくいが、天井に設置されたグリッド上のパイプに9本のスピーカーが取り付けられている。この9本は「田」の字の各交点に設置されているとイメージしていただきたい。さらに仮設として正面床面に直置きでのスピーカーも3本あり、正面の壁面に関しても「田」の字の各交点に9本の配置がなされている。
これらの合計36本のスピーカーはすべて個別に駆動するようなシステムとなっている。さらにサブウーファーを天井グリッド内に4箇所設置、設置位置は前後左右の十字に配置し、それぞれ個別駆動が可能となっている。つまり合計36本のスピーカーと8本のサブウーファーがすべて個別に駆動、全体のシステムとしては36.8chのスピーカーシステムである。
天井のスピーカー。空調ダクト等を避けて写真の位置に9本のスピーカーと8本のサブウーファーが設置された。
2:ロスなく長距離伝送するDanteを採用
スピーカー側より順番に機材を見ていきたいが、アンプの直前にはDante-AnalogのコンバーターとしてFocusrite REDNET A16Rが設置されている。これは1Fに設置されている調整室から3Fにあるアンプルームまでの伝送を、最高のクオリティーを保ったまま行うという目的。そして、これだけの数のスピーカーのマネージメントを行うために導入されたYAMAHA MMP-1をベストなコンディションで動作させるためにDanteが採用されている。1Fの調整室から送られた信号は、Danteにより長距離をロスなく伝送されてくる。それをDante-Analogのコンバーターとして最適なクオリティーを提供するFocusrite社の製品によりAnalogでアンプへと接続が行われているということになる。
このDanteの回線に組み込まれたYAMAHA MMP-1は最新のスピーカー・マネージメント・プロセッサーである。1台で32chのスピーカーマネージメントが行える優れた機器で、システムアップに応じて自在に入力信号を各スピーカーに振り分けたりといったことが可能となっているが、Artware hubの36.8chのスピーカーをプロセスするためには2台が必要となった。サブウーファーのチャンネルに関しては、FIRフィルターによるLPFが使えるというのは特筆に値する機能である。この36.8chのスピーカーの調整には1週間の時間を要した。個別のチャンネルのイコライザーによる周波数特性の調整、ディレイによる位相合わせ、音圧の調整、さすがに36.8chともなるとなかなか終わらない。それぞれ隣合うスピーカーとのファンタム音像に関しても聴感でのピーク・ギャップが無いか、サウンドキャラクターが変化しないか、といったチェックを行っている。この調整作業は株式会社SONAの中原氏に依頼を行い実施した。スタジオのようにリスニングポイントに対してガチガチに調整を行うのではなく、リスニングエリアを広めにとれるように調整は行われている。
Dante Networkの入り口にはFocusrite REDNET D64Rが2台用意され、調整室内の基本回線となるMADIからDanteへのコンバートが行われている。ここでMADIは64chあるので1台で済むのでは?と考えられるかもしれないが、Artware hubのシステムはすべて96kHzで動作するように設計されている。そのため、MADI回線は32chの取り扱いとなり、この部分には2台のREDNET D64Rが導入されることとなった。
3:ハイクオリティを誰もが扱える、スペースとしての命題解決
そして、Artware hubのシステムの中核となるAVID MTRX。Pro ToolsともAVID S6Lとも接続されていない「MADI Matrix Router」としてこの製品がインストールされている。このAVID MTRXには5枚のMADI option moduleがインストールされ13系統のMADI IN/OUTが用意されている。システムのシグナルルーティングを行うだけではなく、システムのボリュームコントロールもこのMTRXが行っている。36.8chものチャンネルのボリュームコントロールが行える機器はなかなか存在しない。しかも、最終の出力は96kHzということもあり2系統のMADIにまたがっている。専任のオペレーターがいる利用時は良いが、講演会やVideoの視聴といった簡易的な利用の場合、誰でも手軽に操作ができるハードウェアコントローラーが必須となる。そこでArtware hubのシステムではAVID MTRXに組み合わせてTAC SYSTEM VMC-102をスピーカーコントローラーとして採用している。
TAC SYSTEM VMC-102はそれ自体にMADIを入力し、モニターソースのセレクトを行い、AVID MTRX/NTP/DADもしくはDirectOut ANDIAMOをコントロールし出力制御を行うという製品。しかし、Artware hubではVMC-102にMADIは接続されていない、AVID MTRXコントロール用にEthernetだけが接続されている。通常でのVMC-102は、入力されたMADI信号をモニターソースとしてそれぞれ選択、選択したものがVMC-102内部のモニターバスを経由してMADIの特定のチャンネルから出力される、という仕様になっている。そして、その出力されたMADIが、接続されるMTRX/NTP/DADもしくはDirectOutの内部のパッチの制御とボリュームの制御を行い、スピーカーセレクトとボリューム調整の機能を提供している。
今回は、このパッチの制御とボリュームコントロールの機能だけを抽出したセットアップを行っている。通常であればVMC-102の出力バスをスピーカーアウトのソースとして設定するのだが、ダイレクトにAVID MTRXの物理インプットを選択している。この直接選択では、物理的な入力ポートをまたいだ設定は出来ないため2つのスピーカーアウトを連動する設定を行い、今回の96kHz/36.8chのシステムに対応している。そして、VMC-102のタッチパネルには、ソースセレクトが表示されているように見えるが、実はこのパネルはスピーカーセレクトである。説明がややこしくなってしまったが、このパネルを選択することにより、AVID MTRXの入力を選択しつつ、出力を選択=内部パッチの打ち換え、を行い、その出力のボリュームコントロールを行っているということになる。YAMAHA MMP-1も同じような機能はあるが、2台を連携させてワンアクションでの操作が行えないためVMC-102を使ったシステムアップとなった。
具体的にどのような設定が行われているかというと、マルチチャンネルスピーカーのディスクリート駆動用に40ch入力、40ch出力というモードが一つ。コンソールからのStereo Outを受けるモードが一つ。Video SwitcherからのStereo Outを受けるモード、そして、袖に用意された簡易ミキサーであるYAMAHA TF-Rackからの入力を受けるモード、この4パターンが用意されている。ちなみにVMC-102は6系統のスピーカーセットの設定が可能である。今後入出力のパターンが増えたとしても、36.8chで2パターン分を同時に使っているので、あと1つであればVMC-102のスピーカーセットは残っているため追加設定可能だ。
システム設計を行う立場として、やはり特注の機器を使わずにこのような特殊フォーマットのスピーカー制御が行えるということは特筆に値する機能であると言える。VMC-102はスピーカーセット一つに対して最大64chのアサインが可能だ。極端なことを言えば48kHzドメインで6系統すべてを同期させれば、384chまでのディスクリート環境の制御が可能ということになる。これがAVID MTRXもしくはNTP/DAD社製品との組み合わせにより200万円足らずで実現してしまうVMC-102。新しい魅力を発見といったところである。AVID MTRXには、Utility IN/OUTとしてDirectOut ANDIAMOが接続されている。この入出力はVideo Systemとのやり取り、パッチ盤といったところへの回線の送受信に活用されている。ここも内部での回線の入れ替えが可能なため、柔軟なシステムアップを行うのに一役買っている部分である。
4:36.8chシステムの中核、FLUX:: SPAT Revolution
そして、本システムのコアとなるFLUX:: SPAT Revolution。このソフトウェアの利用を前提としてこの36.8chのスピーカーシステムは構築されている。SPAT Revolutionは、空間に自由にスピーカーを配置したRoomと呼ばれる空間の中に入力信号を自由自在に配置し、ルームシュミレートを行うという製品。Artware hubのような、特定のサラウンドフォーマットに縛られないスピーカー配置の空間にとって、なくてはならないミキシングツールである。SPAT Revolutionは、単独のPCとしてこれを外部プロセッサーとして専有するシステム構成となっている。
入出力用にはRME HDSPe-MADI FXを採用した。これにより、64ch@96kHzの入出力を確保している。入力は64ch、それを36.8chのスピーカに振り分ける。SPAT Revolutionにはサブウーファーセンドが無いため、この調整は規定値としてYAMAHA MMP-1で行うか、AVID S6Lからのダイレクトセンドということになる。といっても36chのディスクリートチャンネルへのソースの配置、そして信号の振り分けを行ってくれるSPAT RevolutionはArtware hubにとっての心臓とも言えるプロセッサーだ。執筆時点ではベータバージョンではあるが、将来的にはS6Lからのコントロールも可能となる予定である。数多くのバスセンドを持ち、96kHz動作による音質、音楽制作を行っている制作者が慣れ親しんだプラグインの活用、AVID S6LのセレクトもSPAT Revolutionとともに強いシナジーを持ちArtware hubのシステムの中核を担っている。
FLUX:: SPAT Revolutionに関しての深いご紹介は、ROCK ON PRO Webサイトを参照していただきたい。非常に柔軟性に富んだソフトウェアであり、このような特殊なフォーマットも制約なくこなす優れた製品だ。Artware hubでは、既存のDolby AtmosやAUROといったフォーマットの再生も念頭においている。もちろん、完全な互換というわけにはいかないが、これだけの本数のスピーカーがあればかなり近い状態でのモニタリングも可能である。その場合にもSPAT Revolutionは、スピーカーへのシグナルアサインで活躍することとなる。現状では、既存のImmersive Surroundの再生環境は構築されてないが、これは次のステップとして検討課題に挙がっている事案である。
◎FLUX:: 関連記事
FLUX:: / ユーザーから受けた刺激が、 開発意欲をエクスパンドする
Immersive Audioのキー・プロダクト Flux:: / Spat Revolution 〜ROCK ON PRO REVIEW
5:可動式のS6Lでマルチチャンネルミックス
ミキシングコンソールとして導入されたAVID S6Lは、大規模なツアーなどで活躍するフラッグシップコンソールの一つ。コンパクトながら高機能なMixing Engineを備え、96kHzで192chのハンドリング、80chのAux Busを持つ大規模な構成。SPAT Revolutionでのミキシングを考えた際に、Aux Busの数=ソース数となるため非常に重要なポイント。音質とバス数という視点、そして何より前述のSPAT Revolutionをコンソール上からコントロール可能という連携により選択が行われている。そしてこれだけのマルチチャンネル環境である、調整室の中からでは全くミキシングが行えない。そこでS6Lはあえてラックケースに収められ、会場センターのスイートスポットまで移動してのミキシングが可能なように可動式としている。
S6Lには、録音、再生用としてAVID Pro Toolsが接続されている。これは、AVID S6Lの持つ優れた機能の一つであるVirtual Rehearsal機能を活用して行っている。S6Lに入力された信号は、自動的に頭わけでPro Toolsに収録が可能、同様にPro ToolsのPlaybackとInputの切替は、ボタン一つでチャンネル単位で行えるようになっている。マルチトラックで持ち込んだセッションをArtware hubの環境に合わせてミキシングを行ったり、ライブ演奏をSPATを利用してImmersive Soundにしたりとどのようなことも行えるシステムアップとしている。これらのシステムが今後どの様に活用されどのようなArtが生み出されていくのか?それこそが、まさにArtware hubとしての真骨頂である。
AVID S6L はこのように部屋の中央(スピーカー群のセンター位置)まで移動させることが可能。イマーシブミキシング時は音を確認しながら作業が行える。
Artware hubには、音響だけではなく、映像、照明に関しても最新の設備が導入されている。映像の収録は、リモート制御可能な4台の4Kカメラが用意され、個別に4Kでの収録が可能なシステムアップが行われた。4K対応機器を中心にシステムアップが行われ、将来への拡張性を担保したシステムとなっている。音響システムとは、同期の取れる様にLTC/MTCの接続も行われている。照明は、MIDIでの制御に対応し、PCでの事前仕込みの可能な最新の照明卓が導入された。LED照明を中心に少人数でのオペレートで十分な演出が行えるよう配慮されたシステムとなっている。
さまざまなArtistがこのシステムでどのようなサウンドを生み出すのか?実験的な施設でもあるが、観客を入れて多くの人々が同時に新しい音空間を共有できる環境であり、すべてにおいて新しい取り組みとなっている。Roland時代の梯郁太郎氏は早くも1991年にRSS=Roland Sound Spaceという3D Audio Processorを開発リリースしている。その次代を先取りした感性が、今このArtware hubで現実の環境として結実していると思うと感慨深いものがある。
本誌では、これからもArtware hubで生み出されるArtを積極的に取り上げていきたい。また、今回ご紹介したシステム以外にも照明映像関連などで最新の設備が導入されている、これらも順次ご紹介をしたい。最後にはなるがこの設備のコンセプトの中心となった、かけはし芸術文化振興財団専務理事で梯郁太郎氏のご子息である梯郁夫氏、そして同じく理事であるKim Studio伊藤圭一氏の情熱により、この空間、設備が完成したことをお伝えしまとめとしたい。
*ProceedMagazine2018-2019号より転載
Media
2018/05/23
株式会社カプコン様 / Dynamic Mixing Room-[B] / [W]
日本を代表するゲーム会社カプコン。前号でもリニューアルしたDynamic Mixing Stageをご紹介したが、それに続いて新たにDynamic Mixing Room-[B]とDynamic Mixing Room-[W]が作られた。VR、イマーシブといった言葉が先行しているゲーム業界におけるオーディオのミキシングだが、それらのコンテンツを制作する現場はアプローチの手法からして大きな変革の中にある。ゲームではカットシーン(ユーザーが操作をせずに動画が再生され、ストーリを展開する部分)と呼ばれるMovieとして作られたパートが次々と減少し、昨年リリースの同社『バイオハザード7 レジデント イービル』では遂にカットシーンが全くないというところにまでたどり着いている。こういった背景もあり、しっかりとした音環境でDynamic Mixingを行える環境というものが切望されていた。その回答が前回ご紹介したDynamic Mixing Stageであり、今回のDynamic Mixing Roomとなる。
◎求められていたDynamic Mixing「Room」
昨年のDynamic Mixing Stageは各素材の最終確認、そして最後の仕上げという部分を重点的に担っているが、その途中の生成物であるオーディオデータが全てファイナルのミックス時点でオブジェクトに埋め込まれ、プログラムされていくわけではない。しかし、オーディオデータをプログラムに埋め込み、他のサウンドとの兼ね合いを確認しながら作業を行う必要が日に日に大きくなっているのが現状だ。カプコンでは各スタッフに専用のパーテーションで区切られたブースが与えられ、5.1chでの視聴環境が用意されている。ただし、あくまでも仮設の環境であり、スタジオと比べてしまえば音環境としてお世辞にも良いと言えるものではない。ほかにもPro Toolsが常設された防音室が用意され、そこへシステムを持ち込み確認作業が行えるようになっていたが、常設のシステムに対して持ち込みのシステムを繋ぎ込む必要があるため、それなりのエンジニアリング・スキルが要求される環境であった。この環境改善を図ったのが今回の目的の第一点となる。
もちろん、ここにはサウンドクオリティーへの要求も多分に含まれる。海外のゲーム会社を視察した際に、クリエイター各自が作業スペースとしてスタジオクラスの視聴環境で作業しているのを目の当たりにした。これが、世界中のユーザーに対してゲーム開発をおこなうカプコンとして、同じクオリティーを確保するための重要な要素と感じた。各クリエイターが、どれだけしっかりとした環境でサウンドクオリティーを確認することが出来るのか。これこそが、各サウンドパーツレベルのクオリティーの差となり、最終的な仕上がりに影響をしているのではないか、ということだ。これを改善するため、自席のシステムそのままにサウンドの確認を行うことのできるDynamic Mixing Roomへとつながっている。
さらにもう一つ、VRなど技術の発展により、3Dサラウンド環境での確認が必要なタイトルが増えてきたというのも新設の大きな要因。昨年、Xbox OneがDolby Atmosに対応したことなどもその一因となったそうだ。今回はスピーカーの増設だけでその対応を行うということではなく、やるのであればしっかりとした環境自体を構築する、という判断を後押しするポイントになったという。
そして、Dynamic Mixingにおいてサウンドを確認するためには、DAWからの出力を聴くのではなくゲーム開発機からの出力を聴く必要がある。ゲームエンジンが実際に動き、そこにオーディオデータがプログラムとして実装された状況下でどの様に聴こえるのか、プログラムのパラメーターは正しかったか?他のサウンドとのかぶりは?多方面から確認を行う必要があるからだ。そうなると、自分の作っているゲームの開発機を設置して、繋ぎ込んで音を聴くというかなりの労力を要する作業を強いられてしまう。
すでに開発中のデータ自体はネットワーク化されておりサーバー上から動くが、端末はそのスペックにあった環境でなければ正確に再現されない。今回のDynamic Mixing Roomはそういった労力を極力減らすために設計された部屋ということになる。そのコンセプトは利便性とスピード感。この二つに集約されるということだ。
◎部屋と一体になった音響設計
実はこの部屋にはDAWが存在しない、2つの鏡写しに作られた黒い部屋と白い部屋。その間の通路に置かれたラックに開発PCを設置して作業が行えるようになっている。接続された開発PCはHDMIマトリクススイッチャーを経由してそれぞれの部屋へと接続される。開発PCの音声出力はHDMIのため、部屋ではまずAV ampに接続されデコード、モニターコントローラーの役割として導入されたRME UFX+を経由してスピーカーを鳴らす。なぜRME UFX+がモニターコントローラーとして採用されているかは後ほど詳しく説明するとして、まずはサウンドに対してのこだわりから話を始めたい。
この環境を作るにあたりリファレンスとしたのはDynamic Mixing Stage。こちらと今回のDynamic Mixing Roomでサウンドの共通性を持たせ、迷いのない一貫した作業を実現したいというのが一つの大きなコンセプト。全てのスピーカーは音響設計を行なったSONAのカスタムメイドでバッフルマウントとなっている。サラウンド側、そして天井に至るまで全てのスピーカーがバッフルマウントという部屋と一体になった音響設計が行われている。このスピーカーは全てバイアンプ駆動され、そのマネージメントを行うプロセッサーはminiDSPが採用されている。miniDSPはFIRフィルターを搭載し、位相問題のないクリアなコントロールを実現している。しっかりとした音響設計がなされたこのDynamic Mixing RoomはDynamic Mixing Stageと高いサウンドの互換性を確保できたということだ。今後はDynamic Mixing Stageで行われているダイヤログの整音と並行してDynamic Mixing Roomで実装された状態での視聴を行う、といった作業も実現できる環境になっているということ。もちろん、同じクオリティーでサウンドを確認できているので、齟齬も少なく済む。まさに「スピード感」というコンセプトが実現されていると言える。
◎RME Total Mixで実現した柔軟なモニターセクション
それでは、次にRME UFX+の部分に移っていきたい。UFX+の持つTotal Mixを使ったモニター機能は非常に強力。複数のマルチチャンネルソースを自由にルーティングすることが出来る。これまで自席で仕込んだサウンドをしっかりした環境で聴こうと思うと、前述のように自席のPC自体を移動させて仮設する必要があった。この作業をなくすために、DiGiGridのネットワークが構築されている。それぞれのPCからの音声出力はDiGiGridのネットワークに流れ、それがDynamic Mixing RoomのUFX+へと接続。もちろんDiGiGridのままでは接続できないため、DiGiGrid MGO(DiGiGrid - Optical MADI Convertor)を介しMADIとして接続されている。
開発PCからのHDMIはAV ampでデコードしてアナログで接続され、各スタッフの自席PCからはDiGiGirdネットワークを介して接続、ということになる。これらの入力ソースはRME Total Mix上でモニターソースとしてアサインされ、ARC USBによりフィジカルにコントロールされる。このフィジカルコントローラーの存在も大きな決め手だったということだ。そもそも複数の7.1.4サラウンドを切り替えようと思うと具体的な製品がなかなか存在しない。フィジカルコントロールも必要となるとAVID S6 + MTRX、TAC System VMC-102 + MTRXといった大規模なシステムになってしまうのが実情。リリース予定の製品にまで目をやったとしてもGrace Design m908がかろうじて実現出来るかどうかというレベルとなる。その様な中でUFX+とARC USBの組合せは過不足のない機能をしっかりと提供することが出来ており、フィジカルなコントローラーを手に入れたことで使い勝手の高いシステムへと変貌している。実は、Total MixのモニターコントロールはRock oN渋谷店頭でスピーカー試聴の切替にも使用されている。こちらも試聴中に数多くの機器をスムーズに切り替える必要があるのだが、その柔軟性が遺憾なく発揮されている実例でもある。
◎利便性とスピード感を具現化
このDynamic Mixing Roomは3Fに位置しており、先行してDiGiGridのネットワークが構築されたコンポーザーの作業場は14Fとかなり距離が離れていたが、その距離も既存のネットワーク回線を活用することで簡単に連携が実現ができた。ここはネットワークが会社中に張り巡らされているゲーム会社ならではの導入障壁の低さかもしれないが、追加で回線を入れるとしてもネットワーク線の増設工事であれば、と考えてしまうところでもある。ちなみに自席PCはDynamic Mixing Roomから画面共有でリモートしている。画面共有サービスもブラッシュアップされておりレスポンスの良い作業が実現したこともこのシステム導入の後押しになったということだ。
今後は、コンポーザーだけではなくSEスタッフの自席も活用しようと検討しているということだ。全社で70名近いというサウンドスタッフすべてのPCがDiGiGrid Networkを介してつながる、まさに未来的な制作環境が実現していると言えるのではないだろうか。自席PCでサウンドを仕込みながら、持ち込んだ開発PCに実装し、その場で確認を行う。理想としていた制作環境に近づいたということだ。また、開発PCを複数置けるだけのスペースも確保したので、タイトルの開発終了まで設置したままにできる、ということも大きい。HDMI出力と操作画面用のDVI、そして操作用のUSB、これらの繋ぎ変えだけで済むということは、これまで行なっていたPCごと移動するスタイルからの大きな進化。利便性とスピード感。このコンセプトに特化した環境が構築されたと言えるのではないだろうか。
また、Dynamic Mixing Roomには常設のMouseもKeyboardも無い。自席と同じ様な作業環境を簡単に構築できるという考え方のもと、機材の持ち込みは自由にされているということだ。共有の設備にも関わらず、PCもなければMouseもKeyboradもない。少し前では考えられなかったような設備が完成した。言わば「何も置かない」というミニマルさが、ゲームの開発という環境に特化して利便性とスピード感を追求した結果。これは、ゲーム制作だけではなくシェア・ワークフローそのものを考える上で大きな転換点に来ているということを実感する。
すでにITでは数年前からSaaS(Software as a Service)という形態が進化を続けている。手元にあるPCはあくまでも端末として、実際の処理はクラウドサービスとして動作をしているシステム。映像の業界はすでにSaaS、クラウドといったイントラネットから飛び出したインターネット上でのサービスの活用が始まっている。今後は、サウンドの業界もこの様な進化を遂げていくのではないか、そのきっかけとなるのが今回のカプコン Dynamic Mixing Roomの実例なのではないかと感じている。
(手前)株式会社カプコン サウンドプロダクション室 室長 岸 智也 氏 / (奥左)同室 コンポーザー 堀 諭史 氏 / (奥右)同室 オーディオ・ディレクター 鉢迫 渉 氏
*ProceedMagazine2018Spring号より転載
Media
2017/11/14
株式会社カプコン様 / Dynamic Mixing Stage
日本を代表するゲーム会社である株式会社カプコン。もともと7.1ch対応のAVID S6が設置されたDubbing Stage、そして7.1ch対応のAVID D-Control(ICON)が設置されたDynamic Mixing Stageの2部屋を擁していたが、今後起こりうるImmersive Audioの制作へ対応するためDynamic Mixing Stageのシステム更新を行った。今回の更新でDOLBY ATMOS HOME対応のシステムが組まれ、今後AURO 3Dなどにも対応できるよう準備が行われている。
◎Dynamic Mixingというコンセプト
今回、スタジオを改修するにあたりそのコンセプトについても根本的に見直しが行われた。これまで、カプコン社内スタジオ「bitMASTERstudio」は、レコーディングと大型セッションのミキシングを可能とする「Dubbing Stage」と、そのサテライトとして同等の能力を持ちつつ、レコーディングを除いたプリミックスや仕上げの手前までを想定した「Dynamic Mixing Stage」という構成であったが、これを従来型のPro ToolsとS6によるミキシングを中心に行う「Dubbing Stage(旧Dubbing Stage)」と、今回改修を行ったスタジオをゲーム内のインタラクティブシーンを中心としたミキシングを行うための「Dynamic Mixing Stage(旧Dynamic Mixing Stage)」としている。
この「Dynamic Mixing」は、ゲームの中でプログラムによって制御される方法でミキシングを行うことを指している。つまり、このステージはゲーム内のプログラムミキシングを行う場所であり、従来のミキシングステージとは一線を画するものだと考えているとのことだ。したがって、この部屋の音響空間及びシステムの設計思想は「リファレンスとなりうる音を再生できる特性を持ち、プログラムによるミキシングを効率的に行えるシステム」であることを第一義としている。
システムを構築する上で大切にしたことは、WindowsPC内にインストールされたゲームエンジンとオーディオミドルウェアのパラメーターを操作するのと同時に、ゲームに組み込むためのオーディオエディット/ミキシングをPro Tools上で効率的に行えるようにすること。Ultra Wideディスプレイと壁付けのTVによってそれらの情報をすべて表示し、ゲーム音声とProTools上の音声を瞬時に切り替え、あるいは同時に再生することのできるシステムにしておくことは、ゲームオーディオ制作では極めて重要、とのことだ。
◎既存スタジオをブラッシュアップするアイデア
メインのミキシング、ナレーションなどの収録に活躍するDubbing Stageと、ユーティリティ性を持たせプレビューなどにも対応できるように設計されたDynamic Mixing Stage。そのDynamic Mixing Stageはモニター環境をブラッシュアップし新しいフォーマットへの準備を行なった格好だ。部屋自体はそれほど広い空間が確保されているわけではなく、天井高も同様。その中にDOLBY ATMOS、そしてAURO 3Dといった次世代のフォーマットへ対応したモニタリングシステムを導入している。音響設計・内装工事を行った株式会社SONAからも様々な提案が行われ、そのアイデアの中から実現したのが、このスタジオのイメージを決定づける音響衝立と一体となったスピーカースタンドだ。天井に関してはスピーカーを設置するために作り直されており、内装壁も全面改修されているが、壁の防音層と床には手を加えずに最低限の予算で今回の工事を完了させている。
併せてDAWシステムについても更新が行われ、コントローラーはAVID D-Control(ICON)からAVID S3へとブラッシュアップされた。また、Dubbing Stageでモニターコントローラーとして活用されていたTAC system VMC-102はDynamic Mixing Stageへと移設され、マルチフォーマット対応のモニターコントローラーとして再セットアップが行われている。Dubbing Stageのモニターセクションには最新のAVID MTRXがインストールされ、AVID S6からの直接のコントロールによるモニタリングを行うようにこちらも再セットアップされている。
◎フォーマットに対応する柔軟性を持つ
それでは、各パートごとに詳細にご案内を行なっていきたい。まずは、何といっても金色に光り輝く音響衝立。これは完全にカスタムで、背の高いものが8本、低いものがセンター用に1本制作された。その設置はITUサラウンドの設置位置に合わせて置かれている。フロントはセンターを中心に30度、60度の角度で、Wide L/Rを含めたフォーマットとして設置が行われている。サラウンドはセンターより110度、150度と基本に忠実な配置。これらの音響衝立は、天井側のレールに沿ってサラウンドサークルの円周上を移動できるようになっている。これは、物理的に出入り口に設置場所がかかってしまっているため、大型の機器の搬入時のためという側面もあるが、今後この8枚の音響衝立の設置の自由度を担保する設計となっている。この衝立の表面は穴の空いた音響拡散パネルで仕上がっており,内部に吸音材が詰められるようになっている。吸音材の種類、ボリュームを調整することで調整が行えるようにという工夫である。
そしてちょうど耳の高さに当たる部分と、最上部の2箇所にスピーカー設置用の金具が用意されている。この金具も工夫が行われており、上下左右全て自由に微調整が行えるような設計だ。写真で設置されている位置がITU-R準拠のサラウンドフォーマットの位置であり、そのままDOLBY ATMOSのセットアップとなる。最上部の金具の位置はAURO 3D用のものであり、Hight Layerの設置位置となる。現状では、AURO 3D用のスピーカーを常設する予定はなく、AURO 3Dに変更する際には追加でこの位置へスピーカーを設置する事となる。完全に縦軸の一致する上下に設置ができるため、理想的な設置環境といえるだろう。
センターだけはTVモニターとの兼ね合いがあり背の低い衝立となっている、また、AURO 3D用のHC設置はTVの上部に設置用の金具が準備される。そして、TVモニターの下の空間にはサブウーファー2台が左右対象の位置に設置されている。天井にはセンターから45度の角度を取り、4本のスピーカーが正方形に配置されている。これが、Top Surround用のスピーカーとなる。もちろんAURO 3D用にTチャンネル用として天井の中心に金具が用意されている。また、wide L/Rの位置にも音響衝立が用意されているので、現状設置されている7.1.4のフォーマットから、9.1.4への変更も容易になっている。
このサラウンド環境はコンパクトな空間を最大限に活かし、完全に等距離、半球上へのスピーカー設置を実現している。そのために、各チャンネルの音のつながりが非常に良いということだ。また、音響衝立の中にスピーカーを設置したことにより、バッフル設置のようなメリットも出ているのではないかと想像する。スピーカー後方には十分な距離があり、そういった余裕からもサウンド面でのメリットも出ているのではないだろうか。
◎3Dにおける同軸モニターの優位性
今回の更新にあたり、スピーカーは一新されている。カプコンでは以前より各制作スタッフのスピーカーをGenelecに統一している。できるだけ作業スペースごとの視聴環境の差をなくし、サウンドクオリティーの向上と作業効率の向上がその目的だ。そのような流れもあり、Dynamic Mixing StageではGenelecの最新機種である8341がフロントLCRの3ch用として、サラウンド及びTop Layerには一回りコンパクトな8331が選定されている。このモデルは同軸2-way+ダブルウーファーという特徴的な設計のモデル。従来の筐体より一回り小さな筐体で1クラス上の低域再生を実現してるため、DOLBY ATMOSのように全てのスピーカーにフルレンジ再生を求める環境に適したモデルの一つと言える。ちなみに8341のカタログスペックでの低域再生能力は45Hz~(-1.5dB)となっている。従来の8030クラスのサイズでこの低域再生は素晴らしい能力といえるのではないだろうか。また、スピーカーの指向性が重要となるこのような環境では、スコーカーとツイーターが同軸設計であるということも見逃せないポイント。2-way,3-wayのスピーカー軸の少しのずれが、マルチチャンネル環境では重なり合って見過ごすことのできない音のにごりの原因となるためである。
これら、Genelecのスピーカー調整はスピーカー内部のGLMにより行われている。自動補正を施したあとに手動で更にパラメーターを追い込み調整が行われた。その調整には、最新のGLM 3.0のベータバージョンが早々に利用された。GLMでは最大30本のスピーカーを調整することが出来る。そのためこの規模のスピーカーの本数であっても、一括してスピーカーマネージメントが可能となっている。
今回の更新に合わせて新しく作り直したデスクは、部屋のサラウンドサークルに合わせて奥側が円を描く形状となっている。手前側も少しアーチを描くことで部屋に自然な広がり感を与えている印象だ。もちろん見た目だけではなく作業スペースを最大限に確保するための工夫でもあるのだが、非常に収まりのよい仕上がりとなっている。このデザインはカプコンのスタッフ皆様のこだわりの結晶でもある。そしてそのアーチを描く机の上には、AVID S3とDock、モニターコントローラーのTAC system VMC-102、そして38inch-wideのPC Dispalyが並ぶ。PC Displayの左右にあるのは、BauXer(ボザール)という国内メーカーのMarty101というスピーカー。独自のタイムドメイン理論に基づく、ピュアサウンドを実現した製品が評価を得ているメーカーだ。タイムドメインというと富士通テンのEclipseシリーズが思い浮かべられるが、同じ観点ながら異なったアプローチによりタイムドメイン理論の理想を実践している製品である。また、さらにMusik RL906をニアフィールドモニターとして設置する予定もあるほか、TVからもプレビューできるようにシステムアップが行われている。
◎AVID MTRXをフル活用したDubbing Stage
Dynamic Mixing StageのシステムはVMC-102とDirectout TechnologyのANDIAMO2.XTが組み合わされている。DAWとしてはPro Tools HDX2が導入され、I/OとしてMADI HDが用意されている。MADI HDから出力されるMADI信号はANDIAMOへ入り、VMC-102のソースとして取り扱われる。ANDIAMOにはATMOS視聴用のAV AMPのPre-OUTが接続されている。AV AMPはDOLBY ATMOS等のサラウンドデコーダーとしてPS4、XBOX oneなどが接続されている。VMC上ではストレートにモニターを行うことも、5.1chへのダウンミックス、5.1chでリアをデフューズで鳴らす、ステレオのダウンミックスといったことが行えるようにセットアップされている。
ちょっとした工夫ではあるが、AV AMPの出力は一旦ANDIAMOに入った後、VMCへのソースとしての送り出しとは別にアナログアウトから出力され、Dubbing Stageでもそのサウンドが視聴できるようにセットアップされている。実はこのANDIAMOは以前よりスタジオで利用されていたものであり、それを上手く流用し今回の更新にかかるコストを最低限に押さえるといった工夫も行われている。
Dubbing StageはVMC-102が移設となったため、新たにAVID MTRIXが導入されている。Pro ToolsのI/Oとして、そしてS6のモニターセクションとしてフルにその機能を活用していただいている。7.1chのスピーカーシステムはそのままに、5,1chダウンミックス、5.1chデフューズ、stereoダウンミックスといった機能が盛り込まれている。また、CUE OUTを利用しSSL Matrixへと信号が送り込まれ、Matrixのモニターセクションで別ソースのモニタリングが可能なようにセットアップされている。AVID MTRXには、MADIで接続された2台のANDIAMO XTがあり、この2台がスピーカーへの送り出し、メーター、そしてブースのマイク回線、AV AMPの入力などを受け持っている。せっかくなので、Dubbing Stage/Bの回線をAVID MTRXに集約させようというアイディアもあったが、サンプルレートの異なった作業を行うことが出来ないというデメリットがあり、このようなシステムアップに落ち着いている。やはり収録、素材段階での96kHz作業は増加の方向にあるという。従来の48kHzでの作業との割合を考えるとスタジオ運営の柔軟性を確保するためにもこの選択がベストであったという。
AVID MTRXのモニターセクションは、AVID S6のモニターコントロールパネル、タッチスクリーンとフィジカルなノブ、ボタンからフルにコントロールすることが可能である。DADmanのアプリケーションを選択すれば、モニターセクション、そしてCUEセンドなどのパラメーターをAVID S6のフェーダーからもコントロールすることもできる。非常に柔軟性の高いこのモニターセクション、VMC-102で実現していた全てのファンクションを網羅することができた。GPIO等の外部制御を持たないAVID MTRXではあるが、AVID S6と組み合わせることでS6 MTMに備わったGPIOを活用し、そのコマンドをEuConとしてMTRXの制御を行うことができる。もう少しブラッシュアップ、設定の柔軟性が欲しいポイントではあるが、TBコマンドを受けてAVID MTRXのDimを連動することができた。少なくともコミュニケーション関係のシステムとS6 + MTRXのシステムは協調して動作することが可能である。今後、AVID S6のファームアップによりこの部分も機能が追加されていくだろう。日本仕様の要望を今後も強く出していきたいと感じた部分だ。
今回の更新ではコンパクトなスペースでもDOLBY ATMOSを実現することが可能であり、工夫次第で非常にタイトでつながりの良いサウンドを得ることができるということを実証されている。これは今後のシステム、スタジオ設計においても非常に大きなトピックとなることだろう。今後の3D Surround、Immersive Soundの広がりとともに、このような設備が増えていくのではないだろうか。この素晴らしいモニター環境を設計された株式会社SONA、そして様々なアイデアをいただいた株式会社カプコンの皆様が今後も素晴らしいコンテンツをこのスタジオから羽ばたかせることを期待して止まない。
左:株式会社カプコン プロダクション部サウンドプロダクション室 瀧本和也氏 右:株式会社ソナ 取締役/オンフューチャー株式会社 代表取締役 中原雅考氏
*ProceedMagazine2017-2018号より転載