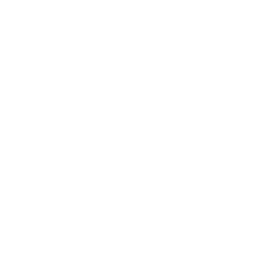«Works
Author
清水 修平
[ROCK ON PRO Sales Engineer]大手レコーディングスタジオでの現場経験から、ヴィンテージ機器の本物の音を知る男。寝ながらでもパンチイン・アウトを行うテクニック、その絶妙なクロスフェードでどんな波形も繋ぐその姿はさながら手術を行うドクターのよう。ソフトなキャラクターとは裏腹に、サウンドに対しての感性とPro Toolsのオペレートテクニックはメジャークラス。Sales Engineerとして『良い音』を目指す全ての方、現場の皆様の役に立つべく日々研鑽を積み重ねている。

株式会社 SureBiz様 / 〜Dolby Atmos、技術革新に伴って音楽表現が進化する 〜
2021年6月、Appleが空間オーディオの配信をスタートした。そのフォーマットとして採用されているはご存知の通りでDolby Atmosである。以前より、Dolby Atmos Musicというものはもちろん存在していたが、この空間オーディオの配信開始というニュースを皮切りにDolby Atmosへの注目度は一気に高まった。弊社でもシステム導入や制作についてのご相談なども急増したように感じられる。今回はこの状況下でDolby Atmos制作環境を2021年9月に導入された株式会社 SureBizを訪問しお話を伺った。
SureBizは楽曲制作をワンストップで請け負うことにできる音楽制作会社。複数の作家、エンジニアが所属しており、作曲、編曲、レコーディング、ミキシング、マスタリングをすべて行えるのが特長だ。都心からもほど近い洗足池にCrystal Soundと銘打たれたスタジオを所有し、そのスタジオで制作からミキシング、マスタリングまで対応している。今回はそのCrystal SoundへDolby Atmos Mixingが行えるシステムが導入された。2020年の後半よりDolby Atmosでのミキシングがどのようなものか検討を進めていたそうだが、Appleの空間オーディオがスタートしたことでDolby Atmosによるミックスの依頼が増えたこと、さらなる普及が予測されることからシステム導入を決断されたという。
我々でも各制作会社のお客様からDolby Atmosに対してのお問合せを多くいただいている状況ではあるが、現状ではヘッドフォンなどで作業したものを、Dolby Atmos環境のあるMAスタジオ等で仕上げるというようなワークフローが多いようだ。その中で、SureBizのような楽曲制作を行っている会社のスタジオにDolby Atmos環境が導入されるということは、制作スキームを一歩前進させる大きく意味のあることではないだろうか。
まず、既存のスタジオへDolby Atmosのシステムを導入する際にネックになるのは天井スピーカーの設置だろう。Crystal Soundは天井高2500mmとそこまで高くはない。そこで、できるだけハイトスピーカーとの距離を取りつつ、Dolbyが出している認証範囲内に収まるようにスピーカーの位置を指定させていただいた。L,C,Rまでの距離は130cm、サイドとリアのスピーカーは175cmにスタンド立てで設置されている。スタジオ施工についてはジーハ防音設計株式会社によるものだ。その際に課題となったのがスタジオのデザインを損なわずにスピーカーを設置できるようにすること。打ち合わせを重ねて、デザイン、コストも考慮し、天井に板のラインを2本作り、そこにスピーカーを設置できるようにして全体のデザインバランスを調和させている。電源ボックス、通線用モールなど黒に統一し、できるだけその存在が意識されないように工夫されている。
Dolby Atmos Musicの制作ではDAWとRendererを同一Mac内で立ち上げて制作することも可能だ。ただし、そのような形にするとCPUの負荷が重くマシンスペックを必要とする。本スタジオのエンジニアであるmurozo氏は普段からMacBook Proを持ち歩き作業されており、そこにRendererを入れて作業することはできなくはないのだが、やはり動作的に限界を感じていた。そのためCrystal Soundにシステムを導入されるにあたっては、そのCPU負荷を分散するべくRendererは別のMacにて動作させるようシステム設計をした。Renderer側はFocusrite REDNET PCIeR、Red 16LineをI/Oとしている。
RendererのI/OセットアップではREDNET PCIeRがInput、Red 16Line がOutputに指定される。Pro Toolsが立ち上がるMacBook ProのI/OにはDigiface Danteを選択している。Pro Tools 2021.7からNativeでのI/O数が64chに拡張されたので、このシステムでは64chのMixingができるシステムとなる。ちなみに、Pro Tools側をHDX2、MTRXを導入することにより128chのフルスペックまで対応することも可能だが、この仕様はコスト的に見てもハードルが高い。今回の64ch仕様は導入コストを抑えつつ要件を満たした形として、これからの導入を検討するユーザーには是非お勧めしたいプランだ。

📷 CPU処理を分散するため、Pro ToolsのミキシングマシンとDolby Atmos Rendererマシンを分離。Danteを使用したシステムを構築している。64chのDolby Atmosミキシングが可能な環境となっている。Pro Tools 側のハードウェアのアップグレードにより128chのシステムも構築可能だ。
モニターコントロールにはREDNET R1とRed 16Lineの組み合わせを採用している。これがまた優秀だ。SourceとしてRendererから7.1.4ch、Apple TVでの空間オーディオ作品試聴用の7.1.4chを切り替えながら作業ができるようになっている。また、Rendererからバイノーラル変換された信号をHP OUTに送っているため、ヘッドフォンを着ければすぐにバイノーラルのチェックもできる。スピーカーについてはGENELEC 8330APと7360Aが使われており、補正についてはGLMでの補正にて調整している。マルチチャンネルを行う際は補正をどこで行うか、というポイントが課題になるが、GLMはやはりコストパフォーマンスに優れている。今回のFocusrite Redシリーズ、GENELECの組み合わせはDolby Atmos導入を検討されている方にベストマッチとも言える組み合わせと言えるだろう。
実際にDolby Atmosシステムを導入されてからの様子についてどのような印象を持っているかも伺ってみたところ、Apple TVで空間オーディオ作品を聴きながら、REDNET R1で各スピーカーをSoloにしてみて、その定位にどんな音が入っているかなどを研究できるのが便利だというコメントをいただいた。空間オーディオによって音楽の新しい世界がスタートしたわけだが、スタートしたばかりだからこそ様々なクオリティの音源があるという。システムを導入したことにより、スピーカーでDolby Atmos作品を聴く機会が増え、その中での発見も多くあるようだ。ステレオミックスとは異なり、セオリーがまだ固まっていない世界なので、Mixigを重ねるごとに新しい発見や自身の成長を確認できることがすごく楽しいと語ってくれた。その一例となるが、2MixのステムからDolby Atmos Mixをする際は、EQやサチュレーションなどの音作りをした上で配置しないと迫力のあるサウンドにならないなど、数多くの作品に触れて作業を重ねることで、そのノウハウも蓄積されてきているとのことだ。

📷 Dolby Atmos用のモニターコントロールで使用されているREDNET R1、各スピーカーのSolo機能は作品研究に重宝しているとのことだ。Source1にRendererのプレイバックの7.1.4ch。Source2にAppleTVで再生される空間オーディオに試聴の7.1.4chがアサインされている。制作時も聴き比べながら作業が可能だ。
最後に今後の展望をmurozo氏に伺ってみた。現状、Dolby Atmos Mixingによる音楽制作は黎明期にあり、前述のようにApple Musicの空間オーディオでジャンル問わずにリリース曲のチェックを行うと、どの方法論が正しいのか確信が持てないほどの多様さがあり、まだ世界中で戸惑っているエンジニアも多いのではないか、という。その一方で、技術革新に伴って音楽表現が進化することは歴史上明らかなので、Dolby Atmosをはじめとする立体音響技術を活かした表現がこれから益々の進化を遂げることは間違いないとも感じているそうだ。「そんな新しい時代の始まりに少しでも貢献できるように、またアーティストやプロデューサーのニーズに応じて的確なアプローチを提供できるように日々Dolby Atmosの研究を重ね、より多くのリリースに関わっていければと考えています。」と力強いコメントをいただいた。
今後さらなる普及が期待されるDolby Atmos。世界が同じスタートラインに立った状況で、どのような作品が今後出てくるのか。ワールドワイドで拡がるムーブメントの中で、いち早くシステムを導入し研鑽を積み重ねているSureBiz / Crystal Soundからも新たな表現のセオリーやノウハウが数多く見出されていくはずである。そしてそこからどのようなサウンドが生まれてくるのか、進化した音楽表現の登場に期待していきたい。
*ProceedMagazine2021-22号より転載
*記事中に掲載されている情報は2022年02月04日時点のものです。